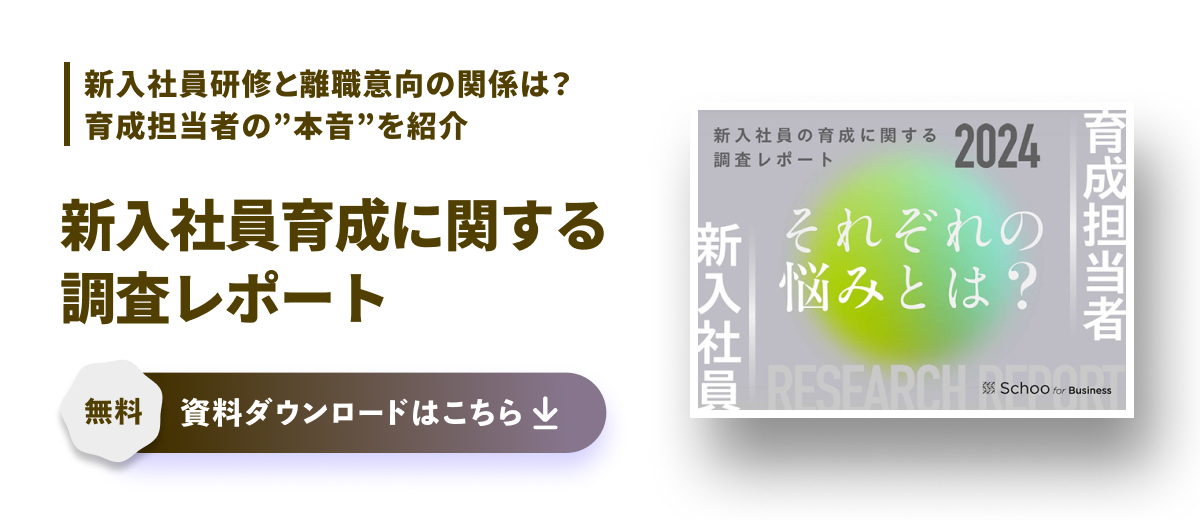新入社員研修の目的とは?研修の内容例を目的別に解説

新入社員研修とは、企業に新しく入社してきた社員に向けて指導・育成する研修のことを指します。このページでは、特に知識がなく教育が必要な「新卒の新入社員向け」の企業研修を対象としながら、新入社員研修の目的や、新入社員の特徴、新入社員のキャリア観やマネジメント方法などをご紹介します。
- 01.新入社員研修の目的
- 02.新入社員研修の目的を決めるポイント7選
- 03.目的別|新入社員研修の内容例
- 04.Schoo for Businessの新入社員研修
- 05.まとめ
01新入社員研修の目的
新入社員研修の目的は以下の7つです。
- ・学生から社会人の切り替え
- ・基本的なビジネススキルの習得
- ・自社の理解を深めてもらう
- ・自ら学び成長する習慣をつくる
- ・コンプライアンスについての理解
- ・社内コミュニケーションの活性化
- ・業務に必要なスキルの習得
また、日本の人事部が行った調査によると、新入社員研修の目的として、「学生から社会人の切り替え」を選択した企業が最も多く71.5%、次いで僅差で「基本的な社会人スキルの取得」と回答した企業が71.3%という結果となっています。
その後は、「会社のルールや方向性の理解」・「業界・企業・事業の理解促進」と続いており、自社の理解を深めてもらうことを目的にしている企業も一定数いることがわかります。
また、「自律型人材の育成」・「成長意欲の向上」がその後に続くことを見ると、新入社員の段階から自分で成長を掴みにいく姿勢を身につけてほしいという目的もあるようです。
▶︎参考:日本の人事部|人事白書 調査レポート
学生から社会人の切り替え
新入社員研修は、社会人としての自覚を持ってもらうことが目的の1つといえます。多くの新社会人が学生時代にアルバイトやインターンシップを経験していますが、社会人としての自覚を持って働いている人は多くありません。
そのため、社会人としてのマインドセットを新入社員研修で身につけてもらうことが重要なのです。仕事とは何か。お金をもらうということは、どういうことなのか。自分の行動や言動がチームや組織、企業全体に良い影響も悪い影響も与える可能性があることなどを、新入社員研修でしっかりと理解してもらう必要があります。
基本的なビジネススキルの習得

HR総研の調査によると、新入社員研修の内容で最も多いものが「社会人としての心構え」で86%。続いて「マナー」が84%、「会社の仕組み・ルール」が76%という結果となっています。
つまり、ビジネススキルという観点では、ビジネスマナー・コミュニケーション能力・コンプライアンスの理解を重視している企業が多いということでしょう。
また、人事預かりの期間が長い企業では、仕事の段取りやPCスキルなども研修内容に含んでいるようです。新入社員研修でビジネススキルをどの範囲まで教えるのかは、企業ごとの人事預かりの期間であったり、予算の大きさであったりといった要因が関わってくるので、自社において必要と思われるビジネススキルを優先して研修内容に含めるようにしましょう。
▶︎参考:HR総研|人材育成(階層別研修)に関する調査 結果報告【新入社員研修編】
自社の理解を深めてもらう
新入社員研修には、自社の理解を深めてもらうという目的もあります。自社が属している業界や競合企業との違い、これまで歩んできた歴史や創り上げてきた文化、その企業独自の規則などが、主な研修内容です。
また、自社がどのような事業を展開していて、どのような価値を顧客に提供しているのかなども研修で学ぶことにより、入社前には気づかなかった自社の魅力に気づくこともあります。
特に事業展開が多岐にわたる企業では、売上の源泉となっている事業しか認知されていないことが多いので、各事業部の責任者にそれぞれの事業内容を語ってもらう場を用意すると良いでしょう。
自ら学び成長する習慣をつくる
新入社員研修の目的に、「自律型人材の育成」や「成長意欲の向上」を置く企業も一定数います。つまり、自ら学び成長する姿勢や習慣を、新入社員の間から身につけてほしいと考える企業が徐々に増えてきているということでしょう。
昨今、社員一人ひとりが自らキャリアを形成していく時代と言われています。特に大企業では、人材戦略として「個の成長」や「主体的なキャリア形成」を掲げる企業が増え、ますますこの傾向は強まるでしょう。
そのような中で、会社に学びや成長機会を与えてもらうという姿勢ではなく、新入社員の間から自ら学びや成長機会を掴み取る姿勢を習慣化したいという企業側の意図もあるようです。
コンプライアンスについての理解
組織内のコンプライアンスポリシーや規制に対する理解は、事業の健全性と安定性を確保する上で不可欠です。近年では、コンプライアンスに対しての企業意識も高まっており、注目が集まっています。そのため、新入社員が法律、規制、企業倫理に準拠する必要性を理解し、業務遂行において適切な判断を行うための基礎を築くことが重要です。また、コンプライアンス研修を実施することで、新たに入社する新入社員は、自社のコンプライアンスへの取り組みを知り、安心感を持って、働くことができるという利点もあるため、コンプライアンス研修は、重要と言えます。
▼コンプライアンス研修について詳しく知りたい方はこちらから▼
【関連記事】コンプライアンス研修とは|目的・内容・実施方法について紹介
社内コミュニケーションの活性化
社内コミュニケーションの活発化は、チームワークやプロジェクトの円滑な進行に不可欠です。新入社員が組織内の役割、責任、情報共有の重要性を理解し、効果的なコミュニケーションスキルを身につけることで、組織全体の連携が向上し、それに伴い、成果の向上も期待することができます。
業務に必要なスキルの習得
新入社員が業務に必要なスキルや知識を習得することは、組織の生産性と競争力を高める上で不可欠です。これには、特定の業務に関連する技術的スキルだけでなく、問題解決能力、リーダーシップスキル、プロジェクト管理能力など、幅広いスキルが含まれます。
02新入社員研修の目的を決めるポイント7選
目的は達成不可能なものにしても意味がなく、努力すれば達成できるくらいの目的を設定するのが適切と言われています。
新入社員研修の目的も同様で、新入社員研修の時期が1週間と設定されているのに、「社会人としてのマインドセットを醸成して、基本的なビジネススキルを習得してもらい、自ら学ぶ習慣を身につけてもらう」という目的を設定しても達成は不可能でしょう。
そのため、新入社員研修の目的を決めるためには、会社の状況や時間的な制約を明確にしておく必要があります。この章では、どのような流れで情報を整理すると、新入社員研修の目的を決めることができるのかを紹介します。
必要なスキルをヒアリングをする
配属後に活躍する人材を育成するためには、配属先となる現場の状況や必要とされているスキルなどを理解しておくことが重要です。ビジネスマナーやマインドセットなど社会人として最低限必要なスキルはもちろんですが、現場に配属された際に必要となるスキルについてもヒアリングをしましょう。
ヒアリングの対象者は、現場の管理職と昨年の新入社員がおすすめです。例えば、管理職の目線では「マインドセットとビジネスマナーだけあれば、後は現場で教える」という回答となり、昨年の新入社員の目線では「Excelや議事録の取り方について、研修で学べておいたらよかった」という回答が得られるかもしれません。このギャップを知ることで、研修カリキュラムの改善だけでなく、現場のOJT担当者の育成が必要という新しい課題に気づくこともできるでしょう。
また、現場の管理職にヒアリングをすることで、どこまでは人事が新入社員研修で教えて、どこから現場のOJTに任せるのかの区分が明確になります。さらには、研修で学んだことが実際に現場で活かされているのかを、管理職に確認してもらうなどの協力を得やすくなります。
配属日を確認・調整する
新入社員の配属日が既に決まっている企業も多くあるでしょう。配属日によって、新入社員研修の期間も自動的に決まり、教えられる内容の限界も見えてくるはずです。
HR総研の調査によると、新入社員研修の期間を1週間以内にしている企業は全体の37%。2週間〜1ヶ月に設定している企業は33%。2ヶ月が14%、それ以上は16%という結果となっています。

▶︎参考:HR総研|人材育成(階層別研修)に関する調査 結果報告【新入社員研修編】
1週間以内、2週間〜1ヶ月、2ヶ月以上で分けた際に、教えられる内容は以下のようになるケースが多いでしょう。
| 研修期間 | 内容 |
| 1週間以内 |
|
| 2週間〜1ヶ月 |
|
| 2ヶ月以上 |
|
このように期間が伸びれば、教えられる内容は増えていきます。配属日の調整が可能なのであれば、現場からヒアリングをした結果をもとに、Excelやロジカルシンキングまで教えるので配属日を2週間先に伸ばすなどの調整も行えると良いでしょう。
予算やリソースを確認する
研修期間の他に、予算やリソースも確認が必要です。例えば予算が全くなく、リソースも人事1人しかいないといった場合に、あれもこれも研修で教え切るのは難しいでしょう。
仮に人事が1人しかいなくても、予算が一定あれば外部の研修会社に一部の研修を任せるという選択肢を取ることができます。何をどこまで実施可能なのかも含めて、新入社員研修の目的を設定することで達成できない目的を設定するリスクを避けることができるでしょう。
また、外部の研修会社に依頼するにしても高額なものから低額なもの、セミナー形式からeラーニングのようなオンライン研修まで幅広くあり、事前の調査が必要になります。
新入社員のスキルの把握
新入社員の研修を計画する前に、新入社員のスキルや経験レベルを把握することが重要です。
新卒社員であれば、学生時代にインターンをしており、ExcelやPowerPointのスキルを要していたり、中途社員であれば、前職での経験からできること・できないことがそれぞれあるかと思います。スキル把握の具体的な方法としては、面接やエントリーシート、適性試験などを通じて、個々の能力や経験を評価することが含まれます。
スキルマップの作成
新入社員のスキルや経験レベルを把握した後、スキルマップを作成します。スキルマップは、個々の新入社員が持つ強みや成長のポイントを示すツールです。スキルマップを作成することで、個々の新入社員の強化すべきスキルや研修ニーズを特定しやすくなります。
また、身につけるべきスキルが明確になることで社員の成長意欲やモチベーションの向上を期待でき、研修の意義を明確にしていくことが可能となります。
▼スキルマップについて詳しく知りたい方はこちらから▼
【関連記事】スキルマップとは|作り方やテンプレートを紹介
アウトプットもさせる
研修プログラムにおいて、単なる受講や情報の受け入れだけでなく、実際に学んだ内容を実践し、アウトプットとして示す機会を提供することが重要です。アウトプットを通じて、新入社員は自らの理解を深め、実務に活かすスキルを身につけることができます。
アウトプットの具体例としては、「レポートの提出」「習熟度テストの実施」などが挙げられます。
また、アウトプットがあることで研修を受ける新入社員は、受け身にならず、一定の緊張感を持って、研修に臨むことができます。そのため、研修のゴールとして、アウトプットを設けることで研修そのものが意義のあるものにすることができます。
「新入社員研修にオンラインを取り入れたけどイマイチ」
「社員が受け身で学ばない」を解決!
新入社員研修+自己学習の習慣化ができるスクーの資料をダウンロードする
■資料内容抜粋
・大人たちが学び続ける「Schoo for Business」とは?
・研修への活用方法
・自己啓発への活用方法 など

03目的別|新入社員研修の内容例
ここまで新入社員研修の目的について紹介してきました。ここでは、目的に応じた新入社員研修例を紹介します。
ビジネスマナー研修のカリキュラム例
ビジネスマナー研修では、社会人として必要なビジネスマナーや報連相などを学びます。電話やメールといったコミュニケーション面や名刺交換、身だしなみなど社会人として基礎スキルが身につけられるような内容にしましょう。
| 第1回 | 会社での働き方と仕事の基本 |
| 時間 | 60分×1コマ |
| 研修内容 |
|
| 第2回 | ビジネスコミュニケーションのマナー〜電話・メール・チャット |
| 時間 | 60分×1コマ |
| 研修内容 |
|
| 第3回 | 来客応対・訪問のマナー |
| 時間 | 60分×1コマ) |
| 研修内容 |
|
| 第4回 | 身だしなみのマナー |
| 時間 | 60分×1コマ) |
| 研修内容 |
|
| 第5回 | 会議・打ち合わせのマナー |
| 時間 | 60分×1コマ) |
| 研修内容 |
|
マインドセット研修
新入社員向けマインドセット研修では、業務遂行に必要な基礎的思考や行動スタンスを早期に定着させることが目的です。本カリキュラムでは「頼られる社員」をテーマに、目的意識・論理的思考・やり切る力といった“仕事ができる”ためのマインドセットを体系的に学びます。実務前に必要な意識と行動の型を習得できる構成です。
| 第1回 | 頼られる新入社員になるために今すぐ身に付けたいこと |
| 時間 | 60分×1コマ |
| 研修内容 |
|
OAスキル研修
Excel、PowerPoint、Wordといった社会人にとって必要不可欠な OAスキルの習得を目的に内容を検討しましょう。座学だけでなく実習や課題を用いることで参加者の理解促進にもつながります。
| 授業名 | 最速のExcel術 |
| 時間 | 1時間(60分×1コマ) |
| 研修内容 |
|
| 授業名 | Word入門 仕事上のドキュメント作成効率化 |
| 時間 | 5時間(60分×5コマ) |
| 研修内容 |
|
| 授業名 | PowerPoint入門 仕事上のスライド作成効率化 |
| 時間 | 3時間(60分×3コマ) |
| 研修内容 |
|
自社の理解促進
自社が属している業界や競合企業との違い、これまで歩んできた歴史や創り上げてきた文化、その企業独自の規則などを理解してもらいましょう。
| 研修タイトル | 自社研修 |
| 時間 | 1時間(60分×1コマ) |
| 研修内容 |
|
04Schoo for Businessの新入社員研修

オンライン研修/学習サービスのSchoo for Businessでは約9,000本の講座を用意しており、様々な種類の研修に対応しています。新入社員研修はもちろんのこと、若手社員研修・管理職研修からDX研修まで幅広いコンテンツで全てを支援できるのが強みです。
| 受講形式 | オンライン (アーカイブ型) |
| アーカイブ本数 | 9,000本 ※2023年5月時点 |
| 研修管理機能 | あり ※詳細はお問い合わせください |
| 費用 | 1ID/1,650円 ※ID数によりボリュームディスカウントあり |
| 契約形態 | 年間契約のみ ※ご契約は20IDからとなっております |
Schooの新入社員研修の特長は、ビジネスマナーからマインドセット、ロジカルシンキングやExcelまで、新入社員に求められるスキルに関する幅広いコンテンツが充実しているという点にあります。また、営業基礎やマーケティング基礎のような授業も揃っており、現場に配属されてからの研修や自律学習という側面でも活用できるという点も特長です。
また、Schooはeラーニングによる研修受講となるので、社員1人ひとりが好きな時間や場所、タイミングで研修を受講することができるので、リモートワークを導入している企業や多拠点展開している企業におすすめです。
Schooの新入社員研修カリキュラム
様々な研修に対応できるSchoo for Businessでは、新入社員研修にも対応しています。Schooの新入社員研修パッケージには、ビジネスマナーやロジカルシンキング、さらにはOAスキルなどがラインナップされており、この記事内で紹介したスキルを全てこの研修パッケージで網羅できます。
さらに、社員に研修動画を受講してもらった後に、意見の共有会やディスカッションを行うことで、学んだことをより効果的に定着させることができます。
社会人基礎スキル
-
新社会人のためのビジネスマナーの基本を学ぶカリキュラムです。第一印象の磨き方(身だしなみ・挨拶・敬語)や、社内マナー(ホウレンソウ・名刺交換・電話応対など)について解説しています。
-
社会人としてのマインドセットを習得するためのカリキュラムです。「思考」「実行」の2つの視点で、すぐに現場で実践できるビジネスに必要な力を学びます。
OAスキル
-
基本的なPowerPointの使い方を学ぶことができます。スライドや図表の作成やスライドショーの使い方など、新入社員や若手社員が身につけるべきスキルについて学ぶことができます。
-
見やすいグラフやスライド資料の作成方法を学ぶカリキュラムです。独学で悩みがちなテーマを、具体例や実践例を交えながらお伝えします。
-
Excelを活用したデータ分析について学べる研修パッケージです。データ分析をする際の考え方から、「並べ替え」「オートフィルタ」「ピボットテーブル」などのExcel分析に必要な機能について学ぶことができます。
ロジカルシンキング
-
「ロジカルシンキング」という言葉を初めて聞いた人、言葉は知っていても具体的にイメージできない人を対象とした入門編の授業です。 具体的には、「ロジカルシンキングとは何か」「ロジカルシンキングの基礎となる技術」などについて、2回の授業を通じて学びます。 この授業を通じて、ロジカルシンキングに興味を持っていただくことがゴールです。
-
若手社員向けのロジカルシンキングに必要な思考法について学ぶカリキュラムです。論理性を高めて業務を遂行していく際に必要な思考法について解説していきます。
プレゼンテーションスキル
-
人前で話すときのポイントや論理的に話す力、シンプルに伝えて相手を動かす技術について学び、プレゼンテーションの基礎を身につけることができます。
-
相手の心を動かすストーリーのあるプレゼンテーションを学ぶことができます。プレゼンテーションのプロが一般の方のプレゼンを添削し、より良いプレゼンに修正する過程を見て、伝わるプレゼンの法則を学ぶ授業をすることもできるため、より実戦的なスキルを身につけることができるはずです。
Schooの新人研修カリキュラム例
研修時間目安: 10時間(60分×10コマ)
全10時間で、ビジネスマナーや報連相を学ぶことができます。ビジネスメールや名刺交換などのビジネスマナーだけでなく、報連相の重要性や適切なタイミングも同時に学ぶことで、社会人としての基礎スキルを習得できる研修パッケージとなっています。
| 授業名 | 仕事がデキると思われるビジネスマナーの基本 |
| 時間 | 5時間(60分×5コマ) |
| 学べること | ・好印象を与える身だしなみ、あいさつ ・敬語の仕組み ・電話対応の方法 ・報連相のポイント ・来客応対の方法 ・円滑に進める会議術 ・訪問時の対応方法、名刺交換 ・プレゼンの基本 ・クレーム時の対応方法 ・接待のポイント |
| 授業名 | もっと伝わるコミュニケーション術 |
| 時間 | 3時間(60分×3コマ) |
| 学べること | ・伝わるメールの書き方 ・コミュニケーションのポイント ・質問力の重要性、磨き方 ・伝わるプレゼンの方法 |
| 授業名 | デキる若手の報連相 |
| 時間 | 2時間(60分×2コマ) |
| 学べること | ・報連相の目的、重要性 ・報連相のポイント ・報連相に必要なベーススキルとは ・ロジカルシンキングの基本 ・MECEの重要性、実践ワーク |
05まとめ
新入社員研修の目的は、社会人としての意識変革や基本的なビジネススキルの習得を設定する企業が多くいます。
しかし、目的を設定する際は達成可能かどうかを加味する必要があり、自社の状況をまずは確認する必要があるでしょう。
また、目的が達成できたかを確認するための指標も事前に決めておくことで、研修自体のPDCAを回すこともできるようになります。