生成AI研修は企業に必要?選び方や費用相場、導入のポイントを解説

2022年11月のChatGPT登場以来、生成AIサービスは急速に利用者を拡大しており、いまやビジネスシーンにおいて無くてはならない技術となっています。そのような中、生成AIを活用して企業競争力を強化するには体系的な研修が不可欠です。生成AI研修とは、ChatGPTなどの生成AIツールの基本操作から業務での具体的な活用方法までを体系的に学ぶ研修です。業務効率化や新規事業創出の鍵として、多くの企業が注目する重要な取り組みです。この記事では、研修の選び方、費用相場、導入ポイントを解説します。
- 01.生成AI研修とは?
- 02.生成AI研修を実施するメリット
- 03.育成担当者向け:生成AI研修サービスの選び方
- 04.Schooでおすすめの生成AI研修・講座10選
- 05.生成AI研修の費用相場
- 06.生成AI研修の導入ポイント
- 07.まとめ
「研修をしてもその場限り」「社員が受け身で学ばない」を解決!
研修と自己啓発で学び続ける組織を作るスクーの資料をダウンロードする
■資料内容抜粋
・大人たちが学び続ける「Schoo for Business」とは?
・研修への活用方法
・自己啓発への活用方法 など

01生成AI研修とは?
生成AI研修とは、ChatGPTに代表される生成AIの基礎知識から、業務での具体的な活用方法などを習得する研修のことです。
生成AI研修を受講することで、業務効率化や生産性向上を実現できます。また、生成AIを使いこなすことで、新たなビジネス機会の創出や、組織全体の競争力強化にもつながります。
生成AI研修が必要とされる背景
生成AI研修が必要とされる背景には、ChatGPTに代表されるAI技術の急速な発展があります。2024年にデロイト トーマツが行った調査によると、プライム上場企業の約9割が生成AIを導入しており、「活用しないと競争力で劣る」という認識が広がっています。一方で単なる導入では成果に繋がらず、AIの基礎知識を社内に浸透させ、具体的なビジネス活用案を企画し、アイデアを実行に移すための開発・運用体制を整えることが強く求められています。そのため、企業内での生成AI知識を底上げし、活用水準を引き上げるために体系的な研修が必要とされています。
▶︎参考リンク:デロイト トーマツ、プライム上場企業における生成AI活用の意識調査~社内の利用割合が高いほど成果を感じる
生成AI研修の種類
生成AI研修は、主に基礎・応用・実践の3種類の研修があります。基礎研修は、生成AIの仕組みや歴史、利活用に必要な基礎知識を習得する研修です。応用研修は、業務効率化や新規事業創出など、ビジネスでの具体的なAI活用方法を学びます。そして、実践研修ではAIモデルの構築・運用に必要なプログラミングや機械学習スキルを習得します。基礎から実践まで体系的な研修を受講することで、AIを使いこなし、組織の競争力強化を実現する人材を育成できます。
02生成AI研修を実施するメリット
生成AI研修は、業務効率化、生産性向上、競争力強化を実現し、実践スキル習得に貢献します。
現場で役立つ実践的なスキルが身につく
生成AI研修のメリットは、座学に留まらず、現場で即活用できる実践的なスキルが身につくという点です。ChatGPTなどの基礎知識に加え、業務効率化や新たなビジネス機会創出に向けた具体的な活用方法、プロンプトエンジニアリング、ツールの操作方法などを習得できます。これにより、単なる生成AIの導入で終わらず、実務への落とし込みや生産性向上、競争力強化に直結する成果へと繋がります。
業務効率化・生産性向上を実現できる
生成AI研修のメリットとして、業務効率化と生産性向上を実現できることも挙げられます。AI技術の基礎知識に加え、現場の具体的な業務に即した活用方法や実践的なスキルを習得することで、これまで時間のかかっていた作業を自動化し、メール作成やリサーチなどの頻出業務を効率化できるようになるでしょう。
差別化を図り、競争優位性を確保できる
急速に普及する生成AIにおいて、どの企業でもできる汎用的な使い方をしている場合は、それを差別化や競争優位の確立に結びつけるのは難しいです。一方で生成AIを使い、自社の独自データと結びつけたビジネス展開、全社的な生産性の改善などができた場合は、大きな飛躍につながる可能性があります。生成AI研修は、単なる導入から一歩進んだ活用を可能にする点で、企業競争力の強化に繋がるでしょう。
組織全体でAIリテラシーを高められる
生成AIはとてもインパクトのあるツールですが、決して万能ではありません。利用にあたっては、AI利用にかかる潜在的なリスクを理解し、出力内容を適切に判断・活用する総合的な能力が必要です。生成AI研修は、従業員一人ひとりがAIの基礎知識や仕組み、倫理的側面を正しく理解する機会を提供します。これにより、組織全体でAIリテラシーが底上げされ、ハルシネーションのリスクなども回避しながら、正しい生成AIの活用を促進できます。
ガバナンス強化にもつながる
コーポレートガバナンスとは、企業が適切に意思決定し、健全に経営されるための仕組みやルールです。生成AI研修は、AI利用における著作権侵害やプライバシー侵害、情報の偏りといった倫理的リスク・セキュリティリスクを正しく理解する機会になり、企業のガバナンス強化に役立ちます。
「研修をしてもその場限り」「社員が受け身で学ばない」を解決!
研修と自己啓発で学び続ける組織を作るスクーの資料をダウンロードする
■資料内容抜粋
・大人たちが学び続ける「Schoo for Business」とは?
・研修への活用方法
・自己啓発への活用方法 など

03育成担当者向け:生成AI研修サービスの選び方
この章では、研修や人材育成のご担当者向けに生成AI研修サービスの選び方を紹介します。選ぶ軸としては、目的・コスト・柔軟性・カリキュラムの4つがあり、この章でそれぞれについて詳しく紹介します。
自社の目的に合ったサービスを選ぶ
生成AI研修を選ぶ際は、まず「何のためにAI研修を実施するのか」という目的を明確にすることが最も重要です。参加者のAIリテラシー向上、業務効率化、新規事業創出、AIモデル開発など、目指すゴールは多岐にわたります。また、受講者の現在のスキルレベルも考慮し、それに合ったカリキュラムを選択することで、より実践的な成果に繋がりやすくなります。貴社の現状や課題に合わせて、研修カリキュラムをオーダーメイドで提供してくれるサービスを検討することも有効です。
コストと柔軟性のバランスで選ぶ
生成AI研修を選ぶ際は、コストと柔軟性のバランスも重視しましょう。多くの研修はパッケージ化されていますが、自社の具体的な目的や課題、受講者のスキルレベルに合わせてオーダーメイドで提供されるカリキュラムは、より実践的な成果に繋がりやすいでしょう。費用を抑えるために短期集中型や団体割引、助成金活用も検討しつつ、対面・オンライン(eラーニング含む)など柔軟な受講形式が選べるかも重要です。予算内で最大の効果を引き出すため、総合的な費用対効果で判断する必要があります。
実践的なカリキュラムを選ぶ
生成AI研修に限らず、研修は「学んだ知識をいかに実務で成果に繋げるか」が重要です。単にツールの使い方や基礎知識を学ぶだけでは、現場での具体的な業務効率化やビジネス変革には繋がりません。実践を重視したカリキュラムを選び、実際の業務に合わせた活用方法、最適なプロンプト、具体的なビジネス変革の企画・運用力を習得できるかを確認しましょう。これにより「導入して終わり」ではなく、生産性向上や競争力強化に直結する、真に価値ある研修が期待できます。
現場経験のある講師で選ぶ
生成AI研修の成果を最大化するには、講師の質が極めて重要です。単に知識だけでなく、実際の業務で生成AIを活用し、成果を出した経験を持つ「実践のプロ」であるかを重視しましょう。普通の研修講師では、理論や知識の伝達だけに留まってしまい、「学んだだけで終わる研修」に陥りがちです。現場の課題に即した具体的な活用事例やノウハウを伝えられる講師であれば、業務効率化や生産性向上に直結する、真に価値ある研修を実現できるでしょう。
研修後の支援体制で選ぶ
生成AI研修は、受講後の「実践への定着」も成功のポイントとなります。研修直後は理解できても、実際に業務で活用しようとすると、思い通りに進まないケースも少なくありません。そのため、研修後の継続的なサポート体制が充実しているとより安心です。例えば、今後の活用推進プランの提案や、担当者による伴走支援など、アフターフォローが手厚いサービスは、学んだ知識を確実に実務へ落とし込み、「導入して終わり」にせず、具体的な成果へと繋げるために不可欠です。
「研修をしてもその場限り」「社員が受け身で学ばない」を解決!
研修と自己啓発で学び続ける組織を作るスクーの資料をダウンロードする
■資料内容抜粋
・大人たちが学び続ける「Schoo for Business」とは?
・研修への活用方法
・自己啓発への活用方法 など

04Schooでおすすめの生成AI研修・講座10選
DX人材の育成は、DX人材の定義から始まり、現状分析によるギャップ把握、適性ある人材の選出、知識のインプット、現場での活用などのステップを踏みながら進めていきます。
1:「生産性が高い人」の生成AI社内活用術
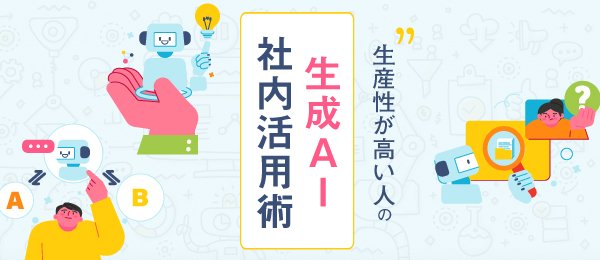
本講座では、ニッセイアセットマネジメントの山田智久氏が、社内利用率80%超を達成した生成AI活用術を解説しています。進化の速いAIの最新動向から、誤字脱字チェック、姓名分離、メール作成、議事録、プレゼン準備、Excel関数代替、プログラム作成まで、実践的なプロンプトと活用事例を豊富に紹介。業務フローを壊さずAIを溶け込ませる「非破壊」アプローチや、トップダウン・ボトムアップの啓蒙活動で利用率を高めた道のりも学べます。生産性向上と業務効率化をしたい方におすすめの講座です。
▶人事育成担当者限定!『「生産性が高い人」の生成AI社内活用術』を無料で観る
2:情報整理を加速させるGemini活用法

本講座では、Google公認エバンジェリストの丹羽国彦先生をお迎えし、Google Workspaceと連携したGeminiならではの機能や、NotebookLMによる情報整理・業務効率化の方法を具体的に解説しています。普段からGoogleドキュメントやスプレッドシートなどを使っている方にとって、実践的なヒントが得られる内容です。
▶人事育成担当者限定!『情報整理を加速させるGemini活用法』を無料で観る
3:そのDX、AIでは無理ですよ
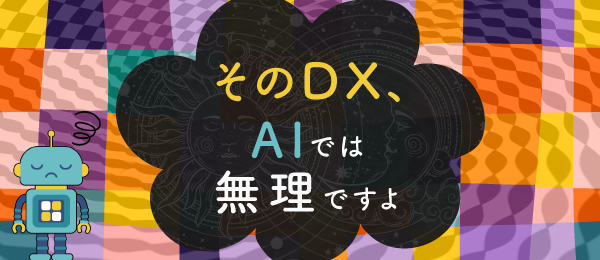
本講座では、「AIを導入するだけで競争に勝てるのか?」という視点から、そもそもAIを使うメリットは何か、AIを使わないと今後どうなっていくのかを、日本IBM、デロイトトーマツコンサルティングにてデザイン思考の専門家として活躍してきたBeth合同会社の河上泰之社長に解説いただいています。
▶人事育成担当者限定!『そのDX、AIでは無理ですよ』を無料で観る
4:その作業はAIにやらせてみよう

本講座では、最先端のAI講師が実際に活用している生成AIの活用方法を学ぶことができます。議事録作成や英語学習、Excel関数やプレゼン資料など、ビジネスにおける様々なシーンでの活用方法を知ることができます。生成AIに関する情報のキャッチアップが追いつかないけど、活用してみたいという方におすすめのコースです。
▶人事育成担当者限定!『その作業はAIにやらせてみよう』を無料で観る
5:AIエージェントで業務はどう変わる?
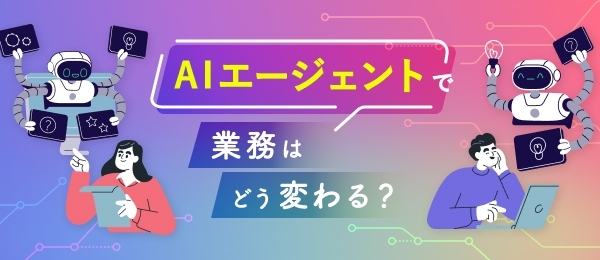
本講座では、生成AIから一歩進んだ自律的に判断し行動する「AIエージェント」の活用法を2回にわたって解説しています。第1回ではその基本概念や仕組み、生成AIとの違いを理解し、第2回では即戦力となるAIエージェントをハンズオン形式で実践的に学びます。「AIエージェントで何ができるか分からない」という疑問を解消し、自社業務の改善や生産性向上を目指す方におすすめの講座です。
▶人事育成担当者限定!『AIエージェントで業務はどう変わる?』を無料で観る
6:ホントにMicrosoft 365 Copilot 仕事で使えるの?

本講座では、Microsoft 365 Copilotの活用法を徹底検証・解説しています。Excel・Teams・PowerPointなどのMicrosoft 365アプリに搭載されたCopilotの全体像や、業務シーンに即した機能、効率化アイデア・テクニックを学べます。名刺管理ツールの比較表作成やミーティングからの企画書作成など、実践的な活用事例を豊富に紹介。Microsoft 365 Copilotを導入済み、または導入検討中の方に特におすすめで、「これなら活用できる!」という確信とアイデアを得ていただくことをゴールとしています。
▶人事育成担当者限定!『ホントにMicrosoft 365 Copilot 仕事で使えるの?』を無料で観る
7:「Microsoft Copilot」が業務にもたらす未来

本講座では、Microsoft Copilotの基本機能と、Excel・PowerPoint・Word・Outlookといった主要アプリとの連携による業務効率化事例を学びます。長いメールの要約、Excel関数の自動生成、資料作成・再利用、プレゼン準備、アンケート作成など、具体的な業務課題の解決策を豊富に紹介します。Microsoft環境を導入している企業でDX推進や業務効率化を目指す方に特におすすめです。本講座でCopilotの機能を深く理解し、自身の業務を効率化する具体的なイメージとアイデアを得られます。
▶人事育成担当者限定!『「Microsoft Copilot」が業務にもたらす未来』を無料で観る
8:100日間AIを毎日使ったら人生が変わった話

本講座では、話題の著者・大塚あみ氏が、ChatGPTを活用した「100日チャレンジ」の経験を語っています。宿題をサボるためAIを使い始めた怠け者の女子大生が、AIを相棒にプログラミングを学び、海外論文で評価されるまでの変貌をトーク形式で紹介します。“AIに育てられた第一世代”を自認する彼女の言葉から、AI時代の学び方、挑戦と成長の楽しさを実感できます。生成AIの具体的な使い方が不明な方や、何か新しいことに挑戦したい方に特におすすめです。
▶人事育成担当者限定!『100日間AIを毎日使ったら人生が変わった話』を無料で観る
9:さわって学ぶPower Platform Copilot

本講座では、ローコード開発ツールPower Platformと生成AIツールMicrosoft Copilotの連携を実際に手を動かしながら学習することができます。Power Appsによるアプリ開発、Power Automateでの業務自動化、Copilot Studioでのチャットボット作成といった実践的な活用法を解説。Copilotの自然言語指示で開発を効率化し、生産性向上を目指します。Power Platformを利用中の方や、Copilotの具体的な活用法を知りたい方に特におすすめです。
▶人事育成担当者限定!『さわって学ぶPower Platform Copilot』を無料で観る
10:DX時代のAIの使いどころ

本講座は、加速する企業DXとAI活用について幅広く学ぶことができます。DXの定義から、企業単位でのAI活用事例、個人の業務に活かせるプロンプト活用術(ハンズオン含む)まで網羅的に解説しています。企業でのAI活用に興味はあるが導入イメージが湧かない方、自社のDXやAI導入で何が変わるか知りたい方、事業改革を目指すDX担当者におすすめです。DXを取り巻く外部環境の変化と、競争優位性確立のためのデータ・テクノロジー活用が鍵となることを理解できます。
05生成AI研修の費用相場
生成AI研修の費用は、研修内容や期間、受講形式によって大きく異なります。大まかな費用相場は以下の通りです。
| 研修内容 | 受講形式 | 費用相場 |
| オンライン研修 | eラーニング | 数千円~数万円 |
| オンライン研修 | ライブ配信 | 数万円~数十万円 |
| 公開型研修 | – | 数万円~数十万円 |
| オーダーメイド研修 | – | 数十万円~数百万円 |
eラーニングを用いた研修は数千円から受講できる一方で、オーダーメイドで研修を実施する場合は受講者数によっては数百万円かかる場合もあります。短期集中型や団体割引を活用するほか、厚生労働省の助成金を利用することで最大75%OFFと費用を抑えられる場合もあります。無料体験や相談会も積極的に活用し、自社の予算と求める成果に合った研修を検討しましょう。
06生成AI研修の導入ポイント
生成AI研修は、目的・成果指標を明確化し、実務に即した設計で学習意欲を高め、補助金活用でコストを抑えることが導入成功の鍵です。
研修の目的と成果指標を明確にする
生成AI研修を成功させるには、まず「研修で何を達成したいのか」という目的を明確にすることが不可欠です。目的によって対象者やカリキュラム内容が大きく異なるため、漠然とした導入では実践的な成果に繋がりません。例えば、「全社員のAIリテラシー向上」か「特定業務の効率化」のように、具体的な目的の設定が重要です。加えて研修の成果指標を明確にし、研修が目的を果たせたのか、学んだ知識が生産性向上や競争力強化にどう貢献したかを評価できる状態にしておきましょう。
実務に沿った研修設計で学習意欲を高める
生成AI研修の導入では、実務に即した研修設計をしましょう。単なる基礎知識やツールの使い方だけでなく、実際の業務にどう活用し、具体的な成果に繋がるかを体験することで、受講者はスキルの習得が自身の業務効率化や生産性向上に直結するイメージを持ちやすくなります。これにより、学習意欲が飛躍的に高まり、モチベーションの維持・向上を実現し、「導入して終わり」ではない研修にすることができます。
補助金・助成金制度を活用する
生成AI研修の導入において、補助金や助成金制度の活用は、導入コストを抑える上で非常に有効です。例えば、厚生労働省が提供する「人材開発支援助成金」などを活用することで、研修費用が最大75%OFFとなるケースもあります。多くの研修サービスが助成金申請に関する無料相談やアドバイスを提供しているため、これらを積極的に活用し、コスト効率良く組織全体のAIリテラシー向上を実現しましょう。
▶︎参考:厚生労働省|人材開発支援助成金
「研修をしてもその場限り」「社員が受け身で学ばない」を解決!
研修と自己啓発で学び続ける組織を作るスクーの資料をダウンロードする
■資料内容抜粋
・大人たちが学び続ける「Schoo for Business」とは?
・研修への活用方法
・自己啓発への活用方法 など

07まとめ
「生成AI研修」は、AI時代の企業競争力強化に不可欠です。業務効率化や生産性向上、ガバナンス強化を実現し、実践スキルの習得を支援します。研修会社を選ぶ際は、明確な目的設定と成果指標、実務に即した実践的カリキュラム、現場経験豊富な講師、充実した研修後支援体制が重要です。補助金を活用してコストを抑えつつ、AI活用できる組織を目指しましょう。

