【2025年最新】ChatGPT研修の費用・メリット・選び方をわかりやすく解説

昨今、生成AIの導入が加速する中で、ChatGPT研修への注目が高まっています。業務効率化や生産性向上、競争優位の確立に向けて、どの企業もAIリテラシーの底上げが急務です。本記事では、ChatGPT研修の費用相場、導入メリット、研修を選ぶ際のポイントまで、初心者にもわかりやすく丁寧に解説します。自社に合ったChatGPT研修を見極めるための情報を網羅していますので、AI活用を本気で進めたい企業担当者は必見です。
01ChatGPT研修とは?
ChatGPT研修は、OpenAI社のサービスである「ChatGPT」の活用レベルを最大化するための知識とスキルを習得する研修です。ChatGPTは2022年11月のリリース以降、その自然な対話能力と多様な応用範囲によりビジネスに変革をもたらすと大変注目されています。
ChatGPT研修では、例えばAIに対する適切な指示(プロンプト)の出し方、文書作成やデータ分析といったビジネス上の使い方について学びます。これにより、業務効率化を図るだけでなく、アイデア創出などのより高度なビジネス活用を目指します。
ChatGPTをはじめとした生成AIの活用は企業の生産性向上、創造性向上、競争優位性の確立に貢献します。一方で単に使うだけでは真価を発揮しないため、研修を通してより高度な活用方法が浸透することを目指します。
02ChatGPT研修の実施メリット
ChatGPT研修には業務効率化、創造的なアイデア創出、競争優位の強化といった多面的なメリットがあります。生成AIの活用スキルを従業員に身につけさせることで、単なる業務支援にとどまらず、組織全体の付加価値を高めることが可能になります。ここでは、ChatGPT研修によって得られる主なメリットを具体的に紹介します。
業務効率化・生産性向上が期待できる
ChatGPTを活用することで、これまで人が行っていたさまざまな業務をAIに対応させ、業務時間の大幅な短縮が可能となります。そのため、研修により従業員がChatGPTに関する正しい知識とスキルを習得することは、企業の業務効率化と生産性向上に大きく貢献します。例えばChatGPTは従来のチャットボットと比較して、非常に自然なコミュニケーションが可能です。そのため文書作成にとどまらず、よくある質問への自動応答や問い合わせ内容の要約といった顧客対応業務にも活用が可能です。その他ドキュメントの処理も得意であり、議題や要件に沿った提案書の作成も可能です。さらに、情報収集では大量のデータ分析や必要情報の抽出・整理が迅速に行えるほか、多言語対応の自動翻訳機能により翻訳業務も効率化されます。
新しいアイデアの創出につながる
社員がChatGPTをより効果的に活用できるようになることで、新しいアイデアの創出にもつながります。具体的にはChatGPTを使ってブレストを実施することで、従来の発想に囚われない斬新なアイデアを生み出すことが可能です。例えば、「顧客の購買意欲を高める革新的なマーケティング戦略」のような具体的なテーマを与え、多様なアイデアを提案させるなどが挙げられます。またChatGPTを使えば、膨大なデータの分析も可能です。分析対象データを読み込ませて顧客ニーズや市場トレンドを分析することで、より顧客満足度の高いサービスを開発することにもつなげられます。このように、ChatGPT研修を通じて、ChatGPTによるブレストや市場調査の手法を習得することで、従業員の創造性を向上させ、新しいアイデアの創出に繋げることができます。
競争優位性が高まる
生成AI技術が普及していくこれからの社会において、社員の生成AI活用力を引き上げることは、企業が他社との差別化を図り、競争優位性を確立するために不可欠な取り組みです。生成AIを使えば、パーソナライズされたコンテンツや顧客体験の提供など、従来であれば開発リソースを多く要するような施策についてもスピーディに対応することが可能になります。さらにAIによる業務の自動化は、組織の生産性の向上とコスト削減に役立ち、価格競争においても優位に働きます。また、AIを積極的に活用する姿勢を示すことで、社内外に先進的で革新的な企業イメージを発信でき、優秀な人材や顧客からの支持を得る要因にもなります。このように、ChatGPT研修は単なるスキル習得にとどまらず、企業の成長戦略を支える重要な要素となるのです。
03ChatGPT研修の費用相場
ChatGPT研修の費用の費用は提供企業や形態によってさまざまです。相場としては、eラーニング型で1人あたり約1万〜15万円、公開セミナーで2万〜5万円、講師派遣型では一日あたり20万〜100万円が目安ですが、カスタマイズ型ではさらに高額になる場合もあります。
条件を満たせば「人材開発支援助成金」などの公的助成金を活用でき、研修費用の一部を補助することが可能です。助成対象や申請条件は変動するため、適宜最新情報の確認を実施していきましょう。
▶︎参考リンク:厚生労働省|人材開発支援助成金
04ChatGPT研修の選び方・比較のポイント
ChatGPT研修を導入する際は、研修の実施形式や提供企業の実績、カリキュラムの内容、料金体系、サポート体制などを比較することが重要です。自社の目的や課題に合った研修を選ぶことで、より高い効果が期待できます。ここでは、研修選びで注目すべき主なポイントについて詳しく解説します。
研修の実施形式で選ぶ
ChatGPT研修の実施形式は、主にeラーニングと集合研修の2種類があり、自社のニーズに合わせて選ぶことが重要です。
eラーニングは場所を選ばず繰り返し学べ、費用も集合研修より安い傾向があります。しかし、疑問点をすぐに解決できない、基本的には一人で受講するためモチベーション維持が難しいといった課題もあります。
一方、集合研修は、講師に直接質問ができ、他の受講者との交流で刺激を得られる点がメリットです。しかし、場所や時間に制約があり、費用がeラーニングよりも高くなる傾向があります。
費用を抑えつつ効率的に学習したい場合はeラーニングやオンライン研修が適しており、会場費や移動費を抑えられるため比較的低価格で受講できます。深い理解やディスカッションを求める場合は集合研修が良いでしょう。
提供企業の実績・専門性で選ぶ
生成AIの技術は日進月歩で進化しているため、ChatGPT研修を選ぶ上で提供企業の専門性は非常に重要です。
企業の専門性を見極めるには、生成AIに関するプロジェクトの実績、講師が生成AI分野の専門知識や実務経験を持っているか、最新のAIトレンドや技術に対応した研修内容を提供しているか、そして顧客満足度や業界での評判が高いかといった信頼性を確認すべきです。
これらのポイントを参考に、質の高い研修を提供できる専門性の高い企業を選ぶことで、どのレベルの受講者に対しても陳腐化しない最新の知識とスキルを習得させることが可能となり、信頼できる学習体験を確保できます。
カリキュラムの内容で選ぶ
ChatGPT研修のカリキュラムは、自社の目的や受講者のレベルに合致しているかが重要です。初級者には、ChatGPTの概要やプロンプトの基本など、基本的な使い方から学べる内容が安心です。業務効率化を目指す中級者には、業務効率化のための活用術やデータ分析への応用、自動化ツールの作成などが適しています。
新規事業開発など応用力を高めたい上級者には、ChatGPT APIの活用やプロンプトエンジニアリングといった高度な内容を選びましょう。
医療や金融など自社の属する業界に特化した内容であれば、より実践的なスキルが身につきます。個々のレベルや課題に合わせた指導を求める場合は、マンツーマン指導や少人数制の個別指導型研修が特に有効です。
料金体系・コストパフォーマンスで選ぶ
ChatGPT研修の費用は上でもご紹介した通り、提供内容や受講人数、研修時間で大きく変動します。費用を抑えたい場合は、会場費や移動費がかからないオンライン研修やeラーニングが比較的低価格で提供されており、コストパフォーマンスに優れています。大人数なら1人あたりの料金が安いプラン、少人数で実践的な内容を学びたい場合はパッケージや個別指導を検討すると良いでしょう。また、人材開発支援助成金やIT導入補助金といった国や地方自治体の助成金制度を活用することで、研修費用の一部または全額を補助してもらえる可能性があります。
サポート体制で選ぶ
研修のサポート体制は、提供事業者により大きく異なるので、研修効果を最大限に引き出すためにも確認しておくと良いでしょう。
サポート内容の具体例としては、研修の実施に関するアドバイス、コンテンツに対する提案、研修内容に関する質疑応答、受講者同士が交流し疑問を解決できるコミュニティフォーラム、最新の活用事例や応用事例が共有される実践事例共有、そして個別の課題解決に向けた個別相談の機会などが挙げられます。
充実したサポートは、ChatGPTの活用スキルを継続的に向上させ、業務へのスムーズな導入を促します。どのレベルの受講者にとっても、学習した知識を実践に繋げ、疑問を解消するために不可欠な要素であるため、必ず比較検討時に確認しましょう。
「研修をしてもその場限り」「社員が受け身で学ばない」を解決!
研修と自己啓発で学び続ける組織を作るスクーの資料をダウンロードする
■資料内容抜粋
・大人たちが学び続ける「Schoo for Business」とは?
・研修への活用方法
・自己啓発への活用方法 など

05【目的別】ChatGPT研修の選び方
ChatGPT研修を導入する際は、自社の目的や課題に合ったプログラムを選ぶことが成功のカギとなります。コストパフォーマンス、実践的な内容、業種特化型、実施スタイルなど、重視するポイントごとに選び方の基準が異なります。ここでは、目的別に押さえておきたい選定のポイントをわかりやすく解説します。
コストパフォーマンスを重視する場合
ChatGPT研修においてコストパフォーマンスを重視する場合、前述の通り、低価格で実施できるeラーニングやオンライン研修がおすすめです。これらの実施形式は、集合研修と比較して会場費や移動費といった追加コストが発生しないため、比較的低価格で提供される傾向にあります。
また、一部の研修では無料体験や割引キャンペーンを実施している場合があるため、これらを活用して試用期間を経てから本格導入を検討することも有効です。受講人数が多い場合は1人あたりの料金が安くなるプランを、少人数で実践的な内容を深く学びたい場合はパッケージ料金や個別指導料金を検討するなど、自社の状況に合わせた料金体系を選ぶことも重要です。
実践的なカリキュラムを重視する場合
ChatGPT研修において実践的なカリキュラムを重視する場合、単なる座学に留まらず、豊富な演習やワークショップ形式を通して、実際にChatGPTを使いこなす力を養える研修を選ぶことが重要です。このような研修では、実際の業務を想定した実践的な演習内容が組まれているかを確認すると良いでしょう。
具体的な内容としては、報告書・議事録の作成、大量のアイデア出し、提案書や企画書のたたき台作成、ブログ記事の作成、キャッチコピーやSNS投稿文の作成といった、多岐にわたるChatGPTの活用例を学べるものがあります。特に業務効率化を目指すのであれば、データ分析への応用や自動化ツールの作成、あるいはChatGPT APIの活用やプロンプトエンジニアリングといった高度なスキル習得に焦点を当てたカリキュラムが適しています。
自社の業種に特化した内容を重視する場合
ChatGPT研修において、自社の業種に特化した内容を重視する場合、ChatGPTの活用方法が業界によって大きく異なるため、自社の属する業界に特化した研修を選ぶことが重要です。これらは、業界特有の課題解決に焦点を当てたカリキュラムが提供されます。
例えば、医療業界では、膨大な医療データの分析や診断支援に活用する症例データ分析の自動化や診断支援AIの開発が挙げられます。金融業界であれば、リスク管理や顧客対応の効率化を目指す与信審査の自動化や顧客からの問い合わせ対応が対象となるでしょう。また、製造業界では、製品開発の効率化や品質管理の向上に向けた設計開発におけるアイデア創出や不良品検知の自動化などが具体例として挙げられます。
研修を選ぶ際には、そのカリキュラムが業界特有の課題解決に焦点を当てているか、そして過去の受講企業の事例などを参考にすることが推奨されます。
実施スタイルを重視する場合
ChatGPT研修を選ぶ際には、研修の実施形式が自社に合っているかも重要なポイントとなります。前述のようにeラーニングは、場所を選ばずに自分のペースで学習でき、繰り返し学習が可能である点がメリットです。そのため、例えばリモートワークの社員が多い環境や多拠点展開している企業の場合は取り入れやすいです。また、業務の空き時間を活用して効率的に学習させたいときにも有効でしょう。
対照的に、集合研修は講師に直接質問ができ、他の受講者との交流を通じて理解を深めることができる利点があります。受講者の反応を直接確かめたい場合や、演習を通じた学習が必要な場合に適しています。
技術の最新性を重視する場合
ChatGPT研修において技術の最新性を重視する場合、日進月歩の生成AI分野に対応するため、最新のAIトレンドや技術に対応した研修内容を提供している企業を選ぶことが極めて重要です。単にプロンプトの書き方やChatGPTの基本操作を学ぶだけでなく、最新の技術を活用した応用的な内容が含まれているか確認しましょう。
また提供企業の生成AIに関する実績や、講師が持つ専門知識と実務経験は、研修内容の最新性と質を担保するうえで重要なポイントです。候補企業が生成AIについてどんな情報を発信しているのか、講師は知識だけではなく生成AIに関する実務経験があるのかなどを確認するとよいでしょう。
06SchooでおすすめのChatGPT研修・講座5選
ここではChatGPTに関するSchooのおすすめ講座をご紹介します。講座ごとに対象者や目的も解説していますので、参考にしてみてください。
今日から始めるChatGPT

| 受講対象者 | ・ChatGPTに興味がある人 ・ChatGPTを使ったことはあるが詳しくは知らない人 ・ビジネス・プライベートでChatGPTをもっと活用したいと考えている人 |
| 受講目的 | ・ChatGPTの基本的な仕組みや特性を正しく理解する ・生成AIに対する苦手意識や不安を解消する ・日常生活やビジネスの中での活用イメージを持てるようになる ・効果的なプロンプトの作成・活用方法を学ぶ ・ChatGPTを使った業務効率化やアイデア発想の方法を習得する ・初心者が自信を持って生成AIを活用できるようになる |
| 特徴・学べるテーマ | ChatGPTの基本から日常・ビジネスで役立つプロンプト活用法まで、初心者でも実践できる入門知識を体系的に学べる講座です。 |
この講座は、ChatGPTに興味はあるが使いこなせていない初心者に最適な入門講座です。基礎的な知識からプロンプトの作り方、実際の活用シーンまでを一気通貫で学べるため、「今さら聞けない…」と感じている方でも安心して取り組めます。講師はAI専門メディア「AINOW」編集長の小澤健祐氏。SNSなどで日々アップデートされるChatGPTの活用法を体系的に整理し、ビジネス・プライベート問わず使える知識として提供してくれます。進化が早くて置いていかれがちな生成AIの世界を、やさしく丁寧に理解できるのが大きな魅力です。
-
 AICX協会 代表理事
AICX協会 代表理事
「人間とAIが共存する社会をつくる」をビジョンに掲げ、AI分野で幅広く活動。著書『生成AI導入の教科書』の刊行や1000本以上のAI関連記事の執筆を通じて、AIの可能性と実践的活用法を発信。 一般社団法人AICX協会代表理事、一般社団法人生成AI活用普及協会常任協議員を務める。Cynthialy取締役CCO、Visionary Engine取締役、AI HYVE取締役など複数のAI企業の経営に参画。日本HP、NTTデータグループ、Lightblue、THA、Chipperなど複数社のアドバイザーも務める。 千葉県船橋市生成AIアドバイザーとして行政のDX推進に携わる。NewsPicksプロピッカー、Udemyベストセラー講師、SHIFT AI公式モデレーターとして活動。AI関連の講演やトークセッションのモデレーターとしても多数登壇。 AI領域以外では、2022年にCinematoricoを創業しCOOに就任。PRやフリーカメラマン、日本大学文理学部次世代社会研究センタープロボノ、デヴィ夫人SNSプロデューサーなど、多彩な経験を活かした活動を展開中。
※研修・人材育成担当者限定 10日間の無料デモアカウント配布中。対象は研修・人材育成のご担当者に限ります。
Excel業務はAIにやらせてみよう

| 受講対象者 | ・Excel業務に悩む方(業務の多くをExcel入力に費やす、関数が分からずに日々調べるなど) |
| 受講目的 | ・Excel作業にかかる時間や負担を減らしたい ・関数や数式に苦手意識があり、AIに助けてもらいたい ・日々の業務を効率化し、生産性を上げたい ・ChatGPTなどのAIツールの具体的な活用方法を知りたい ・Excel初心者でも実践できるAI活用術を習得したい |
| 特徴・学べるテーマ | Excel初心者でも安心。ChatGPTなどのAIツールを活用して、入力作業や関数処理を効率化し、業務時間を短縮する方法を学べる講座です。 |
この講座は、Excelに不慣れな方や日々の業務で入力・関数処理に時間を取られている方に向けて、ChatGPTなどの生成AIを使った効率化のテクニックを学ぶ実践的な内容です。特に、関数の使い方が分からない、毎回調べる手間がかかるといった悩みを、AIがサポートすることで大幅に軽減できます。お昼の生放送形式で進行するため、リアルタイムの学びや気軽な参加も可能です。AIとExcelの組み合わせによって「難しい」「面倒」と感じていた業務がぐっと楽になることを体感できる、初心者にもやさしい入門講座です。
-
 Michikusa株式会社 代表取締役
Michikusa株式会社 代表取締役
AIの研究開発を行うPKSHA Technologyを母体としたファンドPKSHA CapitalにてAssociate、Amazon JapanにてAccount Manager、AIベンチャーにて取締役を経験後、Michikusa株式会社を創設。国際基督教大学卒。
※研修・人材育成担当者限定 10日間の無料デモアカウント配布中。対象は研修・人材育成のご担当者に限ります。
事例で学ぶ生成AIの導入と活用

| 受講対象者 | Microsoftの環境を導入している企業のDX推進担当者や、効率化を求める各部門の担当者 |
| 受講目的 | ・生成AIの導入効果や活用方法を実例から学びたい ・組織で生成AIを効果的に活用するための知識を得たい ・従来のAI導入との違いや最新のAI動向を理解したい ・業務効率化や残業削減を実現するヒントを得たい ・生成AI導入に不安や疑問があるが、具体的な道筋を知りたい |
| 特徴・学べるテーマ | 生成AI導入企業の実例をもとに、業務変革や効率化のポイント、組織での活用方法をわかりやすく解説する実践講座です。 |
本講座では、ChatGPTをはじめとする生成AIをいち早く導入した企業の事例を基に、従来のAI導入との違いや、生成AIがもたらす業務効率化の具体的効果について学びます。実際に残業削減や自動化を実現した企業の成功例を踏まえ、組織やチームで生成AIを効果的に活用するためのポイントを解説。著者であり人気講師の小澤健祐氏が、生成AI導入の全体像と現場での活用イメージを丁寧に伝えるため、これから導入を検討する企業担当者や実務者に特におすすめです。AI活用の「現場のリアル」を知ることができる貴重な講座です。
-
 AICX協会 代表理事
AICX協会 代表理事
「人間とAIが共存する社会をつくる」をビジョンに掲げ、AI分野で幅広く活動。著書『生成AI導入の教科書』の刊行や1000本以上のAI関連記事の執筆を通じて、AIの可能性と実践的活用法を発信。 一般社団法人AICX協会代表理事、一般社団法人生成AI活用普及協会常任協議員を務める。Cynthialy取締役CCO、Visionary Engine取締役、AI HYVE取締役など複数のAI企業の経営に参画。日本HP、NTTデータグループ、Lightblue、THA、Chipperなど複数社のアドバイザーも務める。 千葉県船橋市生成AIアドバイザーとして行政のDX推進に携わる。NewsPicksプロピッカー、Udemyベストセラー講師、SHIFT AI公式モデレーターとして活動。AI関連の講演やトークセッションのモデレーターとしても多数登壇。 AI領域以外では、2022年にCinematoricoを創業しCOOに就任。PRやフリーカメラマン、日本大学文理学部次世代社会研究センタープロボノ、デヴィ夫人SNSプロデューサーなど、多彩な経験を活かした活動を展開中。
※研修・人材育成担当者限定 10日間の無料デモアカウント配布中。対象は研修・人材育成のご担当者に限ります。
それ、AIでサクッと自動化できちゃいます
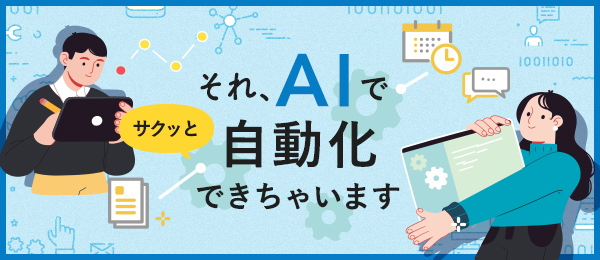
| 受講対象者 | ・チームに生成AIの導入を考えている方 ・他社が生成AIをどのように活用しているか気になる方 ・ChatGPTを実際に活用している企業の話を聞きたい方 |
| 受講目的 | ・業務効率化や自動化にチャレンジしたいが専門知識に不安がある ・ChatGPTとGASを活用し、簡単に業務を自動化したい ・プログラミング初心者でも実践できる自動化の具体的方法を知りたい ・トラブル時の解決方法を習得し、自信を持って業務改善に取り組みたい ・AIとスクリプトを組み合わせて、日常業務の負担を軽減したい |
| 特徴・学べるテーマ | ChatGPTとGoogle App Scriptを活用し、プログラミング初心者でも業務効率化や自動化を手軽に実現する方法を学べる講座です。 |
本講座は、業務効率化を目指すものの自動化に対して「専門知識がないと難しい」と感じている方に最適です。ChatGPTを活用して効率化アイデアを引き出し、Google App Script(GAS)で実際の自動化を実践する流れを丁寧に解説します。GASの基本操作やトラブル時の解決法をChatGPTにサポートしてもらいながら学べるため、初心者でも無理なく取り組めるのが大きな魅力です。業務の中で「自動化できるかも」という具体的なイメージが湧き、「自分でもできる!」と自信を持てるようになる点が特におすすめポイントです。
-
 Schooのディレクター
Schooのディレクター
1995年生まれ、天秤座。大学院では物理学を専攻し、少し変わった結晶構造の超伝導現象をテーマに研究。学びたい人が等しく学べる学び場を提供すると意気込み、2021年に株式会社Schooに入社。2022年でAI領域の収録コンテンツ制作を担当。2023年4月より『その作業はAIにやらせてみよう』というお昼の生放送番組を担当。
※研修・人材育成担当者限定 10日間の無料デモアカウント配布中。対象は研修・人材育成のご担当者に限ります。
”悩む時間”をカット 思考プロセス時短術

| 受講対象者 | ・ChatGPT初心者の方 ・ある程度は使っているけれど、あらためて効果的な使い方を学びたい方 |
| 受講目的 | ・ChatGPTの基本から実践的な活用法を体系的に学びたい ・仕事や趣味の効率を大幅に向上させたい ・副業にチャレンジし、収益を上げたい ・書けない・思いつかないなどの悩みを解消したい ・効果的なプロンプトの作成方法を習得したい |
| 特徴・学べるテーマ | ChatGPT初心者から中級者向けに、仕事や趣味での実践的活用法や副業収益化までを段階的に学べる実用講座です。 |
この講座は、ChatGPTを初めて使う方や、使い始めたものの効果的な活用法を体系的に学びたい方に最適です。第1回では講師である人財プロデューサーの岡崎 かつひろ先生が考案した「オカザキ式プロンプト」を活用し、ビジネスや趣味の分野で効率よくタスクを進める実践的な方法を解説します。第2回では、ChatGPTを使って副業商品を作成し、月10万円の収益を目指す具体的な手法に挑戦します。単なる操作方法だけでなく、成果を出すためのノウハウを段階的に学べるため、実践力を高めたい人におすすめです。書けない・思いつかないといった悩みを解消し、作業効率アップと収益化の両面で役立つ充実の内容です。
-
 人財プロデューサー
人財プロデューサー
全国出版オーディション主宰 一般社団法人 食育日本食文化伝承協会理事 株式会社XYZ 代表取締役 研修講師/ビジネス書作家。 「すべての人の最大限の可能性に貢献する」を企業理念に、研修講師をはじめ著作活動、全国出版オーディション主宰、20-30代若手人材育成など活動は多岐にわたる。 東京理科大学卒業後、ソフトバンク入社。20代にして、コールセンターのKPIを構築し、2008年起業。飲食店経営での組織マネージメントを経て、2017年に『自分を安売りするのは“いますぐ”やめなさい。』(きずな出版)は、新人著者としては異例の3万部を超えるヒットとなる。現在著作9冊、累計16万部を超えるベストセラー作家として全国での講演活動など、『学び』をテーマに日本人の知的リテラシーの向上を啓蒙するリーダーとして活躍している。
※研修・人材育成担当者限定 10日間の無料デモアカウント配布中。対象は研修・人材育成のご担当者に限ります。
07ChatGPT研修に関するよくある質問
疑問や不安を解消し、導入検討に役立つ情報をまとめました。研修で習得できるスキルや費用の目安、リスクについての疑問に回答しているので、導入検討の参考にしてください。
質問:ChatGPT研修で身に付けられるスキルは?
回答:ChatGPT研修では、ChatGPTの基本操作や効果的なプロンプト作成の基礎知識を習得できます。また、報告書作成やデータ分析、翻訳など業務効率化のためのスキルや、アイデア創出、マーケティングといったビジネス活用の応用スキルも身につけられます。上級者向けにはChatGPT APIの活用やプロンプトエンジニアリングも学習可能です。
質問:ChatGPT研修の費用はどのくらい?
回答:研修費用は、研修内容、受講者数、研修時間によって大きく変動します。1人あたり数千円から数十万円が目安で、eラーニングやオンライン研修は会場費や移動費が不要なため比較的低価格です。また、人材開発支援助成金やIT導入補助金の活用も検討できます。
質問:ChatGPT研修にリスクはある?
回答:ChatGPTの業務利用には、情報漏洩や誤情報の生成、著作権侵害のリスクがあります。また、過度な依存による人間の判断力低下や、AIが事実ではない情報を生成することへの対策不足も課題です。これらを理解し、適切な利用ガイドラインの策定と継続的な監視が必要です。
「研修をしてもその場限り」「社員が受け身で学ばない」を解決!
研修と自己啓発で学び続ける組織を作るスクーの資料をダウンロードする
■資料内容抜粋
・大人たちが学び続ける「Schoo for Business」とは?
・研修への活用方法
・自己啓発への活用方法 など

08まとめ
生成AIの活用が進む中、ChatGPT研修は業務効率化や創造的アイデアの創出、競争優位性の強化に有効です。費用は内容や形式によって幅がありますが、eラーニングや助成金を活用することでコストを抑えることができます。
また、研修選びでは実施形式や専門性、カリキュラム内容、サポート体制が重要で、自社の目的やレベルに合った研修を選ぶことが成功の鍵です。
本記事で解説した内容を参考に最新技術対応の研修で継続的なスキル向上を目指しましょう。

