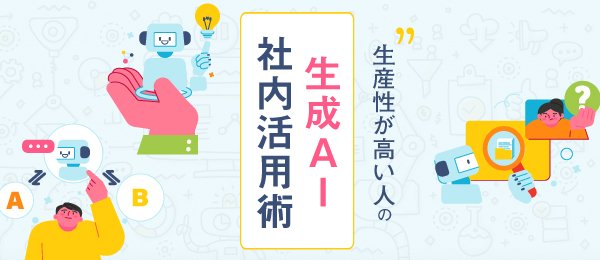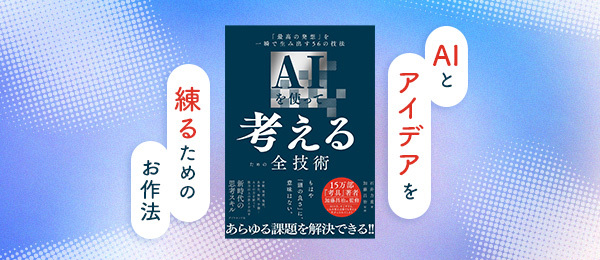生成AIを活用した人材育成とは?メリットや注意点、活用事例まで紹介

生成AIを活用した人材育成は、従来の画一的な集合研修やOJTの課題を解決し、従業員個々の学習を最適化する強力な手段として注目されています。生成AIを活用することで指導者の負担が軽減され、個別サポートや学習設計に注力できるようになり、学習効率の向上とコスト削減にもつながります。この変革は、人材育成の効果と効率を飛躍的に向上させると期待されています。この記事では生成AIを活用した人材育成におけるメリットや注意点、活用事例などを解説します。
01生成AIを活用した人材育成とは
生成AIを活用した人材育成は、従業員個々の学習を最適化する強力な手段として期待されています。従来の集合研修やOJTは内容が画一的になりやすく、品質が指導者のスキルやリソースに依存しがちであるという課題がありました。生成AIを活用することにより、学習内容のパーソナライズや個人に合わせたペースでの効率的な学習が可能になります。
また組織内での伝達が難しかった熟練者の暗黙知も、AIを使って形式知化・検索可能にすることで、組織全体のノウハウの底上げにつながります。これにより、研修担当者の負担が軽減され、個別サポートや学習設計に注力でき、業務効率向上とコスト削減に繋がります。
02生成AIが変える人材育成の具体的な活用シーン
生成AIは、人材育成の在り方を大きく変えつつあります。活用により、従来の研修では実現が難しかった個別最適な学習支援や、実務に即したトレーニングが可能になると期待されています。ここでは、具体的な活用シーンを紹介します。
コンテンツ作成・設計支援への活用
従来は人の手で、時間とコストをかけて作成・更新していた教材や研修資料を、短時間で作成することが可能になります。これにより、新入社員向けの基礎知識から中堅社員向けの応用コンテンツ、さらには理解度チェック問題の作成まで効率化できます。
教材作成にかかる時間を大幅に短縮することで、育成担当者は学習設計やサポートといった業務により注力することができます。また定期的な情報更新も簡単なため、常に最新の内容で学習機会の提供が可能になります。
トレーニング実践・ロールプレイ相手としての活用
生成AIは、トレーニング実践において画期的な役割を果たします。例えば営業や顧客対応の研修では、AIがロールプレイングの相手となり、学習者の話し方や改善点をリアルタイムでフィードバックしてくれます。これにより育成者側のリソースを節約しながら実践的なトレーニングを効率的に繰り返し行うことが可能になります。
また、外国語学習のようなスキル習得においても、即時のフィードバックを提供し、個人のペースでの習熟を支援します。
フィードバック・振り返り支援としての活用
生成AIは、人材育成におけるフィードバックと振り返りの質・量を高めるツールとしても活用できます。従来は上司や指導担当者が個別に対応していたフィードバック業務ですが、生成AIを用いることで一貫性のあるコメントや指摘を、学習者の発言内容や記述内容に基づいてリアルタイムに提供可能です。
また、研修や面談のログをAIが解析することで、行動傾向や改善点を抽出・要約し、より客観的な振り返りを促すことにも活用できます。これにより、受講者自身が自ら気づき、次の行動に結びつけやすくなります。
自己学習・質問応答ツールとしての活用
社員一人ひとりの学習履歴や業務データを基に、リアルタイムでパーソナライズされた教材を生成し、個人のペースで効率的な学習を可能にします。例えば新人や若手社員が「こんなことで上司・先輩の時間を取ってもいいのか」と質問をためらう場面でも、AIであれば気軽に問いかけることができ、即時に回答が得られるため、学習のハードルが下がります。
FAQや社内資料をAIに学習させれば、企業独自の情報を反映した応答が可能となり、実務に直結した支援にも活用できます。
OJTやメンタリングの補助ツールとしての活用
生成AIは、OJTやメンタリングの強力な補助ツールとなります。特に、熟練技術者が持つ「暗黙知」を「勘所集」として形式知化・文書化し、容易に活用できるようにします。これにより、若手社員などが熟練者のノウハウを効率的に学習でき、指導者の負担を大幅に軽減します。
従来のOJTでは難しかった経験に基づくノウハウの体系化と伝承を加速し、さらに、過去のOJT履歴や指導メモをAIが分析・整理することで、育成状況の可視化にもつながり、指導漏れや重複の防止にも役立ちます。
「研修をしてもその場限り」「社員が受け身で学ばない」を解決!
研修と自己啓発で学び続ける組織を作るスクーの資料をダウンロードする
■資料内容抜粋
・大人たちが学び続ける「Schoo for Business」とは?
・研修への活用方法
・自己啓発への活用方法 など

03生成AIを活用した人材育成のメリット
生成AIを活用することで、人材育成の効率と効果は飛躍的に向上します。コンテンツ作成の手間を省くだけでなく、社員一人ひとりに合った学習の最適化や、繰り返し学べる環境の提供が可能です。また、OJTやメンタリングの負担も軽減され、現場の育成力強化にもつながります。
育成コンテンツの作成・更新コストを大幅に削減できる
生成AIはプレゼンテーション資料の作成などに広く使用されていますが、研修や育成に関わるコンテンツ制作にも活用ができます。これにより、育成担当者の研修準備コストを大幅に削減できます。また、新しい制度やシステム導入時にも、内容に応じたマニュアルやQ&AをAIにより迅速に用意できるため、現場の混乱を最小限に抑えつつ教育を進めることができます。
研修担当者は教材作成に割いていた労力を削減することで、全体設計などより重要度の高い業務に時間を割くことができるようになるのです。
社員一人ひとりに合った個別学習が可能になる
従業員が業務修得や推進におけるサポート役として生成AIを活用することで、社員一人ひとりに合った個別学習が可能になります。これまでの育成においては、従業員に対して一律に研修などの必要な学習ソースを提供し、必要に応じてフォローアップを行う形が一般的でした。
しかし育成担当者のリソースも限定されており、個人に合わせたきめ細かい指導を実現するのは困難でした。一方で生成AIが相手であれば、学習者側も育成者のリソースを気にすることなく疑問を深ぼることができ、それぞれの得意や苦手に応じたスキル伸長が可能になります。
学習の即時性と反復性が高まり、定着率が向上する
生成AIは、必要な知識を即座に提供できる点で優れています。従業員が業務中に疑問を感じたタイミングでAIに質問して解決できるため、業務効率高くスキルを修得できます。また生成AIが相手であれば、学習者は何度でも質問したり、トレーニングに付き合ってもらうことが可能です。
つまり生成AIを活用すると、「すぐに聞ける・すぐに直せる・何度でも試せる」という学習環境を整えることができるので、スキルやノウハウの定着率アップが期待できます。
OJT・メンタリングの業務負担を軽減できる
現場における先輩社員によるOJTやメンタリングは、新人や異動者の育成にとって非常に重要です。一方で育成担当者にとっては、育成以外の業務状況によって負担も大きくなりがちです。生成AIは、このような育成の現場で「補助的なトレーナー」として活用することができます。
たとえば基本的な業務の進め方や用語の解説、資料作成の手順などをAIが説明したり、事例に基づくシミュレーション演習を提供したりすることで、人が対応すべき場面を減らすことができます。また、質問応答型のAIチャットを活用すれば、受講者は遠慮せずに繰り返し質問できるため、教育効果の向上にもつながります。
04生成AIを人材育成に活用する際の注意点
生成AIは人材育成の効率化や個別最適化に大きな可能性をもたらしますが、活用にあたっては注意も必要です。活用方法を誤ると、逆に育成の質や信頼性を損なう恐れもあります。ここでは、生成AIの導入・活用に際して特に留意すべきポイントを整理します。
▶︎参考リンク:Artificial Intelligence and the Future of Teaching and Learning (アメリカ教育省,2023)
誤情報や不適切な回答が含まれる可能性に注意
生成AIの出力には、不正確な情報や現実に基づかない内容が含まれる可能性があります。特に専門知識が必要な分野など、AIの学習データが不十分な場合に事実と異なる内容や不適切な言い回しが含まれる可能性が高まります。そのためAIの活用には、結果を鵜呑みにせず、確認・検証する知見が欠かせません。
これらの特性から、社員教育に生成AIを用いる場合には、受講者がこれらのAIの特性を理解して利用することが必須です。また、ファクトチェックの方法や、誤情報に気づくための視点を教育に組み込むことで、誤った知識の定着を防ぐことができます。
情報漏洩リスクを踏まえた運用ルールの整備
生成AIの利用には、データプライバシーとセキュリティのリスクを伴います。AIシステムの導入は、AIに学習させる企業独自のデータに加え、学習者の行動に関する詳細なデータへのアクセスを必要とします。例えば管理状況によって、1on1での会話内容や顧客情報、自社のノウハウなどの重要な情報が、AIを通じて想定外の場所で出力されてしまう可能性もあります。
企業は、個人データの収集、使用、転送、および保持に明確な制限を設け、情報を最小限に抑えるようプラットフォームに義務付ける必要があります。
利用者に生成AI自体に対するリテラシーが求められる
生成AIはその利便性ゆえに、誰でも簡単に使える一方で、「どう使えばよいか」「どこまで信用すべきか」を理解していなければ、誤った使い方や過信につながります。たとえば、曖昧な質問文では精度の低い回答が返ってくることもあり、出力の良し悪しを見極めるスキルが必要です。
また生成AIを使った研究では、自ら考えずにAIに頼り切る状態を作ってしまうと、却って思考力などのスキル低下につながるリスクも指摘されています。人材育成においてAIを活用するには、受講者や運用担当者自身に、生成AIの仕組みや限界を理解したうえで使いこなすための「AIリテラシー」を身につけてもらう必要があります。
AI任せにならない上司・現場の関与が必要
生成AIを導入すると、教育や育成の一部を自動化できるため、現場の上司やメンターが「AIに任せればいい」と考え関与を減らしてしまうケースがあります。しかし、人材育成は単なる情報伝達ではなく、本人の理解やモチベーション、課題感に応じた対話やフィードバックが不可欠です。
AIは補助ツールとしては優秀ですが、個々の感情や状況を汲み取る能力には限界があります。だからこそ、上司やOJT担当者はAIを活用しつつ、適切なタイミングで介入・支援を行うことが重要です。たとえば、AIによるフィードバックを踏まえた1on1を実施したり、ロールプレイの後に人が評価・助言するような設計が有効です。
05生成AIを活用した人材育成の事例
生成AIを活用した人材育成は、すでに多くの企業で実践が進んでいます。本章では、AIを活用して個別学習を支援した事例や、研修コンテンツの自動生成によって教育効率を高めた事例など、具体的な活用シーンを紹介します。実際の取り組みから、導入のヒントを得てみてください。
株式会社アトレ
株式会社アトレは、Google Geminiを全社員の「AIメンター」として導入し、業務効率の向上や社員教育に活用しています。2025年の4月に導入を開始し、2ヶ月半で全社員の82%が利用するようになりました。普及のポイントは、社員がAIメンターをより効果的に活用できるよう、ゲーミフィケーションを取り入れて楽しみながらAIスキルを向上させる仕組みを作ったこと、アイデアソンなどの取り組みを全社的に行って活用を促進した点にあります。これにより、現場における生産性向上を実感する声がすでに上がっています。
▶︎参考リンク:株式会社アトレ ニュースリリース
株式会社日立製作所
株式会社日立製作所は、生成AIの社内活用推進とLumada事業での事業創生加速、およびAI利用に伴うリスク管理を目的とし、「Generative AIセンター」を新設しました。データサイエンティストらがアイデア創出やソースコード生成にAIを活用し、社内向けには「Generative AIアシスタントツール」を展開しています。リスクマネジメントを含む社内AI利用ガイドラインを策定し、安全かつ効率的な活用を促進。これにより、AIの社内活用と人材育成が加速し、事業創生のサイクルを推進しています。
▶︎参考リンク:株式会社日立製作所 ニュースリリース
ライオン株式会社
ライオン株式会社は、衣料用粉末洗剤生産技術領域における熟練技術者の暗黙知継承の困難さに対し、NTTデータと協働し「知識伝承AIシステム」を導入しました。熟練者のノウハウを「勘所集」として文書化し、これを生成AIで検索可能にすることで、新規参画者への技術継承を支援しています。NTTグループの技能抽出手法を基に熟練者へのインタビュー等で暗黙知を収集。これにより、効率的な技術継承と短期間での技術力向上、および指導負荷の軽減に寄与しています。
▶︎参考リンク:NTTデータ ニュースリリース
「研修をしてもその場限り」「社員が受け身で学ばない」を解決!
研修と自己啓発で学び続ける組織を作るスクーの資料をダウンロードする
■資料内容抜粋
・大人たちが学び続ける「Schoo for Business」とは?
・研修への活用方法
・自己啓発への活用方法 など

06生成AI活用に関する学習講座の事例
生成AIの基礎理解や実務への応用力を高めるため、多くの企業や教育機関がAI活用に関する学習講座を提供しています。本章では、ビジネスパーソン向けに実践的な知識やスキルを習得できる講座の事例を紹介し、社内研修や自己学習に活かせるポイントを解説します。
事例で学ぶ生成AIの導入と活用
この講座は、ChatGPTのような生成AIの企業への導入と活用を検討している管理職やDX担当者を主な対象としています。導入はしたものの、社内での活用が進まない、どの業務に活かせば良いか分からないといった課題感を解決することを目的としており、生成AIの活用・推進方法や社内に浸透させるためのノウハウを実践事例と共に理解できます。講師は『生成AI導入の教科書』の著者であるAICX協会代表理事の小澤健祐氏が務めます。構成は全2回で、それぞれ60分間。「生成AI導入の方法」と「生成AI活用のベストプラクティス」という具体的なテーマで解説されます。
※研修・人材育成担当者限定 10日間の無料デモアカウント配布中。対象は研修・人材育成のご担当者に限ります。
「生産性が高い人」の生成AI社内活用術
本講座は、生成AIの社内活用に関心がある管理職やDX担当者向けに提供されています。ニッセイアセットマネジメントで生成AIの利活用推進を手がける山田智久氏が講師となり、社内の生成AI活用率を80%以上に引き上げ、生産性を高めた具体的な実践例と方法を紹介するのが特徴です。受講者は、生成AIを業務にどう活かせば生産性が向上するのか、実際の事例を通じて具体的にイメージできるようになります。この講座は全1回60分で構成されており、生成AIの推進における実践的なノウハウが凝縮されています。
※研修・人材育成担当者限定 10日間の無料デモアカウント配布中。対象は研修・人材育成のご担当者に限ります。
AIとアイデアを練るためのお作法
この講座は、AIを使いながら発想を広げ、深め、整えることを目的にしています。業務にAIを用いているものの、アイデア出しにおいてはいまいち上手く使いこなせない、あまり良いアイデアにつながらない、という悩みはないでしょうか?授業では、アイデア・デザイン論を専門とする石井力重先生から、AIを相棒とするための問いかけ・壁打ち・視点拡張の技術を学びます。よりよいプロンプト作成を通じて、AI活用でのアイデア出しを行いたい方におすすめの授業です。
※研修・人材育成担当者限定 10日間の無料デモアカウント配布中。対象は研修・人材育成のご担当者に限ります。
07まとめ
生成AIを活用した人材育成は、従業員個々の学習を最適化する強力な手段として注目されています。従来の画一的な集合研修やOJTの課題を解決し、学習履歴などに基づきパーソナライズされた教材をリアルタイムで生成することで、各従業員が自身のペースで効率的に学習できるようになります。
一方で、生成AIに全てを任せるにするにはリスクがあるため、十分な注意や対策を施しながら活用していくことが望ましいでしょう。