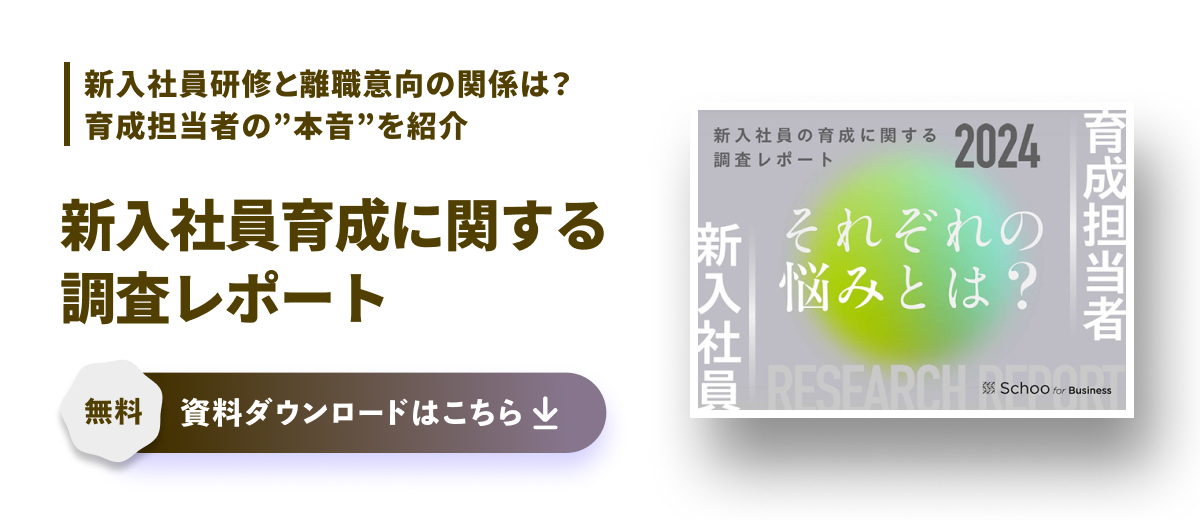新入社員研修の流れを企画から実施後の振り返りまで解説

新入社員にはビジネスの基礎やマナー、実務内容など研修すべきことが豊富です。人事部として新入社員向けに研修を行うための流れや手法、外注か内製どちらにすべきかなどを解説します。
- 01.新入社員研修の流れ(企画編)
- 02.新入社員研修の流れ(運営編)
- 03.新入社員研修の流れ(振り返り編)
- 04.新入社員研修|Schoo for Business
- 05.まとめ
01新入社員研修の流れ(企画編)
新入社員研修を企画する流れは、以下のとおりです。
| Step | 実施項目 |
| 1 | 新入社員の1年後の姿を定義する |
| 2 | 経営陣・管理職へのヒアリング |
| 3 | パフォーマンスゴールを決める |
| 4 | 研修内容を決める |
| 5 | 研修方法を決める |
| 6 | トレーニングゴールを決める |
| 7 | 効果測定の方法を決める |
まず、新入社員の1年後の姿を経営陣や管理職層とすり合わせをします。次に、具体的なスキル要件を決めて、研修で教えることを明確にします。
この手順に沿って研修を企画することで、「研修がやりっぱなし」という状態や、「研修は意味がない」という社員の声を払拭できるはずです。
1.新入社員の1年後の姿を定義する
まず、新入社員に1年後どのような姿になってほしいかを、経営陣や管理職層と擦り合わせましょう。これが組織全体での育成目標となります。
例えば、「社会人としての常識を持ち、基本的な行動ができる」であったり、「上司や先輩の支援を受けながら、担当業務を理解し実行できる」などが主な1年後の目標例です。
2.経営陣・管理職・一般社員へのヒアリング
次に、経営陣や管理職にヒアリングをして、新入社員の1年後の理想の姿や現場配属後に必要なスキルを把握します。
特に管理職にヒアリングをしておくことで、研修で教えることと現場配属後にOJTで教えることを擦り合わせすることができ、組織全体での新入社員育成が促進されます。
3.パフォーマンスゴールを決める
パフォーマンスゴールとは、「どのような行動を社員が取れるようになるのか」という目標のことです。
例えば、「議事録を決められたフォーマットに沿って記載することができる」であったり、「PDCAを主体的に回すことができるようになる」などが、パフォーマンスゴールと言えます。
研修を実施する上で、このパフォーマンスゴールの策定が最も重要と言っても過言ではありません。研修がやりっぱなしの状態になったり、研修が意味ないと社員に思われてしまうのは、研修が実務での行動変容に結びついておらず、社員に成長実感を与えられていないことが要因だからです。
4.研修内容を決める
パフォーマンスゴールを決めたら、具体的な研修内容の策定に進みます。
例えば、「PDCAを主体的に回すことができるようになる」をパフォーマンスゴールに設定した場合、研修内容はPDCAの重要性を理解してもらい、具体的な振り返りの方法を知ってもらうことなどとなるでしょう。
この際に、ヒアリングした内容が効果を発揮します。管理職から「振り返りが弱い」という一次情報を得られていたら、特にその点を重視した研修内容を組むことができます。
このように、ヒアリングを徹底的に行っておくことで、行動変容に結びつく効果的な研修内容を設定できるようになるのです。
5.研修方法を決める
具体的な研修内容を決めたら、研修方法を決めます。
研修方法を決める際は、インプットとアウトプットで分けて考えましょう。社内のリソースも加味しながらインプットを決め、アウトプットとしてはどのような手法が適しているのかを考えると効率的です。
まず、インプットの手法を費用や工数で整理すると以下のようになります。
| インプットの手法 | 費用 | 自社の工数 |
| 集合研修(外部) | 高い |
|
| eラーニング(外部) | 安い |
|
| 自社 | なし(人件費のみ) |
|
このように、自社で実施すれば費用負担は人件費のみで済みますが、研修資料の作成や講師の打診など作業が大幅に増えます。一方で、集合研修を外部に依頼すれば、費用は高いという反面、アウトプットも含めて実施してくれる可能性もあり、自社の工数負担は軽減されるでしょう。eラーニングは自社と集合研修の中間で、費用は安いですがアウトプットは自社で行う必要があるという側面もあります。
それぞれの手法にメリット・デメリットがある上に、各研修内容でも自社で実施すべきものと外部に任せた方がスムーズなものがあります。それぞれの研修手法の特性を活かして、どの手法を選択するとパフォーマンスゴールを達成できるのかを考えなければなりません。
6.トレーニングゴールを決める
トレーニングゴールとは、「研修を受け終わった時に何を理解しているか」を定めた目標のことを言います。
先述したPDCAの例で言えば、「振り返りの具体的な方法や振り返りを習慣化するためのコツ」を理解していれば、トレーニングゴールを達成したことになるでしょう。
ただし、あくまでも研修で達成すべきものは、パフォーマンスゴールである行動変容であることを忘れてはいけません。知識やスキルを理解することと、実践できることの間には大きな壁があり、知っていても使いこなせなければ意味がありません。
研修が経営に資する投資と認識されるためには、トレーニングゴールを中間指標とおき、最終的に達成したい指標はパフォーマンスゴールという認識を持つ必要があります。
7.効果測定の方法を決める
最後に、研修の効果測定の方法を決めます。パフォーマンスゴールとトレーニングゴールでそれぞれ測定方法が異なるので、以下の表を参考にしてみてください。
| パフォーマンスゴール |
|
| トレーニングゴール |
|
パフォーマンスゴールの測定方法
最も正確にパフォーマンスゴールが達成されているかを確認できるのは、「社員へのヒアリング」です。例えば、マネジメント研修であれば実際にマネジメントされる現場の一般社員にヒアリングをして、マネジメント研修で学んだ内容が実践できているかを確認しましょう。
しかし、現場へのヒアリングが簡単ではないこともわかっています。多くの企業でパフォーマンスゴールを設定しないのは、現場へのヒアリングにかかる工数が大きいためです。そのため、研修を受けた当事者に数ヶ月後にアンケートを取るという測定方法も紹介します。
例えば、研修の3ヶ月後に以下のような項目を聞くと効果的です。
- ・研修で学んだことを実践できていますか?
- ・実践できている場合、具体的に実践できた場面を含めて教えてください
- ・実践できていない場合、何が要因ですか?
このアンケートで重要なポイントは、実践できていないことも率直に記載してもらうことにあります。「実務で使う機会がなかった」という理由で実践できていないのであれば、研修に課題があるのではなく、職場での実践機会を作れていないことに課題があると分かり、対策を打つことができます。
トレーニングゴールの測定方法
トレーニングゴールの測定方法としては、アンケートやテスト、レポート提出があります。
この中で、パフォーマンスゴールを意識するのであれば、レポート提出が最もおすすめの方法です。テストで測定してしまうと、知識を知っているかどうかしか測定することができず、行動変容に結びつけにくいためです。
レポートで最低限聞くべき項目は以下の2つです。
- ・研修で何を学びましたか?
- ・研修で学んだことを、どのように実務で活用しますか?
このように、レポートでどのように実務で活用するかを、研修受講者が自らイメージして記載することで、パフォーマンスゴールの達成確率を上げることができます。
一方で、アンケートは研修自体の評価を得るために活用すると良いでしょう。「研修の満足度」・「講師の評価」・「研修へのフィードバック」などをもらうことで、研修自体のPDCAを人事が回せるようにするためです。
02新入社員研修の流れ(運営編)
研修成果には、「研修前の意識付け」が4割・「研修プログラム」が2割・「研修後のフォロー」が4割の影響を与えると、ロバート・ブリンカーホフ教授は提唱しています。つまり、研修そのものよりも、研修前に参加に対しての納得感を持せたり動機づけを行ったり、研修後に業務・実務に転用させる働きかけを行ったりする方が研修の効果を高めるということです。
この章では、研修効果を高めるために新入社員研修において研修前・研修中・研修後でどのような取り組みをするべきか紹介します。
研修前
研修前にすべきことは、参加者の動機付けです。「この研修を受けてみたい!」・「この研修を受けることで自分は成長できる!」という感情に研修受講者を導くことで、研修効果を高めることができます。
新入社員研修の場合は「社会人として必要不可欠のスキルだから」で全て説明ができてしまいますが、Excelやビジネスマナーがなぜ必要なのか、実際に使う場面などを紹介しながら丁寧に説明すると良いでしょう。
研修中
研修そのもの自体も重要で、講師や講義内容の質は当然ながら担保されていなければなりません。特に意識すべきことは、実践を意識した内容になっているかです。
実践に近いインプットを用意する
研修講師が現場のことを全くわかっておらず、机上の空論を語ってしまうことは避けなければなりません。また、誰が話すのかも受講者の納得度に影響を与えます。営業経験のない研修講師が語る営業研修と、誰もが知っている営業代行会社のトップセールスマンが語る営業研修では、後者の方が参加者の納得度が高いのは想像に難くないでしょう。
そのため、研修講師を現場で活躍するビジネスパーソンに依頼し、実務に即した内容にしてもらったり、eラーニングを活用しながら実務者の講義を研修素材として利用したりするなどの取り組みをすると、研修効果を高めることができます。
現場での実践をイメージさせる
現場での活用イメージを膨らませながら、インプットを行うことで行動変容につなげやすくなります。
インプットの中にグループワークやロールプレイング、練習問題などを織り交ぜると、現場での実践をイメージしやすくなります。
研修後
研修後は、学んだことを実践するためのフォローが欠かせません。現場配属後の管理職やOJT担当者、メンターなどを巻き込み、現場と人事が一体となって新入社員の育成をしましょう。
現場での実践機会をつくる
研修で得た学びを実務で活かすためには、実践機会は必ず提供しなければなりません。例えば、議事録の取り方を研修で教えても、会議に参加させなかったら議事録を取る機会はなく、研修で学んだことを実際に使えるようになっているのかを誰も判断することができません。そのため、研修と実務での機会提供は基本的にセットで考えるべきことなのです。
実践経験を与えるためには、どうしても管理職の理解や協力が欠かせません。そのため、管理職を巻き込みながら、職場全体で人材を育成していくように人事部や経営が働きかけをしていく必要があります。
管理職から定期的に確認をしてもらう
研修で学んだことを実践できているか、定期的に管理職から声をかけてもらうことで、受講者の学びっぱなしを防ぐことができます。
管理職にチェック機能を委ねる際には、事前にどのような研修を行い、どのようなことを学ばせたのかを知らせておく必要があります。このコミュニケーションの質で、管理職が主体的に協力してくれるかに差が出ます。
03新入社員研修の流れ(振り返り編)
新入社員研修にもPDCAは欠かせません。来年に向けて反省すべきところは反省し、改善をしていく必要があります。
1:KPTを洗い出す
まず、人事・経営陣・管理職・OJT担当者・メンターなど、新入社員の育成に関する全ての人を集め、「Keep(成果が出ていて継続すること)」・「Problem(解決すべき課題)」をポストイットやmiroなどのツールを使いながら洗い出しましょう。この段階ではブレインストーミングで問題ありません。思いついたものを書き出していき、重複なども気にせずに出来るだけ多くの意見を洗い出します。
2:Keep・Problemに対してディスカッションする
洗い出したKeep・Problemを整理します。カテゴリーを大まかに決めながら、重複するものはまとめておくことで複数人が同じ意見を出したことも可視化できるようになります。
次に、全員がそれぞれの意見を発表しディスカッションをしながら分析を行います。Keep・Problemとした理由や、それぞれの要因・原因は何なのかをきっちり掘り下げて真因を明らかにすることが重要です。ここではKeepを更に良くするという観点もありますが、Problemがある場合は特にそちらを中心に議論と分析を進めて課題の解決にフォーカスすることがより重要です。
3:Tryの詳細を詰める
最後に、議論したProblemに対して、具体的にどのようなアクションを取るのかをTryとして書き出します。出来るだけ具体的に「~をする」というように、行動として記載することを意識しましょう。
そして、洗い出したTryの中から実際に実施するものを決めて振り返りは終了です。
04新入社員研修|Schoo for Business

オンライン研修/学習サービスのSchoo for Businessでは約9,000本の講座を用意しており、様々な種類の研修に対応しています。新入社員研修はもちろんのこと、若手社員研修・管理職研修からDX研修まで幅広いコンテンツで全てを支援できるのが強みです。
| 受講形式 | オンライン (アーカイブ型) |
| アーカイブ本数 | 9,000本 ※2023年5月時点 |
| 研修管理機能 | あり ※詳細はお問い合わせください |
| 費用 | 1ID/1,650円 ※ID数によりボリュームディスカウントあり |
| 契約形態 | 年間契約のみ ※ご契約は20IDからとなっております |
Schooの新入社員研修の特長は、ビジネスマナーからマインドセット、ロジカルシンキングやExcelまで、新入社員に求められるスキルに関する幅広いコンテンツが充実しているという点にあります。また、営業基礎やマーケティング基礎のような授業も揃っており、現場に配属されてからの研修や自律学習という側面でも活用できるという点も特長です。
また、Schooはeラーニングによる研修受講となるので、社員1人ひとりが好きな時間や場所、タイミングで研修を受講することができるので、リモートワークを導入している企業や多拠点展開している企業におすすめです。
大企業から中小企業まで4,000社以上が導入

Schoo for Businessは、大企業から中小企業まで4,000社以上に導入いただいております。利用用途も各社さまざまで、階層別研修やDX研修としての利用もあれば、自律学習としての利用もあり、キャリア開発の目的で導入いただくこともあります。
05まとめ
新入社員向けの研修には、すべての新入社員に向けて行うものと、部署・職種ごとに行うべき実務的な研修があります。また研修を内製で研修を設計していくか、外注で行うのかを決める必要があるでしょう。いずれの場合も、準備期間を相当に設ける必要があり、目的の設定や方法などをしておかなければ、研修に費やす時間やコストが無駄になってしまう可能性があります。また行った研修を活かすため、事前に受講者に対して目的や目標を共有しておくことで、研修後の目標達成度に期待が持てるかもしれません。そして研修報告書を提出してもらうことで、研修内容の振り返りになり、研修を十分に活かして実務に進めます。