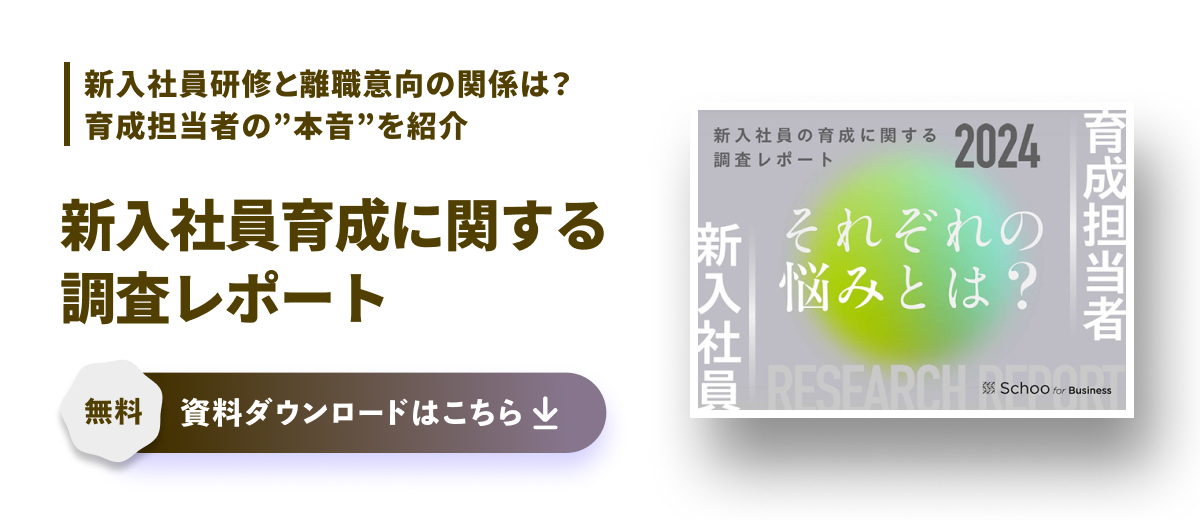新入社員にありがちな問題行動に対する対処方法と具体的なフォローの仕方を紹介

本記事では、令和時代における新入社員の特徴を踏まえながら、新入社員にありがちな問題行動に対する対処法と具体的なフォローの仕方について解説していきます。これから新入社員を自社に迎える企業や、研修を考えている企業は参考にしてください。
- 01.最近の新入社員の傾向とは
- 02.新入社員の問題行動あるある10選と対処方法
- 03.問題のある新入社員への対処方法とは
- 04.新入社員をフォローすべき理由とは
- 05.新入社員の具体的なフォローのポイントとは
- 06.まとめ
01最近の新入社員の傾向とは
教育や時代の変化により、最近の新入社員は自分の内的世界にとどまる人が多いことが特徴に挙げられます。ここでは、今どきの新入社員によくみられる傾向について紹介します。また、研修を考えている方は、こちらの傾向をもとに新入社員研修のテーマを決めると有効です。
受け身の姿勢
いまどきの新入社員は、受け身の姿勢が強く、言われた以上のことはしない、という傾向があります。主体性や積極性に欠けているパターンが多く、指示待ちの状態がよくみられます。
失敗をおそれる
他の世代と比べて他人からの評価を過剰に気にする人が多く、失敗を過度におそる傾向にあります。決して能力が低いわけではありませんが、失敗を恐れるあまり自主的にブレーキをかけてしまうことが多々見受けられます。
仕事よりプライベート
仕事よりもプライベートを重視する若者が増加傾向にあります。働くことの目的を、プライベートの時間を充実させるためと考え、将来について悲観的になるよりも、自分のやりたいことを大切にして人生を楽しみたいという気持ちが伺えます。
02新入社員の問題行動あるある10選と対処方法
新入社員にありがちな問題行動とは、どのようなものがあるのでしょうか?ここではよくある問題行動を10個紹介します。新入社員あるあるな問題行動を是正していくことが、先輩社員の役割となるため、ぜひ参考にしてください。
身だしなみが悪い
学生生活を終えたばかりの新入社員は、社会人にとってのマナーとされている身だしなみについてきちんと理解ができていないことが少なくありません。
対処法
身だしなみに注意を払わない新入社員に対して、上司や人事部門は会社の規定に従うように促す必要があるでしょう。身だしなみに関するワークショップを行うことで、身だしなみの改善につながる可能性があります。
挨拶ができない
メールやSNSが当たり前の時代に育った世代のため、対面間でのコミュニケーション能力が低いこともしばしば見受けられます。また前述した通り、受け身体制が多い世代でもあるため自分から挨拶を積極的に行えないといった課題も感じられます。
対処法
挨拶の重要性を理解できない新入社員には、挨拶を習慣化させるような取り組みが必要です。実践の機会を与えたり、口頭で伝えるなど習慣として身につくまで伴走しましょう。
敬語が使えない
学生時代は、親や友人といった親しい間柄の人とだけ付き合うという選択が可能です。そのため目上の人と接する機会が少なく、正しい接し方や、敬語が身についていない場合があります。
対処法
敬語の使用に慣れていない新入社員には、敬語のルールや実践を教え、練習の機会を提供するトレーニングが必要です。またビジネスマナー研修を通して敬語の使い方を学ぶのも有効的です。
理由なしに休む
学生時代は授業を欠席しても強く咎められることがあまりないため、学生気分が抜けきらないうちは、学校を休むことと同じ感覚で理由なく仕事を休んでしまうことも少なくないです。
対処法
新入社員には出勤規則と休暇申請の手順を教育し、休暇の理由がある場合には事前に連絡を取るよう促しましょう。透明性とコミュニケーションを重視し、問題を予防しましょう。
会社の備品を私物化する
会社の物と私物の区別がきちんとついてないことから、会社の備品であるペンやノートを持ち出してしまったり、配布されたケータイやパソコンなどを私用で利用してしまったりすることがあります。
対処法
備品の私物化に対処するために、社内での備品の使用ポリシーやガイドラインを明確に伝えることが重要です。また、備品の管理と利用に関するトレーニングを提供し、適切な利用を促進します。
仕事中にSNSをする
今どきの新入社員は、小さい頃からスマホを使ってきた人が多いと考えられます。そのため、会社でも仕事中にスマホをいじることに抵抗がないことが多く、中には悪気なく使ってしまう人もいます。
対処法
SNSの利用に制限を設け、仕事中の適切な利用を奨励するポリシーを策定します。新入社員には会社のSNSポリシーを教育し、仕事に集中する重要性を説明しましょう。同時に、定期的な休憩時間を設けてSNS利用を認めることで、適切なバランスを取りましょう。
アドバイスを受け入れない
自分の意見やアイデアを優先し、他人の意見や経験を軽視することががあります。自分の方法が最善だと信じ、他の意見に対して開かれていないため、協力やチームワークが妨げられます。アドバイスを受け入れないことで成長の機会を逃し、職場での信頼性を失う可能性があります。対処法
自己主張が激しい
自分の意見や立場を強調しすぎることで議論や衝突を引き起こすことがあります。適切なタイミングやコンテクストでの自己主張は重要ですが、過度な自己主張は協力関係を損なう可能性があります。
対処法
自己主張が激しい新入社員には、適切なコミュニケーションスキルとチームプレイの重要性を教え、過度な自己主張が対人関係に及ぼす悪影響を説明します。また、チームでの協力プロジェクトやチームビルディング活動を通じて協力と柔軟性を育む支援を行います。チームビルディング研修なども有効的です。
すぐに落ち込んでしまう
この傾向の新入社員は、プレッシャーや失敗に対して敏感で、すぐに落ち込むことがあります。彼らはストレス耐性が低く、課題に対するポジティブなアプローチを欠いているかもしれません。
対処法
新入社員のストレスや落ち込みに対処するために、メンタルヘルス研修の導入が有効的です。心理的なストレス管理方法や効果的な問題解決スキルを教育し、ストレスの適切な処理をサポートします。また1on1の時間をとってメンタルケアを行うことも重要です。
報連相ができない
情報共有やコミュニケーションの欠如により、職場での混乱や誤解を招く可能性があります。プロジェクトの進行状況や問題点を適切に伝えず、チームの協力関係に支障をきたすことがあります。
対処法
報連相を身につけるためには、習得と実践が重要になります。まずはコミュニケーション研修によって報連相の基本的な原則やスキルを教育しましょう。効果的なコミュニケーションのテクニックやコミュニケーションスキルの向上に役立つ内容が望ましいです。また新入社員の報連相のスキルを定期的に評価し、フィードバックを提供します。改善の余地があれば、具体的なアドバイスとサポートを提供して成長を促進します。
03問題のある新入社員への対処方法とは
いくら新入社員側に問題があったとしても対応を誤ってしまうと、訴訟問題に発展するリスクがあるため、適切な対処を行うことが大切です。今回は、問題のある新入社員への対処法を詳しく解説します。
意図が伝わっているか確認する
認識違いを防ぐためにも、話した内容の意図が伝わっているか、きちんと解釈してもらえているか確認してください。「伝えたつもり」状態を事前に防ぐことがトラブル防止につながります。
定期的に1on1ミーティングなどの機会を設ける
1on1ミーティングを実施し、コミニュケーションの機会を積極的に設けることで部下の育成や成長支援ができます。新入社員にとっても、相談や評価をタイムリーに受け取ることができるといったメリットがあります。
コミュニケーションを密にする
コミュニケーションを密にとり、不安やストレスになりがちな要因を取り除いてあげる工夫が必要です。受け身体制な人が多い世代でもあるので、こちらから歩み寄り、話しやすい雰囲気作りが必要です。
手本を見せる
新入社員は日々の上司の仕事ぶりをよく見ています。口やマニュアルを用いて指導を行うよりも、まずは手本を見せて真似してもらうことが新入社員の教育に一番効果的かつ効率的です。
良いところは褒めつつも丁寧に教える
新入社員は、当然のことながら、担当業務はもちろん、ビジネスマナーや社会人としての正しい振る舞いについても未習得の状態にあります。丁寧な指導とあわせて順調に成長していることをフィードバックしてあげることが大切です。
マナーやルールを教える
社会人として社会生活を営む上では、マナーやルールをきちんと守ることが非常に重要になってきます。学生時代は良しとされてきた部分も、社会に出た後は順守してもらわなければならないことを認識してもらいましょう。
情報セキュリティの重要性を教える
さまざまなデバイスやWebサービスの普及により、個人情報の漏洩や不正ウイルスへの感染といったトラブルが近年問題視されています。「知らなかった」では済まされない大きなトラブルへと発展するおそれもあるため、情報セキュリティ教育はしっかりと行いましょう。
04新入社員をフォローすべき理由とは
新入社員をフォローする理由として、早期離職の防止や職場環境を良好にするため、早期に戦力化させるため、の3つが挙げられます。それぞれどういうことか詳しく解説します。
早期離職の防止と経費削減
マイナビが実施した調査によると、人員の採用にはひとりあたり約50万円の経費が発生しています。入社後に研修やセミナーなどを行えばその分金額は上がります。せっかくお金をかけて採用活動を行っても、すぐに退職されてしまってはコストが無駄になってしまいます。その意味でも新入社員への的確なフォローは、必要不可欠だといえます。
職場環境が良くなる
離職率が高い企業は、採用や教育をする側が、「新人社員何かあったらすぐに辞める」と教育やマネジメントに対するモチベーションがもともと低い傾向にあります。 良好な人間関係を構築する努力も怠りがちのため、誰もが職場を大切にしない雰囲気が蔓延してしまいます。 教育を行う側は、新入社員へのフォローをしっかり行うことで組織の生産性や職場環境にも大きな影響を与えます。
早期戦力化を目指す
IT化・グローバル化が進んだことで、より優秀な人材を育てて上を目指さなければ会社も生き残れない時代になってきました。 若手社員をはやく戦力化するために注力することが、のちに企業の成長スピードや経営戦略に繋つなっていきます。
05新入社員の具体的なフォローのポイントとは
新入社員は、社会人として右も左もわからない状態であるため、適時適切なフォローをしてあげなければなりません。新入社員への具体的なフォローのポイントは以下の通りです。
新入社員研修にビジネスマナーのカリキュラムを組み込む
新入社員研修の内容としてビジネスマナーは外せません。学生を卒業したばかりの彼らに社会人の基礎となるビジネスマナーを覚えさせることで、学生と社会人の違いを改めて認識させることができます。また、組織や社会とどのように関わっていくべきか学んでもらうきっかけとなります。
Schooのビジネスマナー研修パッケージ
-
新社会人のためのビジネスマナーの基本を学ぶカリキュラムです。第一印象の磨き方(身だしなみ・挨拶・敬語)や、社内マナー(ホウレンソウ・名刺交換・電話応対など)について解説しています。
-
テレワークの普及が進む中、必要性が増しているのがテレワークマナーについての研修です。この研修パッケージでは、テレワークならではのマナーやデジタルコミュニケーション力について学ぶことができます。
-
グローバルマナーについて学べる研修パッケージです。海外の人と関係を築く上でのビジネスマナーやコミュニケーション方法、メールの書き方などを学ぶことができます。
フォローアップ面談を行う
フォローアップ面談を定期的に行うことで、新入社員の現状や思い、上司やチームメンバーとのコミュニケーションについても確認できます。ヒアリングシートを元に個別に面談を行うことで、業務や給与・勤務状況など処遇に関する内容について、新入社員の本音を聞き出すことが可能です。
メンター制度を取り入れる
最近では新入社員の育成や早期離職防止を目的として、多くの企業でメンター制度を導入しています。メンター制度は、社会に出たばかりで業務内外でさまざまな悩みを抱えがちな新入社員に相談しやすい環境を作る非常に有効な手法です。 担当メンターはOJTを行う担当者とは別の担当者を設けることが望ましいです。職場でのリアルな悩みを相談しやすく、仕事や将来についての視野が拡大する効果が期待できます。
リモート勤務に対する悩みや不安を取り除く
リモート勤務は、不明点があってもその場ですぐに上司や先輩に相談できる環境ではないため、悩みや不安を抱える新入社員も多いようです。事前に、Zoomなどの会議ツールの使い方や進行方法を教えておき、チャットツールを活用しリアルタイムで確認できる体制を整えるなどの工夫が必要です。
即戦力となる新入社員を育成
・社会人基礎力をきちんと身につけられる
・現場に即した実践的なスキルアップも可能
スクーの資料をダウンロードする
■資料内容抜粋
・大人たちが学び続ける「Schoo for Business」とは?
・研修への活用方法
・自己啓発への活用方法 など

06まとめ
この記事では、最近の新入社員の傾向や、対応法について紹介してきました。相手を年齢で決めつけたり、理解できないからと締め出してしまうことは、会社にとっての資源となる貴重な人材を手放してしまうことになりかねません。 人材教育という観点では、彼らが、自分たちと違う時代に生まれ育ち、異なる価値観や考え方を持っていることを理解した上で、上手に育成していくことが重要です。
▼【無料】若手の離職を止めるには?〜多様な個性を重視するインターネット的な会社の作り方〜|ウェビナー見逃し配信中

Z世代の自律型組織開発法をテーマにしたウェビナーのアーカイブです。将来の会社の成長を担う若手世代。「すぐに離職してしまう」「モチベーションの管理方法がわからない」など、Z世代を含む若手の扱いに対して課題を抱えている人事責任者の悩みに対し、若手社員の成長を促進する組織作りについて深掘ります。
-
登壇者:高木 一史 様サイボウズ人事本部 兼 チームワーク総研所属
東京大学教育学部卒業後、2016年トヨタ自動車株式会社に新卒入社。人事部にて労務(国内給与)、全社コミュニケーション促進施策の企画・運用を経験後、2019年サイボウズ株式会社に入社。主に人事制度、研修の企画・運用を担当し、そこで得た知見をチームワーク総研で発信している。