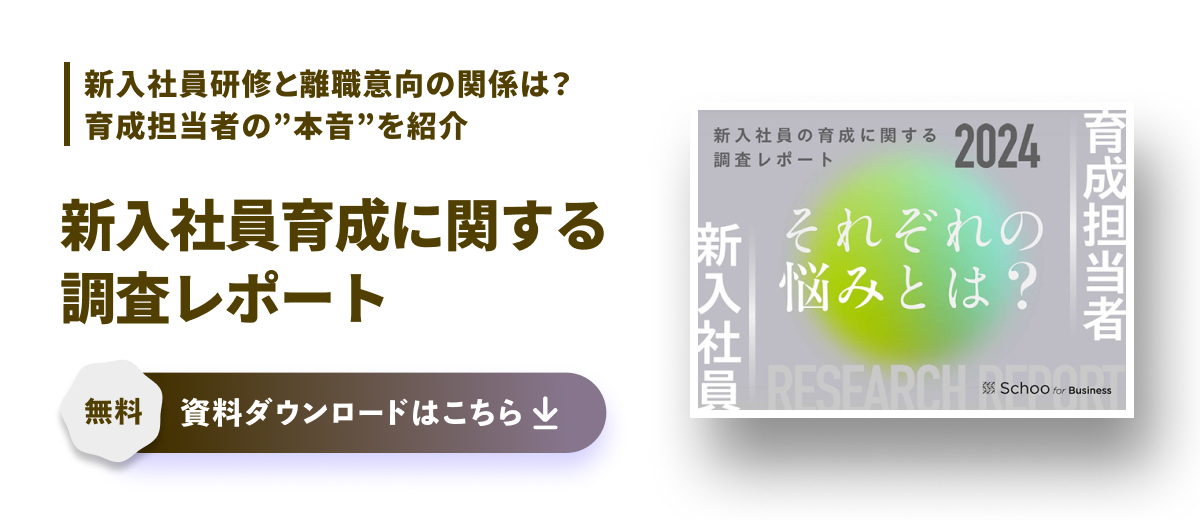成果と成長を左右する「マインドセット」とは?個人と組織で考える基本と実践

マインドセットとは、個人が無意識に持つ思考や行動のパターンを指します。この考え方は、ビジネスにおける成果や組織文化にも深く関わっています。本記事ではマインドセットの定義と重要性を解説し、成長型マインドセットを育むための組織的な変革手法を具体的に紹介します。
01マインドセットとは?
マインドセットとは、人が無意識のうちに持っている「考え方の前提」や「物事の捉え方の癖」を指します。仕事への向き合い方や学習姿勢、困難に直面したときの行動選択に大きな影響を与えるため、近年は人材育成や組織開発の分野でも重要な概念として注目されています。本章では、マインドセットの基本的な意味と、ビジネスで語られる理由を整理します。
マインドセットの基本的な意味
マインドセット(mindset)は、直訳すると「心のあり方」「思考の枠組み」を意味し、心理学では個人が無意識に持つ思考や行動のパターンを指す言葉として使われてきました。人は過去の経験や教育、成功・失敗体験、周囲からの評価などを通じて、物事をどのように捉え、どう行動するかの基準を形成します。この基準となる考え方がマインドセットであり、判断のスピードや挑戦への姿勢、失敗への向き合い方などに影響を及ぼします。重要なのは、マインドセットは生まれつき固定されたものではなく、後天的に形成され、意識や習慣によって変えていける点です。
マインドとマインドセットの違い
マインドセットは「マインド(心構え)」と混同されがちですが、両者には違いがあります。マインドがその場その場の意識状態や感情、気持ちの持ちようを指すのに対し、マインドセットはより深い階層にある「考え方の癖」や「前提となる信念」を意味します。例えば、「今回は頑張ろう」という気持ちはマインドですが、「努力すれば成長できる」「失敗は学びになる」といった考え方はマインドセットにあたります。マインドは一時的に変わりやすい一方、マインドセットは長期的に行動や意思決定へ影響を与えるため、人材育成や組織変革ではこちらが重視されるのです。
ビジネスでマインドセットが注目される理由
ビジネスの現場でマインドセットが注目される理由は、成果や成長がスキルや知識だけで決まらないことが明らかになってきたためです。同じ能力を持っていても、挑戦を避ける人と前向きに学び続ける人とでは、長期的な成果に差が生まれます。その違いを生む要因が、マインドセットです。特に変化の激しい時代では、過去の成功体験に固執せず、新しい学びや役割に適応できるかどうかが重要になります。その前提となる考え方を整えることが、人材の成長や組織の競争力を左右するため、マインドセットはビジネスにおける重要テーマとして語られています。
02マインドセットが重要視される理由
マインドセットが注目されている背景には、知識やスキルそのものよりも、それらを「どう使うか」「どう学び続けるか」が成果や成長を左右する時代になっていることがあります。同じ環境に置かれても、考え方の前提によって行動や結果に差が生まれるため、マインドセットは個人の成長だけでなく、組織の競争力にも影響する重要な要素として捉えられています。
判断や行動の前提となり、成果に直結するため
マインドセットは、日々の判断や行動の「前提」となる考え方です。新しい業務や課題に直面したとき、それを挑戦と捉えるか、避けるべきリスクと捉えるかは、マインドセットによって大きく異なります。その結果、行動量や学習の質、周囲との関わり方に差が生まれ、長期的な成果にも影響を及ぼします。スキルや知識は同じでも、マインドセット次第で活かし方が変わるため、成果を安定的に生み出す土台として重要視されています。
学習や成長を継続できるかを左右するため
変化の多い環境では、一度身につけたスキルだけで成果を出し続けることは難しくなっています。その中で重要になるのが、学び続ける姿勢を保てるかどうかです。マインドセットが成長志向であれば、失敗や壁に直面しても学びの機会と捉え、改善を重ねていくことができます。一方、考え方が固定的な場合、うまくいかない経験が学習意欲の低下につながりやすくなります。この差が、成長の継続性を大きく左右します。
変化の激しい時代に適応する力の土台になるため
市場環境や技術の変化が激しい現代では、過去の成功体験や従来のやり方が通用しなくなる場面も少なくありません。そうした状況で求められるのは、変化を前向きに受け止め、自らを更新していく姿勢です。マインドセットは、その変化対応力の土台となります。新しい役割やスキルに向き合う際の心理的ハードルを下げ、柔軟に行動を選択できるかどうかが、個人や組織の持続的な成長を左右します。
03心理学におけるマインドセットの種類
マインドセットとは、物事の捉え方や考え方の前提となる思考の枠組みを指します。心理学の分野では、学習や成長への向き合い方を大きく左右するものとして、「成長型マインドセット」と「固定型マインドセット」の2種類が整理されています。ここではそれぞれの特徴を比較しながら、どのような違いが行動や結果に影響を与えるのかを見ていきます。
停滞型マインドセット(fixed mindset)
硬直・固定マインドセットとも呼ばれ、「能力や才能は生まれつき決まっており、大きくは変わらない」という前提で物事を捉える考え方です。この前提が強いと、結果がそのまま自分の評価だと感じやすくなります。そのため、新しい挑戦や難易度の高い課題に対して慎重になり、失敗を避ける行動を選びやすくなる傾向があります。
停滞型の特徴
停滞型マインドセットを持つ人は、失敗を「能力不足の証明」と捉えやすいため、挑戦そのものを避ける傾向があります。また、批判や指摘を受けた際、それが改善のための助言であっても、否定されたと感じて防御的に反応しやすくなります。その結果、フィードバックを活かす機会が減り、行動の修正が起こりにくくなります。さらに、他者の成功を自分との比較で捉えてしまうことで、焦りや不安が強まり、学習や成長が停滞しやすくなる点も特徴です。
成長型マインドセット(growth mindset)
成長型マインドセットとは、「能力やスキルは経験や努力によって伸ばすことができる」という前提で物事を捉える考え方です。この前提を持つ人は、現時点での結果を最終評価とは考えず、学習や試行錯誤の途中段階として位置づけます。そのため、新しい挑戦や未知の課題に直面しても、成長の機会として受け止めやすく、行動を止めにくいという特徴があります。
成長型の特徴
成長型マインドセットを持つ人は、挑戦そのものを前向きに捉える傾向があります。困難な課題に直面しても避けるのではなく、「経験値を高める機会」として向き合います。また、努力は無駄にならず、スキルの習熟につながるものだと考えるため、失敗を過度に恐れません。失敗が起きた場合も、自分の能力を否定する材料ではなく、改善点を知るための情報として扱います。さらに、他者の成功やフィードバックに対しても防御的にならず、「学べる要素は何か」という視点で受け取るため、行動改善につながりやすい点が特徴です。
なぜリスキリングでは成長型が重要なのか
リスキリングは、正解があらかじめ決まっていない分野に取り組むケースが多く、短期間で成果が出るとは限りません。そのため、「今できていない=向いていない」と捉える固定型マインドセットでは、途中で行動が止まりやすくなります。一方、成長型マインドセットは、不完全な状態を前提として学びを進める考え方です。不確実性の高い環境下でも試行錯誤を続けやすく、結果として学習の継続やスキル獲得につながりやすい点で、リスキリングとの相性が良いといえます。
04リスキリングにおけるマインドセットの考え方
リスキリングは個人の意欲や努力だけで完結するものではありません。リスキリングの本質は「組織の戦略を実現するために、必要な人材を育成する取り組み」にあります。そのため、個人のマインドセット変革と同時に、組織側の考え方や制度設計が極めて重要です。になります。本章では、Schoo講座「リスキリングのはじめ方」で紹介の内容を参考にリスキリングを個人任せにしないために、組織・ビジネスの視点から押さえるべきポイントを整理します。
▶︎参考:Mindset : The New Psychology of Success
▶研修・人事育成担当者限定!『リスキリングのはじめ方』を無料で視聴する
リスキリングは「個人任せ」ではなく組織の責任
リスキリングは「組織が従業員を再スキル化する」ことを意味し、主語はあくまで組織にあります。個人が自発的に学ぶ「学び直し」とは異なり、新しい事業戦略や変化する業務に対応するために、企業が計画的に人材を育てる取り組みです。そのため、学習の時間確保や機会提供、学んだスキルを活かす場の用意まで含めて、組織が責任を持つ必要があります。マインドセットの変革も、個人の意識改革だけに委ねるべきではありません。
リカレント教育・アップスキリングとの違い
リスキリングは、リカレント教育やアップスキリングと混同されやすい概念です。授業で紹介していたように、リカレント教育は個人の関心を起点とした生涯学習であり、費用や時間の負担は基本的に個人が担います。一方アップスキリングは、現在の職種の延長線上でスキルを高める取り組みです。これに対してリスキリングは、組織の戦略転換や事業変化を前提に、新しい職種や役割への移行を見据えた人材育成を指します。ここを混同すると、制度設計や期待値にズレが生じやすくなります。
リーダー・マネージャーに求められるマインドセット
授業でも強調しているように、リスキリングは従業員本人だけでなく、リーダーやマネージャーの責任でもあります。Harvard Business Reviewでも、リスキリングは経営戦略上の必須事項であり、現場を率いる管理職が主体的に関与すべきテーマだと整理されています。短期的な成果だけを重視する姿勢では、学習の時間や挑戦の余地が奪われてしまいます。中長期の視点で人材を育てる意識を持つことが、組織全体のマインドセット転換につながります。
個人のキャリアと組織戦略をどう揃えるか
リスキリングが機能するかどうかは、従業員個人のキャリア志向と組織の方向性がどれだけ一致しているかに大きく左右されます。どれほど制度を整えても、本人の将来像と結びつかないリスキリングは「やらされ感」を生み、定着しません。重要なのは、どのスキルを身につけると、どのような役割やキャリアにつながるのかを具体的に示すことです。個人の納得感を高める設計が、学習の継続と成果創出を支えます。
マインドセット変革を支える制度・環境づくり
マインドセットは意識だけで変わるものではなく、日々の行動を後押しする制度や環境によって定着します。就業時間内での学習機会の確保、挑戦を評価する仕組み、失敗を許容する文化がなければ、成長型マインドセットは育ちにくくなります。逆に、学びと実践を往復できる環境が整えば、個人の意識変化と組織成果は連動しやすくなります。リスキリングを成功させるためには、マインドセットと制度をセットで考える視点が不可欠です。
05個人のマインドセットを変える方法
マインドセットは生まれつき固定されているものではなく、日々の意識や行動の積み重ねによって変えていくことができます。Schoo講座「リスキリングのはじめ方」で紹介していたように、リスキリングにおいて重要なのは、強い意志や才能よりも「どのような前提で学びに向き合うか」です。本章では、前章に続き、Schoo講座「リスキリングのはじめ方」の内容を参考に個人がリスキリングを進める際に直面しやすい壁と、それを乗り越えるための具体的な考え方を整理します。
▶︎参考:Mindset : The New Psychology of Success
▶研修・人事育成担当者限定!『リスキリングのはじめ方』を無料で視聴する
リスキリング開始時に立ちはだかる3つの壁
授業で紹介していたように、リスキリングを始める際には多くの人が共通して三つの壁に直面します。一つ目は「認識の壁」で、外部環境が変化していてもリスキリングの必要性を自分事として捉えられない状態です。二つ目は「周囲の壁」で、就業時間内に学習が認められない、理解者がいないなど、環境要因が行動を妨げます。三つ目は「継続の壁」で、意欲はあっても習慣化できず途中で止まってしまうことです。これらは個人の能力不足ではなく、考え方と仕組みの問題として整理することが重要だとされています。
7つのマインドセット
3つの壁を乗り越えるための考え方として、成長型マインドセットに基づく7つの心構えが紹介されていました。
- ①まずやってみる(正解は後で考える)
- ②6割理解で進む(完璧主義を手放す)
- ③コンフォートゾーンを出る(健全な危機意識)
- ④いつでも軌道修正できる
- ⑤繰り返しを恐れない(忘れたらまた学べばいい)
- ⑥すぐ成果が出なくても焦らない(レジリエンス)
- ⑦発展途上の自分に自信を持つ
これらに共通しているのは、「完璧な理解や即時の成果を求めない」という姿勢です。まず行動すること、理解が6割の状態でも前に進むこと、繰り返しを前提に学ぶことなど、学習を止めないための考え方が整理されています。これらは“独立したノウハウ”ではなくセットで考えるとスムーズなため、以下にて詳しく解説していきます。
まずやってみる・6割理解で進む
リスキリングでは「正しく理解してから動く」よりも、「動きながら理解を深める」姿勢が重要とされています。変化のスピードが速い分野では、すべてを理解してから行動しようとすると、学びそのものが進みません。6割程度の理解であっても実践に移し、足りない部分は後から補うことで、学習と行動の循環が生まれます。完璧主義を手放すことは、不確実な環境で前進するための現実的な選択だといえます。
コンフォートゾーンを出る・軌道修正を恐れない
授業では、安定した状態にとどまり続けることが、結果的にリスクになる可能性についても触れられていました。慣れた業務や得意な領域から一歩外に出ることで、新しい学びが始まります。また、取り組んでみた結果「合わない」と感じた場合に、方向転換することも否定されるべきではありません。最初の選択に固執せず、状況に応じて軌道修正する柔軟さが、リスキリングを継続するうえで重要な要素になります。
繰り返し・焦らない・発展途上の自分に自信を持つ
新しい分野の学習では、忘れることやうまくいかないことが頻繁に起こります。授業で紹介していたように、リスキリングでは「忘れたらもう一度学べばよい」という前提に立つことが大切です。また、短期間で成果が出ないからといって焦る必要はありません。成長の途中にある自分を否定せず、「学び続けている状態そのもの」に価値を見出すことが、継続と自己効力感の維持につながります。
マインドセット転換の実例
授業では、後藤氏自身の経験として、40歳までデジタル分野の経験がなかったにもかかわらず、業務を通じてリスキリングを進めてきた事例が紹介されていました。その過程で大きな転機となったのが、「知らないことは恥ではない」という認識への切り替えです。他者と比較することをやめ、学びの途中にある自分を受け入れたことで、新しい分野への挑戦が継続できるようになったと語られています。この実体験は、マインドセットが行動に直結することを示す具体例といえます。
06ビジネスにおけるマインドセットの種類
心理学で語られるマインドセットの概念は、ビジネスの現場では「成果の出方」や「成長スピード」の違いとして表れます。マインドセットは個人の内面だけの問題ではなく、役割や立場、さらには組織の仕組みや文化とも密接に結びついています。ここでは、ビジネスにおけるマインドセットを「個人」と「組織・企業」という2つの視点から整理し、どのような違いが生まれるのかを見ていきます。
個人のマインドセット
ビジネスにおける個人のマインドセットは、職種や能力以上に「どの立場にいるか」によって求められる形が変わります。人は置かれた環境や期待される役割の中で思考や行動の癖を形成していくため、成長段階ごとにマインドセットのアップデートが必要になります。
新入社員
新入社員のフェーズでは、「正解を教えてもらう姿勢」から「学びを自分事として捉える姿勢」への転換が重要になります。学習を受け身で捉えている状態では成長は頭打ちになります。分からないことを前提とし、質問やフィードバックを学習機会として受け取れるかどうかが、その後の成長を大きく左右します。失敗を避けるよりも、早く試し、早く修正するというマインドセットが求められる段階です。
若手社員
業務に慣れ始めた若手社員は、「こなす」から「成果を出す」段階へ移行します。このフェーズでは、努力や学習を単なるインプットで終わらせず、成果につなげる視点が不可欠です。うまくいかなかった経験を能力不足と捉えるのではなく、改善材料として扱えるかが分かれ道になります。挑戦と振り返りを繰り返す姿勢が、次のステージへの土台になります。
中堅社員
中堅社員は、自身の成果に加えて、周囲への影響力が求められる立場です。個人の学びや挑戦が組織全体に波及しないケースも少なくありません。自分の成功体験に固執せず、後輩やチームの成長を促す視点を持てるかどうかが、組織の停滞を防ぐ鍵になります。
管理職・リーダー
管理職やリーダーには、個人の成長型マインドセットを組織に広げる役割が求められます。学習や挑戦は「許されるかどうか」が重要な要素です。挑戦を評価しない言動や、失敗を避ける空気は、部下のマインドセットを固定化させます。自ら学び続ける姿勢を示し、学習や挑戦を前提とした意思決定を行うことが、組織全体のマインドセットに直結します。
組織や企業のマインドセット
マインドセットは個人だけでなく、組織や企業にも存在します。個人任せの学びには限界があり、組織の前提となる価値観や仕組みが、社員の思考や行動を大きく左右します。
事業特性による違い
扱う商品やサービス、競争環境によって、組織が重視するマインドセットは異なります。変化の激しい領域では挑戦やスピードが重視されやすく、一方で安定性が求められる事業では慎重さが評価されやすい傾向があります。どちらが良い悪いではなく、事業特性に応じた前提が、社員の行動基準を形づくっている点を理解することが重要です。
理念・ビジョンの影響
経営理念やビジョンは、組織がどのようなマインドセットを良しとするかを示す指針です。組織がどこへ向かうのかが曖昧な場合、学びや挑戦は個人の努力に委ねられがちになります。理念として学習や成長が位置づけられているかどうかは、学びが定着するかを左右します。
企業の史実
企業がどのような歴史を辿ってきたかで組織のマインドセットは異なります。たとえば、過去に大きなインシデントがあった企業は、過去の出来事を踏まえて社内規制やリスク対策が整っていたり、会社としてもリスクはあまり取らないという前提が根づいているかもしれません。一方で歴史の浅い企業であれば、挑戦的で一定のリスクを許容する前提を持っているなど、過去の出来事が組織の行動基準に影響を及ぼします。
07組織のマインドセットを変える方法
組織のマインドセットを変える方法は、以下の通りです。
- ・MVVに組み込む
- ・経営から会社が求めるマインドセットを発信する
- ・評価制度を刷新する
- ・昇格の基準に反映する
- ・採用段階で見極める
前章で整理したように、ビジネスにおけるマインドセットは個人の意識だけで完結するものではなく、組織の制度や文化と強く結びついています。授業で語られていた通り、リスキリングや成長型マインドセットを個人任せにしてしまうと、認識の壁や周囲の壁、継続の壁に直面しやすくなります。ここでは、マインドセットを「仕組みとして」組織に定着させるための具体的なアプローチを整理します。
1:MVVに組み込む
組織のマインドセットを変える第一歩は、MVVにその価値観を明確に位置づけることです。学びや挑戦が理念として語られていない組織では、社員は「やってもいいのか分からない」状態に陥りやすくなります。マインドセットを言語化し、組織として何を大切にするのかを明示することで、社員は判断に迷ったときの基準を持つことができます。理念に組み込むことは、意識改革ではなく「前提条件」を変える行為だと言えるでしょう。
2:経営層から一貫したメッセージを発信する
マインドセットの変革において、経営層の姿勢は極めて重要です。リスキリングは組織の戦略上の必須事項であり、トップがどのような言動を取るかが現場の空気を決定づけます。挑戦を口では奨励しながら、失敗を評価しない姿勢を見せてしまうと、社員のマインドセットはすぐに固定化してしまいます。経営層が自ら学び続ける姿勢を示し、意思決定の場で価値観を繰り返し語ることが、変革の土台になります。
3:評価制度・昇格基準に反映する
どれほど理想的なマインドセットを掲げても、評価制度と結びついていなければ定着は難しくなります。授業で紹介されていたように、人は評価される行動を無意識に選びます。成果だけでなく、挑戦の過程や学習の姿勢を評価に組み込むことで、成長型マインドセットが行動として表れやすくなります。特に昇格基準に反映することは、「次のリーダーにどのようなマインドセットを求めるのか」を明確にする強いメッセージになります。
4:学習・挑戦が許容される環境をつくる
業務が忙しく、学ぶ時間が確保されていなかったり、学習が業務外の努力として扱われていたりすると、リスキリングは続きません。学習や挑戦を業務の延長として位置づけ、時間や機会を制度として確保することで、マインドセットは初めて行動に変わります。組織のマインドセットを変えるために、安心して試し、修正できる環境づくりが不可欠です。
5:採用・配置の段階で見極める
組織のマインドセットは、採用や配置によっても強化・固定化されます。失敗や学習をどう捉えているかは、過去の経験や語り方に表れます。採用時の質問設計や、配置の判断にマインドセットの視点を取り入れることで、組織全体の前提を揃えやすくなります。入社後に変えることが難しいからこそ、入口の設計は重要なポイントです。
08成長型マインドセットへの変革に成功した企業事例
成長型マインドセットへの変革に成功した企業は、以下の通りです。
- 1:マイクロソフト
- 2:テルモ株式会社
- 3:テレノール
- 4:Cigna
- 5:HP Inc.
成長型マインドセットを文化として根づかせた企業は、トップの姿勢、制度の刷新、従業員との対話、評価の見直しなど、複数の角度から一貫した取り組みを実践しています。本章では、変革に成功した5社の具体的な事例を紹介します。
1:マイクロソフト
2014年、サティア・ナデラ氏がCEOに就任したマイクロソフトは、それまでの「何でも知っている(know-it-all)」文化から「何でも学ぶ(learn-it-all)」文化への転換を図りました。従来の個人競争をやめ、「顧客中心主義」や「One Microsoft」といった協働姿勢を重視する企業文化へと再定義しています。ナデラ氏自身が成長型マインドセットの体現者となり、行動指針の言語化や評価制度への反映を進めるなど、意識変革を主導しました。その結果、クラウド事業を中心に業績は急回復し、全社的に挑戦と学びを評価する風土が浸透しています。
2:テルモ株式会社
テルモは若手社員の成長と組織活性化を目指し、グロービスと連携して新興人財向け育成プログラム「MIRAI」を導入しました。プログラムでは成長型マインドセットの習得を土台に、リーダーシップや新規事業への挑戦を促進。具体的には「チャレンジ→振り返り→学び」の3ステップを繰り返し、内省や発言の場を意図的に設けています。医療業界の保守的な風土は課題でしたが、経営層の深い関与と部門横断の支援体制により、若手の自発性と挑戦意欲が芽生える環境が整いつつあります。
3:テレノール
ノルウェーの大手通信企業テレノールは、デジタル競争への対応力を高めるため、成長型マインドセットの浸透を全社で推進しました。バッジ形式の社内学習モジュールを展開し、8,500人超がオンラインで学習に参加。「失敗から学ぶ」文化を育むべく、「working red」と呼ばれるコンセプトも導入されています。こうした取り組みにより、上司と部下の対話が活発になり、成果よりもプロセスを重視する評価が根づき始めました。継続的な学習と共有を通じて、硬直的だった企業文化が少しずつ変化しています。
4:Cigna
米国の医療保険大手Cignaでは、組織全体で成長型マインドセットの醸成を目指し、経営層が率先して「長期的な成長」「失敗からの学び」といった価値観を発信。ポスター掲示や社内イベントを活用しながら、理念の可視化と浸透を図りました。また、年1回の評価制度を対話型フィードバックに刷新し、マネージャーとの継続的な対話を促進。これにより従業員エンゲージメントが向上し、職場内の協働意識が高まっています。制度改革への抵抗はありましたが、繰り返しの対話と支援によって意識変革を実現しています。
5:HP Inc.
Hewlett-Packardからの分社後、HP Inc.は成長型マインドセットを中核とした文化変革を進めました。従来のランク付け評価制度を撤廃し、全社員がフィードバックを通じて学べる環境を整備。CHRO主導のもと、経営陣にも改革の必要性を共有し、社内イベントや共通言語の徹底を図りました。その結果、売上は2桁成長を記録し、株価も倍増。エンゲージメントは22%上昇しています。変革への抵抗に対しては、社員参加型の対話と実績の共有によって、柔軟で挑戦を歓迎する職場文化が確立されました。
「研修をしてもその場限り」「社員が受け身で学ばない」を解決!
研修と自己啓発で学び続ける組織を作るスクーの資料をダウンロードする
■資料内容抜粋
・大人たちが学び続ける「Schoo for Business」とは?
・研修への活用方法
・自己啓発への活用方法 など

09学び続ける組織文化への変革を支援|Schoo for Business

オンライン研修/学習サービスのSchoo for Businessでは約9,000本の講座を用意しており、様々な種類の研修に対応しています。また、講座も汎用的なビジネススキルから職種に特化した専門スキルまで幅広く、自己啓発の支援ツールとしても利用いただいております。
研修と自己啓発を掛け合わせることにより、誰かに要求されて学ぶのではなく、自発的に学び、成長していく人材を育成することが可能になります。ここでは、Schoo for Businessの具体的な活用方法と、特徴、さらにはどのようなメリットがあるのかを解説します。
| 受講形式 | オンライン (アーカイブ型) |
| アーカイブ本数 | 9,000本 ※2023年5月時点 |
| 研修管理機能 | あり ※詳細はお問い合わせください |
| 費用 | 1ID/1,500円 ※ID数によりボリュームディスカウントあり |
| 契約形態 | 年間契約のみ ※ご契約は20IDからとなっております |
大企業から中小企業まで幅広く導入

Schoo for Businessは、大企業から中小企業まで幅広く導入いただいております。利用用途も各社さまざまで、階層別研修やDX研修としての利用もあれば、自律学習としての利用もあり、キャリア開発の目的で導入いただくこともあります。
導入事例も掲載しているので、ご興味のあるものがあれば一読いただけますと幸いです。以下から資料請求いただくことで導入事例集もプレゼントしております。そちらも併せて参考にいただけますと幸いです。
Schoo導入企業事例
Schoo for Businessを活用しながら、組織開発・人材開発に取り組んでいる企業の事例を3社紹介いたします。
いずれの企業も、変化の激しい時代に対応するために、社員の主体的な学びや成長を支援したいという想いで、日々取り組まれています。
1.旭化成株式会社

日本を代表する総合化学メーカーの旭化成株式会社は、2022年春に発表した中期経営計画で、HRの方針として「終身成長」を掲げたことを契機に自己啓発に注力し始めました。「終身成長」とは、社員一人ひとりが自分の人生の目的をもち、自律的にキャリアを考えて成長し続けることを意味し、それを会社が支援するという方針を立てたのです。
このような背景を受けて、仲間と学び自らを高めていくための取り組みとして、自社内の学びのプラットフォーム「CLAP(Co-Learning Adventure Place)」を開始しました。自律的なキャリア形成を目指して幅広い分野を学べる学習プラットフォームとしてSchoo for Businessを含めた社内外の学習コンテンツを搭載し、コース化して提供できるツールです。
この取り組みの特筆すべき点は、約2万人の全社員へIDを付与した点にあります。eラーニングを活用した自己啓発は、公募で希望者のみにIDを付与するケースが多いですが、旭化成株式会社は全社員にIDを付与して、誰しもがいつでも自由に学べる環境を整えたのです。希望者だけに留まらず全社員にIDを付与し、会社として社員の成長を支援するという経営やHRの意志を示し、大々的に自己啓発を推奨したことが成功のポイントです。
サントリーホールディングス株式会社

サントリーホールディングス株式会社には、「寺子屋」という社内だけの学びのプラットフォームがあります。寺子屋は全社員がアクセスでき、社員が自発的に開催した勉強会であったり、Schoo for Businessのような外部コンテンツが受講できるプラットフォームとなっています。
この「寺子屋」の特筆すべき点は、社員が自主的に勉強会やイベントを開催し、学びによって社員同士の繋がりを増やしている点にあります。もちろん、「寺子屋」が開始した直後は社員の利用率も低く、愚直にお知らせを出したり、社内で発信力の強い人に登壇してもらう勉強会を人事主導で企画するなど、苦労の連続だったそうです。
コロナを契機に自宅勤務になったことで利用者が伸び始め、次第に自主的なイベントや勉強会の開催が増えていきました。今では、社員による社員のための学びのプラットフォームとしてSUNTORYの人材開発・組織開発を支えている重要な施策の1つとなっています。
株式会社ポーラ

国内有数の化粧品メーカーである株式会社ポーラは、会社の中長期計画を受けて、不足しているスキルや知識が多くあることに気づき、人材育成の強化に踏み切りました。
株式会社ポーラの「人材成長プログラム」では、まずは社員一人ひとりが自分を知り、どうなりたいかのビジョンを描き、その実現に向けて学び、得た能力を活かすという「知る」「描く」「学ぶ」「活かす」の4つのフェーズがあります。この「学ぶ」の部分で、Schoo for Businessを公募の自己啓発施策として活用いただいています。
その結果、「Schooを導入してくれてありがとう」とか「毎日楽しく勉強してるよ」といった声が人事部門に届き、会社の雰囲気も変わってきていると感じ始めていただいております。日頃の業務だけでも手一杯で、なかなか自分の領域を広げられないという課題を感じていた社員が、「Schoo楽しいんだよね」と学んでいたり、上司とのコミュニケーションのきっかけにもなっているとのことです。
10まとめ
組織のマインドセットを変えるには、個人の成長意欲を引き出すだけでなく、それを支える制度や文化の見直しが欠かせません。MVVの再定義や経営陣からの発信、評価・昇格・採用における一貫した姿勢が、行動変容を促す鍵となります。変革に成功した企業に共通するのは、トップが模範を示し、学びと挑戦を尊重する環境を継続的に整備している点です。小さな意識の転換を積み重ねることで、組織全体の文化は変わっていきます。