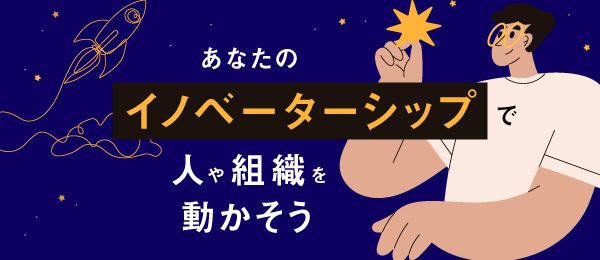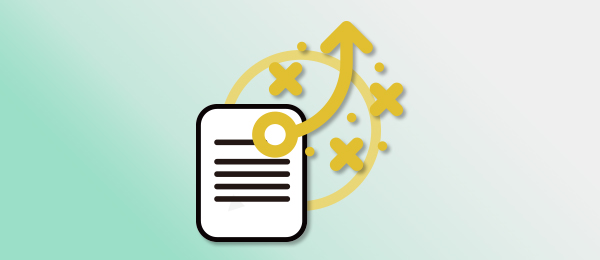部長研修 - 部長の役割から研修のポイントまで解説

部長は企業等の組織における部門の最高責任者として、部門の目標や所属メンバーの成果に対して責任を負う役職です。課長と比較してより経営的判断を求められやすい立場であり、戦略思考や広範囲のマネジメント能力が必要となります。そのため部長に対しても、自己変革を促す計画的な研修と内省支援は重要です。本記事では、このような部長という役職の役割から、部長研修の目的とその効果的な実施ポイントを詳細に解説します。
- 01.部長研修とは
- 02.部長とは
- 03.部長に求められる役割
- 04.部長が身につけるべき能力
- 05.なぜ部長に研修が必要なのか
- 06.部長研修を実施する上でのポイント
- 07.部長研修にはeラーニングが効果的
- 08.部長研修のおすすめ講座
- 09.まとめ
01部長研修とは
部長研修は、課長から部長へ昇格した社員、または既存の部長を対象に、経営視点を持った判断力や組織マネジメント力の強化を目的として実施されます。
その内容は主にリーダーシップの発揮、戦略立案、人材育成、部門間の調整といった実務に直結する内容が中心であり、経営陣と現場の橋渡し役としての役割を果たすための思考力や実行力を体系的に学びます。
02部長とは
部長は企業内で特定の部門、事業、または機能を統括する役職を指します。その組織上の立ち位置は経営層に近い位置にあり、社長や役員の経営判断をサポートする存在とされます。部長には中長期的な経営視点が求められ、企業ビジョン達成に向けた戦略立案や部門目標の牽引を担います。
部長と課長との違い
部長と課長は、企業内での役割と責任範囲が大きく異なります。課長は現場管理職として、経営層や部長が定めた戦略に基づき、少数の部下を直接的にマネジメントし、計画実行と目標達成を担うプレイヤー型の役割を果たすことが多いです。
一方、部長は特定の部門や事業を統括する経営層に近い存在です。複数の課やプロジェクトを束ねて全体をマネジメントするため、課長に比べて組織全体を「間接的に」牽引する形になります。また部長は経営と現場をつなぐハブとして、中長期視野に基づく「経営視点での意思決定」が求められ、部署の全責任を負うことが大きな違いです。
そのため求められる能力としても、課長はピープルマネジメントやプロジェクト遂行力などの重要度が高いことに対して、部長は戦略的思考や財務マネジメントなどの重要性が増します。
03部長に求められる役割
部長に求められる具体的な役割として、組織の中核を担う多面的な役割が求められます。戦略策定から人材育成、部門間調整、意思決定まで幅広い責任を果たし、持続的な組織成長をけん引します。ここではその詳細を解説します。
部門戦略の策定と実行
部長は企業のミッション・ビジョン実現に向けた部門の最高責任者として、部門戦略と戦術の策定と実行を行います。課長が中短期的な計画実行を担うのに対し、部長はより中長期的な視点で外部・内部環境を分析し、部門のあるべき姿を描き、新しい価値創造を目指します。
組織マネジメントと体制構築
部長は基本的に大きな規模の部門を統括することが多いです。経営視点から組織全体の成果を最大化する体制構築者としての役割を担います。目標達成に向けた最適な組織設計やリソース配分を行い、変革を推進する責任があります。課長がメンバーに対して直接的なマネジメントを行うのに対し、部長は課長やリーダーを通じた間接的な働きかけにより、戦略の実行を行います。
課長層の育成と任用
部長には部門の事業推進と目標達成のため、自身の右腕となる課長層を育成し、その能力を最大限に引き出す育成者としての責任もあります。課長層にはプレイヤーとしての能力だけでなく、育成やチームビルディングといったマネジメント能力、リーダーとしてのマインドセットなどさまざまなスキルが求められます。そのため、課長層を育成する部長には、長期的目線かつ戦略的な育成計画と実行が求められます。
部門間連携・調整役
部長は企業全体の成果を最大化するため、他部門との調整役を担います。課長が自課の目標達成に責任を負うのに対し、部長は部門全体の結果に責任を負います。そのため部門戦略の実行に向けては、時に他部門と全社最適を実現するための交渉や調整を行うことが求められます。これは事業を円滑に推進し、組織全体の成果を最大化するために不可欠な役割です。
意思決定と説明責任
部長は部門の意思決定者として、課長層よりもハイリスクで影響範囲の広い判断を迅速に行う責任があります。経営層から示された全社戦略を正しく理解したうえで部門戦略に落とし込み、中長期的な視点かつ広い視野で部門の最終判断を下す役割です。自身の判断が経営に与える影響が大きいため、経営層に対して部門成果やリソース配分について説明責任も負います。
組織文化・風土の形成
部長は複数の課やチームを束ねる立場として、健全な組織文化・風土を形成する役割を担います。課長よりも広い影響力を持つため、自身の言動を通じて共通の価値観を発信し、メンバーが自律的に行動できる環境をソフト・ハード両面から築き上げる必要があります。
「研修をしてもその場限り」「社員が受け身で学ばない」を解決!
研修と自己啓発で学び続ける組織を作るスクーの資料をダウンロードする
■資料内容抜粋
・大人たちが学び続ける「Schoo for Business」とは?
・研修への活用方法
・自己啓発への活用方法 など

04部長が身につけるべき能力
部長に求められる能力は部門戦略の策定・実行を通じて事業を推進することや、組織全体を間接的にマネジメントし、横断的な調整・交渉で全社連携を促す力など多岐に渡ります。ここでは主に必要とされる能力について解説します。
部門戦略の策定力
部長は経営層に近い存在として、経営戦略を部門戦略に落とし込み、部門に与えられた目標を達成することが求められます。そのため、精度の高い部門戦略を策定する力は、部長職にとって非常に重要です。具体的には中期経営計画や外部環境を踏まえ、SWOT・3C分析などの手法を用いて部門の重点戦略を立案し、組織に伝達して実行につなげていきます。部門戦略によって各課や所属社員のアクションが決まるため、部長の戦略策定力が低いと経営目標の達成が困難になります。
組織マネジメント力
部長は比較的大きな規模の組織を統括し、経営視点から成果を最大化する責任があるため、この組織マネジメント力は重要です。組織マネジメントにおける管理対象は、所属人員だけでなく、予算や製品、情報など多岐にわたります。最適な組織設計やリソース配分、部署全体の管理とリスクマネジメント、ハード・ソフト両面からの組織開発を通じて、事業推進と組織統合を推進する必要があるため、育成から財務管理までさまざまなノウハウを要します。
横断的な調整・交渉力
単一部門に留まらず、企業全体の成果を最大化するため、他部門との連携を指揮する立場であり、事業推進には部門間の協力関係構築が不可欠なため、この能力が求められます。実務では、他部署や対外的な顧客・取引先との間で積極的に対話し、Win-Winの関係を築くための交渉力を発揮し、問題解決に貢献します。この力が欠けると、部門間の連携が不足し、全社的な目標達成が阻害され、孤立した部門運営に陥り組織全体の競争力が低下する恐れがあります。
部門を導く意思決定力
経営層に近く、課長よりもハイリスクで影響範囲の広い判断を迅速に行う「意思決定者」の役割を担うため、部長にとって意思決定力は必須のスキルです。VUCAと呼ばれる不確実性の高い現代において、部門戦略を実現するにあたってすべてが計画どおりに進むことはなかなかありません。環境変化や予測出来ていなかった事象にも適切に対処して部門を達成に導くには、スピーディな情報収集と状況分析、リスク判断によって、精度の高い意思決定を行う必要があるのです。
自己認知・自己成長力
自身の強みや課題を理解し、常に学び成長し続ける姿勢は、変化が激しい環境でリーダーシップを発揮するうえで欠かせません。自身の経験や価値観を内省し、必要であればそれを勇気を持って手放し、新しい思考を身につけることで自身をアップデートすることが求められます。この力が不足すると、時代や環境の変化に対応できず自身の成長が停滞し、結果として組織全体の変革も阻害されリーダーシップを発揮できなくなる可能性があります。
05なぜ部長に研修が必要なのか
部長は昇進に伴い、以前と比べて広範囲のマネジメント、ハイリスクな意思決定を行うことになります。課長時代と同じやり方では業務遂行が困難であるため、適応課題に直面し、自分自身の価値観や行動をアップデートする必要に迫られることがあります。具体的には「戦略的な視点の不足」や「意思決定の迷い」など、役割転換に伴う壁に直面しやすくなります。加えて部長職に求められるスキル範囲が広く高度であることから、現場での経験やOJTだけでは十分に習得することが難しいという課題もあります。
そのため、部長職に求められるさまざまなスキルを体系的に獲得する場として、部長研修が必要なのです。研修を通じて部長に求められる役割を再認識し、戦略策定や部門運営に必要な実践的スキルを身につけることが、組織全体の成果向上に直結します。
「研修をしてもその場限り」「社員が受け身で学ばない」を解決!
研修と自己啓発で学び続ける組織を作るスクーの資料をダウンロードする
■資料内容抜粋
・大人たちが学び続ける「Schoo for Business」とは?
・研修への活用方法
・自己啓発への活用方法 など

06部長研修を実施する上でのポイント
効果的な部長研修を実現するには、単に知識を得るだけでなく、研修内容を通じて自らのマネジメントスタイルを見直したり、新たな視点を得たりすることを目指します。また研修内容が実務と密接に結びついていること、さらに継続的に学べる環境が整っていることも、効果を高める重要なポイントです。
自らのマネジメントスタイルを振り返る機会を設ける
部長研修では、参加者が自身のマネジメントスタイルや無意識の価値観を深く内省し、自己変革を促す機会を設けることが重要です。部長職には、これまでに培われた経験だけに依存するのではなく、自らを客観的に捉え、成果創出に向けて主体的に変化する姿勢が求められるためです。例えば360度サーベイを用いるなど、課題を自覚させる実践的な仕掛けを取り入れることで、研修内容の受容性を高め、行動変容へ繋がります。
他の管理職との交流・視点共有を促す
他部門や他社の管理職との交流を積極的に促すことも有効です。背景の異なる参加者同士のディスカッションやワークショップを通じて、日頃の業務では得られない新たな視点や幅広い視野を獲得できます。これにより、経営方針を自部門に落とし込む際に必要な多角的な視点を獲得します。またさまざまな視点を得ることは、交渉力や協働体制構築のスキル向上にも寄与します。
実務との接続を意識した設計にする
部長研修を行う際は、実務への接続と行動変容を強く意識した設計が不可欠です。例えば第一線で活躍する経営者やリーダーの実体験に基づいた講義で思考をアップデートすることや、担当役員や上長と連携しながら行動変容をサポートする仕組み作りなどが考えられます。その他、全社ビジョン・戦略を自部門に落とし込み、具体的な施策として部門へ浸透させる実践型のプログラムは、理論を理想論で終わらせず、受講者が主体的に考え行動するきっかけとなるでしょう。
継続的に学べる仕組みを取り入れる
変化の速い現代において、部長には絶え間ない学習による知識・スキルのアップデートが必須です。一方で、多忙な管理職は日々の業務に追われる中、学びの機会を後回しにしてしまうという課題もあります。そのため研修実施の際は、その後も継続的に学べる仕組みを導入することが重要です。例えば社内外のネットワークやコミュニティ形成、オンライン学習を取り入れた自己啓発支援などを取り入れることで、知識の定着と成長の継続を支援できます。
07部長研修にはeラーニングが効果的
部長研修は、単なる知識の習得に留まらず、学んだ内容を実務での行動変容に繋げる実践的な設計が重要です。その観点からはグループディスカッションや実務に即した課題への取り組みなどが想起されますが、部長研修においてもeラーニングの活用は有効です。まず多忙な部長にとって、時間や場所を選ばずに自身の空き時間を活用して効率的に学習できる柔軟性が大きなメリットです。また、個々のスキルや課題に合わせて必要な講座をピンポイントで選択し、効率的に学べる点も優れています。
事前のインプットにeラーニングを使い、そこで得た知識を対面研修で活用するなど、柔軟に手法を組み合わせることで効果的な研修が設計できるでしょう。
「研修をしてもその場限り」「社員が受け身で学ばない」を解決!
研修と自己啓発で学び続ける組織を作るスクーの資料をダウンロードする
■資料内容抜粋
・大人たちが学び続ける「Schoo for Business」とは?
・研修への活用方法
・自己啓発への活用方法 など

08部長研修のおすすめ講座
新任管理職研修
新任管理職研修は、より大きな責任が伴う判断力を養う方法、個人だけでなく組織として成長していくための組織マネジメント、戦略的思考の基礎といった内容がおすすめです。
ビジネスパーソンに必要な「即断力」の鍛え方
この講座は、Yahoo!アカデミア学長の伊藤羊一先生に、周囲の信頼をつかみ味方を増やすリーダーに必要な要素を教わる授業です。「頭の働かせ方」「リーダーのマインド」「マネジメントにおける知識」といったスキルをワークショップを通じて、実務でも”できる"ようになることを目的としています。
-
 多摩大学大学院名誉教授/株式会社ライフシフトCEO
多摩大学大学院名誉教授/株式会社ライフシフトCEO
武蔵野大学アントレプレナーシップ学部 学部長。日本興業銀行、プラスを経て2015年ヤフー。現在Zアカデミア学長としてZホールディングス全体の次世代リーダー開発を行う。 またウェイウェイ代表、グロービス経営大学院客員教授としてリーダー開発を行う。
※研修・人材育成担当者限定 10日間の無料デモアカウント配布中。対象は研修・人材育成のご担当者に限ります。
あなたの『イノベーターシップ』で人や組織を動かそう
この講座は、変化の激しい現代において、個人や組織が成長し続けるために不可欠な「イノベーターシップ」を学ぶものです。イノベーションを生み出すリーダーに必要な「未来構想力」「実践知」「突破力」「パイ(Π)型ベース」「場づくり力」という5つの力に焦点を当て、それぞれの概念と具体的なトレーニング方法を習得できます。受講者は、新しい発想を生み出し、主体的に変革を起こすための思考法とマインドセットを身につけることがゴールとされています。
-
 多摩大学大学院名誉教授/株式会社ライフシフトCEO
多摩大学大学院名誉教授/株式会社ライフシフトCEO
日産自動車人事部、欧州日産を経て、1999年よりフライシュマン・ヒラード・ジャパンのSVP/パートナー。また、2006年から多摩大学大学院教授を兼任。 多摩大学大学院教授 ・研究科長。野中郁次郎名誉教授との共同開発によるMBB(思いのマネジメント)の第一人者。著書に『40代からのライフシフト実践ハンドブック』、『MBB:思いのマネジメ ント』(野中郁次郎名誉教授、一條和生教授との共著)、『ビジ ネスモデルイノベーション』(野中名誉教授との共著)、『人工知能×ビッグデータが「人事」を変える』(福原正大氏との共著)、 『イノベーターシップ』など多数。東京大学教養学部卒業。
あなたの『イノベーターシップ』で人や組織を動かそうを無料で観る
※研修・人材育成担当者限定 10日間の無料デモアカウント配布中。対象は研修・人材育成のご担当者に限ります。
基礎から学ぶ事業戦略策定のノウハウ
事業戦略策定の初心者向けに、その手順やプロセス、SWOT・3C分析などの必要な分析手法、差別化やビジネスモデルといった主要コンセプトを体系的に学ぶことができます。桜美林大学の坂本雅明准教授が講師を務め、基本的な事業戦略の策定方法を再現可能なスキルとして身につけ、自ら一定レベルの事業戦略を策定できるようになることを目指します。
-
 桜美林大学 ビジネスマネジメント学群 准教授
桜美林大学 ビジネスマネジメント学群 准教授
1969年生まれ。NEC、NEC総研を経て、富士ゼロックス総合教育研究所(現・パーソル総合研究所)入社。戦略系の研修・コンサルティング、戦略策定合宿の企画・ファシリテーション、管理職研修、経営幹部候補者研修を担当。2020年より現職、および東証プライム上場企業社外取締役。その間、一橋大学非常勤共同研究員、東京都立大学ビジネススクール非常勤講師を歴任。 上智大学経済学部卒業、一橋大学大学院修士課程修了(MBA)、東京工業大学大学院博士後期課程修了(博士(技術経営))。
※研修・人材育成担当者限定 10日間の無料デモアカウント配布中。対象は研修・人材育成のご担当者に限ります。
管理職研修
既存の管理職に対する研修は、より経営に近いレベルでの戦略立案のノウハウや、企業全体を成長させるための組織開発の考え方などの内容がおすすめです。
ビジョン達成のためにA4一枚の経営計画を作る
この講座は、会社のビジョンを明確にし、それを実現するための経営計画の作成方法を学びます。何枚にも及ぶ計画書ではなく、金融機関にも提出可能な、簡単かつ必要な項目を網羅したA4一枚の経営計画書を作成するノウハウが中心です。この授業を通じて、会社の経営ビジョンを明確にし、無駄な行動をなくして目標達成を目指す計画立案スキルを習得できます。
-
 中小企業診断士、社会保険労務士
中小企業診断士、社会保険労務士
株式会社千葉銀行に入社後、株式会社ちばぎん総合研究所にてコンサルティングを25年間経験、部長職など歴任し、現在公的機関で企業の経営相談をしている。 経営計画の作成・推進支援、経営改善支援、5S指導や商工会議所などで講演を行ってきた。 おもな著書は『A4一枚で作成できる・PDCAで達成できる経営計画の作り方・進め方』(日本実業出版社)、『1から学ぶ企業の見方』(近代セールス社)、『5Sで決算書がグングンよくなるんです』(日刊工業新聞社)など多数。
※研修・人材育成担当者限定 10日間の無料デモアカウント配布中。対象は研修・人材育成のご担当者に限ります。
自律的組織を目指した組織開発において必要なこと
この講座は、フレデリック・ラルー氏の『ティール組織』に着想を得て、自律的な組織を目指すための組織開発の必要性を学びます。『ティール組織』に掲載されたオズビジョンの具体的な試行錯誤事例を通して、組織変革の「3つの突破口」と、個人・組織の成長を促すための実践的な取り組みを共有します。受講者は、自律的な組織を構築するためのロードマップとなる知識と実践方法を習得できます。
-
 株式会社オズビジョン 取締役COO
株式会社オズビジョン 取締役COO
1977年生まれ 千葉県船橋市出身 中小企業診断士 MBA in Innovation Management 大学卒業後、システムエンジニアからスタートしたキャリアが、上場準備を契機に管理部門へシフト。その後2社で2度のIPOを経験。 社会人大学院の修了に合わせて組織開発の実践の場を求め『ティール組織』に日本企業で唯一紹介された株式会社オズビジョンに参画。取締役COOとして事業と組織の統合を推進。 ありのまーま合同会社代表社員も兼務。
自律的組織を目指した組織開発において必要なことを無料視聴する
※研修・人材育成担当者限定 10日間の無料デモアカウント配布中。対象は研修・人材育成のご担当者に限ります。
09まとめ
部長研修は、リーダーシップの発揮、戦略立案、人材育成、部門間の調整といった実務に直結する多くの内容を学び、経営視点を持った判断力や組織マネジメント力の強化を目的としています。部長という役職柄、業務で忙殺されて学びの機会が減ってしまいがちになるため、効率的に学べるような研修設計が重要になります。