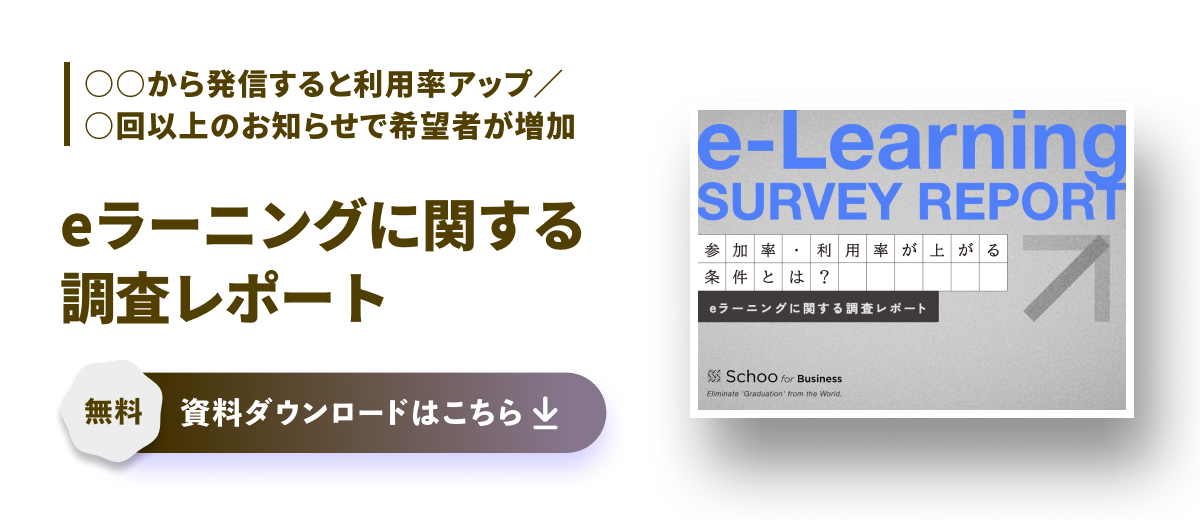eラーニングコンテンツの作り方を解説|自作する際の注意点を紹介

PCやスマートフォンを使って時間や場所を選ばずに学習できるeラーニング。人材育成の手法の一つとして導入する企業は増えています。 導入を検討している担当者の中には「作り方がよくわからない」、「効果の高いeラーニングを作りたい」といった課題を抱えている方も少なくないと思われます。 そこで、この記事ではeラーニングコンテンツの種類やその準備方法、自社で制作方法などを詳しく解説します。
01eラーニングコンテンツの形式
eラーニングコンテンツにはさまざまな形式があり、大きく5つに分類できます。各形式には特徴があり、目的や受講者層に応じた使い分けが重要です。
- 資料アップロード形式
- アニメーション形式
- 動画講義型
- 漫画形式
- VR形式
以下では、それぞれの概要と特徴について解説します。
資料アップロード形式

従来の紙資料やスライドをそのままアップロードして活用する形式です。既存資料を再利用できるため、準備にかかる工数が少なく、早期に運用を開始できる点が特徴です。
アニメーション形式

キャラクターやアニメーションを活用して学習内容を説明する形式です。視覚的に理解しやすく、受講者の興味を引きやすい一方で、制作には時間とコストがかかります。
動画講義型

講師の講義を収録した動画を視聴する形式です。スライドや資料を併用しながら解説でき、集合研修の代替として導入されることが多く、汎用性の高いスタイルです。
漫画形式
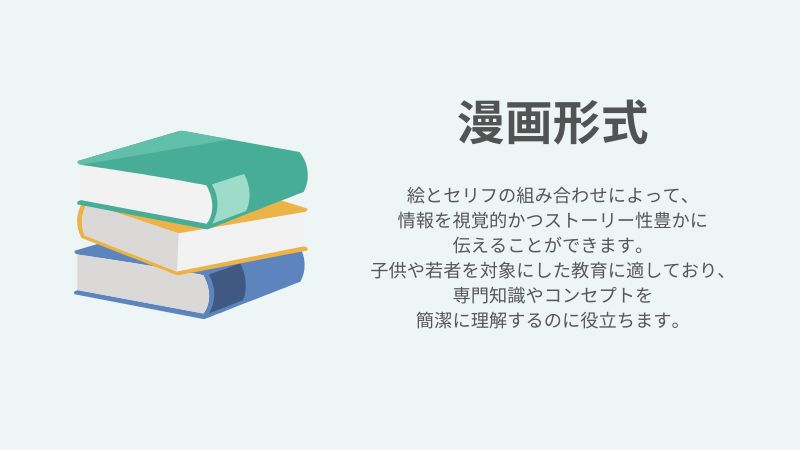
ストーリー仕立てで内容を伝える形式です。視覚的に理解しやすく、感情移入しやすいため、若年層や入門者向けの教材に適しています。短時間でも印象に残る効果があります。
VR形式

仮想空間内で実践的なトレーニングが可能な学習形式です。臨場感のある体験を通じて、実務に近い環境でスキル習得を行えるため、高度な研修に適しています。
02eラーニングコンテンツのトレンド
近年、テクノロジーの進化によりeラーニングコンテンツはこれまでよりもユーザーファーストになり、スマートフォンやタブレットで視聴することができたり、学習管理も最適化されてきております。加えて、これまでのeラーニングは一方向の学習が主流でしたが、実践型の学習も可能になっています。本章では、そんなeラーニングコンテンツのトレンドについて詳しく解説していきます。
動画教材による実践型の研修・教育の増加
近年、eラーニングコンテンツのトレンドの1つとして、実践的な研修や教育に動画教材が増えています。動画は、視覚的な情報伝達手段として非常に効果的であり、従来のテキストや静止画像よりも参加者の関心を引きやすく、情報の吸収度も高いとされています。さらに、動画を使用することで具体的な事例やシミュレーションを再現できるため、実践的なスキルや知識の習得を促すことができます。また、動画教材は時間や場所に制約されずに利用できるため、自分のペースで学習する柔軟性もあります。
スマートフォンやタブレットに適した教材
モバイルデバイスの普及に伴い、eラーニングコンテンツもスマートフォンやタブレットに最適化された形式に進化しています。従来のパソコンやラップトップだけでなく、ユーザーはいつでもどこでもスマートフォンやタブレットを使用して学習することができます。そのため、教材は画面サイズやタッチ操作を考慮して最適化されており、モバイルデバイス上で快適に利用できます。また、アプリケーションやプラットフォームを活用したモバイル学習も増えており、ユーザーエクスペリエンスの向上にも力が入れられています。
ICTツールとの連携
ICT(情報通信技術)ツールとの連携により、eラーニングコンテンツはさらなる進化を遂げています。人工知能(AI)を活用した教育支援システムや学習分析ツールの導入により、学習者の進捗や理解度を評価・分析し、個別に最適化された学習体験を提供できるようになりました。また、仮想現実(VR)や拡張現実(AR)などの技術を組み合わせた教材も登場し、より身体的な体験やインタラクティブな学習が可能になっています。ICTツールとの連携により、効果的で魅力的なeラーニングコンテンツが開発され、学習者の学習体験が飛躍的に向上しています。
03eラーニングコンテンツを用意する手段
eラーニングコンテンツを用意する手段は、以下の通りです。
- 1:自作する
- 2:市販のコンテンツを購入する
- 3:外部に制作を依頼する
- 4:サブスク型のツールを活用する
eラーニングを導入する際、コンテンツの用意には複数の手段があります。自社で作成する方法のほか、市販の教材を購入したり、外部に制作を依頼する選択肢もあります。最近では、月額課金で多くの教材を活用できるサブスク型のサービスも普及しています。自社のリソースや目的に応じて、最適な方法を検討することが重要です。
1:自作する
社内のノウハウや過去の研修資料をもとに、自社でeラーニングコンテンツを制作する方法です。社内ルールや業務フローに即した内容を反映できるため、高いカスタマイズ性が得られます。費用を抑えやすく、更新も柔軟に対応できる一方で、企画から制作までの手間やノウハウ不足が課題になることもあります。
2:市販のコンテンツを購入する
既にパッケージ化されたeラーニング教材を購入し、社内で活用する方法です。汎用的なテーマに対応した高品質な教材が揃っており、即時導入が可能です。コストパフォーマンスに優れる反面、自社固有の業務や文化には対応しにくい場合もあります。導入前に内容の確認が必要です。
3:外部に制作を依頼する
制作会社に依頼して、自社専用のeラーニングコンテンツを作成してもらう方法です。専門知識や技術を活用し、質の高いコンテンツを効率的に制作できます。独自性のある教材が得られる一方で、コストや納期、修正対応などの管理も必要になります。要件定義や目的の明確化が成功の鍵となります。
4:サブスク型のツールを活用する
月額課金でさまざまなコンテンツが利用できるeラーニングサービスを導入する方法です。多数の動画教材を社員に提供でき、管理機能や受講履歴の確認機能も備えたものが多くあります。初期費用を抑えつつスピーディに研修を開始できる点がメリットですが、自社特有の内容を補う工夫が求められます。
04eラーニングコンテンツの作成方法
eラーニングコンテンツの作成方法は、以下の通りです。
- 1:対象者と目的を整理する
- 2:コンテンツの内容を箇条書きにする
- 3:構成を整理する
- 4:目的に沿った形式で制作を行う
- 5:品質に問題がないか確認する
効果的なeラーニングコンテンツを作成するには、いきなり制作に着手するのではなく、事前の整理と設計が重要です。対象者や目的の明確化、内容の箇条書き整理、構成設計、形式の選定、そして最終的な品質チェックまで、順を追って進めることで、実用的で分かりやすい教材を制作することができます。
1:対象者と目的を整理する
まずは、誰のために、何のために学習してもらうのかを明確にすることが重要です。対象者の職種やレベル、業務内容によって必要な知識やスキルは異なります。研修の目的も、理解促進、行動変容、資格取得などさまざまです。対象者と目的を具体的に設定することで、以降の内容設計や評価軸が明確になります。
2:コンテンツの内容を箇条書きにする
企画段階では、いきなりスライドを作り始めるのではなく、まずテキストベースで内容を洗い出しましょう。テーマごとに箇条書きで要素を並べることで、漏れや重複を防げます。文字で構成することで、情報の優先度や流れも整理しやすくなり、のちの構成や演出にもつなげやすくなります。
3:構成を整理する
箇条書きで洗い出した要素をもとに、導入・本論・まとめといった全体の構成を組み立てます。導入では目的やゴールを明示し、本論では要点ごとに展開、最後に復習や確認を入れることで、学習効果が高まります。ナレーションやアニメーションを加える場合も、構成に沿った設計が重要です。
4:目的に沿った形式で制作を行う
構成が決まったら、目的や学習内容に最適な形式で制作を行います。知識のインプットが中心であれば動画形式、手順やルールの理解には図解やアニメーション、体験的な理解が必要であればVRやシミュレーションなど、形式ごとの特性を活かすことで、受講者の理解促進や行動変容につなげることができます。
5:品質に問題がないか確認する
制作後は必ず品質チェックを行いましょう。誤字脱字、音声や映像の不具合、リンク切れなどがないかを確認することはもちろん、対象者がスムーズに理解できるか、構成に矛盾がないか、専門用語の説明が足りているかなど、受講者目線での最終確認が欠かせません。第三者レビューの導入も効果的です。
05eラーニングコンテンツを自作する際の注意点
eラーニングコンテンツを自作する際は、以下に注意しましょう。
- 1:コンテンツの賞味期限を考える
- 2:目的に沿った内容だけに抑える
- 3:行動変容につながる内容にする
- 4:できるだけ作成工数を抑える
eラーニングコンテンツを内製する際は、作ること自体が目的にならないよう注意が必要です。長期的に使える内容か、目的に適した範囲に収まっているか、受講者の行動を促せるか、などの観点が重要です。また、社内工数を過剰にかけず効率的に制作する工夫も求められます。以下に具体的な注意点を紹介します。
1:コンテンツの賞味期限を考える
スキルニーズの変化が激しい現代では、コンテンツの「賞味期限」を意識する必要があります。たとえば、マネジメントスキルひとつを取っても、以前は業績管理が中心でしたが、現在はピープルマネジメントが重視されるなど、求められるスキルが変化しています。頻繁に更新が必要になる内容を内製すると、保守・管理の負担が増すため、長期間使える設計かどうかを初期段階で見極めることが大切です。
2:目的に沿った内容だけに抑える
eラーニングは情報量が多ければ良いというものではありません。対象者の職種やスキルレベル、研修の目的に対して本当に必要な内容に絞ることが重要です。目的と無関係な知識まで詰め込みすぎると、学習負荷が高くなり、肝心なポイントの理解が進まなくなる恐れがあります。必要最低限の範囲に抑えることで、学習効率も高まります。
3:行動変容につながる内容にする
単なる知識のインプットに留まらず、受講後に「何をどう変えるか」を意識した内容設計が重要です。具体的な行動例やシチュエーション別の対応方法、チェックリストの提示など、職場で実践できる形に落とし込むことで、学びが行動へとつながります。受講者が「自分事」として考えられるような構成を意識しましょう。
4:できるだけ作成工数を抑える
自社制作では工数がネックになるケースが多くあります。そのため、必要に応じてAIなどのツールを活用しましょう。構成案の整理、ナレーション原稿の作成、図表の生成など、AIをうまく使えば短時間で質の高いコンテンツが作れます。リソースの限られた現場こそ、効率的な制作体制が求められます。
06法人向けeラーニング|Schoo for Business

Schoo for Businessは約9,000本の講座を用意しており、様々な種類の研修に対応しています。階層別研修からDX研修、部署別の研修まで幅広いコンテンツで全てを支援できるのが強みです。
| 受講形式 | オンライン (アーカイブ型) |
| アーカイブ本数 | 9,000本 ※2024年2月時点 |
| 研修管理機能 | あり ※詳細はお問い合わせください |
| 費用 | 1ID/1,650円 ※ID数によりボリュームディスカウントあり |
| 契約形態 | 年間契約のみ ※ご契約は20IDからとなっております |
Schoo for Businessの資料をダウンロードする
大企業から中小企業まで幅広く導入

Schoo for Businessは、大企業から中小企業まで幅広く導入いただいております。利用用途も各社さまざまで、階層別研修やDX研修としての利用もあれば、自律学習としての利用もあり、キャリア開発の目的で導入いただくこともあります。
導入事例も掲載しているので、ご興味のあるものがあれば一読いただけますと幸いです。以下から資料請求いただくことで導入事例集もプレゼントしております。そちらも併せて参考にいただけますと幸いです。
eラーニングコンテンツの種類
Schoo for Businessでは、約9,000本の授業を提供しており、ビジネススキルや自己啓発、テクノロジー領域など多様なジャンルを網羅しています。目的や職種に応じて必要な知識を柔軟に選べるため、社員一人ひとりに合った実践的な学習機会を提供できます。
07まとめ
本記事では、eラーニングコンテンツの形式やトレンド、導入手段、作成手順、注意点までを体系的に紹介しました。コンテンツは一度作って終わりではなく、学習者の課題や状況に応じて改善・更新し続けることが重要です。とくに法人研修では、受講者の職種やスキルレベル、行動変容を意識した設計が求められます。自社で制作する場合も、目的を絞った構成や工数削減の工夫を取り入れることで、効果的かつ継続的な学習環境を整えることができます。