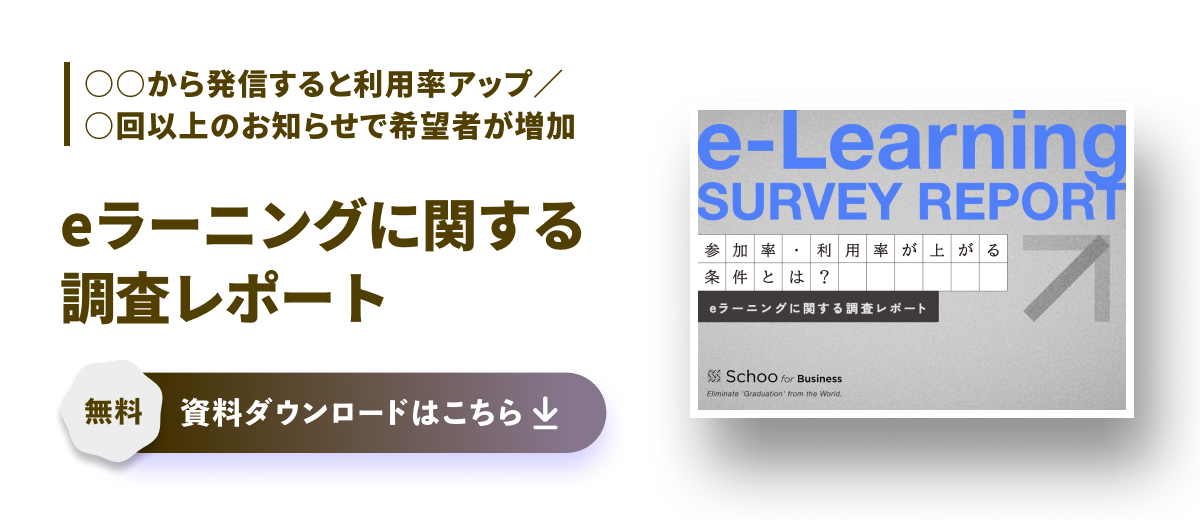eラーニングのメリットとデメリットを学習側と企業側の2つの視点で紹介

eラーニングという言葉を耳にして、気になるのは、「eラーニングってどういうもの?」「eラーニングのメリットやデメリット?」今回は、eラーニングの概要やメリットとデメリットついて解説します。
01eラーニングにおける学習者側のメリット
eラーニングが学習者側にもたらすメリットとして、以下の6つが挙げられます。
- 1.自分のペースで学習ができる
- 2.講師によって理解度にブレが生じない
- 3.何度も復習できる
- 4.学習したということが会社にしっかりと伝わる
- 5.受講ハードルが低い
- 6.社内での共通言語になる
さらに以下でそれぞれについて詳しく解説していきます。
学習者側のメリット1:自分のペースで学習ができる

忙しい人でも隙間時間で学習できることがeラーニングの大きなメリットです。 特に普段の仕事で任されている業務量が多く、まとまった時間が取れないといった中堅社員などにとってはこのメリットを一番享受できるのではないでしょうか。 また、eラーニングで提供されている講義動画は何度でも視聴が可能なので、一度では理解できなかった内容も繰り返し学習することができ、知識・スキルをしっかりと定着させることが可能です。
学習者側のメリット2:講師によって理解度にブレが生じない

集合研修では学習者が大勢いる場合は、複数人のグループにわかれて講義を行うということもあるでしょう。その場合、講師の教え方にはどうしても違いが生じてしまうため、他の学習者と理解度にブレが生じてしまうことも考えられます。 しかし、eラーニングでは、皆が同じ講師の研修を受講するため、講師の違いによる問題が生じにくくなります。
学習者側のメリット3:何度も復習できる

集合研修は一度受講するとそれっきりで終わりですが、eラーニングサービスの多くはは何度も繰り返し受講できるサービスとなっています。繰り返し受講できると、一度見ただけでは理解しにくかったことを何度も繰り返し見て定着させることができるため、学習効果が上がります。さらに、すでに理解したコンテンツでも繰り返し見ることでまた違った理解が生まれることもあるため、eラーニングは効果的なのです。
学習者側のメリット4:学習したということが会社にしっかりと伝わる

eラーニングサービスの多くには、学習管理機能が備わっており、学習者がどの程度学習したのかを管理者が簡単に確認することができます。もちろん、勉強していないとそれも管理者側からは分かってしまうのですが、しっかりと勉強しているとそれが管理者側に伝わり、評価が上がることもあります。しっかりと学習した人が適正に評価されやすいのがeラーニングともいえます。
学習者側のメリット5:受講ハードルが低い
今の若手社員世代はYoutubeやNetflixなどで動画を見ることに慣れ親しんでおり、eラーニングの受講もハードルが低いというメリットがあります。また、進学塾でeラーニングを用いて学習していたという人も多く、学習は動画で効率良く行うことが一般的な社員は今後益々増えていくでしょう。
学習者側のメリット6:社内での共通言語になる
eラーニングであれば、全ての社員が同じ内容の研修を受けることが可能なので、社内の共通言語を増やすことも可能です。例えば、営業部門の管理職から一般社員まで全員が同じ研修を受けることによって、業務で実践できているかの振り返りも容易になります。また、誰が実践できているかどうかの可視化も、管理職だけでなくメンバー間で行うことができ、互いに学び合う組織を作ることもできるようになるでしょう。
02eラーニングにおける学習者側のデメリット
eラーニングが学習者側にもたらすデメリットとして、以下の4つが挙げられます。
- 1.実技を伴うスキルが身に着きづらい
- 2.実技を伴うスキルが身に着きづらい
- 3.インターネット環境が必要
- 4.横の繋がりが作りにくい
さらに以下でそれぞれについて詳しく解説していきます。
学習者側のデメリット1:実技を伴うスキルが身に着きづらい
eラーニングは集合研修とは異なり、面と向かって行う講義ではないため、ロールプレイングなどの実践を伴うような内容には向かないことが多いです。 そのため事前に学習して実際の業務で実践する形をとるなど、学習内容のアウトプット方法を工夫する必要があります。
学習者側のデメリット2:講師とのコミュニケーションがとれない
eラーニングの講義では、収録された動画講義で学習することがメインになるため、疑問があっても講師に直接質問することができません。 ただし、eラーニングのサービスにはLIVE配信で講義を行っていることもあるので、そういった場合にはチャットを使って講師と直接コミュニケーションをとることができます。
学習者側のデメリット3:インターネット環境が必要
eラーニングを受講するにはインターネット環境が必要不可欠です。オフィスワーカーであれば個人にパソコンが支給されているのが普通かと思いますが、パソコンを使わない仕事をする人も多くいます。そのような人にとっては、仕事時間中にeラーニングを受講することは難しく、個人のスマホやパソコンから視聴するしかありません。
学習者側のデメリット4:横の繋がりが作りにくい
eラーニングは基本的に個人で受講することになるため、社員同士の横の繋がりを作るという文脈には不向きです。例えば、内定者研修や新入社員研修などでは社員同士が互いのことを知り、関係性を作るというのも目的の1つになるでしょう。このような研修で、全てをeラーニングにしてしまうと、横の繋がりが作れなくなってしまうので、研修とは別に懇親会などの取り組みを行う必要が出てきます。
03eラーニングにおける企業側のメリット
eラーニングが企業側にもたらすメリットとして、以下の5つが挙げられます。
- 1.研修をセッティングするコストを節約できる
- 2.研修スケジュールの調整が不要になる
- 3.学習の進捗状況を常に把握できる
- 4.集合研修に比べて低コストで行える
- 5.学習データを貯めることができる
さらに以下でそれぞれについて詳しく解説していきます。
企業側のメリット1:研修をセッティングするコストを節約できる

通常の集合研修では、研修を企画する度に会場を借りたり、講師を招待する費用がかかります。どちらも1日単位で数十万円にもなることがあるため、研修を一度行うだけでも高額なコストがかかってしまいます。 eラーニングではサービスの利用料が1万円~10万円ほどなので、集合研修を行うよりもはるかに格安で学習してもらうことが可能になります。
企業側のメリット2:研修スケジュールの調整が不要になる

集合研修に参加する場合、従業員は自分の業務を中断することになるため、主催者側も細心の注意を払って研修のスケジュールを組まなければならないため、必要なスキルであってもすぐに研修ができないといったケースも考えられます。 eラーニングであれば、場所を選ばず学習ができるため、非常に素早い研修が可能になります。
企業側のメリット3:学習の進捗状況を常に把握できる

学習者側のメリットの部分でも説明したように、多くのeラーニングサービスには学習者の学習進捗を管理する機能が備わっています。そのため、雇用者側は簡単に学習者の学習進捗を知ることができ、学習がしっかり進んでいない受講生には学習を促すことができ、しっかりと学習している受講生を適正に評価することができます。学習者側に直接学習状況を聞くよりもお互いにとって負担が少なく、簡単なのが大きなメリットです。
企業側のメリット4:集合研修に比べて低コストで行える

全てのeラーニングサービスで、集合研修よりもコストを抑えられるというわけではありませんが、eラーニングにかかる費用の方が、集合研修にかかる費用よりも安いという傾向があります。集合研修では会場代や講師へのお給料、講師の交通費など、様々なコストがかかってしまいます。しかし、eラーニングではそれらのコストがかからず、かつ質の高い教育コンテンツを提供できるというメリットがあるのです。
企業側のメリット5:学習データを貯めることができる
人的資本開示が求められてきています。その中で学習データの重要性はさらに増しています。学習データと従業員エンゲージメントや離職率などのデータを掛け合わせ、社員の成長という観点だけでない研修の効果測定の仕方に取り組んでいる企業も増えています。eラーニングであれば、自動で学習データを貯めることができるので、工数が新たにかかることはありません。また、タレントマネジメントと連携することで自動で学習データを送信することもでき、戦略を立てる上で分析だけに時間を使うことができます。
04eラーニングにおける企業側のデメリット
eラーニングが企業側にもたらすデメリットとして、以下の4つが挙げられます。
- 1.学習者のモチベーションの維持が難しい
- 2.学習状況の把握が煩雑になる
- 3.教材の作成に手間がかかる
- 4.ITリテラシーが必要
さらに以下でそれぞれについて詳しく解説していきます。
企業側のデメリット1:学習者のモチベーションの維持が難しい
eラーニングは各人がそれぞれ時間を作って学習することになるため、一人では中々学習意欲が沸かなかったり、業務が忙しいなどと理由を作って学習しないケースが考えられます。 半ば強制的に学習する機会を設定する集合研修とは異なり、学習者が能動的に取り組むことが重要です。 そのため、企業側としては学習者がモチベーションを維持できるよう、学習者同士のコミュニティーを作るなどの施策を講じる必要があります。
企業側のデメリット2:学習状況の把握が煩雑になる
企業が自製でeラーニングのシステムを導入する場合に発生するデメリットになります。 eラーニングは学習者が興味のある分野を自由に学習できる一方で、誰が何を・どこまで学んだのかを把握するシステムが必要になります。 具体的には、学習管理システム(LMS:Learning Management System)というツールを導入することで、学習内容や進捗管理を行うことができます。 また、eラーニング教材を提供している企業のサービスに学習管理ツールも組み込まれていることも多いため、eラーニングシステムを内製するよりもはるかに容易に導入することができるでしょう。
企業側のデメリット3:教材の作成に手間がかかる
eラーニングには、教材を自社で作成するタイプのものと、コンテンツ込みのeラーニングの2つのパターンがあります。教材を自社で作成するタイプのものは、自社に最適化された研修内容にすることができるというメリットがある一方で、作成コストがかかるというデメリットがあります。Excelの関数を学ぶようなコンテンツであれば、長年使い回すことも可能ですが、コンプライアンスやハラスメントなどの研修コンテンツは法改正なども起こる可能性があり、一定期間で刷新を求められることも珍しくありません。
企業側のデメリット4:ITリテラシーが必要
eラーニングの受講は、パソコンやスマートフォンによって行われます。平成世代は子供の頃から携帯電話やパソコンに慣れ親しんでいますが、高齢の人の中にはあまり慣れていないという人もまだいるでしょう。そのため、受講してもらうために社員のITリテラシーをまず上げる必要があるという場合もあります。人事が社員のトラブルエラーを1件ずつ対応していく余力があれば別ですが、ひとり人事の場合はeラーニングを導入する前に社員のITリテラシーの把握から始めた方が良いかもしれません。
05累計4,000社導入のeラーニング|Schoo for Business

オンライン研修/学習サービスのSchoo for Businessでは約9,000本の講座を用意しており、様々な種類の研修に対応しています。階層別研修からDX研修、部署別の研修まで幅広いコンテンツで全てを支援できるのが強みです。
| 受講形式 | オンライン (アーカイブ型) |
| アーカイブ本数 | 9,000本 ※2024年2月時点 |
| 研修管理機能 | あり ※詳細はお問い合わせください |
| 費用 | 1ID/1,650円 ※ID数によりボリュームディスカウントあり |
| 契約形態 | 年間契約のみ ※ご契約は20IDからとなっております |
Schoo for Businessの資料をダウンロードする
大企業から中小企業まで幅広く導入

Schoo for Businessは、大企業から中小企業まで幅広く導入いただいております。利用用途も各社さまざまで、階層別研修やDX研修としての利用もあれば、自律学習としての利用もあり、キャリア開発の目的で導入いただくこともあります。
導入事例も掲載しているので、ご興味のあるものがあれば一読いただけますと幸いです。以下から資料請求いただくことで導入事例集もプレゼントしております。そちらも併せて参考にいただけますと幸いです。
06eラーニングのメリットにおける人事の声
本章では、Schoo for Businessの導入企業様が実際に感じられているeラーニングのメリットをご紹介します。
株式会社しまむら 水野様

反響が大きかったのは、PC関連の講座です。店長として勤務する間はほとんど使わないのですが、本社勤務に移るとPCのスキルが求められます。同じデスクトップ上で操作画面を見比べながら学べる、eラーニングならではの学習方法が大変好評でした。
九州旅客鉄道株式会社 押方様

知識の導入からすごく噛み砕いて説明してくれるので敷居が低く、取り組みやすいですね。鉄道業は基本的には決められたルールに沿って手順通りに進めていくことがベースとなる仕事なのですが、新しい知識を取り入れて変わりたい・成長したいと思う社員には、非常に学びをそそられるツールだと思います。
また、空いた時間を有効活用できる手軽さも魅力的ですよね。通勤時間が1時間以上かかる社員もいて、その途中の列車の中で受講するなど隙間時間を上手く使って学ぶ社員も多いようです。
コニカミノルタジャパン株式会社 河村様

スクーの導入によって、私たち人財開発部門の意識も変化したと感じています。 スクーを使うようになってから、私たちが用意した研修を社員に展開するよりも、社員自身が自分の業務に合った内容、自分に合った講師を「選択できる」方が、当事者意識をもってスピーディに学習てきで良いなという気づきがありました。
その気づきによって、私たちは「研修のデリバリー」に留まらず、様々な領域の専門家の力を活用しながら、「興味を持って学びたくなる仕掛けづくり」や「現場実践との接続」などに注力していこうという意識転換に繋がっています。 スクーで学んだことを、深めたり応用につなげていったりという環境づくりをした方が、効果的な人財開発になると感じています。
KDDI株式会社 秋山様
とにかく授業数が豊富で、ビジネスの第一線で活躍中の方が講師として登壇されることも多いです。 中には、当社と関わりのある業界の先駆者である方ご自身による講義もあり、最新のビジネストレンドや具体的な企業の取り組みを知る意味でも、大変役立っています。
また場所の制約を受けず、どこでも学べるのが魅力です。 同様な内容のセミナーなどが首都圏で開催される場合、遠方から参加は難しいことも多いですが、スクーの形式であれば場所や時間に関係なく都合のよいときに学べます。 その積み重ねにより、学ぶ習慣づけという好循環が自然と生まれると思っています。
シンフォニアテクノロジー株式会社 池上様
当初は、自ら学ぶ人はそれほど多くないと思っていたのですが、ほぼ毎日利用したいという申請が来るなど、社員の学習意欲が高まってきていますね。管理職からも「こういう講座はないの?」といった話題が上がることが多くなり、全体感としても、学びへの関心が日々高まってきています。
07まとめ
eラーニングは、場所や時間を選ばず学習者のペースで受講できるのがメリットです。一方で、学習者にとっては実技を伴う研修が難しいことや、講師と直接のコミュニケーションがとれないなどのデメリットもあります。eラーニングによる研修を検討する際は研修方式や目的を設計の上、判断するといいでしょう。
▼【無料】働き方改革から学び方改革へ~学ぶ時間の創出で離職率が低下した事例~|ウェビナー見逃し配信中

働き方に関する制度改善を多数行ってこられた株式会社クロスリバー 代表取締役 越川慎司氏をお招きし、「残業削減ではない方法で働き方改革を行い、社員の自発性と意欲を著しく向上させ、離職率を低下させるための自律学習の制度設計」について語っていただいたウェビナーのアーカイブです。同社の調査・分析内容と自律学習の制度設計を深堀ります。
-
登壇者:越川 慎司様株式会社クロスリバー 代表取締役
ITベンチャーの起業などを経て2005年に米マイクロソフト本社に入社。業務執行役員としてパワポなどの責任者を経て独立。全メンバーが週休3日・リモートワーク・複業の株式会社クロスリバーを2017年に創業し、815社17万人の働き方と成果を調査・分析。各社の人事評価上位5%の行動をまとめた書籍『トップ5%社員の習慣』は国内外で出版されベストセラーに。