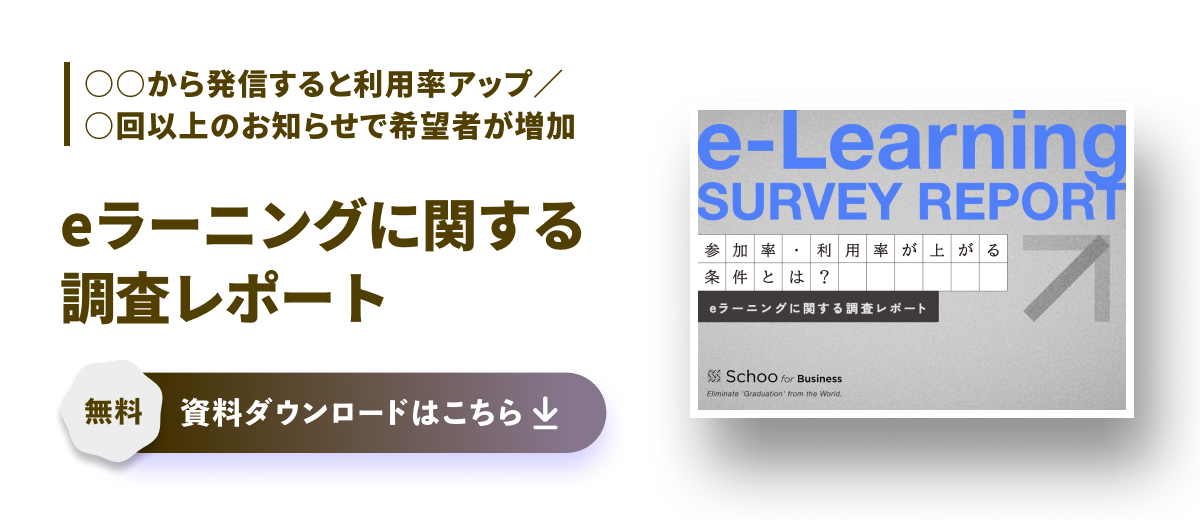eラーニングの導入を成功させるための5つのポイントと導入する際のフローを紹介

アフターコロナも見据えて、いまe-ラーニングを社員研修や人材育成に利用しようと考える企業は増えています。しかし、e-ラーニングを会社に導入するためには、その必要性・有用性を社内で理解してもらう必要があるため、担当者がその知識を身につけなければなりません。そこで、このコラムではe-ラーニングを導入するメリットから、導入する際のフローまで含めてご紹介します。
01eラーニング導入を成功させる5つのポイント
eラーニング導入を成功させるポイントは以下の5つがあります。
- 1:自社の課題を明確にする
- 2:利用するユーザーは誰かを明確にする
- 3:どのLMSを利用するのか決める
- 4:どのようなコンテンツが必要かを考える
- 5:利用促進をするための体制を考える
1:自社の課題を明確にする
システムやツールを導入する理由は、自社の課題を解決するためです。そのため、まずは自社の課題を把握しましょう。e-ラーニングの場合、「研修にかかる費用が多い」や「人材育成が社内に根付いておらず、離職率が高い」などが主な課題となるでしょう。それらの解決策としてeラーニングを導入すると、どういう効果が得られるのかを考える必要があります。例えば、離職率が高い要因が人材育成体制が確立していないことではなく、社内の人間関係や評価制度や給与水準が明確でないといったものである場合、eラーニングを導入しても、その課題は解決されません。したがって、e-ラーニングに限らず、ツールを導入する前には自社の課題を明確にしておく必要があるのです。
2:利用するユーザーは誰かを明確にする
eラーニングを利用して、どのような課題を解決したいかを明確にした後は、具体的にどの社員が利用するかを考える必要があります。エンジニアなのか営業なのかによっても、コンテンツの内容が異なりますし、新入社員なのか管理職なのかによっても、必要とするコンテンツは異なります。そのため、e-ラーニングを導入する際には、どのユーザーに利用して欲しいのかを明確にしておく必要があるのです。多くの企業がe-ラーニングを提供していますが、業種特化型のものもあれば、全社員に対応しているものもあります。誰に利用して欲しいかを見極めた上で、ツールの選定をすることによって、より効果的にe-ラーニングを導入することができるでしょう。
3:どのLMSを利用するのか決める
LMSとはLearning Management Systemの略で、学習管理システムのことを指します。LMSを導入することにより、「コンテンツ」や「社員の受講状況」、「学習成果」などを一元管理することができるので、e-ラーニングを導入する上でLMSは必要不可欠と言えるでしょう。LMSは自社サーバーを活用する方法と他社(e-ラーニングの提供企業)のサーバー上で利用する方法があります。しかし、多くの場合では、LMSとコンテンツを分けて考えずに、同じ会社で提供しているLMSとコンテンツを合わせて契約し、自社にe-ラーニングを導入するので、LMSを深く考える必要はありません。ただし、社員の進捗状況の確認や、学習成果の管理、社内へのアラートメールの可否など、利用用途に合わせてLMSの機能も考慮する必要があります。
4:どのようなコンテンツが必要かを考える
受講者にどのような教材=コンテンツを見てもらう必要があるのかを考えましょう。そのためには、受講者の課題は何かを明確にし、どのようなスキル・知識が身につくことが目標となるのかを具体化しなければなりません。例えば、新入社員研修としてe-ラーニングを導入する場合は、OAスキルやビジネスマナーが充実していた方が良いかもしれません。一方でエンジニアのスキルアップを目的にするのであれば、社内で多く利用されている言語は何かを把握し、今後どのような言語を利用していく可能性があるかも視野に入れる必要があります。また、コンテンツを自社で用意するという方法もあります。一定以上のクオリティーが担保された動画を製作するには工数がかかるものの、社内で必要とされているスキルのみを効果的に動画に落とし込むことができるので、e-ラーニングの効果を高めるには良いかもしれません。自社内で作成した動画と、他社のコンテンツを並行して利用することもできるe-ラーニングもあるので、どのようなコンテンツが最も学習効果が高いと思われるかを考え、逆算してコンテンツ選びをしましょう。
5:利用促進をするための体制を考える
eラーニングを社員研修のために導入する場合は、ある意味で強制的に利用してもらうことになるので、利用促進は必要ありません。しかし、福利厚生の1つとしてe-ラーニングを導入したり、人材育成を目的として導入する場合は、強制力がないため社内で利用促進をする取り組みとセットでe-ラーニングの導入を考える必要があります。例えば、半期面談で浮き彫りになった課題を解決するために、上長がe-ラーニングの存在を周知するといったような取り組みがあると、社内での利用も広まるでしょう。また、チャットツールで面白かったコンテンツや勉強になったコンテンツを語るチャンネルを作っても良いかもしれません。社内でのコミュニケーションツールの1つにもなりますし、勉強会を社員主導で開くといった主体的な学びが広がるきっかけになる可能性もあります。
02eラーニング導入における企業側のメリット
eラーニングを導入することで、企業側には以下の3つのメリットがあります。
- 1:研修コストの削減
- 2:研修内容を均質化できる
- 3:人材管理が効率的になる
1:研修コストの削減
オフラインの集合研修にかかるコストには、主に以下のようなものが考えられます。
- ・研修資料の印刷費用
- ・講師の登壇料
- ・研修担当の管理工数(日程の調整・研修の周知・学習状況の管理)
- ・会場費用
これらは、eラーニングに置き換えることにより大きく削減が可能です。特に管理工数の削減は大きなメリットでしょう。大規模な企業ほど、研修を受ける人数も増えるため管理工数が大幅にかかる傾向にあります。e-ラーニングにすることで、学習状況を一元管理でき、データも蓄積できるので、人事評価などにも簡単に反映させることができるはずです。
2:研修内容を均質化できる
研修は講師の能力次第で、学習効果が大きく異なります。実務が探れていても人に教えることを不得手としている人も中にはいるため、実務で優秀な人が講師としても優秀とは限らないのです。しかし、eラーニングであれば、同じ講師の授業を時間や場所を問わず受けることができます。事前にその講師の授業を研修担当が受講して、品質を確かめることもできるので、研修した後に失敗だと気づくことが無くなります。
3:人材管理が効率的になる
LMSを人事評価システムなどと組み合わせることによって、人事配置や昇格に応じて適切なコンテンツの受講を促すことができ、社内の人材育成が促進されます。また、LMSで受講状況なども一元管理できるので、その受講状況や習得度に応じて人事評価をつけることも可能です。可視化された人事評価システム、自発的に学習する習慣を社員に根付かせることもできるかもしれません。
03eラーニング導入における企業側のデメリット
eラーニングのメリットを解説しましたが、当然ながらデメリットも存在します。メリット・デメリットを比較したうえで導入するかを検討することが大切です。
モチベーションの維持が難しい
eラーニングは受講者が時間や場所に捉われず学習ができますが、裏を返せば受講者の自主性に依存するため、モチベーションの維持が難しい部分があります。研修を視聴したものの、内容について理解できていないということも起こりがちなので、モチベーション維持に繋がる対策を同時に考えておくことが大切です。
実技の習得が難しい
プログラミングなどのパソコンを使った作業を除いて、eラーニングは画面上での学習になるので、実技学習には不向きとされています。全ての実技学習ができないというわけではないため、社員に身に着けてもらいたいスキルとeラーニングでできることを照らし合わせつつ導入を検討する必要があります。
学習内容が一般的な内容が多い
研修の効果を高めるためには、研修内容は自社の実務につながるものが望ましいです。eラーニングはどの企業にも通じやすい一般的な内容に最適化しているため、自社独自に内容をカスタマイズしたいという場合には、研修教材を内製で用意する必要があるでしょう。
「研修をしてもその場限り」「社員が受け身で学ばない」を解決!
研修と自己啓発で学び続ける組織を作るスクーの資料をダウンロードする
■資料内容抜粋
・大人たちが学び続ける「Schoo for Business」とは?
・研修への活用方法
・自己啓発への活用方法 など
04eラーニングを導入する際のフローを解説
05eラーニング導入における従業員側のメリット
eラーニングを導入することで、従業員にとって次のようなメリットが挙げられます。
- ・時間や場所を問わず自分のペースで学習できる
- ・個別最適化された学習が可能
- ・反復学習が可能
eラーニングの導入は従業員にとって柔軟かつ効率的な学習を可能にし、個々の成長をサポートする重要な仕組みとなります。ここでは、それぞれについて具体的に解説していきます。
時間や場所を問わず自分のペースで学習できる
eラーニングの最大の利点の一つは、学習者が時間や場所を選ばずに学習できることです。従来の集合研修では決められた時間・場所に参加する必要があり、業務の都合や個人の事情によっては参加が難しくなることもあります。しかし、eラーニングであれば、インターネット環境があれば自宅や外出先でも学習が可能です。また、早朝や深夜など、学習者のライフスタイルに合わせて学習のタイミングを選べるため、仕事の合間や移動時間などを有効活用することができます。さらに、理解が進むまで何度でも学習を進めることができるため、短時間で効率的に学びたい人も、じっくりと時間をかけて学びたい人も、それぞれのペースに応じた学習が可能です。この柔軟性が、従業員の学習の継続を促し、スキルの向上につながる大きなメリットとなります。
個別最適化された学習が可能
eラーニングは、学習者のスキルや知識レベルに応じて個別最適化された学習が可能です。従来の集合研修では、全員が同じ内容を同じペースで学ぶため、すでに知識を持っている人にとっては退屈に感じることがあり、逆に初心者にとっては内容が難しすぎる場合もあります。しかし、eラーニングでは、学習者の理解度に応じて異なるコンテンツを提供する適応型学習システムが活用できます。例えば、事前テストの結果に基づいて適切な学習内容が提示されたり、苦手な分野を重点的に学習できるように設計されたりすることが可能です。これにより、学習者は自身の課題に応じた学習ができ、効率よくスキルアップを図ることができます。また、個々の進捗状況を記録し、必要なタイミングで復習を促す機能もあるため、学習の定着がより効果的に行えます。
反復学習が可能
eラーニングのもう一つの大きな利点は、反復学習が容易にできる点です。従来の集合研修では、一度の講義を聞いたら終わりで、後から復習しようと思っても詳細を思い出せないことがよくあります。しかし、eラーニングでは、一度学習した内容をいつでも再確認できるため、理解が不十分な箇所を何度でも復習することができます。特に、難易度の高い専門知識や業務手順を学ぶ際には、繰り返し学習することで理解が深まり、実務での活用につながりやすくなります。また、クイズや確認テストなどを活用することで、自分の理解度をチェックしながら学習を進めることができるため、知識の定着度が向上します。さらに、定期的に更新されるコンテンツにアクセスすることで、新しい情報を取り入れながら学び続けることが可能となり、学習の習慣化にもつながります。
06eラーニング導入における従業員側のデメリット
企業がeラーニングを導入する際、手軽に学習できるメリットがある一方で、従業員側には次のようなデメリットが生じる可能性があります。
- ・自己管理が必要
- ・疑問点をすぐに解決しにくい
- ・学習環境に左右される
これらのデメリットを軽減するためには、学習の進捗管理をサポートする仕組みを整えたり、質問対応の充実、インタラクティブなコンテンツの導入などの工夫が必要です。ここでは、上記のデメリットについて具体的に解説していきます。
自己管理が必要
eラーニングでは、学習の進捗を自分で管理する必要があります。従来の集合研修では、決まった時間に受講するため、学習のペースが自然と保たれます。しかし、eラーニングは時間や場所を自由に選べる分、学習の計画を立て、継続的に取り組む姿勢が求められます。特に、業務が忙しい場合や、モチベーションが低いと後回しになりがちです。また、明確な期限が設定されていない場合、学習の優先度が下がり、途中で挫折してしまうこともあります。そのため、企業側は適切な進捗管理ツールやフォローアップの仕組みを導入し、学習の習慣化を促す工夫が必要になります。
疑問点をすぐに解決しにくい
eラーニングは自己学習が基本であるため、学習中に疑問が生じた際にすぐに質問できないというデメリットがあります。集合研修では講師に直接質問できるため、その場で理解を深めることができますが、eラーニングでは即時の対応が難しい場合があります。特に、専門的な内容や実務に直結する学習では、適切な回答を得るまでに時間がかかると、学習のモチベーションが低下する可能性があります。この課題を解決するためには、FAQやフォーラム、チャット機能などを活用し、疑問を解決しやすい環境を整備することが求められます。
学習環境に左右される
eラーニングは、学習者が自分の好きな場所で受講できるメリットがある一方で、学習環境に左右されやすいというデメリットもあります。例えば、自宅やオフィスの環境によっては、周囲の騒音や業務の合間で集中しにくい場合があります。また、インターネット環境が不安定な場所では、動画がスムーズに再生されなかったり、システムにアクセスできなかったりすることもあります。こうした問題を防ぐためには、学習者が集中しやすい環境を確保する工夫や、オフラインでも学習できるコンテンツの提供が必要になります。
07eラーニングを導入する際のフローを解説

eラーニングを導入する際のフローを、以下の4つに分けてご紹介します。
- 1:情報収集
- 2:業者の選定
- 3:契約〜導入準備
- 4:運用開始
1:情報収集
コンテンツ・LMSの機能・費用の3つの軸で、情報収集すると良いでしょう。いくらコンテンツとLMSが優れていても予算を超える費用はかけることができないため、やはり費用感も重要になるでしょう。コンテンツとLMSに関しては前述した通り、自社の課題を明確にした上で、誰が主にe-ラーニングを利用するのかを考えて検討する必要があります。多くの企業では、デモアカウントを付与して実際の画面を体験することができるので、担当者は少し手間に感じるかもしれませんが、自分で体験してみることをおすすめします。
2:業者の選定
情報収拾で目星をつけた企業の中から、実際に業者を選定する作業に移ります。どの企業にも良し悪しはあるものなので、自社が解決したい課題に最適なツールを選ぶようにしましょう。この際に、多くの企業が利用しているからといった理由で導入を決めるべきではありません。確かに導入企業の多さは安心材料の1つにはなるかもしれませんが、実際に利用してみたら自社の課題に対して効果的な解決策になっていない可能性も十分にあります。また、大手の導入目的と自社の導入目的は異なる可能性もあるため、導入企業や実績といった指標は参考材料の1つにはすべきですが、ツール導入の決め手とするべきではないのです。
3:契約〜導入準備
業者が決まったら、あとは契約して導入の準備を進めるだけです。特に導入準備の部分ではサポート体制が充実しているかどうかが重要になります。初めて利用するツールなので、どの画面で管理するのか、どのように社内に周知するのかなど、知らないことばかりのはずです。ある程度の取扱説明書のようなものは付与されるかもしれませんが、聞いた方が早い内容も多くあるでしょう。その際に担当者のサポートがすぐに受けられるかどうかは、実装までの時間短縮にも繋がるため、検討しておくべき材料の1つと言えます。また、一定期間は伴走してくれるサービスを行なっている企業もあるので、伴走サービスも上手に利用してe-ラーニングを社内に導入していきましょう。
4:運用開始
運用が開始したら、エラーなどの対応が主な業務となるでしょう。オンライン上で全て行うので、エラーがサーバー側の問題なのか利用者側の問題なのか見極める必要があります。サーバー側の問題は問い合わせをすれば解決されますが、利用者側の問題だった場合は、研修担当者や人事担当者がエラー解決に向けて尽力しなければなりません。運用開始の前に、想定されるエラーを洗い出しておき、その対処法を誰でもアクセスできる社内情報共有システムにアップロードしておくなどの準備をしておくと、スムーズな運用が可能になるはずです。
08Schooのeラーニングの導入事例
eラーニングを導入する流れを解説しましたが、ここではSchooのeラーニングサービスを導入した企業の事例をご紹介します。
KDDI株式会社
通信を中心に周辺ビジネスを拡大する「通信とライフデザインの融合」を推進しているKDDI株式会社。社員一人ひとりが自立的に学び、組織の成果につなげる姿勢を持つことを課題としていました。 そこで約9,000本の研修動画を提供し、各社員のレベルに合わせてオンラインで学べるSchooの導入を決めました。 活用方法は学習進捗のグラフや視聴時間トップ3を共有して、学習のモチベーション維持に努めているそうです。 今後は、各社員が自分の課題を分析し、Schooを活用して学ぶことで自主学習のサイクルを定着させていくことを目指しているそうです。
株式会社丸井グループ
百貨店と商業施設の小売、フィンテックを営む株式会社丸井グループはコロナ禍で研修や学びの場が減ってしまったことを課題としていました。オンラインかつ、生放送の授業を通じてリアルタイムで双方向性のある学習ができることを理由にSchooの導入を決定したそうです。 活用方法は半年区切りで利用したい人を公募して抽選し、集合学習機能を活用して利用を促進しています。今後はオンライン集合学習で生放送への参加を促進しつつ、自発的に学んでいく風土を加速させていくことを目指しているそうです。
サントリーホールディングス株式会社
酒類、食品事業をはじめとして、健康食品事業など新規分野にも取り組み、国内に限らずアジア・中国での事業展開やアメリカ・オセアニアにおける飲料ビジネスなど、世界各国で幅広く事業を展開しているサントリーホールディングス株式会社。 外部から学び、刺激を受けられる機会作りが足りておらず、社員の危機意識が不足していることが課題でした。そこで約9,000本の研修動画を提供し、ビジネススキルから雑学まで幅広く学べるSchooの導入を決めました。 活用方法は推奨授業を選定し、研修カリキュラムを作成。また、社内限定の生放送を実施して利用を促進したり、動画視聴とディスカッションを組み合わせて反転学習を行っています。 今後は、生放送授業への参加促進で外部から学べる機会を増やすとともに、学んだ内容をアウトプットできる仕組みを整えていくことを目指しているそうです。
09Schooが提供する企業向け学習パッケージ
schooビジネスプランでは、動画配信という形でさまざまなニーズに応えられる授業を提供しています。授業へのご登壇には、各業界における第一人者や著名な専門家の方々をお迎えしています。ご登壇される講師の方々は、ビジネス現場での経験に基づいた事例などを教えてくださるので授業は具体的でわかりやすく、受講者はチャットなどを通じて講師に直接質問をすることもできるため、eラーニングであっても、実際の研修を受けるのと限りなく近い状態で学習することが可能です。受け身型の学習にならないようなコンテンツが多いのも、Schooのeラーニングの特徴です。
「研修をしてもその場限り」「社員が受け身で学ばない」を解決!
研修と自己啓発で学び続ける組織を作るスクーの資料をダウンロードする
■資料内容抜粋
・大人たちが学び続ける「Schoo for Business」とは?
・研修への活用方法
・自己啓発への活用方法 など

10Schooのオンライン研修を紹介
Schooビジネスプランでは、オンライン研修に使える、6,500本を超える数の幅広いジャンルの授業をご用意しており、様々なスキルやノウハウを、オンラインで学ぶことができます。授業の講師には、各業界で働くトップランナーの方々をお迎えしています。それぞれの講師自らが経験したことに基づいて授業を行うため、分かりやすく、かつ実践で活かすことができるスキルやノウハウを学ぶことができます。さらに、生放送の授業限定ですが、受講者から講師にチャットで質問することもできるため、受け身型の学習にならないという点も、Schooのオンライン学習の特徴です。
Schooの研修パッケージ
Schooビジネスプランでは9,000本以上の授業から、自由に研修で使用する授業を選択し、各社に適した研修カリキュラムを組むことができます。また、100本以上の研修カリキュラムのテンプレートを用意しているので、これまで手間のかかっていた研修設計も、カリキュラムと対象者を選択するだけで完了することができ、研修担当者の工数を大きく削減することもできます。
階層別研修におすすめの研修パッケージ
階層別研修では、新入社員には基礎的なマナーやスキルを学んでもらい、中堅社員や管理職には部下の育成やマネジメントなどについて学んでもらうことが一般的です。ここでは、新入社員から管理職までの研修におすすめの研修パッケージを紹介します。
-
「ロジカルシンキングとは何か」や「ロジカルシンキングの基礎となる技術」などについて学ぶことができるパッケージです。
-
このパッケージでは、新入社員や若手社員が最低限知っておくべきExcelのスキルを学ぶことができます。
-
全10時間で、ビジネスマナーや報連相を学ぶことができるパッケージです。
-
報連相やPDCAといったビジネスマンとしての基礎の部分をしっかりとやり抜く「業務遂行力」について学ぶことができるパッケージです。
-
ビジネスパーソンに必須である課題解決力を身につけられる研修パッケージです。
-
社員一人ひとりが自分の悩みに合わせたコミュニケーションスキルについて学ぶことができる研修パッケージです。
-
マネージャーがチームのパフォーマンスを最大化させるために必要な部下育成のスキルを学ぶことができるパッケージです。
職種別研修におすすめの研修パッケージ
職種によって求められるスキルは様々ですが、Schooの研修パッケージを活用して職種別研修を行うことができます。Schooでは、営業職からデザイナー・エンジニアまで、幅広い職種に対応した授業を用意しているため、多様な職種に対応した研修を行うことができます。
-
営業経験が浅い、もしくは経験のない方を対象とした研修パッケージです。
-
基礎からwebマーケティングを学びたいという方を対象とした研修パッケージです。
-
プログラミング言語Javaを基礎から学びたい方を対象にしたパッケージです。
-
1人でWebデザインの全行程を行えるようになりたいWebデザイナーの方を対象とした研修パッケージです。
-
WebエンジニアとしてこれからRubyを勉強したいという方に向けて、基礎から学んだ知識を活用してWebアプリケーション作成を行うことのできる研修となっています。
テーマ別研修におすすめの研修パッケージ
社員それぞれの課題や改善点によって必要になってくるスキルは違います。Schooではビジネスマナーからチームビルディングまで、様々な種類の研修に対応できる研修パッケージを用意しています。
-
リモートワークで社内のコミュニケーションに課題を感じている、もしくはオンラインコミュニケーション力を身につけたい方を対象とした研修パッケージです。
-
チームビルディングの基礎的なことから、チームで成果を出すために必要なことや、現場力を上げるための仕掛けづくりなどを学ぶことができるパッケージです。
-
初めてロジカルシンキングを学ぶ方を対象に、基礎から学ぶことができるパッケージです。
-
部下に業務指導を行う管理職向けに、業務指導とパワハラの線引きの判断要素や業務指導とパワハラの線引きの判断要素が学べる研修パッケージです。
-
デザイナーやアプリ開発に関わる企画職、エンジニア1人1人がアプリデザインの考え方やプロトタイプ制作について学習できるパッケージです。
-
デザイナーとしてこれからWebデザインを勉強したいという方に向けて、デザインの基礎(レイアウト、色、文字、デザインの考え方など)とAdobe Photoshop CC / Illustrator CCの使い方について学ぶことができる研修パッケージとなっています。
管理画面で受講者の学習状況を可視化できる
Schooビジネスプランには学習管理機能が備わっているため、研修スケジュールの作成を容易に行うことができます。さらに、社員の学習進捗度を常に可視化することができる上に、レポート機能を使って学んだことを振り返る機会を作ることも可能です。ここでは学習管理機能の使い方を簡単に解説します。

まず、Schooビジネスプランの管理画面を開き、「研修を作成するという」ページで作成した研修の研修期間を設定します。ここで期間を設定するだけで自動的に受講者の研修アカウントにも研修期間が設定されるため、簡単にスケジュールを組むことができます。

この、管理者側の管理ツールでは受講者がスケジュール通りに研修を受けているかを確認することができます。もし決められた研修をスケジュール通りに行っていない受講者がいれば注意したり、話を聞くことができるなど、受講者がしっかりスケジュールを守っているかを確認することができます。
11まとめ
e-ラーニング導入を成功させるには、自社の課題を明確にする必要があります。その課題がe-ラーニングを導入することで解決されない可能性もあるため、まずは自社の課題が何かを具体的にしましょう。その上で誰が利用するのか、どのようなコンテンツが必要なのかを洗い出し、管理する側に必要な機能も検討する必要があります。導入目的が研修であるならば、社内の利用促進は考える必要がないですが、福利厚生の1つとしてや、人材育成目的として導入するという場合は、どのように利用促進するかも導入前に考えておきましょう。