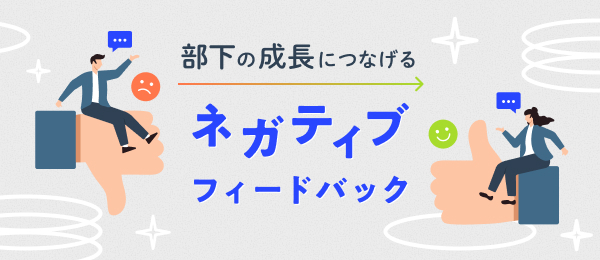アサーティブコミュニケーションとは? 人間関係を円滑にする伝え方を紹介

アサーティブコミュニケーションとは相手の気持ちを尊重しつつ、適切に自己主張するコミュニケーションの手法です。上手に活用することで円滑な人間関係を築くことに役立ちます。当記事ではアサーティブコミュニケーションを用い、相手を不快にさせず自分もストレスを溜めない、快適なコミュニケーションについて解説します。
01アサーティブコミュニケーションとは
アサーティブ(assertive)には「自己主張する」という意味があります。自己主張といっても一方的に自分の主張を伝えるのではなく、相手の気持ちに配慮し、かつ自分の気持ちも大切にする伝え方のことを指します。アサーティブコミュニケーションを身につけることで、自分もストレスを溜めず、相手も不愉快にさせない良好な意思疎通が可能になります。
アサーティブコミュニケーションが人間関係を円滑にする理由
相手に気を遣いすぎて言いたいことが言えずストレスを抱え込んでしまったり、反対に感情的に主張しすぎて関係が悪化してしまうケースは珍しくありません。アサーティブコミュニケーションは、性格を変えるものではなく、「どのように伝えるか」を工夫することで、衝突や我慢を最小限に抑えながら対話を進めるための手法です。相手の立場を尊重しながら、自分の考えも率直に伝えることで、双方が納得感を持てる関係が生まれ、信頼関係の維持や心理的安全性の向上につながります。訓練によって誰でも身につけられるスキルであり、意識して活用することで前向きで円滑な人間関係の構築が期待できます。
自分も相手も尊重する「Win-Win」の考え方
アサーティブコミュニケーションの根底にあるのは、「自分だけを守る」のでも「相手に合わせ続ける」のでもなく、双方が尊重されていると感じられる“Win-Win”の関係を目指す考え方です。相手の感情や立場を理解しながら、自分の意見や感情も率直に伝えることで、一方的な我慢や強引な押し付けを避け、建設的で協力的なコミュニケーションが可能になります。このWin-Winの姿勢は、信頼関係を育み、心理的安全性の高い良好な職場づくりにもつながる重要な要素といえるでしょう。
02アサーティブコミュニケーションの目的
アサーティブコミュニケーションは、単に「優しい伝え方」や「言い方を柔らかくする」ための手法ではありません。相手の立場や感情を尊重しながら、自分の意見や考えも適切に表現することで、無用な衝突や我慢を減らし、健全で建設的なコミュニケーションを実現することを目的としています。ここでは、その背景や企業・職場における重要性について整理します。
なぜ今、アサーティブコミュニケーションが求められるのか
働き方の多様化、価値観の違い、オンラインコミュニケーションの拡大などにより、職場での意思疎通はこれまで以上に複雑になっています。従来の「察する」「空気を読む」だけではすれ違いが生じやすく、一方的な主張や我慢が積み重なることで関係性が悪化するケースも少なくありません。そのような環境のなかで、お互いを尊重しながら率直に伝え合うアサーティブコミュニケーションは、信頼関係を保ちながら前向きに協働するための基盤として大きな役割を果たします。
ハラスメント防止・心理的安全性との関係
アサーティブコミュニケーションは、ハラスメント防止や心理的安全性の向上とも深く関係しています。攻撃的な言い方や威圧的な指示が減ることで、相手を傷つけるコミュニケーションが起こりにくくなり、受け身や沈黙による不満の蓄積も軽減されます。また、率直に意見を伝えやすい環境が生まれることで、「言いたいことが言えない」「間違っても指摘できない」といった不安が緩和され、安心して意見交換ができる職場づくりにつながります。その結果、組織全体のコミュニケーションの質向上にも寄与します。
管理職・評価者にとっての重要性
管理職や評価者にとって、アサーティブコミュニケーションは特に重要なスキルです。部下に対する指導・フィードバック・評価面談などの場面では、ただ厳しく伝えるだけでも、曖昧に配慮しすぎるだけでも問題は解決しません。相手の立場を尊重しつつ、必要な指摘や改善点を明確に伝える能力が求められます。アサーティブな関わり方ができれば、部下の納得感や成長意欲を高めるとともに、信頼関係を損なわずに組織として求める方向へ導くことが可能になります。
03アサーティブコミュニケーション4つの柱とは
NPO法人アサーティブジャパンの代表理事・森田汐生氏は、アサーティブコミュニケーションを構成する4つの柱について紹介しています。ここでは、Schoo講座「ハラスメントへの「アサーティブ」な対応 - 全ビジネスパーソン向け」の内容を参考に、森田氏が提唱しているアサーティブコミュニケーションの4つの柱について解説します。
誠実
まず「誠実」とは、自分自身にも相手にも嘘をつかず、真摯に向き合う姿勢を指します。本心を誤魔化したり、相手を操作しようとしたりするのではなく、互いを尊重したうえで率直に対話することが重要です。たとえ耳の痛い意見や批判を受けたとしても、感情的に否定するのではなく、その背景や意図を冷静に受け止めようとする姿勢が信頼関係の構築につながります。こうした誠実な対話が、双方の立場を尊重しながら問題解決へ進むための基盤となるのです。
率直
「率直」とは、自分の考えや感情、要望を回りくどい表現ではなく、具体的かつ分かりやすく伝えることを意味します。沈黙や遠回しな表現、嫌味な態度による間接的な意思表示ではなく、「私はこう思う」「こうしてほしい」と明確に言葉にすることで、誤解や推測によるすれ違いを減らすことができます。事実・感情・要望を分けて伝えることで相手が受け取りやすい対話が成立し、透明性の高いコミュニケーションが実現するのです。
対等
「対等」とは、職場での役職や経験の差にかかわらず、一人の人間として相手を尊重して向き合う姿勢を指します。相手を見下して攻撃的になったり、逆に自分を卑下して極端に遠慮したりするのではなく、互いの権利と立場を等しく尊重することが重要です。この対等な関係性があることで、安心して意見を伝え合える心理的安全性が保たれ、立場を超えた建設的な対話が可能になります。対等な姿勢は、協力して課題に向き合うための大切な前提といえます。
自己責任
「自己責任」とは、自分の発言や行動だけでなく、「伝えなかった」という選択を含めたコミュニケーションの結果についても自ら責任を持つ姿勢を意味します。自分の感情や不満を相手だけの問題として捉えるのではなく、どのように伝え、どのように関わったかに目を向けることで、主体的に人間関係を築いていく意識が高まります。自らの意思で対話を選択し、その結果として生じる変化や合意を受け止める姿勢が、自律した健全な人間関係の形成につながります。
▶研修・人事育成担当者限定!『ハラスメントへの「アサーティブ」な対応 - 全ビジネスパーソン向け』を無料で視聴する
-
 NPO法人アサーティブジャパン 代表理事
NPO法人アサーティブジャパン 代表理事
岡山県生まれ。一橋大学社会学部卒業。学生時代、イギリス滞在中にアサーティブに出会う。社会福祉士の資格を取得後、渡英先でソーシャルワーカーとして勤務した。アサーティブトレーナーの資格を取得して帰国後、2004年にNPO法人アサーティブジャパンを設立。多様な個人がお互いに誠実で対等な人間関係を築くことを目的に「アサーティブ」を伝える仕事を続けて20年、全国のトレーナーと共に、年間2万人を超える方々にアサーティブの研修・講演をしています。多様性が尊重され価値が認めあえる社会を願って、全国を飛び回っています。好きなことは、双子の子どもと家族の時間、それから一人ピアノを弾くことです。
04アサーティブではない3つのコミュニケーションタイプ
まずは、人間関係を悪化させやすいアサーティブではないコミュニケーションについて見てみましょう。次の3つのタイプが挙げられます。いずれのコミュニケーションタイプも、根底にあるのは自己中心性であるといえます。
攻撃的タイプ
攻撃的タイプは、自分の意見や感情を一方的かつ強い口調で相手にぶつけてしまうコミュニケーションスタイルです。本人にとっては「はっきり伝えている」つもりでも、相手にとっては威圧的に感じられやすく、不快感や反発、萎縮を招く原因となります。結果として、相手が距離を置くようになったり、建設的な話し合いが成立しなくなったりする可能性があります。短期的には主張が通るように見えても、信頼関係や心理的安全性を損なうため、職場やチームにおいて望ましいコミュニケーションとはいえません。
受け身的タイプ
受け身的タイプは、対立や摩擦を避けるために、自分の意見や感情を十分に表現しないコミュニケーションスタイルです。その場が円満に収まるように見える一方で、自分の不満や違和感をため込みやすく、ストレスや疲弊につながるリスクがあります。また、周囲から「本音が分からない」「頼りづらい」と認識され、意思決定や連携に影響が出ることも考えられます。結果的に、本人だけでなくチーム全体の関係性にも影響を及ぼす可能性があるため、適切な自己表現が重要になります。
作為的タイプ
作為的タイプは、直接的には表現せず、遠回しな言い方や態度、皮肉や示唆的な言動などで自分の不満や意図を伝えようとするコミュニケーションスタイルです。表面上は衝突を避けているように見えても、相手に不信感や違和感を抱かせやすく、「何を考えているのか分からない」「気を使う相手」という印象につながりやすくなります。結果として、コミュニケーションが複雑化し、不要な誤解や感情的なわだかまりを生む可能性があります。率直で透明性の高い対話を行うためにも、意図を明確に伝える姿勢が重要です。
05アサーティブな自己主張のポイント
ここまで、アサーティブではない自己主張のタイプを見てきました。いずれも相手を不愉快にさせたり、自分がストレスを溜めたりと健全なコミュニケーションとはいえないようです。それではアサーティブな自己主張とはどういったものか、4つのポイントを確認していきます。
主語は「私」で伝える(Iメッセージ)
相手(you)ではなく、私(I)を主語にして伝えることで、攻撃的な表現になることが避けられます。「私がOOだから、あなたにOOしてほしい」「あなたがOOしてくれると、私はOOだ」というような伝え方です。 例えば、相手の話に専門用語やカタカナ語が多く理解しにくいとき、「あなたの話は分かりにくいです」と言うと、相手を責めるニュアンスが強くなります。「私の勉強不足で分からない言葉があります、もう少し噛み砕いて説明していただけると(私は)ありがたいのですが」というように、「私」を主語にすると率直に自分の気持ちを伝えやすくなります。
正直に伝える
自分の気持ちを偽らずに正直に伝えることは、相手に対する誠実さであるといえます。たとえ意見の対立があったとしても、自分の気持ちに背いてまで賛同する必要はありません。その場合は一旦、相手の考えを受け止めたうえで、自分の考えを示すと良いでしょう。冷静に相手の話を聴き、言葉を選んで自分の意見を伝えることで相互理解が深まります。
対等な立場で伝える
アサーティブコミュニケーションでは、対等な立場で自分の意見を伝えることが重要なポイントです。上司と部下といった上下関係を理由に、意見を曲げ我慢することは、その場での衝突は避けられるかもしれませんが、問題の根本的な解決ができないため誠実であるとはいえません。また、上下関係を利用して、強い立場の者が意見を押し通すといったこともあってはなりません。
すべては自己責任
アサーティブコミュニケーションにおいては、すべてのコミュニケーションの結果は自己責任と考えることが必要です。相手の非を責める気持ちがあると、自らを省みることをしなくなります。コミュニケーションがうまくいかない場合、多少なりとも自分に責任があると考えることで、事態を好転させようとする工夫が生まれます。
06アサーティブコミュニケーションのメリット
アサーティブコミュニケーションは、日常の人間関係だけでなく、職場の人間関係にもメリットをもたらすとして重要視されています。相手に配慮しながら自分の考えを率直に伝えられる状態は、コミュニケーションの活性化とチームワークの強化が図られ、生産性の向上につながるメリットがあります。
離職の防止
離職の原因としてもっとも多いのは、職場の人間関係の悪化であるといわれています。アサーティブによる良質なコミュニケーションが浸透している職場では、良好な人間関係が保たれていて、従業員の離職は少ないのではないでしょうか。こうした職場環境はストレスが溜まりにくく、従業員のメンタルヘルスも良い状態がキープできているといえます。
ハラスメントの防止
コミュニケーションの質が向上し、攻撃的で嫌味な自己主張がなくなることで、無用なハラスメントが発生しなくなります。アサーティブコミュニケーションが浸透した職場においては、お互いが相手の気持ちに配慮するためハラスメントが起こりにくい好循環が生まれているのではないでしょうか。
コミュニケーションロスを防止できる
コミュニケーションロスとは、お互いの意思疎通が不足していることに起因する、仕事上のミスや損失、トラブルを意味します。アサーティブコミュニケーションでは相互の意見交換が円滑に行われるため、職場内の情報共有が活発になり、コミュニケーションロスを防止する効果が期待されるのです。
率直に自分の意見を主張できるようになる
職場内やチーム内で意見交換を行う場面において、素晴らしいアイデアが浮かんでいても、アサーティブコミュニケーションが実現できていなければ、そのアイデアを伝えることが難しくなります。アサーティブコミュニケーションを身につけることによって、受身になることなく自分の意見やアイデアを全体へ的確に伝えられるため、議論の活発化を期待できます。
生産性の向上が見込まれる
アサーティブコミュニケーションでは、相手に対して明確かつ的確に意見を伝えるため、仕事に関する情報共有をより詳しくスムーズに行えるようになります。結果として、相互で仕事量や分担の調整が正しくできるようになり、業務効率が向上すると考えられるのです。業務効率が上がれば、全体でこなせる仕事量が増え、最終的には職場や企業の生産性の向上につながると期待できます。
良好な精神状態が保てるようになる
アサーティブコミュニケーションができないままでは、自分の意見を伝えられずに相手の意見を受け入れる一方で、過度のストレスが溜まってしまうおそれがあります。アサーティブコミュニケーションができない従業員は、仕事や悩みを抱え込んでしまい、精神的に追いつめられてしまうのです。上記のような人間は、アサーティブコミュニケーションを身につけることによって、率直に自分の意見を伝えられるようになり、精神状態を良好に保てると期待できます。
働きやすい職場環境を作れる
アサーティブコミュニケーションが職場内で行われると、従業員はそれぞれの価値観や考え方を相互に尊重できるようになり、円滑なやり取りと良好な人間関係が実現されます。また、アサーティブコミュニケーションの恩恵として、ハラスメントの防止が期待できることも、働きやすい職場環境の形成に寄与するのです。
07アサーティブコミュニケーションのデメリット
アサーティブコミュニケーションはメリットだけではなくデメリットもあります。ここでは主なデメリットを3つ解説します。
あらゆる場面で有効に使えるわけではない
アサーティブコミュニケーションは、自己主張し、自分の権利や意見を適切に表現するための有益なスキルですが、すべての状況で適切ではありません。特に、非常に感情的な状況や緊張した雰囲気の中で、アサーティブな態度を取ることが難しい場合があります。また、組織の文化などによって、アサーティブなコミュニケーションが許容されない場合もあります。そのため、状況や相手との関係性を考慮しながら、適切なコミュニケーションスタイルを選択することが重要です。
相手に攻撃的な印象を与える可能性がある
アサーティブな態度が相手に攻撃的な印象を与えることがあります。強く自己主張することで、相手が攻撃されたり、傷ついたりする可能性があります。特に、コミュニケーションのトーンや表情、言葉の選び方などが適切でない場合、相手を威嚇したり怒らせたりすることがあります。アサーティブなコミュニケーションを行う際には、相手の感情や立場を尊重し、言葉遣いやトーンに気を配ることが重要です。
コミュニケーションにエネルギーを使いすぎる可能性がある
アサーティブなコミュニケーションは、自己主張や自己表現を促進するために重要ですが、その過程で多くのエネルギーを消費することがあります。特に、相手との対立や議論が続く場合、アサーティブなスタンスを維持するためには精神的なエネルギーを要します。このような状況下では、ストレスや疲労が生じる可能性があります。そのため、バランスを保ちつつ、自己表現を行うことが重要です。自己主張をする一方で、ストレスを避けるための適切な休息やリラックスも必要です。
08アサーティブコミュニケーションのトレーニング方法
アサーティブコミュニケーションは前項で紹介したとおり、ビジネスの場面においてさまざまなメリットをもたらし企業の生産性を向上させると期待できます。アサーティブコミュニケーションのメリットを最大限受けるためには、全従業員が正しくトレーニングを行い、アサーティブコミュニケーションを体得することが望ましいです。ここでは、アサーティブコミュニケーションを強化するためのトレーニング方法について紹介します。
DESC法
DESC法とは、Describe(描写)、Express(説明する)、Suggest(提案)、Choose(選択)の頭文字を取った名称のトレーニング方法です。相手を傷つけることなく自分の意見を相手に納得してもらうトレーニングができます。
Describe(描写)
Describe(描写)では、客観的な事実のみを具体的に頭の中で思い描きます。このとき、自分の感情や思い込み、推測など主観が入らないように注意し、あくまでも客観的な事実のみを入れてください。主観が入ってしまうと、正しい情報を相手には伝えきれない可能性があります。
Express(説明する)
Express(説明する)では、前述のように描写した客観的事実に対する自分の感情や意見を相手に表現します。このとき、感情的にならずに冷静に相手に感情や意見を伝えることが大切です。感情を押し付けすぎることで、事実と論点がずれてしまったり、攻撃的になって、相手が怯んでしまいます。また、Expressは、Explain(表現)やEmpathize(共感する)、Expose(見せる)と呼ぶ場合もあります。
Suggest(提案する)
Suggest(提案)では、相手に伝えた事実の解決方法や妥協案を相手に提案します。相手に一方的に意見を押し付けるのではなく、あくまでも提案と依頼という形を取ることが大切です。一方的にならないためにもここでは、承諾して欲しいこと、対応してもらいたいことを具体的に伝えていくようにしましょう。また、Specify(具体的に挙げる)と表す場合もありますが、実施内容は同じと認識しましょう。
Choose(選択)
Choose(選択)では提案した事に対する相手の意見が「Yes」か「No」それぞれの場合に、自分が取るべき行動を選択します。Consequences(結果を伝える)と表すこともあります。注意したいのが、提案は全て通るわけではないということです。提案が通らなかった場合はより良い提案ができるように改めて、Suggestしましょう。
▼DESC法について詳しく知りたい方はこちらから▼
【関連記事】DESC法とは?4つのステップと注意点について解説する
アイメッセージ
相手に対して意見を伝えるとき、自分を主語にする伝え方のアイメッセージを取ることが大切です。反対に、相手が主語のユーメッセージでは、相手が強い命令口調や攻撃性を感じてしまうおそれがあるためです。 アサーティブコミュニケーションを実現するためには、主語は自分にして、「自分はこう思う」という柔らかい口調で意見を伝えることが欠かせません。結果として、相手との人間関係を悪化させず、円滑にコミュニケーションを行えると期待できるのです。
研修の実施
アサーティブコミュニケーションのトレーニング方法として、研修の実施は非常に効果的です。研修では、理論的な知識と実践的なスキルをバランスよく学ぶことが重要です。まず、アサーティブコミュニケーションの基本概念やその重要性についての講義を行います。次に、具体的な技術やテクニックを習得するためのワークショップやロールプレイングを実施します。これにより、参加者は実際のコミュニケーションシナリオを通じて、自己主張の方法や他者の意見を尊重する方法を練習できます。
09アサーティブコミュニケーション研修がもたらす効果
アサーティブコミュニケーション研修では、単に「言い方を柔らかくする」ことを目指すのではなく、自分と相手の双方を尊重しながら、率直で建設的な対話を行うための考え方とスキルを体系的に学びます。ここでは、研修で身につけることができる主なポイントを紹介します。
アサーティブな考え方(自分も相手も尊重)
まず学ぶのは、「自分だけが正しい」「相手に合わせるべき」というどちらか一方に偏った姿勢ではなく、双方を尊重するアサーティブな考え方です。自分の意見や感情を大切にしながら、相手の立場や状況にも配慮して対話するというアサーティブコミュニケーションの基本概念を理解することで、衝突や我慢に頼らない健全な関係づくりの土台を築くことができます。
具体的な伝え方の型(DESC法・Iメッセージ)
次に、実際のコミュニケーションで活用できる具体的な方法を学びます。例えば、事実・感情・提案・結果の順に伝える「DESC法」や、相手を責めるのではなく「私は〜と感じる」と表現する「Iメッセージ」など、実践の場で使いやすいフレームワークを身につけることができます。こうした“伝え方の型”を理解することで、感情的にならず冷静に意思表示を行えるようになります。
職場でのNG/OKの言い換え
研修では、実際の職場を想定した「言い方の違い」についても学びます。同じ内容を伝える場合でも、表現の選び方によって相手の受け取り方は大きく変わります。攻撃的・否定的になりやすいNG表現を、相手を尊重しながらも意図が正しく伝わるOK表現へ言い換える練習を行うことで、日常業務の中で自然にアサーティブなコミュニケーションが取れるようになります。
管理職・評価者が身につけるべき関わり方
さらに、管理職や評価者に求められるアサーティブな関わり方についても扱います。部下へのフィードバックや評価面談、指導場面では、配慮だけでも厳しさだけでも不十分です。必要なことを明確に伝えながらも、相手の尊厳を損なわないコミュニケーションを実践することで、納得感の高い対話や信頼関係の維持につながります。研修では、具体的な場面を想定したロールプレイなどを通じて、現場で活かせる実践力を養うことができます。
10アサーティブコミュニケーション研修|Schoo for Business
Schoo for Businessは、国内最大級9,000本以上の講座から、自由に研修カリキュラムを組むことができるオンライン研修サービスです。導入企業数は4,000社以上、新入社員研修や管理職研修はもちろん、DX研修から自律学習促進まで幅広くご支援させていただいております。
大企業から中小企業まで4,000社以上が導入

Schoo for Businessは、大企業から中小企業まで4,000社以上に導入いただいております。利用用途も各社さまざまで、階層別研修やDX研修としての利用もあれば、自律学習としての利用もあり、キャリア開発の目的で導入いただくこともあります。
導入事例も掲載しているので、ご興味のあるものがあれば一読いただけますと幸いです。以下から資料請求いただくことで導入事例集もプレゼントしております。そちらも併せて参考にいただけますと幸いです。
Schoo for Businessの特長
Schoo for Businessには主に3つの特長があります。
【1】国内最大級9,000本以上の講座数
【2】研修設定・管理が簡単
【3】カスタマーサクセスのサポートが充実
アサーティブコミュニケーション研修についてのSchooの講座を紹介
Schooは汎用的なビジネススキルからDXやAIのような最先端のスキルまで、9,000本以上の講座を取り揃えております。この章では、アサーティブコミュニケーションに関する授業を紹介いたします。
部下の成長につなげるネガティブフィードバック
本講座では、つい「叱る」「注意する」だけで終わってしまいがちなネガティブフィードバックを、相手の成長につながる建設的なコミュニケーションへと変える方法を学びます。ただ問題点を指摘するのではなく、「次にどうすればいいのか」を明確に伝え、前向きな行動変化を促すための考え方や具体的なポイントを、豊富な事例とともに分かりやすく解説します。
-
 アドット・コミュニケーション株式会社代表取締役
アドット・コミュニケーション株式会社代表取締役
立教大学文学部卒業後、株式会社服部セイコー(現セイコーグループ株式会社)にて営業、その後音楽業界企業にて社長秘書を経て2008年にアドット・コミュニケーション株式会社を設立。 研修講師、コンサルタントとして民間企業、官公庁の研修・講演の講師の仕事を歴任し、登壇数は4,500 回を超え、指導人数は25万人に及ぶ。その実績による豊富な事例やアンガーマネジメント、アサーティブコミュニケーション、アンコンシャスバイアス、アドラー心理学をベースにしたコミュニケーションの指導には定評があり、新入社員から管理職まで幅広い対象に研修、講演を実施。多くの企業でわかりやすく、実践的な内容が好評を得ている。 また、一般社団法人日本アンガーマネジメント協会の代表理事として協会運営に携わる。 著書は『すごいフィードバック 心が動き、行動が変わる!』(かんき出版)『アンガーマネジメント』『アサーティブ・コミュニケーション』(日経文庫)『アンガーマネジメント大全』(日経ビジネス人文庫)など20冊、中国、韓国、タイ、台湾でも翻訳出版され、累計30万部を超える
※研修・人材育成担当者限定 10日間の無料デモアカウント配布中。対象は研修・人材育成のご担当者に限ります。
“遠慮しがち”を脱するコミュニケーション
本講座では、「断りづらい」「言いづらい」「つい飲み込んでしまう」といった場面で、自分も相手も尊重しながら率直に意思表示をするためのアサーティブコミュニケーションを学びます。ありがちなビジネスシーンを題材に、誠実・率直・対等というアサーティブの考え方と、角を立てずに主張するための具体的な伝え方を分かりやすく解説します。
取引先や上司に対して言い出しにくさを感じている方、遠慮してしまうことで仕事が滞ったり、無駄なコミュニケーションが生まれていると感じている方に特におすすめです。「言いたいことを飲み込む」状態から一歩進み、率直に伝えられるコミュニケーションを目指したい方はぜひご覧ください。
-
 NPO法人アサーティブジャパン 代表理事
NPO法人アサーティブジャパン 代表理事
岡山県生まれ。一橋大学社会学部卒業。学生時代、イギリス滞在中にアサーティブに出会う。社会福祉士の資格を取得後、渡英先でソーシャルワーカーとして勤務した。アサーティブトレーナーの資格を取得して帰国後、2004年にNPO法人アサーティブジャパンを設立。多様な個人がお互いに誠実で対等な人間関係を築くことを目的に「アサーティブ」を伝える仕事を続けて20年、全国のトレーナーと共に、年間2万人を超える方々にアサーティブの研修・講演をしています。多様性が尊重され価値が認めあえる社会を願って、全国を飛び回っています。好きなことは、双子の子どもと家族の時間、それから一人ピアノを弾くことです。
※研修・人材育成担当者限定 10日間の無料デモアカウント配布中。対象は研修・人材育成のご担当者に限ります。
1行で好感度を上げる言葉えらび
本講座では、メールやチャットで「用件だけになってしまう」「なんだか味気ない」と感じる方に向けて、相手に好印象を与える“ひとこと”を自然に添えられる言葉選びを学びます。クッション言葉や一歩踏み込んだ+αのフレーズなど、実際のコミュニケーションですぐに使える表現を、実践を交えながら分かりやすく解説します。
テンプレート以外の言葉が思いつかない方、文章の印象を少しでも良くしたい方、文章コミュニケーションで信頼感や温かみを伝えたい方におすすめの授業です。「100点の文章」にひとこと添えて「120点」にするコツを身につけたい方は、ぜひご覧ください。
-
 伝える力[話す・書く]研究所/山口拓朗ライティングサロン主宰
伝える力[話す・書く]研究所/山口拓朗ライティングサロン主宰
出版社で編集者・記者を務めたのちに独立。27年間で3700件以上の取材・執筆歴を誇る。現在は執筆活動に加え、講演や研修を通じて「好意と信頼を獲得する伝え方の技術」や「伝わる文章の書き方」等の実践的ノウハウを提供。アクティブフォロワー数400万人の中国企業「行動派」に招聘され、北京ほか6都市で「Super Writer養成講座」も定期開催中。著書に『伝わる文章が「速く」「思い通り」に書ける 87の法則』(明日香出版社)『9割捨てて10倍伝わる「要約力」』『1%の本質を最速でつかむ「理解力」』(共に日本実業出版社)『マネするだけで「文章がうまい」と思われる言葉を1冊にまとめてみた。』(すばる舎)ほか25冊以上。 伝え方の本質をとらえたノウハウは言語の壁を超えて高く評価されており、中国、台湾、韓国など海外でも翻訳されている。
※研修・人材育成担当者限定 10日間の無料デモアカウント配布中。対象は研修・人材育成のご担当者に限ります。
11まとめ
コミュニケーションは、普段は無意識に行なっていることが多く、気づきを得ることが難しいものです。自分ではうまくコミュニケーションをとっているつもりでも相手はストレスを感じていることもあるかもしれません。アサーティブコミュニケーションを研修等で知ってもらうことは、自分のコミュニケーションの問題点に気づく良いきっかけとなります。健全な職場環境構築のために導入を検討してみてはどうでしょうか。