部下育成で大切なポイント9選!上司が押さえておくべきマネジメント術と進め方を解説

「部下育成」は、部下の能力や意欲を引き出し、その成長を支援することです。上司の適切なサポートは不可欠であり、個人の成長だけでなく、組織の生産性向上や活性化、チーム力強化へと繋がる重要な施策です。本記事では、その効果的な進め方や手法、成功の秘訣を解説します。
- 01.部下育成とは?
- 02.部下育成の重要性やメリット
- 03.部下育成でよくある失敗とその対策
- 04.部下育成がうまい上司の共通点とは?
- 05.部下育成で上司に必要なスキル
- 06.部下育成の代表的な手法
- 07.部下育成の進め方5ステップ
- 08.まとめ
「研修をしてもその場限り」「社員が受け身で学ばない」を解決!
研修と自己啓発で学び続ける組織を作るスクーの資料をダウンロードする
■資料内容抜粋
・大人たちが学び続ける「Schoo for Business」とは?
・研修への活用方法
・自己啓発への活用方法 など

01部下育成とは?
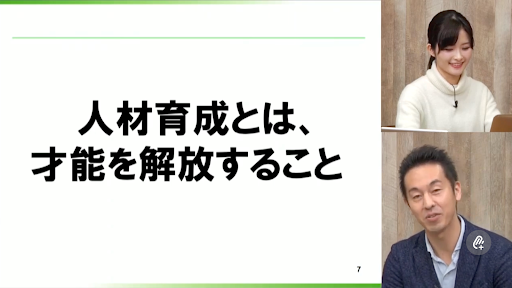
▶︎参考リンク:Schoo|サイバーエージェントに学ぶ人事養成コース
部下育成とは、部下が成果を上げられるよう、その成長を支援する重要な業務です。上司が個々の特性を理解し、能力向上と職場環境の両面から丁寧にサポートすることで、組織の活性化と将来を担う人材の育成に繋がります。
サイバーエージェントの常務執行役員CHOの曽山 哲人氏は、Schooの「サイバーエージェントに学ぶ人事養成コース」という授業内で、人材育成を「才能を解放すること」と定義しています。 この定義を用いるのであれば、部下育成とは部下の才能を解放すること。部下の特性や秘めている才能を見出し、その力を開花させ、発揮できるような支援をすることが部下育成と言えます。
02部下育成の重要性やメリット
部下育成は、人材の成長を支援し、生産性向上、組織活性化、ノウハウ蓄積を実現する重要施策です。
業務効率化・生産性向上に直結する
部下育成は、部下が成果を上げられるよう支援する重要な業務です。その活動を通じて優秀な人材が育つことは生産性の向上や業績アップに直結し、組織全体の活性化にも貢献します。MBO(目標管理制度)などにより部下が自ら目標達成プロセスを管理することで、業務効率の向上も期待できます。
人材育成のノウハウが組織に蓄積される
部下育成は、部下それぞれの能力向上に留まらず、組織全体の知見とノウハウを深める重要な取り組みです。上司が部下を指導・支援する過程で得られる、実践的な人材育成の知見が組織内に蓄積されます。その結果として、企業の持続的な競争力強化に繋げることができるでしょう。
組織全体が活性化する
部下育成は、将来の企業を担う優秀な人材を育み、組織全体の活性化に不可欠です。上司と部下の信頼関係が深まり、スムーズなコミュニケーションが促進されることで、チーム全体の意欲とパフォーマンスが向上し、結果的に生産性や業績向上にも寄与します。
03部下育成でよくある失敗とその対策
部下育成のよくある失敗には、簡単な仕事への限定、指示過多、目標不明確、高圧的態度、部下の成長スピードへの焦りなどがあります。この章では、部下育成でよくある失敗とその対策法について紹介します。
1:簡単な作業しか任せない
部下育成でよくある失敗の1つは、部下に対して簡単な業務や責任の軽い仕事しか任せないことです。これにより、部下は「自分は期待されていない」と感じ、成長意欲を失ってしまうことがあります。経験済みの業務ばかりでは新たな学びや育成には繋がらず、結果として部下の成長が期待できず、組織全体の生産性向上にも影響を及ぼします。上司には「任せる」「挑戦させる」覚悟が求められます。
対策:少しずつ新しいことに挑戦させる
この失敗への対策としては、部下の成長段階に合わせて、徐々に難易度の高い仕事を任せていくことが重要です。部下自身に課題を発見させ、解決策を考え実行する機会を与えることで、主体性を育成し、小さな成功体験を通じて自信をつけさせることが効果的です。
2:手取り足取り教えすぎて指示になってしまう
上司が手取り足取り教えすぎて「指示」になってしまうことも、部下育成のよくある失敗です。これにより、部下は自ら物事を考えなくなり、指示待ちの姿勢が定着してしまいます。部下の主体性が育たず、本来の成長が期待できなくなるだけでなく、組織全体の生産性にも悪影響を及ぼします。
対策:自発的に動くチャンスを与える
この失敗への対策としては、部下には自ら仕事のやり方を考えさせたり、主体的に動く機会を与えることが重要です。質問を投げかけ、課題発見や解決策の検討を促し、自発的な行動を後押ししましょう。
3:目標や計画が不明確
育成の目標や計画が不明確なまま場当たり的に進めてしまうという失敗も、部下育成をする上では珍しくありません。このような状況だと、部下は「何を、いつまでに、どのレベルで目指すのか」が分からず、成長の方向性を見失いがちです。結果として、上司は「教えても反応が薄い」「思うように育たない」といった悩みを抱え、組織全体の長期的な成長が阻害されてしまいます。
対策:育成のゴールと評価基準を明確にする
この失敗への対策としては、まず企業が求める人材像を基に育成のゴールを明確に設定し、部下と合意形成することが重要です。具体的かつ客観的な評価基準を設け、プロセスを含めて定期的に振り返り、継続的な成長を促しましょう。
4:押しつけや高圧的な態度をしている
上司が感情的・高圧的な態度を取ったり、自分の考えや価値観を一方的に押し付けたりすることで、部下は恐怖心から主体性を失い、指示待ちになるだけでなく、「自分は期待されていない」と感じて成長意欲を失ってしまうことがあります。時にはパワーハラスメントと見なされ、上司への信頼関係が崩れる原因にもなります。
対策:冷静なコミュニケーションを意識する
この失敗への対策は、感情的にならず、常に冷静なコミュニケーションを意識することが重要です。何か問題が起こった場合も決して部下の人格や人間性を否定せず、改善してほしい具体的な「こと」に焦点を当てて叱り、共感を示しながら対話を進め、部下自身に考えさせる機会を与えましょう。
5:部下の成長を急ぎ過ぎている
上司が短期的な成果を急ぎ、部下の成長を性急に求めることも、部下育成のよくある失敗の1つです。充分な育成時間を確保せず、焦って結果を出すよう求めることは、部下の過度なプレッシャーとなり、自信や成長意欲を奪ってしまいます。結果として、部下の自律的な学びが阻害され、組織全体の長期的な成長にも繋がりません。
対策:長期的な目線で部下と向き合う
この失敗への対策は、焦らず長期的な視点で部下の成長と向き合うことです。部下の状況や成長段階を考慮し、十分な育成時間を確保しながら、根気強く継続的に関わりましょう。小さな成功体験を積ませ、適切な振り返りを通じて、自律的な成長を促すことが重要です。
「研修をしてもその場限り」「社員が受け身で学ばない」を解決!
研修と自己啓発で学び続ける組織を作るスクーの資料をダウンロードする
■資料内容抜粋
・大人たちが学び続ける「Schoo for Business」とは?
・研修への活用方法
・自己啓発への活用方法 など

04部下育成がうまい上司の共通点とは?
部下育成がうまい上司は、部下を傾聴し、個性や価値観を受け入れ、自ら考える機会を与えます。また、成果だけでなくプロセスも評価し、定期的なフィードバックを通じて成長を促します。自身も学び続け、心理的安全性の高いチームを築き、強固な信頼関係を重視することが共通点です。
▶︎関連記事:人材育成ができる人とは|特徴や必要な能力、企業の取り組み例を紹介
1:成果だけでなくプロセスも評価できる
部下育成がうまい上司の共通点として、「部下の成果だけでなくプロセスも評価できること」が挙げられます。成果は外部要因に左右されるため、上司がプロセスに着目し、継続すべき点や改善すべき部分を確認してフィードバックを行うことが重要です。この意識を持つことで、部下は評価への納得度を高め、軌道修正しながらPDCAを回せるようになり、自律的な成長と自信につながります。
2:言動・行動に一貫性を持つ
部下育成がうまい上司は、言動・行動に一貫性を持つという共通点があります。特に発言に責任を持ち約束を守ることは、部下との強固な信頼関係を築く上で不可欠の要素です。上司の言行が一致していれば、部下は安心して業務に取り組め、指示も素直に受け入れやすくなります。口先だけで言行不一致な上司には、部下は従いたいとは思いません。 もし約束を変更せざるを得ない場合は、誠実に事情を説明し、次の機会には必ず約束を守る姿勢を示すことが重要です。これにより、部下は上司を尊敬し、自律的な成長が促されるでしょう。
3:感謝と謝罪を伝えられる
感謝と謝罪を適切に伝えられることも、部下育成がうまい上司の共通点の1つです。感謝や謝罪は関係構築の基本であり、上司が自身のミスや部下からのサポートに対し、役職や立場に関わらず誠実な態度を示すことで、円滑なコミュニケーションを促進し、部下との強固な信頼関係を築くことができます。 部下とコミュニケーションをとる際のポイントは、感謝や謝罪の気持ちが相手に確実に伝わるように意識することです。また、自身の言動が部下や周囲からどのように見られているか、客観的な視点で定期的に見直すことが重要です。これにより、部下は安心して業務に取り組め、上司への尊敬の念も深まるでしょう。
4:傾聴力があり、相手の話を最後まで聞ける
部下育成がうまい上司は、傾聴力があり、部下の話を最後まで真摯に聞きます。これにより、部下は「この人なら話を聞いてくれる」と安心感を抱き、心理的安全性が向上し、本音で話せる強固な信頼関係が築かれます。 また、上司が部下に関心を持ち理解しようと努めることで、育成効果も高まります。コミュニケーションでは、質問で理解を深め、自分の理解を伝え確認し、たとえ意見が異なっても一方的に否定せず、共感を示しながら対話を進めることが重要です。
5:部下の個性や価値観を受け入れられる
部下育成がうまい上司は、部下自身の個性や価値観を理解し、受け入れる共通点があります。部下はそれぞれ異なる属性を持つため、上司が自分の考えを一方的に押し付けず、部下の発言や行動の背景にある感情に関心を持って接することで、心理的安全性が確保され、仕事への意欲やパフォーマンスが向上します。 コミュニケーションでは、部下の考えをいきなり否定せず、まず共感を示してから対話を進め、合意形成を図ることが重要です。これにより、部下の主体的な成長と信頼関係の構築が促されます。
6:自分で考えることを促せる
部下育成がうまい上司は、部下に自ら考え、行動する機会を多く与える共通点があります。これにより、部下の主体性や問題解決能力、自信が向上し、自律的な成長を促せます。 コミュニケーションでは、一方的に指示せず「どうすれば解決できるか」など質問を投げかけ、部下自身に課題発見や解決策を考えさせます。失敗を恐れず挑戦できる環境を提供し、振り返りを通じて学びを引き出しましょう。部下の成長レベルに応じて適切にティーチングとコーチングのバランスを変えていくことが重要です。
7:定期的にフィードバックの機会を設けている
部下育成がうまい上司は、定期的にフィードバックの機会を設けています。定期的にフィードバックをすることで、部下は改善点を認識しやすく、アクションが上手く取れていない場合にも軌道修正がしやすくなります。また、フィードバックの頻度が多いことは、部下に「業務を見てくれている」という安心感も与えます。
8:管理職自身が学び、成長し続けている
管理職自身も学び、成長し続けていることも重要な要素の一つです。上司が知識やスキルを磨く姿勢は、部下の成長意欲の向上にも繋がり、ひいては成長志向の企業文化を醸成します。これにより、部下にとって良い手本となり、彼らの学びへの意欲を高めるでしょう。 コミュニケーションでは、自身の学びの姿勢を示すことで、部下は安心して新しい知識を共有したり、課題について相談しやすくなります。柔軟なリーダーシップを発揮し、部下と共に成長する関係を築くことが重要です。
9:安心できるチーム作りができる
部下育成がうまい上司は、部下が安心して本音を話し、失敗を恐れず挑戦できる心理的安全性の高いチーム環境を築きます。これにより、部下は主体的に考え行動できるようになり、自律的な成長が促されます。 相互理解を深めたり、チーム間での意見交換が行われる定例会を開いたりと、メンバー同士で成長し合うようなチームビルディングをすることも、部下育成が得意な上司に共通する点です。
05部下育成で上司に必要なスキル
部下育成には、上司のリーダーシップ、目標管理、コミュニケーション、論理的思考、柔軟な発想力が不可欠です。
リーダーシップ
部下の育成をする上で、リーダーシップは欠かせません。これは、単に命令するだけでなく、ビジョンを示し、自ら模範となることで部下の信頼とやる気を引き出す力です。 部下の意見を尊重し、適切なフィードバックを通じて信頼関係を築き、チーム全体を明確な目標へ導くことが重要です。上司自身も学び続け、柔軟なリーダーシップを示すことで、部下の成長意欲をさらに高めます。
ロジカルシンキング(論理的思考力)
ロジカルシンキング(論理的思考力)も、部下育成をする上で求められるスキルです。これは、感情や思い込みに囚われず、事実に基づいた判断や指示を行う力です。 上司が複雑な問題を分解し、優先順位をつけて解決へ導くことで、部下は適切な対処が可能となります。この思考プロセスを伝え、繰り返し実践を促すことで、部下自身の問題解決能力や自主性が向上し、自律的な成長が期待できます。論理的に考える習慣は、部下が自ら課題を発見し、解決策を見つける機会を与えることにもつながります。
目標管理能力
部下育成において上司に求められるスキルの1つに、目標管理能力があります。これは、部下の成長に不可欠な明確な目標を共に設定し、その進捗を管理しながら必要な支援を行う力です。 部下の強みや課題を把握した上で、目標をスモールステップに分解し、定期的なフィードバックや軌道修正を行うことで、部下の目標達成への意欲を高め、自律的な成長を促します。過度なプレッシャーを与えず、段階的な目標設定やサポートを示すことが重要です。
コミュニケーション力
部下育成において、コミュニケーション力も上司に求められる重要なスキルです。これは、傾聴とフィードバックを軸に、部下一人ひとりに合わせた伝え方で信頼関係を築く力を指します。 積極的に対話し、部下の話を最後まで真摯に聞き、本音を引き出すことで、心理的安全性を高め、部下の自律的な成長を促すことができます。十分な時間を確保し、感情的・高圧的にならず、部下の意見や感情を尊重することが重要です。
クリエイティブ力(発想力)
部下育成がうまい上司は、柔軟なクリエイティブ力(発想力)を備えています。これは、既存のやり方にとらわれず、新しい視点で部下の可能性を引き出すスキルです。 上司が常に新しい考え方や解決策を示し、固定観念に囚われずに物事を捉える姿勢を促すことで、部下は自らも創意工夫する意欲を高めます。さらに、新しい挑戦を奨励し、失敗を恐れずに試行錯誤できる環境を提供することで、部下自身の問題解決能力や主体性を向上させ、自律的な成長を促進します。結果として、チーム全体のイノベーションにも貢献できるでしょう。
06部下育成の代表的な手法
部下にスキル・能力を習得してもらう手法として、OJTやOff-JT、eラーニングがあります。また、MBOや1on1といったフィードバックの機会をつくる仕組みも、一種の部下育成の手法と言えるでしょう。この章では、部下育成の代表的な手法について紹介いたします。
OJT
部下育成の代表的な手法の1つに、OJT(On-the-Job Training)があります。これは、実際の業務を通じて知識やスキルを身につけさせる育成手法です。上司が実務の中で直接指導・助言を行うことで、現場で即座に役立つスキルを効率的に習得できます。また、日々の密なコミュニケーションを通じて部下の成長を後押しする効果が期待できるでしょう。
Off-JT
Off-JT(Off-the-Job Training)は、職場を離れて行われる研修やトレーニングを指します。企業内外の専門家による講義や演習、ケーススタディなどを通じて、実務では習得が難しい専門知識や体系的なスキルを効率的に学ぶことが可能です。 Off-JTは、部下に新しい技術や基礎知識をスムーズに身につけ、実務への適応が促進されるというメリットが期待できます。また、職場内での教育と比べて、リソースや学習効果の面で効率的である場合が多い点も利点です。
目標管理(MBO)
目標管理制度(MBO)は、部下自身が組織の方針と自身の目指す方向性を擦り合わせ、上司と共に具体的な目標を設定し、その達成プロセスを管理する取り組みです。上司は部下の強みや課題を把握し、現実的な目標設定から進捗管理、そして適切なフィードバックを通じて支援します。 MBOを導入することで、部下は目標達成に向けて主体的に業務へ取り組み、自律的な学びや成長が促されます。これにより、業務効率の向上や、目標達成への意欲向上も期待できるでしょう。
1on1
1on1は、上司と部下が定期的に1対1で面談を行うことで、部下の成長を促す育成手法です。1on1では、単なる業務進捗の確認に留まらず、部下が抱える課題や不安に耳を傾け、対話を通じて新たな気づきを与え、個別の成長をサポートします。 この継続的な関わりにより、上司と部下の相互理解が深まり、強固な信頼関係を構築できる点が大きなメリットです。また、部下は自身の成長を実感しやすくなり、業務へのエンゲージメント向上にも繋がるでしょう。
eラーニング
eラーニングは、パソコン、スマートフォンなどのデジタル機器とインターネットを利用して実施される教育・学習・研修の形態です。eラーニングは、上司が部下の学習進捗・習熟度をチェックし、提出課題へフィードバックを行うなど、双方向型の学習が可能です。特にリモート環境下での学習や、部下の自律的な学びを促す上で有効な手段と言えます。時間や場所に縛られず、個人のペースでスキルアップできる点がメリットです。
自己研鑽
自己研鑽は、上司が部下に対し学習テーマを与え、自発的な学びを促す方法です。最初は上司からの指示という外発的動機付けであっても、学習を続ける中で「役に立つ」「もっと学びたい」といった内発的動機付けへと変化することが期待できます。 部下が主体的に取り組むようになると、習熟の速度が向上し、自律的な成長が促される点が大きなメリットです。上司は、単に学習を促すだけでなく、進捗確認やプロセスに応じたフォローを行うことが重要です。
「研修をしてもその場限り」「社員が受け身で学ばない」を解決!
研修と自己啓発で学び続ける組織を作るスクーの資料をダウンロードする
■資料内容抜粋
・大人たちが学び続ける「Schoo for Business」とは?
・研修への活用方法
・自己啓発への活用方法 など

07部下育成の進め方5ステップ
部下育成は、まず現状を分析し課題を明確にし、次いで目標を設定します。その後、最適な育成手法を検討し、育成を実施します。最終的に評価・改善を行い、持続的な成長へとつなげます。
1:現状を分析し課題を明確にする
部下育成の進め方における最初のステップは「現状を分析し課題を明確にする」ことです。まず、事業や組織の目標、部門が掲げる人材要件、面談での取得情報などに照らして部下の現在のスキルや抱える課題を分析ししましょう。 この段階の目的は、人材育成の障壁を特定することです。部下のスキル面だけでなく、心理的な側面も含めて多角的に現状を把握することが、目標と育成計画立案に役立ちます。
2:目標を設定する
部下育成の次のステップは「目標を設定する」ことです。この段階では、企業や組織が求める人材像と部下自身の目指す方向性も踏まえながら、具体的かつ現実的な目標を定めます。 目標を設定する上では、進捗把握や振り返りの際に困らないような工夫が必要です。なるべく客観的に測定できるように定量的な目標にしたり、具体的な行動を設定するなどするとよいでしょう。 また、目標を設定する上では、前のステップで特定した課題も考慮に入れる必要があります。例えば他部署とのコミュニケーションに課題を持つ場合、他部署連携の力を要するプロジェクトの企画に取り組むなどすると、自然と課題を克服しなければならない状況を作り出すことができます。
▶関連記事:人材育成の目標を設定するときのポイント|職種別の目標例も紹介
3:育成計画と育成手法の設計
部下育成の次のステップは、前項で定めた目標を達成するための具体的な計画を立案することです。また育成と一口に言ってもさまざまな手法があるため、どの手法を選択するかも合わせて設計します。 計画と手法の設計の際には、実業務でどのような機会を与えられるのか、企業契約のeラーニング等使える教材はあるのか、育成支援に割ける組織的なリソース、本人の特性やキャリア志向などを考慮するとよいでしょう。
4:育成を実施する
部下育成の次のステップは育成を実施することです。この段階では、検討した育成計画に基づき育成を開始します。 単に仕事を割り振るだけでなく、上司は部下に対し継続的なフォローやサポートを行います。部下の成長を促すためには、少し難易度の高い業務を任せることも有効で、成果が出れば大きな自信につながり、さらなる成長を促せるでしょう。
5:評価・改善を行う
部下育成の最終ステップは「評価・改善」です。振り返りとフィードバック、すり合わせを行い、その結果を基に次のアクションを決定します。また、最終評価より前の定期的な振り返りも重要です。適宜進捗を確認しながら必要な支援を継続しましょう。これにより、部下の持続的な成長を促し、次の育成計画へとつなげるPDCAサイクルを回していくことが重要です。
「研修をしてもその場限り」「社員が受け身で学ばない」を解決!
研修と自己啓発で学び続ける組織を作るスクーの資料をダウンロードする
■資料内容抜粋
・大人たちが学び続ける「Schoo for Business」とは?
・研修への活用方法
・自己啓発への活用方法 など

08まとめ
部下育成は、部下の才能を解放し、組織の生産性向上や活性化に直結する重要施策です。よくある失敗を避けつつ、上司は傾聴力や目標管理能力などを発揮し、OJTや1on1といった育成手法を適切に活用することが求められます。 育成は、「現状分析・課題明確化」「目標設定」「育成手法検討」「育成実施」「評価・改善」の5ステップで計画的に進め、部下の自律的な成長を促しましょう。

