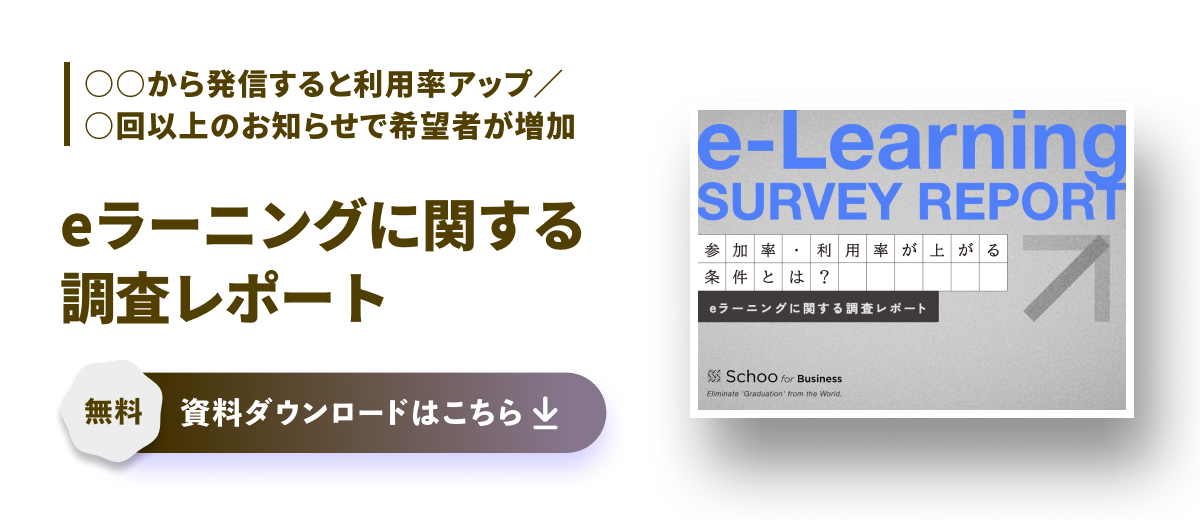eラーニングに最適な受講時間は?学習効果の最大化に向けたおすすめの取り組み方法

インターネットを通じて、オンラインで学習することをeラーニングと呼んでいます。eラーニングは、個人の学習のみに向けられたものに限らず、最近では企業でも研修や教育として活用されるようになりました。eラーニングは、自分のペースで学習できるというメリットがありますが、学習成果を実感するには取り組み方に工夫が必要です。この記事では、eラーニングの効果的な取り組み方を解説します。
01eラーニングにおける最適な時間
eラーニングは自由にすき間時間を活用することができますが、学習にかける時間はどのくらいを目安に考えればよいのでしょうか。ここでは1日の学習時間や、時間配分の仕方について解説します。
1日当たりどれくらいの時間を割くべきか
個人のスキルアップを目的とした学習の場合、ほとんどの方が仕事やプライベートの合間の時間を使って学習されるのではないでしょうか。学習計画を立てる際に注意すべき点は、無理なく継続できる計画になっているかどうかという点です。やったりやらなかったりなど学習にムラがあると、継続自体が難しくなることもあり得ます。継続できるかどうかに重きをおいて考えると、1日あたり合計で1時間から1時半程度の学習が理想です。
学習効率を高めるための最適な時間配分
人が集中できる時間はとても短く、15分程度だと言われています。30分、1時間、1時間半と長い時間連続して学習を行うよりも、15分×3セットというサイクルで間に小休憩を挟みながら学習を行ったほうが効果的です。自分のペースで学習が可能なeラーニングの場合は、一時停止などもできるので、時間を区切った学習に最適です。
集中力に関するSchooのおすすめ授業:集中力 -仕事に没頭する心理学-

「仕事中、気が散ってしまい時間の割に進みが遅い」「苦手な仕事が終わらず残業してしまう」など、仕事のスピードに関する悩みをお持ちの方もいるのではないでしょうか? この授業では、そもそも集中とは何かを理解し、仕事に没頭するためのテクニックを心理学的アプローチによる集中力UP特訓を通して身につけられます。
心理学ジャーナリスト。「ハック」ブームの仕掛け人の一人。専門は認知心理学。 1973年北海道旭川市生まれ。97年獨協大学卒業後、ドコモサービスで働く。2001年アヴィラ大学心理学科に留学。 同大学卒業後、04年ネバダ州立大学リノ校・実験心理科博士課程に移籍。2005年に帰国。
02eラーニングの学習効果・学習効率を最適化するためのポイント
eラーニングの効果を高めるためには、使用デバイス、学習コンテンツ選び、オフラインの活用、アウトプットの機会の4つにおいてそれぞれポイントがあります。ここではそれぞれ詳しく解説します。
eラーニングの学習効果を高める学習方法その1:さまざまなデバイスを活用しよう
eラーニングは、時間や場所が自由になるだけでなく、デバイスも限定されることがありません。スマートフォンやタブレット端末などを介して学習することも可能なので、通勤の電車の中や待ち時間でも気軽に学習ができます。隙間時間の学習は、自宅で学習時間の確保が難しいと感じる方や効率を重視される方にもおすすめです。お気に入りのカフェなどで学習していても、スマートフォンやタブレットであれば、他の人の邪魔になることなく勉強に集中することができます。
eラーニングの学習効果を高める学習方法その2:最終的に学びたいことから逆算してコンテンツを選ぼう
eラーニングの特徴は、とにかくコンテンツが多いことです。さまざまなジャンル、切り口のコンテンツが存在するため、目的も定まらないうちにいきなり学び始めてしまうと、思うような成果につながらないこともあります。数多くのコンテンツがありますから、今の自分にとってどのような学びが必要なのかをきちんと見極める必要があります。ですから、eラーニングを始める前には、自分のなりたい姿や学びを通して何を身につけていきたいかなどを整理しておき、必要に応じたコンテンツを選ぶという手順でスタートすることをおすすめします。
eラーニングの学習効果を高める学習方法その3:オフラインの学びの場も活用しよう
eラーニングで受講するだけで終わりにせず、自分が興味を持った先生のセミナーなどに出かけ実際に講義を受けてみることも、学びをより深める方法としてはおすすめです。eラーニングのタイプによって異なりますが、オンラインでは講師の先生に直接質問することができず、受け身型の学習になってしまうケースも少なくありません。しかし実際に目の前に講師の先生がいれば、わからなかったところは個別に質問することも可能ですし、場合によっては質問を深く掘り下げて講義をしてくれることもあり得ます。それだけではなく、同じテーマに興味を持っている人たちと知り合うこともできます。リアルでのセミナーが情報交換の場となり、より多くの学びを得られることもあります。
eラーニングの学習効果を高める学習方法その4 :アウトプットの機会を設けよう
何事もそうですが、学んだことをアウトプットする機会をきちんと設けることで、学習効果を高めることができます。アウトプットの方法として、自分のノートにまとめるという方法もありますが、ブログに書いたりSNSで情報を発信したりする方法もあります。特に、学んだことを踏まえて情報発信を行う場合、どのようにしたら人に伝わるのかなどと、学んだ内容をより深く考え自分の言葉に置き換えていく作業が必要になりますが、その過程こそが自らの勉強になります。
アウトプットに関するSchooのおすすめ授業:『学びを結果に変えるアウトプット大全』

この授業は、『学びを結果に変えるアウトプット大全』という本について、著者である樺沢紫苑さんが解説してくださる授業です。業務外の研修やセミナーで色々学んでいるが、なかなか仕事で活かせていない、効果が出ているのかわからない。という方もいらっしゃるのではないでしょうか?そこで、この授業では学びを仕事に活かし、結果に結びつけるアウトプット方法や、仕事を効率的に進められるようにするメンタルケア方法、脳科学に基づいた、脳の働きを最大化する生活リズムなどを学ぶことができます。
1965年、札幌生まれ。 1991年、札幌医科大学医学部卒。 札幌医大神経精神医学講座に入局。 大学病院、総合病院、単科精神病院など北海道内の8病院に勤務する。 2004年から米国シカゴのイリノイ大学に3年間留学。 うつ病、自殺についての研究に従事。 帰国後、東京にて樺沢心理学研究所を設立。 神医学の知識、情報の普及によるメンタル疾患の予防を目的に、Facebook 14万人、メールマガジン15万人、 Twitter 12万人、累計40万人のインターネット媒体を駆使し、精神医学、心理学、脳科学の知識、情報をわかりやすく発信している。 毎日更新のYouTube番組「精神科医・樺沢紫苑の樺ちゃんねる」(14万人)も大好評。 著書『学びを結果に変えるアウトプット大全』『学び効率が最大化する インプット大全』(共にサンクチュアリ出版)はシリーズ累計60万部超えの大ベストセラー。
03企業研修の学習効果を最大限高めるeラーニングの取り組み方
企業研修でeラーニングによる学習効果を高める取り組み方は3つありますので、ここで詳しく解説します。
企業研修の学習効果を最大限高めるeラーニングの取り組み方その1:新人研修などで活用しよう
eラーニングは、毎年同じ内容で行われる新人研修などで利用する教材として活用することが可能です。例えば社内や業界で使われる用語の解説や関係する法律・ルールなどの解説は、毎年頻繁に変わるものではありません。受講生全員に平等に教育を行いたいという場合は特に、eラーニングが有効です。場所や時間、人などのコスト削減にもつながります。
企業研修の学習効果を最大限高めるeラーニングの取り組み方その2:新商品やサービスの周知に活用しよう
また、自社の新商品や新たなサービスの概要を社員全員に周知してもらうためのツールとしても役立ちます。eラーニングがあれば、同じ内容の研修を何度も繰り返す必要はありません。自社の他の社員たちは、皆バラバラのスケジュールで活躍していますが、eラーニングがあれば、スケジュール調整を行い全員が出席できるような日程で提示するなんていうことを行わなくてもよいのです。
企業研修の学習効果を最大限高めるeラーニングの取り組み方その3:研修等の復習や達成度チェックなどに活用しよう
同じ内容の授業を何度でも繰り返し受講することが可能なeラーニングは、研修や勉強会などで学んだことの復習や、業務で必要な事柄の再確認などにも活用することができます。例えば研修を終えた新入社員が現場に入って仕事に慣れた頃、達成度チェックのような形でもう一度研修の内容を復習する機会を作る、ということも可能です。
「研修をしてもその場限り」「社員が受け身で学ばない」を解決!
研修と自己啓発で学び続ける組織を作るスクーの資料をダウンロードする
■資料内容抜粋
・大人たちが学び続ける「Schoo for Business」とは?
・研修への活用方法
・自己啓発への活用方法 など

04eラーニングならSchooビジネスプラン
Schooビジネスプランでは約9,000本の授業をご用意しており、様々な種類の研修に対応しています。その上、自己啓発にも効果的な内容の講座を毎日配信しているため、研修と自己啓発の両方に対応することができるシステムになっています。研修と自己啓発を掛け合わせることにより、誰かに要求されて学ぶのではなく、自発的に学び、成長していく人材を育成することが可能になります。ここでは、Schooビジネスプランの具体的な活用方法と、特徴、さらにはどのようなメリットがあるのかを解説します。
研修と自己啓発を両方行うことができる
Schooビジネスプランは社員研修にも自己啓発にも利用できるオンライン学習サービスです。通常の研修動画は、研修に特化したものが多く、社員の自己啓発には向かないものも少なくありません。しかし、Schooの約9,000本にも上る授業では、研修系の内容から自己啓発に役立つ内容まで幅広く網羅しているため、研修と自己啓発の双方の効果を得ることができるのです。
Schooの階層別研修
上記したように、Schooビジネスプランでは6,000本以上の授業を用意しているため、内定者研修から管理職研修までを幅広くカバーすることができます。これまで手間のかかっていた研修設計も、Schooビジネスプランであればカリキュラムと対象者を選択するだけで完了することができ、研修担当者の工数を大きく削減することもできます。
階層別研修におすすめの研修パッケージ
階層別研修では、新入社員には基礎的なマナーやスキルを学んでもらい、中堅社員や管理職には部下の育成やマネジメントなどについて学んでもらうことが一般的です。ここでは、新入社員から管理職までの研修におすすめの研修パッケージを紹介します。
-
「ロジカルシンキングとは何か」や「ロジカルシンキングの基礎となる技術」などについて学ぶことができるパッケージです。
-
このパッケージでは、新入社員や若手社員が最低限知っておくべきExcelのスキルを学ぶことができます。
-
全10時間で、ビジネスマナーや報連相を学ぶことができるパッケージです。
-
報連相やPDCAといったビジネスマンとしての基礎の部分をしっかりとやり抜く「業務遂行力」について学ぶことができるパッケージです。
-
ビジネスパーソンに必須である課題解決力を身につけられる研修パッケージです。
-
社員一人ひとりが自分の悩みに合わせたコミュニケーションスキルについて学ぶことができる研修パッケージです。
-
マネージャーがチームのパフォーマンスを最大化させるために必要な部下育成のスキルを学ぶことができるパッケージです。
Schooの職種別研修
職種によって求められるスキルは様々ですが、Schooの研修パッケージを活用して職種別研修を行うことができます。Schooでは、営業職からデザイナー・エンジニアまで、幅広い職種に対応した授業を用意しているため、多様な職種に対応した研修を行うことができます。
職種別研修におすすめの研修パッケージ
全職種に共通するスキルもありますが、職種によって求められるスキルは様々です。ここでは、それぞれの職種に必要なスキルを体系化した研修パッケージをご紹介します。
-
営業経験が浅い、もしくは経験のない方を対象とした研修パッケージです。
-
基礎からwebマーケティングを学びたいという方を対象とした研修パッケージです。
-
プログラミング言語Javaを基礎から学びたい方を対象にしたパッケージです。
-
1人でWebデザインの全行程を行えるようになりたいWebデザイナーの方を対象とした研修パッケージです。
Schooのテーマ別研修
社員それぞれの課題や改善点によって必要になってくるスキルは違います。Schooではビジネスマナーからチームビルディングまで、様々な種類の研修に対応できる研修パッケージを用意しています。
テーマ別研修におすすめの研修パッケージ
Schooのテーマ別研修では営業スキルやプログラミングスキルなど、幅広い分野のパッケージをご用意しており、それぞれの会社、社員のニーズに合った研修を行えるようになっています。ここではその一部をご紹介します。
-
営業経験が浅い、もしくは経験のない方を対象とした研修パッケージです。
-
基礎からWebマーケティングについて学べる学ぶことができるパッケージです。
-
初めてJavaを学ぶ方を対象に、基礎から学ぶことができるパッケージです。
-
デザイナーやアプリ開発に関わる企画職、エンジニア1人1人がアプリデザインの考え方やプロトタイプ制作について学習できるパッケージです。
-
デザイナーとしてこれからWebデザインを勉強したいという方に向けて、デザインの基礎(レイアウト、色、文字、デザインの考え方など)とAdobe Photoshop CC / Illustrator CCの使い方について学ぶことができる研修パッケージとなっています。
管理画面で受講者の学習状況を可視化できる
Schooビジネスプランには学習管理機能が備わっているため、研修スケジュールの作成を容易に行うことができます。さらに、社員の学習進捗度を常に可視化することができる上に、レポート機能を使って学んだことを振り返る機会を作ることも可能です。ここでは学習管理機能の使い方を簡単に解説します。

まず、Schooビジネスプランの管理画面を開き、「研修を作成するという」ページで作成した研修の研修期間を設定します。ここで期間を設定するだけで自動的に受講者の研修アカウントにも研修期間が設定されるため、簡単にスケジュールを組むことができます。

この、管理者側の管理ツールでは受講者がスケジュール通りに研修を受けているかを確認することができます。もし決められた研修をスケジュール通りに行っていない受講者がいれば注意したり、話を聞くことができるなど、受講者がしっかりスケジュールを守っているかを確認することができます。
▼【無料】働き方改革から学び方改革へ~学ぶ時間の創出で離職率が低下した事例~|ウェビナー見逃し配信中

働き方に関する制度改善を多数行ってこられた株式会社クロスリバー 代表取締役 越川慎司氏をお招きし、「残業削減ではない方法で働き方改革を行い、社員の自発性と意欲を著しく向上させ、離職率を低下させるための自律学習の制度設計」について語っていただいたウェビナーのアーカイブです。同社の調査・分析内容と自律学習の制度設計を深堀ります。
-
登壇者:越川 慎司様株式会社クロスリバー 代表取締役
ITベンチャーの起業などを経て2005年に米マイクロソフト本社に入社。業務執行役員としてパワポなどの責任者を経て独立。全メンバーが週休3日・リモートワーク・複業の株式会社クロスリバーを2017年に創業し、815社17万人の働き方と成果を調査・分析。各社の人事評価上位5%の行動をまとめた書籍『トップ5%社員の習慣』は国内外で出版されベストセラーに。