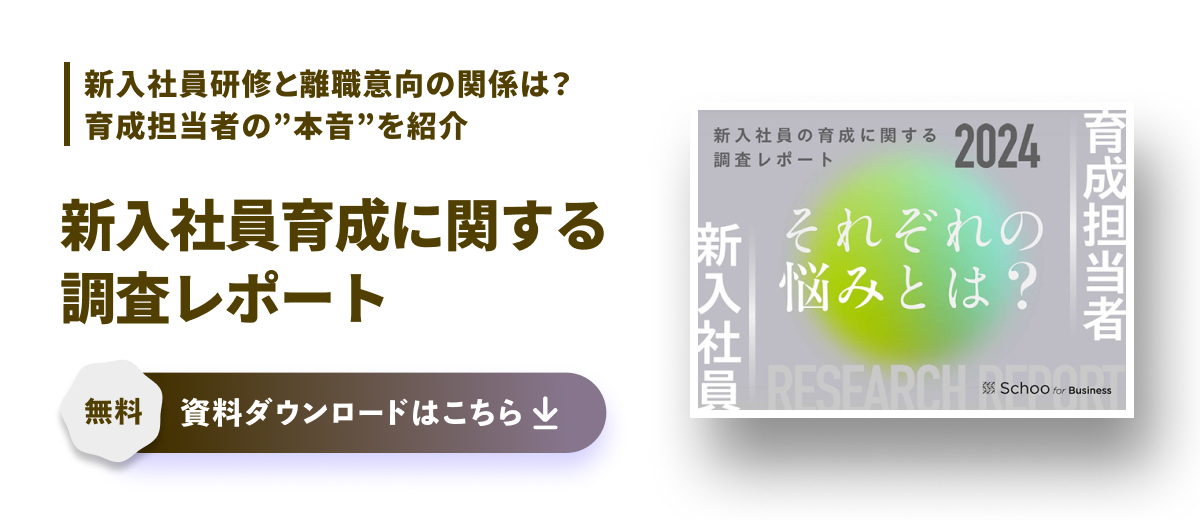新入社員研修のプログラムを作成する際の3STEP

新入社員研修は、階層別研修の中でも非常に重要な意味を持ちます。このコラムでは新入社員研修のプログラム作成方法を詳しくご紹介します。
- 01.新入社員研修の目的
- 02.新入社員研修のプログラムの作り方
- 03.新入社員研修のプログラムもPDCAを回すべき
- 04.新入社員研修を作成する際の注意点
- 05.新入社員研修の方法
- 06.新入社員研修にオススメの内容
- 07.新入社員研修のプログラム例
- 08.まとめ
01新入社員研修の目的
新入社員研修の目的は、社会人として1歩目を踏み出した社員を1人前の社会人にすることです。そのためには、まず以下の5つの項目を新入社員研修で教える必要があります。
- ・自社の理解を深める
- ・コンプライアンスの徹底
- ・基礎的なビジネススキルの習得
- ・ビジネスマナーの習得
- ・報告・連絡・相談(報連相)の徹底
それぞれ、なぜその知識が必要なのか詳しく見ていきましょう。
自社の理解を深める
自社への理解を深めることが、新入社員研修の目的の1つです。どのような事業を行なっているか、どのようなミッション・ビションを掲げていて、どのような戦略を取っているのか。これらを理解することで、今後の業務への取り組み方や意識に大きな変化を与えます。
コンプライアンスの徹底
コンプライアンスは企業に属する上で、絶対に守らなければなりません。コンプライアンスを守れない社員がいると、自社に損害を与える可能性があります。そのため、コンプライアンス研修は新入社員はもちろんのこと、意識が薄れてきた若手社員や中堅社員も受けた方が良い研修と言えるでしょう。
基礎的なビジネススキルの習得
新入社員はWordやExcelといったOAスキルはもちろんのこと、ロジカルシンキングといった考え方の基礎スキルも持っていません。そのため、各部署に配置される前に基礎的なビジネススキルを習得することは、必要不可欠と言えます。
ビジネスマナーの習得
ビジネスマナーも、社会人として必要不可欠です。挨拶や言葉遣いだけでなく、服装やヘアスタイルなども含め、社会人には社会人としてのマナーがあります。ビジネスマナーが守られていないと、相手に悪い印象を与えてしまう可能性があるので、新入社員研修で絶対に身につけておきましょう。
報告・連絡・相談(報連相)の徹底
仕事をする上で、報連相は絶対に必要です。特に新入社員は、先輩社員や上司への報連相を徹底しなければなりません。報連相がなぜ必要なのかや、どのタイミングで報告すべきかを理解せずに実務に入ってしまうと、取り返しが効かないミスをしてしまう可能性もあるので、報連相に関しては新入社員研修で絶対に習得させておきましょう。
マインドチェンジをするため
新入社員は、ついこの前まで学生をしていた新卒社員も該当します。成人しているとはいえ、学生時代と社会人では求められる立ち振る舞いは多く異なりますよ。ですが、多くの新卒社員は学生と社会人の違いを理解していないことがあります。そのため、社会人としての当たり前のマインドを新卒社員に教育するという意味で、新入社員研修を行う必要があるのです。また、転職してきた新入社員の場合、前職のスタンダードと自社のスタンダードは異なる場合があります。中途入社の社員は適応力が求められますが、改めて自社の方針ややり方にマインドチェンジさせるという意味でも新入社員研修は効果的です。
02新入社員研修のプログラムの作り方
新入社員研修のプログラムを作るためには、まず目標を決めましょう。次に、その目標を達成するためには、どのような施策が考えられるのかを複数出した上で、それらを実際に運用した際のイメージトレーニングを繰り返します。これらを行うことで、実際に研修を行った際に発見される問題点を先に予想することができ、施策を根本から変更することもできるのです。
課題の洗い出し
まずは現状の研修における課題の洗い出しを実施しましょう。実施方法としては、次が挙げられます。
- ・研修を受講した社員へアンケート
- ・現場から研修で実施してほしいことをヒアリング
- ・人材育成・社員教育の方針から考える
過去に研修を受講した社員が研修前と研修後で想定通りの変化を遂げているかが重要です。これを知るためには現場の社員へのヒアリングを実施するのが最適と言えます。また、人材育成・社員教育の方針から考えることもおすすめです。客観的に見て、自社の社員が会社の経営ビジョンやクレドなどとズレているかどうかを考えていきましょう。
目標を決める
新入社員研修に限らず、「研修をやること」が目的となってしまうことはよくあります。これは研修を設計する際に、目標を掲げていないことが要因となっている場合がほとんどです。そのため、まずは研修が終わったタイミングで、受講者がどのような状態になっていれば目標達成なのかを決めましょう。新入社員研修の場合、「社会人として1人前の状態になっている」・「各部署に振り分けた際に業務がもらえる状態にする」などが目標の例として挙げられます。
その目標を達成するために、中間目標が必要になる場合もあるでしょう。「社会人として1人前の状態になっている」を大目標としたとき、その大目標を達成するためには「名刺交換ができるようになる」・「Excelで簡単な集計ができるようになる」などの中間目標を立てる必要があるはずです。この中間目標が新入社員研修の各内容に紐付くので、まずは大目標・その大目標を細分化という流れでプログラムを設計していきましょう。
研修プログラムの作成
大目標・中間目標が決まったら、各中間目標に対して、その目標を達成するための案を複数出していきましょう。例えば、「名刺交換ができるようになる」という中間目標を達成するためには、新入社員同士で名刺交換をし合うという方法もあれば、先輩社員10名と名刺交換をするという方法もあります。このように方法を複数出した中で、目標を達成するためには、どの方法が一番良いのかと言う視点でプログラムを作成しましょう。
この際に、案はなるべく多く出したほうがいいので、時間を決めてブレストすることをおすすめします。複数人で意見を出し合っても良いかもしれません。例えば、転職組の人を複数集めてブレストすることで、「自分が新卒で入った会社はこういう方法でやってた」というような知見を集めることができます。
講師の選定
研修の質は講師の専門性と進行力によって大きく左右されるため、適任の講師を選ぶことが重要です。例えば、社内で特定の分野に精通している社員が講師を務めることで、実際の現場視点に基づいた指導が可能となります。
また、ビジネスマナーやリーダーシップといった専門分野では外部講師を招くことで、受講者が多角的な視点から学べるメリットもあります。講師の選定に際しては、研修の内容に応じた経験とスキルを持っているか、また受講者にわかりやすく伝えられるかを重視し、実務に役立つ知識の定着を目指します。
会場の選定
研修会場の準備は、受講者が学びに集中できる環境作りにおいて欠かせない要素です。研修の形式や内容に応じた会場選びが重要で、座学が中心であれば静かな場所が、ディスカッションや実践的な演習が必要な場合は広めのスペースが求められます。
また、プロジェクターやホワイトボードなどの設備も事前に確認し、スムーズに進行できるよう配慮します。会場の快適さは受講者の集中力に影響を与えるため、適切な室温、明るさ、椅子の配置など、細部まで整え、最適な学習環境を提供することが求められます。
運用のシミュレーションを繰り返す
施策を決めたら、それを実際に運用した際のシミュレーションを繰り返し行い、設計の抜け漏れチェックやリスク想定をしましょう。名刺交換の事例で考えてみると、「200名の新入社員がいて、先輩社員10人を呼び、名刺交換をする」という研修を90分で行うこととします。名刺交換の方法についてのレクチャーで30分かかるので、実践できる時間は60分しかありません。この場合、どのような結果が予想できるでしょうか。
この方法の場合、1人の先輩に対して20人の列ができます。単純計算で1人あたりの持ち時間は3分となり、1回の名刺交換にかかる時間が30秒とすると、実践できる回数は6回です。このように実現可能性を検討をすると、名刺交換を実践できる回数が6回では「名刺交換ができるようになる」という目標が達成できない可能性があることに気づくことができます。他の方法でもイメージトレーニングを繰り返し、どの方法が最善策なのかを見定めましょう。
研修の振り返り
研修終了後には、受講者や講師からのフィードバックを基に、プログラム全体の振り返りを行いましょう。参加者の意見を参考にすることで、次回以降の研修内容や進行の改善点を見つけ出します。また、達成した目標に対する評価や、今後のフォローアップが必要な項目を洗い出し、研修の成果を高めるための工夫を加えます。定期的に振り返りを行うことで、研修プログラムの質の向上が期待でき、より実践的かつ効果的な学びの場を提供できるようになります。
03新入社員研修のプログラムもPDCAを回すべき
新入社員研修は、ビジネスマナーやOAスキルのように内容が大きく変わることがないものが多いため、毎年同じ研修を繰り返しているという企業も少なくありません。しかし、同じ内容を繰り返していては成長がありません。新入社員研修を実施したら、その研修が成功だったのか、不足していた部分はないかをアンケートなどで確認するようにしましょう。例えば、ビジネスマナー研修は問題なかったが、OAスキルの習得では受講者によっては意見が異なるかもしれません。
また、アンケートを実施する際は「とても満足している」・「満足している」・「不満である」・「とても不満である」のように「普通」を無くした4択のアンケート行うことがポイントです。「研修」の振り返りをする上で、「普通」という答えは本来あるはずがありません。しかし、日本人は往々にして「普通」という選択肢があると、不満を持っていても波風を立てないために「普通」という選択肢を取ってしまうことが多いです。そのため、最初から「普通」という選択肢を排除して、明暗をはっきりさせましょう。アンケートの場合は、4択の下部に詳細をテキストで記載する欄を設けるのも忘れないでください。何に対して不満だったのか、何に対して満足しているのかを記載してもらうことで、受講者が研修を振り返るきっかけにもなり、人事としても今後のプログラム作成における貴重な意見となるはずです。
04新入社員研修を作成する際の注意点
新入社員研修は様々な目的があり、実施することで社員が早期から活躍することを期待できます。研修を作成するにあたっては先ほど解説したように準備やイメージトレーニングが必要ですが、いくつか注意点も存在します。ここでは、具体的な注意点について解説していくので、これから研修を作成する人はしっかりと押さえていきましょう。
現場との連携をおこなう
基本的に人事主導で新入社員研修を実施後に配属となります。研修で学んだことが配属先でしっかりと活かされなければ意味がありません。そのため、実務に合わせた研修となるように事前に現場と連携を行い、研修内容に問題がないかすり合わせていきましょう。
労働時間をしっかりと管理する
新人社員研修の期間は1〜3ヶ月が一般的ですが、合宿研修なら短期集中で行えます。研修といえど、労働基準法では、会社の指示による新人社員研修は労働時間に該当します。そのため、研修時間が長くならないように、事前に想定時間を見積し、細かいスケジュールを策定していきましょう。
質問しやすい環境を作る
一方通行の座学では受講者の理解度は中途半端なものになってしまいます。受講者自身も研修に退屈さを感じ、飽きてしまいます。場合によっては研修を受けて成長するのではなく、「研修をこなすもの」と捉えてしまいかねません。また、新入社員は新しい環境ということでなかなか発言しづらいと感じる人も多くいます。そのため、ラフな雰囲気にして、なるべく新入社員が質問しやすい環境を作ったり、あえて受講者に答えさせるといったことを実施していきましょう。
専門用語の解説を怠らない
新入社員にとって、職場で使われる専門用語や業界特有の表現は理解の障壁になりがちです。解説を省くと、理解不足が積み重なり、業務に支障をきたすことがあります。まずは基礎的な用語を明確に説明し、背景や実例を交えて理解を促しましょう。研修中に新しい用語が出た際には、都度説明を加えることが大切です。また、用語集や業務ガイドを用意することで、理解を補完する資料として活用できます。社員が疑問を抱かないような環境を整えることが、安心して学習できる雰囲気を作る鍵です。
中だるみが無いような工夫をする
長時間の研修では、新入社員が集中力を維持するのが難しく、中だるみが発生しやすくなります。これを防ぐために、適度にインタラクティブな活動やグループワークを取り入れると効果的です。例えば、ディスカッション形式やケーススタディを交えることで、受講者が主体的に参加できる研修内容にすることが求められます。さらに、適切なタイミングで休憩を取り、リフレッシュの時間を設けることも重要です。コンテンツを細かく区切り、目標を明確に伝えることで、一つ一つの内容に対する集中を促すことが可能です。
資料は適切な量にする
研修資料が多すぎると、情報が過剰になり、新入社員にとって消化不良に陥りやすくなります。一方で、資料が少なすぎると理解が浅くなり、記憶の定着も難しくなるため、適切な量に調整することが求められます。重要なポイントを絞り込み、視覚的にわかりやすく整理することが効果的です。図や表を活用し、要点を見やすく配置することで、理解しやすい資料作成を心がけましょう。また、後から振り返りやすいよう、まとめページを設けるなど、資料の活用性を高める工夫も大切です。
定期的に内容を見直しする
新入社員研修の内容は、会社や業界の状況、社会の変化に応じて見直しが必要です。研修内容が時代に合わなくなると、受講者の学びに不整合が生じる可能性があります。定期的に内容をチェックし、最新の情報やトレンドを反映させることが、研修の質を維持するために重要です。アンケートやフィードバックを参考にし、受講者のニーズに応じて修正を加えると、より効果的な研修プログラムが構築できます。また、社内のベテラン社員や専門家からの意見も取り入れると、現場に即した内容に更新することが可能です。
05新入社員研修の方法
新入社員研修の方法はさまざま存在します。それぞれ特徴が異なるので、対象者によって実施方法は変更することがおすすめです。ここでは大きく5つの方法について解説していくのでぜひ参考にしてみてくださいね。
新入社員研修の方法①.座学
座学とは講義形式で実施するインプット型の学習を指し、大学の講義やセミナーなど対面形式で行われるものが該当します。座学は同時に大人数を相手に研修を行えるので、基礎知識の習得には向いていますが、実践的なスキルは身に付きづらく、講義形式のため、受講者が受け身になってしまうというデメリットがあります。また、長時間実施する場合は受講者の集中力が続かないので注意しましょう。会社のビジョン・ミッション研修、勤怠などのルールを教える際に向いていますよ。
新入社員研修の方法②.グループワーク
グループワークとは、グループでの議論を通じて、最終的にプレゼンや成果物の作成といったアウトプットを作成することを指します。限られた時間制限の中で一定の成果を出すことが求められるので、新入社員の主体性が求められます。また、実務の雰囲気を掴むことができたり、社員同士のコミュニケーションを促すことができます。一方で、社員の自主性に任せすぎると破綻しかねないなど、研修の効果を得られない可能性もあります。
▼新入社員研修のグループワークについて詳しく知りたい方はこちらから▼
【関連記事】新入社員研修でおすすめのグループワーク4種類とポイントを解説
新入社員研修の方法③ロールプレイング
ロールプレイングは、設定された場面において割り当てられた役割を疑似体験することができる研修です。現場での知識や行動について学習できるため、スキルアップを期待できます。一方で、フィードバックありきなので、フィードバックの質次第では体験に留まってしまい、スキルが定着しないという特徴があります。ロールプレイングを実施する場合は、グループワークと組み合わせて実施することで、能力を向上させることができます。
▼新入社員研修のロールプレイングについて詳しく知りたい方はこちらから▼
【関連記事】研修ロールプレイングを成功に導くポイントは?効果の高いロールプレイングの方法を紹介
新入社員研修の方法④ケーススタディ
ケーススタディとは、具体的な事例を用いて行う研修です。事例の分析などを行うので、ケースごとの正しい知識や立ち振る舞いを身につけることができたり、知識が定着しやすいという特徴があります。一方で、講義型の研修で行うと新入社員は受け身となってしまうので、グループワークやロールプレイングなどと組み合わせて実施することがおすすめです。
新入社員研修の方法⑤合宿研修
一定期間同じ場所に新入社員を集めて、短期間で集中的に行う研修です。研修だけに集中できるので効果を期待できると同時に、寝食を共にするので社員同士のコミュニケーションや繋がりを活性化させることができます。一方でコスト面での負担が大きく、拘束時間が長いことからストレスに感じる社員も出てくる可能性があります。新卒社員など、同期同士のつながりを構築する必要のある新入社員には効果的と言えるでしょう。
▼新入社員研修の合宿研修について詳しく知りたい方はこちらから▼
【関連記事】新入社員研修を合宿型で行う場合の効果と注意点を解説する
新入社員研修の方法⑥OJT
OJTは、実際の業務を通じて新入社員に必要なスキルや知識を習得させる手法です。この方法の最大の利点は、実務経験を積みながら学べるため、学んだ内容が即座に業務に活かせる点です。具体的には、先輩社員や上司が新入社員に対して直接指導を行い、実際の業務を体験させることが中心となります。OJTの特徴として、実践的な学習が促進されるため、業務の流れや社内文化を早期に理解できることが挙げられます。また、個々の学び方に応じて柔軟に指導を行えるため、受講者の理解度やペースに合わせた対応が可能です。一方で、指導者のスキルや経験に依存するため、質の均一化が難しい点や、業務が多忙な際には指導が不十分になるリスクも存在します。
▼OJTについて詳しく知りたい方はこちらから▼
【関連記事】成功するOJT研修とは?
新入社員研修の方法⑦eラーニング
eラーニングは、インターネットを活用したオンライン教育手法で、時間や場所にとらわれずに学習できるのが特徴です。新入社員は、自分のペースで学習を進めることができ、必要な知識を必要なタイミングで取得することができます。多様な教材(動画、クイズ、テキストなど)を用いることで、視覚的・聴覚的に学びやすい環境を提供します。この手法の利点は、広範囲の受講者に同時に教育を提供できるため、コスト効率が良く、時間の有効活用が図れる点です。また、進捗状況をトラッキングしやすく、受講者の理解度を評価するためのフィードバックを迅速に提供できます。しかし、自己管理が求められるため、モチベーションの維持が課題となることがあります。また、対面でのコミュニケーションが不足しがちで、質問やディスカッションの機会が限られる点にも注意が必要です。
▼eラーニングについて詳しく知りたい方はこちらから▼
【関連記事】eラーニングって効果あるの?管理者と受講者双方の目線で解説!
06新入社員研修にオススメの内容
新入社員研修のプログラムを作成する際に重要なのが、どんな内容の新入社員研修を作成するか、ということです。新入社員研修は基本的にはビジネスパーソンとして身に着けるべき基礎的なスキルを学んでもらいます。
ビジネスマナー研修
新入社員が最初に身に着けるべきマナー・スキルの1つが、ビジネスマナーです。取引先との商談や営業、社内でのコミュニケーションなど、ビジネスマナーが必要になる場面は日常に多数存在します。ビジネスマナーが悪いと、それだけ相手に悪い印象を与え、商談などの結果に悪影響を及ぼすことがあります。そのため、ビジネスマナーはできるだけ早いうちに身につけてもらう必要があります。
チームビルディング研修
会社という組織で働く上で欠かせないスキルが、チームビルディング力です。どんな会社に入っても全て1人で仕事をこなすことはできないため、ある程度会社の中のチームで動く必要がありますが、チームビルディング力がなければ上手くチームワークを発揮できず、チームの成果にも悪影響を及ぼします。そのため、チームビルディング力を身につけてもらい、チームでしっかりと成果を出せる人材を育成しましょう。
ロジカルシンキング研修
上記の2つの研修と同じく、ロジカルシンキング研修も非常に重要な研修です。言いたいことをわかりやすく端的に伝えるということは、簡単なようですが、できない人も少なくありません。しかし、論点を整理して端的に伝える力は会社内での報連相においても重要であるとともに、会社外でも様々な状況で必要です。この、ロジカルシンキング力を早めに身につけておくことで、より早くビジネスパーソンとして活躍し始めることができるのです。
07新入社員研修のプログラム例
新入社員研修のプログラムを設計する際には、様々なスキルを体系的に学べるようなカリキュラムを作ることを心がけましょう。体系的に学ぶことで、それぞれのスキルの関連性や、より効率的に多くのスキルを身につけることができるのです。
ここでは、Schooビジネスプランの体系的に学ぶことができる新入社員研修をご紹介します。
新入社員研修のプログラム例
-
新社会人のためのビジネスマナーの基本を学ぶカリキュラムです。第一印象の磨き方(身だしなみ・挨拶・敬語)や、社内マナー(ホウレンソウ・名刺交換・電話応対など)について解説しています。
-
社会人としてのマインドセットを習得するためのカリキュラムです。「思考」「実行」の2つの視点で、すぐに現場で実践できるビジネスに必要な力を学びます。
-
Wordの基礎技術を学習するためのカリキュラムです。Wordの操作方法や文書作成の基礎などを学ぶことができます。
-
Excelの基礎技術を学習するためのカリキュラムです。新入社員や若手社員が知っておくべき基本スキルを学ぶことができます。
-
見やすいグラフやスライド資料の作成方法を学ぶカリキュラムです。独学で悩みがちの本テーマを、具体例や実践例を交えながらお伝えします。
-
Excelを活用したデータ分析について学べる研修パッケージです。データ分析をする際の考え方から、「並べ替え」「オートフィルタ」「ピボットテーブル」などのExcel分析に必要な機能について学ぶことができます。
-
ビジネス文書やメール作成ついて学ぶカリキュラムです。社会人として求められる文章能力について詳しく解説していきます。
-
若手社員向けのロジカルシンキングに必要な思考法について学ぶカリキュラムです。論理性を高めて業務を遂行していく際に必要な思考法について解説していきます。
-
若手社員向けのロジカルシンキングに必要な思考法について学ぶカリキュラムです。論理性を高めて業務を遂行していく際に必要な思考法について解説していきます。
-
ファシリテーショングラフィック(グラレコ)のスキルを磨きたい、トレーニングをしたいという方向けの実践的な研修パッケージです。
このプログラム例からもわかるように、ビジネスマナーやロジカルシンキング、OAスキルといった基礎スキルを体系的に学べるプログラムを作ることを心がけましょう。
カリキュラム例(新社会人のためのビジネスマナー研修パッケージ)
研修時間目安: 10時間(60分×10コマ)
全10時間で、ビジネスマナーや報連相を学ぶことができます。ビジネスメールや名刺交換などのビジネスマナーだけでなく、報連相の重要性や適切なタイミングも同時に学ぶことで、社会人としての基礎スキルを習得できる研修パッケージとなっています。
| 授業名 | 仕事がデキると思われるビジネスマナーの基本 |
| 時間 | 5時間(60分×5コマ) |
| 学べること | ・好印象を与える身だしなみ、あいさつ ・敬語の仕組み ・電話対応の方法 ・報連相のポイント ・来客応対の方法 ・円滑に進める会議術 ・訪問時の対応方法、名刺交換 ・プレゼンの基本 ・クレーム時の対応方法 ・接待のポイント |
| 授業名 | もっと伝わるコミュニケーション術 |
| 時間 | 3時間(60分×3コマ) |
| 学べること | ・伝わるメールの書き方 ・コミュニケーションのポイント ・質問力の重要性、磨き方 ・伝わるプレゼンの方法 |
| 授業名 | デキる若手の報連相 |
| 時間 | 2時間(60分×2コマ) |
| 学べること | ・報連相の目的、重要性 ・報連相のポイント ・報連相に必要なベーススキルとは ・ロジカルシンキングの基本 ・MECEの重要性、実践ワーク |
「新入社員研修にオンラインを取り入れたけどイマイチ」
「社員が受け身で学ばない」を解決!
新入社員研修+自己学習の習慣化ができるスクーの資料をダウンロードする
■資料内容抜粋
・大人たちが学び続ける「Schoo for Business」とは?
・研修への活用方法
・自己啓発への活用方法 など

Schoo for Businessの特徴
Schoo for Businessでは約8500本の授業をご用意しており、様々な種類の研修に対応しています。その上、自己啓発にも効果的な内容の講座を毎日配信しているため、研修と自己啓発の両方に対応することができるシステムになっています。研修と自己啓発を掛け合わせることにより、誰かに要求されて学ぶのではなく、自発的に学び、成長していく人材を育成することが可能になります。ここでは、Schoo for Businessの具体的な活用方法と、特徴、さらにはどのようなメリットがあるのかを解説します。
Schoo for Business |
|
| 受講形式 | オンライン (アーカイブ型) |
| アーカイブ本数 | 9,000本 ※2023年3月時点 |
| 研修管理機能 | あり ※詳細はお問い合わせください |
| 費用 | 1ID/1,650円 ※ID数によりボリュームディスカウントあり |
| 契約形態 | 年間契約のみ ※ご契約は20IDからとなっております |
1.研修と自己啓発を両方行うことができる
Schoo for Businessは社員研修にも自己啓発にも利用できるオンライン学習サービスです。通常の研修動画は、研修に特化したものが多く、社員の自己啓発には向かないものも少なくありません。しかし、Schooの約9,000本にも上る授業では、研修系の内容から自己啓発に役立つ内容まで幅広く網羅しているため、研修と自己啓発の双方の効果を得ることができるのです。
2.管理画面で受講者の学習状況を可視化できる
Schoo for Businessには学習管理機能が備わっているため、研修スケジュールの作成を容易に行うことができます。さらに、社員の学習進捗度を常に可視化することができる上に、レポート機能を使って学んだことを振り返る機会を作ることも可能です。ここでは学習管理機能の使い方を簡単に解説します。

まず、Schoo for Businessの管理画面を開き、「研修を作成するという」ページで作成した研修の研修期間を設定します。ここで期間を設定するだけで自動的に受講者の研修アカウントにも研修期間が設定されるため、簡単にスケジュールを組むことができます。

この、管理者側の管理ツールでは受講者がスケジュール通りに研修を受けているかを確認することができます。もし決められた研修をスケジュール通りに行っていない受講者がいれば注意したり、話を聞くことができるなど、受講者がしっかりスケジュールを守っているかを確認することができます。
08まとめ
新入社員研修の目的は、社会人として1歩目を踏み出した社員を1人前の社会人にすることです。そのためには、どのようなプログラムを設計するかが重要になります。プログラムを作成する際には、まず目標を決めることから始めましょう。目標から施策へと落とし込み、運用のイメージトレーニングを繰り返すことで、最善と思われる施策を選ぶことができるはずです。また、新入社員研修の成否もアンケートなどの方法で確認し、次回のプログラム作成に活かすなどPDCAの仕組みも整えておきましょう。