自己啓発とは|メリットや具体的な方法・企業事例を紹介

自己啓発を推奨する企業が増加しています。スキルアップした魅力的な従業員が、職場で幅広い活躍をすることを期待して、人材育成を行う企業も少なくありません。この記事では、自己啓発活動を実施する必要性と具体的な方法を紹介しています。
- 01.自己啓発とは
- 02.自己啓発のメリット
- 03.自己啓発の具体的な方法
- 04.企業による自己啓発の支援状況
- 05.従業員の自己啓発を支援する方法
- 06.従業員の自己啓発を支援する際の課題と対策
- 07.自己啓発を推進している企業事例
- 08.自己啓発の支援ならSchoo for Business
- 09.まとめ
01自己啓発とは
自己啓発とは、『労働者が職業生活を継続するために行う、職業に関する能力を自発的に開発し、向上させるための活動』のことです。そのため、職業に関係ない趣味、娯楽、スポーツ健康増進等のためのものは自己啓発に含みません。
会社から強制的に知識やスキルを習得させられる研修と異なり、あくまでも自身の内発的動機による主体的な学習行動という点が自己啓発の特長です。
自己啓発は、Off-JT(研修)やOJTに並んで、人材開発の代表的な手法です。終身雇用が前提だった少し前の時代までは、企業として自己啓発に注力する企業は多くありませんでした。しかし、VUCAと呼ばれる予測のつかない時代になり、自己啓発の重要性が増し、昨今では多くの企業が自己啓発に取り組むようになっています。
▶︎参考:厚生労働省|能力開発基本調査 用語の説明
02自己啓発のメリット

自己啓発を行うことにより、仕事の質の向上・年収増加・仕事の満足度向上などの効果が見られることがわかっています。
特に仕事の質・仕事の満足度に関しては、自己啓発を行なっている人とそうでない人では、大きな違いが見えます。
この章では、自己啓発を推進することによって期待できる効果を、厚生労働省のデータをもとに紹介します。
▶︎参考:厚生労働省|主体的なキャリア形成に向けた自己啓発の効果と課題について
仕事の質

自己啓発を行うことにより、仕事の質はどの年代でも向上していることがわかります。上記の数値は、担当している仕事が前年と比較した際に、「大幅にレベルアップした」・「少しレベルアップした」割合から「大幅にレベルダウンした」・「少しレベルダウンした」割合を差し引いた値です。
特に35~59歳の世代においては、研修やOJTで学ぶ機会が減るため、自己啓発の有無で仕事の質に大きな差が出ています。また、35歳未満でも自己啓発に取り組んでいる人の方が成長しており、会社から学習機会を得ている若手時代においても自己啓発の有無で成長速度に大きな差が出ることが伺えます。
年収変化

自己啓発は年収にも良い影響を与えます。2年前と比較して、年収が10%以上増加した割合から 10%以上減少した割合を差し引いた値が上記の画像の数値です。
この結果を見ると、年功序列がいまだに風習として残っている日本において、自己啓発によって大幅に年収が上がっているわけではないようです。
一方で、2年間で10%増加した人の割合が多いという結果を見るに、自己啓発の継続した人の生涯年収は、行わなかった人と比較して大きな差が出ることが予想されます。
仕事の満足度

自己啓発は仕事の満足度にも大きな影響を与えることがわかっています。上記の数値は、仕事の満足度について、「満足」・「どちらかというと満足」の割合から「不満」・「どちらかというと不満」の割合を差し引いた値です。
いずれの年代でも、仕事の満足度は自己啓発を行なっている人の方が高くなるという傾向にあります。主体的に学習行動をとっている人は、主体的に仕事に取り組むことも容易に想像できるため、この数値は当然の結果とも言えるでしょう。
03自己啓発の具体的な方法
自己啓発の具体的な方法には、主に以下の7つがあります。
- ・読書
- ・セミナー
- ・スクール通学
- ・勉強会
- ・Youtube
- ・eラーニング
- ・生成AI
この章では、これらの方法について詳しく紹介します。
読書
自己啓発の方法として、多くの人が想起するのが読書でしょう。受験勉強の経験から、「学ぶ」=「本を読む」と考える人が多いようです。
図書館や会社の書籍購入制度を活用することで、読書は費用をかけずに手軽に始めることができます。そのため、お金がかからないという点でも、採用されやすい自己啓発の方法と言えるでしょう。
セミナー
セミナーに参加することで、自身のキャリアや職種に必要な学ぶを得る人も少なくありません。その背景には、新型コロナウイルスを契機にオンライン上でセミナーを実施する企業が増えたことがあります。これにより、さまざまなセミナーに気軽に参加しやすくなりました。
一方で、無料で受講できるセミナーは自社サービスの宣伝目的であったり、ポジショントークが混ざっていたりします。そのため、内容の正確性には注意しなければなりません。
勉強会
個人や企業が主催している勉強会に参加することも、自己啓発の方法の1つです。同じ職種の似た境遇の参加者と一緒に学ぶことで、多様な意見や知見を学ぶことができるというメリットがあります。
一方、セミナーと同様に、宣伝目的やポジショントークが混ざっている勉強会があることには注意が必要です。特に、勉強会と称したコミュニティに参加することで、求人のお知らせやサービス紹介が届いたりするなど、個人情報が利用される可能性があります。
スクール通学
スクール通学で、自己啓発を行う人も中にはいます。この方法を選択する人は、主に資格取得を目的にしている人が多いです。講師に直接質問でき、理解を深めることができるので、専門書を読むだけでは得られない知識を習得できるためです。
一方で、スクール通学は時間を大幅に取られてしまうというデメリットと、費用が高額になってしまうという点には注意が必要です。そのため、1人で黙々と資格取得の勉強をするのが難しく、強制的に自分を律したいという人におすすめの方法と言えるでしょう。
Youtube
無料で学ぶ手段として、Youtubeを活用する人も増えています。専門知識やビジネススキルを紹介しているチャンネルや、ビジネス書の要約をしているチャンネルを視聴することで、お金をかけずに学ぶことができるという利点があります。
その反面、学べる内容が限定的であることも少なくありません。自分が学びたい内容を解説しているチャンネルがない場合、この方法を選択することはできません。さらに、紹介している内容の正確性にも注意が必要です。
eラーニング
Youtubeのように動画で学ぶ手段として、eラーニングがあります。プログラミングやマーケティングなど、職種に特化したeラーニングもあるので、自身の職種に関しての専門性を高めたい場合は、この方法は非常に有効と言えるでしょう。
しかし、eラーニングの利用には基本的に費用が発生します。サブスク型のeラーニングが多いですが、1本買い切り型のeラーニングもあります。何をどの程度学びたいのかが明確になっていない場合、どのeラーニングを選択すればよいか判断が難しいでしょう。
▶︎関連記事:eラーニングって効果あるの?管理者と受講者双方の目線で解説!
生成AI
昨今、ChatGPTやGeminiなどの生成AIを自己啓発に用いる人も増えています。検索の代替手段として生成AIを活用する人もいれば、練習問題の作成を生成AIに依頼している人もいるようです。他にも、生成AIを英会話の練習相手として活用することも、一般的になってきています。
自己啓発の方法として、今後主流になっていくと想定される生成AI活用ですが、まだまだ情報の正確性には注意しなければなりません。そのため、出力されたアウトプットの引用元を参照して、本当に正しい情報かを確認する習慣をつけましょう。
「研修をしてもその場限り」「社員が受け身で学ばない」を解決!
研修と自己啓発で学び続ける組織を作るスクーの資料をダウンロードする
■資料内容抜粋
・大人たちが学び続ける「Schoo for Business」とは?
・研修への活用方法
・自己啓発への活用方法 など

04企業による自己啓発の支援状況
自己啓発の重要度は社会背景を踏まえても疑う余地はありませんが、実態として企業はどの程度支援しているのでしょうか。この章では、厚生労働省が令和4年度に実施した「能力開発基本調査」をもとに、どのくらいの企業が自己啓発を実施しているのか、どのくらいの費用を使っているのかを紹介します。
自己啓発支援への費用支出状況

厚生労働省が行った令和4年度調査における企業の教育訓練への費用の支出状況をみると、Off-JTと自己啓発支援に支出している企業は19.8%。自己啓発のみに支出している企業は4.0%なので、全体の23.8%の企業は自己啓発への支出をしているというのが現状です。
一方で、Off-JTのみに支出している企業は26.5%。Off-JTにも自己啓発に支出していない企業の割合が49.6%という結果となり、社員への教育投資を実施している企業の約40%は自己啓発施策も実施していることがわかります。
自己啓発支援に費用支出した企業割合の推移

自己啓発支援に費用支出した企業割合の推移を見てみると、令和2年度から約4%ほど低下傾向にあることがわかります。

同様にOff-JTに費用支出した企業割合の推移も見てみると、こちらも令和2年度から9%ほど下降しています。
この結果から、自己啓発だけでなくOff-JTへの投資も減少していることがわかり、社会全体として教育への投資が減少していることがわかります。この結果の要因としては、新型コロナウイルスの感染拡大による経営状態の悪化などが影響していると考えられます。経済活動が停滞したことにより、経営が悪化。企業としては、教育への投資を減らしてでも雇用を守るという対応を余儀なくされたのでしょう。
自己啓発支援に支出した費用の労働者一人当たり平均額

自己啓発支援に支出した費用の労働者1人当たり平均額を見てみると、平成30年度から横ばいで3千円を維持しています。
一方で、Off-JTに支出した費用の労働者1人当たり平均額は1.3万円という結果でした。
Off-JTに関しても自己啓発に関しても、企業がOff-JTまたは自己啓発に支払った費用を、全社員数で割った数値です。そのため、研修を受けた人数や自己啓発を実際に実施した人数で割ると、実際の1人当たりの費用はもっと高いと想定されます。
自己啓発の今後3年間の見立て

正社員に対する過去3年間の自己啓発支援に支出した費用の実績は、増加したが9.3%。減少したが6.1%という結果となっています。一方で、今後3年間を見てみると増加させる予定と回答した企業は27.8%とかなり増加傾向にあります。また、過去3年間で自己啓発を実施していなかった企業は70.1%もいましたが、今後3年間も実施しないと答えた企業は56.3%に減少しています。この結果の要因としては、コロナの終息に伴う教育投資の復活と、自己啓発の必要性が浸透してきていることが考えられます。
この傾向は正社員以外でも見られ、今後3年間で自己啓発支援費用を増加させる予定と回答した企業は14.6%でした。まだまだ正社員以外への投資は少ないというのが現実ですが、少しでも上昇傾向にあるという希望が見える結果となっています。
05従業員の自己啓発を支援する方法
従業員の自己啓発を支援する方法には、主に以下の6つがあります。
- ・書籍購入制度
- ・資格取得支援
- ・外部セミナーなどの参加費用負担
- ・勉強会などの開催支援
- ・eラーニング
- ・企業内大学
書籍購入制度は低コストで始められるため、多くの企業で導入されています。また、eラーニングの導入を進める企業も多く、特に昨今の人的資本経営やキャリアオーナーシップなどの流れを受けて、本格的に全社導入する企業も増えてきています。さらには企業内大学という形式でeラーニングや勉強会を総合した取り組みを推進している企業もいます。
書籍購入制度
自己啓発の施策として簡単に始められるものが、書籍購入制度です。書籍の購入はランニングコストではなく、各部署に予算を割り当てておけば稟議の承認者も現場の管理職に全て委ねることができます。
簡単に開始できるというメリットがある反面で、ビジネス本を読むということはハードルが高く、制度の利用者があまり増えないという点が欠点かもしれません。
資格取得支援
資格取得支援も、書籍購入制度と同様に開始までのハードルは低い施策です。企業にもよりますが、資格を取得できた場合に受験費用を負担するというルールを設ければ、企業にとってデメリットが全くない施策となります。
一方で、合格しないと費用負担が受けられないというルールは制度の利用者を限定することになるので、どこまで企業として支援するのかは注意する必要があります。
外部セミナーなどの参加費用負担
企業外で開催している有料セミナーへの参加費用を、会社が負担するという制度を設けている企業もあります。外部セミナーは往々にして費用がそれなりにかかるので、能力向上に意欲的な社員には好まれる傾向にあります。
その反面、1人にかかる費用が大きくなってしまうので、仮に多くの社員が意欲的にこの制度を利用すると予算超過の危険性もあるので注意が必要です。
勉強会などの開催支援
社内で開催される勉強会の支援も、自己啓発施策の1つです。同じ企業に所属する、同じような課題を持った社員が集まるので、社員同士の新たな繋がりを生むことができます。また、基本的に社員が主導して実施されることが多いので、人事としては工数がそこまで割かれないというのもメリットです。
しかし、自発的に勉強会を開催して自己研鑽をしようとする社員は多くないので、最初は社内周知や企画などを人事が伴走し、勉強会を社員が自ら開催するような文化を長い視点で作っていく必要があります。
eラーニング
昨今、注目を集めている自己啓発施策がeラーニングです。働き方改革やコロナの影響でリモートワークを許容する企業が増え、オンラインで自由に学ぶことのできる環境が求められています。このような社会背景の中で、eラーニングを自己啓発の施策としてでなく、Off-JTの一貫として利用する企業も続々と増えているのが現状です。
▶︎関連記事:eラーニングって効果あるの?管理者と受講者双方の目線で解説!
企業内大学
社内勉強会やeラーニングなどの施策を統合して、企業内大学として自己啓発の支援をしている企業も増えてきました。特に大手企業で企業内大学への注目が高まっており、背景には社員が成長できる環境を整えて、社員に選ばれる会社を目指すという思いがあるようです。
06従業員の自己啓発を支援する際の課題と対策
社員の自己啓発を企業が支援する際に、主な課題となるのは以下の3点です。
- ・手が上がらない(参加率が低い)
- ・利用されない
- ・学習が続かない
それぞれの課題について、以下で詳しく紹介します。
手が上がらない(参加率が低い)
eラーニングや外部セミナーなどの自己啓発施策の希望者を公募で集めようと思っても、社員の手が上がらないという課題があります。こちらは、社員への周知がしっかりと出来ていないという要因が考えられます。日々の業務で忙しい社員にとって、いわゆる会社から出されるお知らせは頭になかなか残りません。そのため、複数回にわたって告知をしたり、告知を社長や役員、現場の管理職から発信してもらったりなどの工夫が必要になります。
対策:OJTやOff-JTと併用する
自己啓発は、職場で実際に仕事をしながら学ぶOJTと、職場から離れてセミナーや研修などで学ぶOff-JTの両者を上手く組み合わせて行うことをおすすめします。例えば、OJTやOff-JTで教わった内容の復習として自己啓発を利用するように促したり、Off-JTのインプット部分を自己啓発として導入したツールに任せたりといった組み合わせによる利用促進を意識しましょう。
▶︎関連記事:成功するOJT研修とは?
▶︎関連記事:OFF-JTとは?OJTとの違いやメリット・デメリット、活用方法を解説
利用されない
自らの意志で利用したいと表明した人と言えども、実際はなかなか利用しません。それもある意味で仕方のないことで、社員にもプライベートの時間があります。朝起きて、会社に通勤し、帰宅してからは家族と過ごす時間も、リラックスする時間も必要です。このような状況の中で、自身の成長のために時間を確保して学ぼうとする人の方が珍しいでしょう。
そのため、企業として自己啓発を人材開発のオマケ施策として考えるのではなく、主体的に学び成長する社員が本当に必要という組織での意志統一をする必要があります。そして社員が自ら伸ばしたいスキルや能力に向かう時間を、会社として用意してあげることも時に必要かもしれません。例えば、月に1時間は業務を止めて自由に学ぶ時間を作ってもらうというルールを課している企業もあります。
対策:最初は社員の意向に任せない
これまで研修とOJTが中心の施策だった企業に、唐突に自己啓発としてeラーニングや企業内大学を導入して「自分で学んでください」と言われても、多くの社員は何を学べば良いのかもわからず、学ぶ必要性すら感じていません。
最初は一定のルールを設けて、強制的に学ぶ時間を確保すると良いでしょう。最初は強制で習慣化することを目指し、徐々にルールを緩くしていくといった状態変化に合わせた施策の推進が成功の鍵と言えます。
学習が続かない
一度は自己啓発施策を利用したが、利用が継続しないという課題もあります。習慣化することが苦手な人も多く、いつの間にか使わなくなり、いつの間にか忘れ去られてしまうという状況は想像に難くありません。
この課題を解決するには、定期的なリマインドが効果的です。社内チャットツールや社内イントラを活用しながら、定期的に発信を続け、利用者に思い出してもらい興味関心を持ってもらう仕組みが必要なのです。また、これを人事担当者だけで行うのも工数的に厳しいということもあるでしょう。そのような場合は、社員が自発的にレコメンドし合うような文化をつくると良いです。例えば、チャットツール内に利用者だけのチャンネルを作成し、試聴したコンテンツを投稿してもらうルールを設けるだけでもリマインドとして非常に機能します。
対策:自ら学んでもらえるよう促す
さまざまなメリットを得られる自己啓発ですが、社員が自己啓発を「やらなければいけないこと」と認識している状態は、決して好ましい状態ではありません。自己啓発においては、あくまでも従業員一人ひとりが自主的に勉強しようというモチベーションを持ち、実際に行動へと移すことが重要となるのです。
社員の内発的動機を刺激するためには、上司のフィードバックやキャリアデザインの明確化が必要です。つまり、自己啓発の施策だけを見て成否を決めるのではなく、マネジメント研修でフィードバックが適切にできる管理職を育成したり、キャリアデザイン研修で社員それぞれに自身のキャリアと向き合う訓練を実施したりと、1つの施策ではなく複合的に施策を実施して、自ら学ぶ必要性を感じるような状態を目指すと良いでしょう。
07自己啓発を推進している企業事例
社員が自己啓発を進めることは、本人のみならず企業にとってもメリットとなることから、現在さまざまな企業が社員の自己啓発に対して支援をしています。この章では、実際に自己啓発を推奨している大手企業の導入事例をご紹介します。これから自己啓発を自社内に取り入れたいと考えている方は、ぜひ参考にしてください。
旭化成株式会社

日本を代表する総合化学メーカーの旭化成株式会社では、社員の自律的な学びを支援するため、社内学習プラットフォーム「CLAP(Co-Learning Adventure Place)」を導入しました。この取り組みは、2022年春に発表された中期経営計画で掲げた「終身成長」の方針に基づいており、社員が自らキャリアを考え、成長し続けることを会社として後押しする狙いがあります。
CLAPにはSchoo for Businessをはじめとした社内外の多様な学習コンテンツが搭載され、社員が興味や課題に応じて自由にコースを選べる仕組みになっているのが特徴です。
また、全社員約2万人にIDを付与することで、学びたいときに誰でもアクセスできる環境が整備され、導入からわずか10日で半数以上が利用を開始するなど、自己啓発の習慣化が進んでいます。
トライアルでは、集合学習イベントや周知活動を実施した結果、約49%の社員が「個人の成果が出た」と実感しています。全社展開後は、わずか10日間で約1万人がCLAPにアクセスし、業務への応用も見られるようになりました。現在は、学習目標を共有する小規模コミュニティの構築や、目標管理面談との連動を進めており、社員の学習意欲を継続的に高める取り組みを強化しています。
サントリーホールディングス株式会社

サントリーホールディングス株式会社では、社員の学びを支援するプラットフォームとして「寺子屋」を運営しています。寺子屋は、社員が自発的に企画した勉強会の開催や、Schoo for Businessを含む外部コンテンツの受講ができる場として、社員同士のつながりや学び合いを促進しています。
同社がSchooの導入を決めた背景には、学びの選択肢を社員に広げ、自律的な成長を促す狙いがありました。特に自己啓発については、受け身になりがちな学習環境からの脱却を目指し、コンテンツの多様性や学習体験のしやすさに着目してSchooを採用。社内限定の生放送配信などと連動した取り組みで、エントリー数は20名以上増加するなど、利用促進の成果が表れています。
加えて、人事部門ではSchooを活用した反転学習形式の勉強会を企画し、共通の動画を視聴したうえでディスカッションを行うことで、社員同士の相互理解や具体的な課題解決に結びつく学びの場を創出しています。こうした取り組みを通じて、社員が「思い立ったときにすぐに学べる」環境づくりを強化し、自主的な学習文化の醸成を実現しているのです。
株式会社ポーラ

ポーラでは、「自ら手を挙げて学びを選ぶ」姿勢を醸成するために、Schooの利用にあたって社内公募制度を導入しています。利用希望者を募る形にすることで、受け身ではなく自律的に学びに向かう姿勢を育てることが狙いでした。業務と両立しながらも学びを楽しむ社員の姿が社内で徐々に広がり、「Schooを導入してくれてありがとう」「毎日楽しく学んでいる」といった前向きな声も多く届くようになりました。
こうした自律的な取り組みは、個人の知識習得にとどまらず、上司との対話や部署内での情報共有のきっかけにもつながっています。加えて、個人利用にとどまらず、事業部単位での一括活用や新人研修での導入も進んでおり、組織全体として学びの輪が広がっています。
導入から時間が経つにつれ、学習に対する心理的ハードルが下がり、「Schooの授業をきっかけに別の学びにも取り組むようになった」といったように、学びの連鎖が生まれていることも印象的です。自己啓発を自然な行動として組織文化に根付かせるための仕組みづくりとして、公募制と学びの共有は非常に効果的だったといえます。
大鵬薬品工業株式会社

大鵬薬品工業株式会社では、多様化するキャリアやスキルへの対応として、社員が自ら目的を持って学ぶ「学びの自律化」を掲げ、「タイホウマナビバ」という取り組みをスタートしました。これにより、集合研修に加えて自発的な学習の場を整備し、従来の通信教育からより実務に直結した学びへと進化させています。
Schooの集合学習機能や自律型研修パッケージを活用し、推奨授業の選定やワークショップの設計など、受講者が継続的に学べる仕掛けを導入。第1期(2024年6月〜9月)には144名が応募し、そのうち約4割が管理職でした。受講率はおおむね90%以上を維持し、高い学習定着率を実現しています。
学ぶ内容の自由度を確保する一方で、目的設定と振り返りを重視したワークショップを必須化し、学びの質と意欲を高めました。さらに、学習の成果を社内で共有することで学習が拡散し、第2期では応募者が増加。社員同士が学び合う「学びの自走化」も見られるようになっています。
株式会社ミロク情報サービス

株式会社ミロク情報サービスでは、「プロフェッショナル人材の育成・教育」を基本方針に掲げ、社員の知識習得や能力開発の基盤としてSchooを導入しました。キャリア採用者を含め多様なバックグラウンドを持つ社員に対し、個別ニーズに対応できる学習環境を整備しています。
学びを個人任せにせず、四半期ごとの学習時間の確保をルール化するなど、習慣化に向けた工夫を実施。受講は業務の一部として扱われ、業務時間内での視聴も推奨されるなど、日常の中に学びを組み込む体制を構築しています。その結果、受講率は80%以上を維持し、継続的な学習が定着しています。
さらに「カリキュラムセレクト」を活用し、管理職向け研修にもSchooを導入。アセスメントテストの結果をもとに、必要なスキルに対応した授業を個別に提供することで、より実践的な学びにつなげています。こうした取り組みにより、学びが業務に直結し、営業現場などでも成果が見られるようになりました。
株式会社アトレ

株式会社アトレでは、社員の学習機会を増やすことや個々のニーズに対応した研修設計が課題となっており、2023年度の従業員サーベイを機にオンライン研修の導入を検討しました。特にワーキングマザーを含む社員にとって、限られた時間の中で柔軟に学べる環境の整備が必要とされていました。
また、人事制度の改正を契機に、行動指針「自ら考え自ら行動する」を実現できる前向きな社員に学びの選択肢を提供するため、幅広いジャンルと豊富なコンテンツ数を持つSchooを導入。資格取得だけでなく、日常生活にも活かせるテーマの多さが社風に合っている点も評価されました。
導入後は、主任・副主任研修や担当課長研修、キャリア研修などでSchooを活用しています。受講者が自ら必要なコースを選択する形とし、職位ごとの役割や評価項目に合わせてコンテンツを設計。さらに、担当課長研修では事前にSchooの動画を視聴し、当日のディスカッションにつなげることで、効率的な研修運営と理解促進を実現しました。
研修後は、Schooのレポート機能を活用し、受講者が選択理由や今後の活用方針を記載。その内容を上長へ共有することで、育成に活かす取り組みも行われています。社員からは「自分のペースで学べて良かった」「課題に合ったテーマを選べた」などの声が寄せられ、学習意欲の向上にもつながっています。
ニッポンレンタカーサービス株式会社

ニッポンレンタカーサービス株式会社では、社員の学習意欲の低下や評価制度との乖離といった人材育成の課題を抱えていました。従来の研修は「やらされ感」が強く、実際の評価制度と研修内容のズレが、社員の理解不足や学びへの関心の薄れにつながっていたのです。
このような背景から、会社の重点施策に「人材育成」が明確に掲げられたタイミングで、研修の在り方を見直すこととなりました。Schooを活用し、評価制度と連動した学習内容を整備することで、学ぶ目的や意味を明確化し、受講者の納得感を高める施策を推進しています。
現在は、各階層ごとに10時間の必須研修を設け、Schooの講座と人事制度の要件定義を紐づけたカリキュラムを構築。受講後には業務への応用を記載したレポートを提出してもらい、学習内容の定着と現場実践を後押ししています。また、自律学習の機会も開放されており、希望者は業務時間内でも自身の関心や課題に応じたテーマを自由に学べる環境が整備されています。
導入に際しては、所属長と受講者への事前連携を丁寧に行い、研修に対する理解と協力体制を構築。さらに、1年間で10時間という無理のない学習量に設定することで、日々の業務と両立しやすくなっています。
08自己啓発の支援ならSchoo for Business

オンライン研修/学習サービスのSchoo for Businessでは約9,000本の講座を用意しており、様々な種類の研修に対応しています。また、講座も汎用的なビジネススキルから職種に特化した専門スキルまで幅広く、自己啓発の支援ツールとしても利用いただいております。
研修と自己啓発を掛け合わせることにより、誰かに要求されて学ぶのではなく、自発的に学び、成長していく人材を育成することが可能になります。ここでは、Schoo for Businessの具体的な活用方法と、特徴、さらにはどのようなメリットがあるのかを解説します。
| 受講形式 | オンライン (アーカイブ型) |
| アーカイブ本数 | 9,000本 ※2023年5月時点 |
| 研修管理機能 | あり ※詳細はお問い合わせください |
| 費用 | 1ID/1,650円 ※ID数によりボリュームディスカウントあり |
| 契約形態 | 年間契約のみ ※ご契約は20IDからとなっております |
大企業から中小企業まで4,000社以上が導入

Schoo for Businessは、大企業から中小企業まで4,000社以上に導入されています。利用用途は、階層別研修やDX研修、自律学習、キャリア開発などさまざまです。
導入事例も掲載しています。資料請求いただくことで事例集も併せてお渡ししています。
自己啓発に関するSchooの講座を紹介
Schooは汎用的なビジネススキルからDXやAIのような最先端のスキルまで、9,000本以上の講座を取り揃えております。この章では、『学び方を学べる』自己啓発に役立つ授業を紹介いたします。
学び方入門
本授業は、何かを学び始めたい人が、知っておくべき概念やテクニックを学ぶシリーズ企画です。義務教育で経験した学び方が、必ずしも社会人にも使えたり、自分にとって最適とは限りません。学び始めるその前に、まずはこの授業で学び方を学びましょう。
-
 一般社団法人21世紀学び研究所 代表理事
一般社団法人21世紀学び研究所 代表理事
ハーバード大学経営大学院でMBA取得後、金融機関金庫設備の熊平製作所・取締役経営企画室長などを務めた後、日本マクドナルド創業者に師事し、新規事業開発を行う。昭和女子大学キャリアカレッジでは、ダイバシティおよび働き方改革の推進、一般社団法人21世紀学び研究所ではリフレクションの普及、一般財団法人クマヒラセキュリティ財団ではシチズンシップ教育に取り組む。Learning For All等教育NPO活動にも参画。2018年には、経済産業省の社会人基礎力に「リフレクション」を提案し、採択される。文部科学省中央教育審議委員、内閣官房教育再生実行会議高等教育ワーキンググループ委員、経済産業省『未来の教室』とEdTech研究会委員などを務める。
※研修・人材育成担当者限定 10日間の無料デモアカウント配布中。対象は研修・人材育成のご担当者に限ります。
学びが身につき 人生が豊かになる勉強術
本コースのテーマは「勉強術」です。「学んだことをしっかりと身につけ、人生に活かせる」ようになる大人のための勉強術を学ぶことができます。講師は東進ハイスクールの人気講師でもある吉田裕子先生です。
-
 国語講師・著述家
国語講師・著述家
国語講師。大学受験塾やカルチャースクールで古典文学を教えるほか、航空会社や銀行などで、敬語・言葉遣い・文章力を指導する研修講師も務める。Schooでも約1年間にわたって「大人の語彙力が使える順できちんと身につく授業」を担当した。下は小1、上は90代までを教える中で、分かりやすく楽しく話すことを追求している。近著に『大人らしく和やかに話す 知的雑談術』(日本実業出版社)、『たった一言で印象が変わる大人の日本語100』(ちくま新書)など。東京大学教養学部・慶應義塾大学文学部 卒業。放送大学大学院・京都芸術大学大学院学際デザイン領域 修了。
※研修・人材育成担当者限定 10日間の無料デモアカウント配布中。対象は研修・人材育成のご担当者に限ります。
ChatGPT、私の勉強に付き合って
本コースでは、ChatGPTを「学びの相棒」として活用し、さまざまなスキルを身につけるためのテクニックを紹介します。ChatGPTを活用して“効率よく”学びたい人や、自走できる勉強法を身につけたい人におすすめのコースです。
-
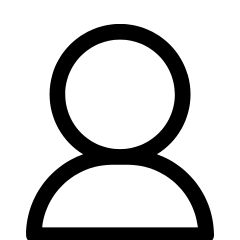 (株)セブンアイズ代表取締役
(株)セブンアイズ代表取締役
株式会社セブンアイズ代表取締役(本社:福岡市/サテライト:長崎市)。 2008年創業。SEO・AIO・SNS対策を専門とするWeb戦略系経営コンサルタント。 ホームページ制作やSEOやSNSなどの集客支援を出発点に、生成AIを活用したDX支援まで、デジタル領域の課題解決を一貫して手がける。All About「SEO・SEMを学ぶ」ガイド、宣伝会議Webライティング講師、Schoo講師。東京〜鹿児島まで広域で活動。コンサルティング実績はひと月120件以上(累計1万件以上)、登壇セミナーはひと月10回以上にのぼる。著書に『これからはじめる SEO内部対策の教科書』(技術評論社)をはじめ、SEO・ChatGPT関連のベストセラー多数。2025.8時点で累計著書13作。
※研修・人材育成担当者限定 10日間の無料デモアカウント配布中。対象は研修・人材育成のご担当者に限ります。
09まとめ
自己啓発は人材の質を上げることにつながる投資ですので、これからの時代に非常に有効な施策です。社員一人ひとりが「よりよい自分」や「より大きな成功」を達成するために奮闘できる手段であるため、企業はぜひサポート体制を整えてあげてください。方法がわからないということであれば、プロの講師が提供する、オンライン研修の実施がおすすめです。自社にマッチした最適なプログラムを正しく活用することが、企業の更なる発展につながることでしょう。




