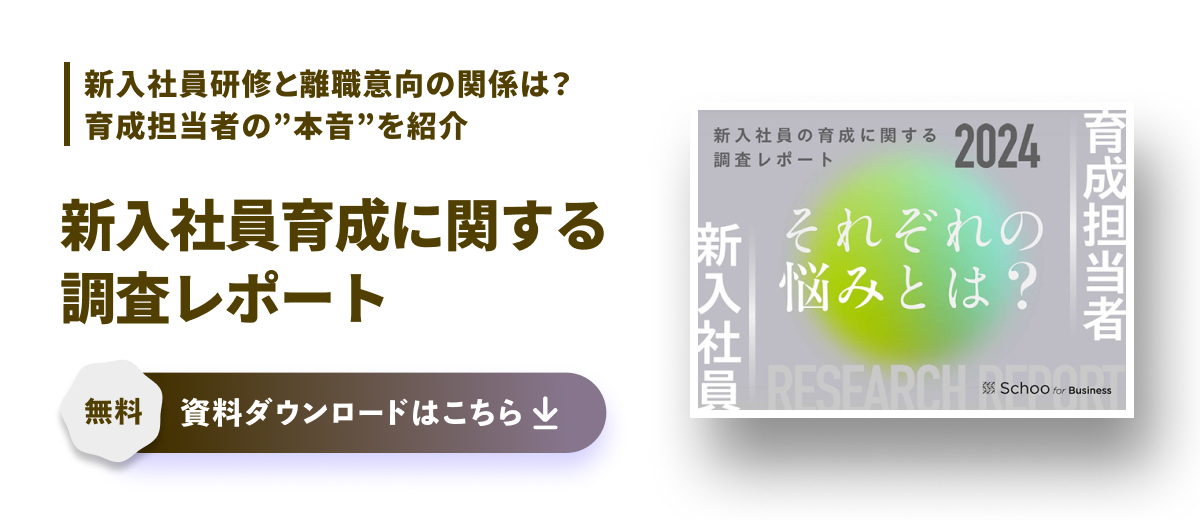新入社員研修で声だしの意義とテーマ選定の注意点を解説する

新入社員研修では声出しを行う意味とはどんなことでしょうか。声出しが無意味と言われることもあるため、その有効性を判断しなければいけないと感じる担当者の方も多くいらしゃいます。そこで、本記事では新入社員研修において声出しを実施する場合のテーマや有効性について解説していきます。
01新入社員研修における声出し研修の内容
新入社員研修において声出しを行う際には、社訓の読み上げや挨拶などを内容として取り入れる企業が多いようです。この章では、具体的な声出しの内容を紹介します。
社訓の読み上げ
多くの企業が取り組んでいるのが、社訓や経営方針の読み上げです。社訓や経営方針とは、企業で働く上で、最初に理解をしておきたい内容になります。これらは就活において働きたいと思うかを判断する材料にもなっており、企業にとっては自社を知ってもらう上で重要な項目です。社訓を声出して読み上げることは、企業を理解しその一員になった意識改革で有効です。声を出すことで、しっかり落とし込みを行い正しく覚えていきます。
基本となる10個の挨拶
ビジネスマナーの基礎は挨拶からと言われるとおり、挨拶は新入社員にとって必要不可欠な習得テーマです。声出しで練習することにより、とっさの行動で実践できる訓練を行います。基本となる10個の挨拶は、以下の通りです。
- ・出社時:「おはようございます」
- ・外出時:「行ってきます」
- ・帰社時:「ただいま戻りました」
- ・帰宅時:「お先に失礼します」
- ・他の社員の外出時:「行ってらっしゃい」
- ・他の社員の帰社時:「お帰りなさい」
- ・他の社員の帰宅時:「お疲れ様です」
- ・入室時:「失礼します」
- ・退室時:「失礼しました」
- ・「よろしくお願いします」
グループワークでの声掛けや発表
もう1つ検討しておきたいのは、グループワークに声出しを取り込むことです。グループワークにおいては、チーム内での協力が必要不可欠です。検討を進める中で声掛けや発表の際に声を出して元気よく発表するなど、声を出すということも意識的に盛り込んでおきましょう。元気よく発表するという視点では、マイクを使わずに発表してもらうなどの工夫を行うことで、大きな声をはっきりと出すという訓練にも繋がっていきます。
02新入社員研修で声出しが導入される理由とは
新入社員研修で声出しを組み込む理由には、社会人としての意識変革を促したり、メンタル面の強化を目的にしたりと多様な理由があるそうです。この章では、新入社員研修で声出しが導入される理由を紹介します。多くの企業が新入社員研修で声出しを取り入れている理由を知ることで、自社では取り入れるべきかを考えていく材料にしてみてください。
社会人としての意識変化を促す
学生から社会人への切り替えとして、社会人としての意識変化を促すことを目的として声出しを行います。部活やサークルとは異なる環境の中で、声出しを行うことで社会人としての意識を芽生えさせ、新たなスタートを切って欲しいという思いを込めて実施します。意識の変化は、きっかけにより進んでいきます。このきっかけが声出しになります。
メンタル面の強化ができる
大きな声を出す声出しは、体力を使うと同時にメンタル面を強化させます。なんども繰り返し声出しをすることや、基準に合格するために繰り返し声出しをしていくことは大変なことです。1度では基準に合格せず、繰り返しチャレンジをし続けることで簡単には折れない精神力を培っていきます。
達成感の体感
努力して基準をクリアすることの達成感は成功体験として新入社員の記憶に残ります。最初は、誰でも失敗します。繰り返し声出しを行い悔しい思いをした分だけ、その達成感は大きなものになります。こうした達成感の体感は記憶だけではなく、自信にも繋がります。実際に業務を担当し始めた際に、何か大変だと感じることがあっても新入社員研修を乗り越えた自信は大きな武器になります。
チームワークの重要性を体感する
人は目の前で頑張っている人を見ると、応援をしたくなります。研修を一緒に受けているメンバーが声出しで頑張っている姿や悔しそうな顔を見れば自ずと応援をしていきます。こうした他人を応援する気持ちは、協調性やチームワークの良さ、重要性を理解する経験になります。一緒に頑張っているメンバーが居れば、自分も頑張れると感じることは、社会人に必要なチームワークを育てる基盤構築にも繋がります。
03声出し研修の有効性が問われる理由
声出し研修は意味がなく、旧時代的な発想という声があるのも事実です。この章では、声出し研修に対して批判的な意見を紹介します。
受講者から厳しい・意味がないという意見もある
声出し研修は厳しい、意味がないと受講生から意見が出る場合もあります。厳しいと感じるのは、慣れない声を出すこと、上手くできない、試験に合格しないというネガティブ体験を感じることが主な要因です。大きな声を出すという動作は、体力を使うということもあり実際に体感した方でないと分からない大変さがあります。声出し研修は往々にして、会場の端から端まで聞こえる声でという指示になり、声を出すことになれていない受講生にとっては、やりたくない、嫌だという感情も生まれやすく厳しいと感じます。こうした意見が、新入社員研修での声出しの有効性を問われる一つの要因です。
メンタルが追い込まれることを危惧する意見もある
繰り返し試験に挑戦しても合格しない場合には、新入社員ではなくてもメンタル的に厳しく追い込まれていきます。社会人となったばかりの新入社員となれば、その追い込まれかたも一層強くなる傾向があります。他の人が合格し始める中で自分が合格しない場合には、自分はダメだ、自分は合格しないのではないのかという感情が生まれてくることで、より一層、メンタルを追い込まれる可能性が増えます。苦労した結果、試験に合格することでの喜びは大きいものですが、大変な思いは記憶に残ってしまうため注意しましょう。メンタルが弱い新入社員が居る場合には特に注意が必要です。メンタルが追い込まれると体調に異変をきたすなど、顕著な症状が出る場合もあり緊急対応を行う必要も出てきます。このように、体力と気力の両側面を使って行われる新入社員研修の声出しではメンタルで追い込まれることを危惧する意見もあります。
今どきではないとの評判がある
現在の新入社員研修においては、IT技術や情報セキュリティなどの研修テーマも必須となってきています。情報処理社会において、声出しをテーマにした研修は時代にあってはいないという意見もあり、大きな声を出すこと自体が、ビジネスにおいては無い、声を張る必要はないなどの意見にも繋がります。この結果、今どきの研修テーマではないという有効性を疑う意見につながることを理解しておきましょう。
04声出し研修が導入されるケースとは
声出し研修を導入したいと考えた場合に、どんなテーマを盛り込むといいのでしょうか。ここでは、声出し研修が導入されるケースについてご紹介していきます。部門により声出しを行うテーマを変えていくこともあります。
新入社員共通で行うのは挨拶から
配属先の部署に関係なく新入社員共通で行うテーマには、社会人の基礎となる「挨拶」を選ぶ企業がメインとなるケースが多くなります。元気の良い挨拶という観点だけはなく、行動の定着化を図り、常に正しい挨拶ができるように訓練するには声出し研修が有効かもしれません。声出し研修で挨拶をテーマにする際には、正しいお辞儀の仕方を含め一連の行動様式を習得させることが必要です。声だけが出ているということではなく、正しいお辞儀と同時に行う基礎を新入社員研修の早い時期に身に付けておくことは、その先の社会人生活でも大いに役立ちます。
営業部門は目標の声出しを行う
配属先が営業部門と決まっている場合などには、その年の「売上」「利益」部門での数値目標を声出し研修のテーマに選定します。営業部門の大きなミッションは、年間の数値目標をクリアすることです。その数値をしっかりと覚えておくことは営業部門の一員になる新入社員にとっても大切なことです。正しい目標を理解し常に覚えておくことで、営業活動を行う上での指針を持つことが可能になります。
05新入社員向けの声出し研修を実施する際の注意点とは
最後に新入社員向けの声出し研修を実施する際の注意点について解説していきます。これから新入社員研修のテーマを決めるなど、声出し研修をどうしていくか検討する上で参考にして頂きたい内容です。
職種や会社の風土にあわせて必要性を決める
新入社員研修で声出しを行う場合には、配属先などの職種や企業のビジネススタイル、風土にあわせて声出し研修を行うのかを決めていく必要があります。新入社員が1名の場合や、声出しを行う必要がある部署がない場合や会社風土にそぐわない場合などは、無理に声出しを行う必要はありません。逆に、メンタル強化を目的として声出しに意義を感じる場合などには研修テーマに取り込むと良いかもしれません。研修を行う目的をどこに定めるかで必要か不要が決まってくることを前提に必要性の検討を行っていきましょう。
新入社員が到達目標を理解することが大切
声出し研修は、体力、メンタルともに負荷のかかる研修です。試験をクリアする基準が高すぎることがなく、新入社員にどのレベルまで到達して欲しいかを整理し目標を設定することが大切です。そして、新入社員がその到達目標を理解し研修に取り組むことが必要になります。どうして新入社員研修で声出しを行うのか、到達目標はどこにあるかをあらかじめ理解する場を設けてから実施するようにしておきましょう。
追い込むだけではなく成功体験が必要
声出し研修の実施は一見、体育会系の雰囲気を持ちます。その中で、「声が小さい」「もう1度」と追い込むことばかりを優先してしまうことを避ける工夫も必要です。新入社員研修を実施する中で、成功体験を積ませていくことも必要です。最初は出来なかったことが、出来るようになった、褒められたという達成感や成功体験は大きな自信となり新入社員を成長させる要素になります。新入社員研修が終わり、配属先で苦労する場面においても大変だった新入社員研修をクリアできた経験は、努力することで達成感を得ることができるという気持ちにすることができます。
即戦力となる新入社員を育成
・社会人基礎力をきちんと身につけられる
・現場に即した実践的なスキルアップも可能
スクーの資料をダウンロードする
■資料内容抜粋
・大人たちが学び続ける「Schoo for Business」とは?
・研修への活用方法
・自己啓発への活用方法 など

06Schoo for Businessの新入社員研修
Schoo for Businessでは9,000本以上の授業をご用意しており、様々な種類の研修に対応しています。その上、自己啓発にも効果的な内容の講座を毎日配信しているため、研修と自己啓発の両方に対応することができるシステムになっています。研修と自己啓発を掛け合わせることにより、誰かに要求されて学ぶのではなく、自発的に学び、成長していく人材を育成することが可能になります。ここでは、Schoo for Businessの具体的な活用方法と、特徴、さらにはどのようなメリットがあるのかを解説します。
1.研修と自己啓発を両方行うことができる
Schoo for Businessは社員研修にも自己啓発にも利用できるオンライン学習サービスです。通常の研修動画は、研修に特化したものが多く、社員の自己啓発には向かないものも少なくありません。しかし、Schooの約7,000本にも上る授業では、研修系の内容から自己啓発に役立つ内容まで幅広く網羅しているため、研修と自己啓発の双方の効果を得ることができるのです。
2.Schooの新入社員研修カリキュラム
様々な研修に対応できるSchoo for Businessの研修パッケージですが、もちろん新入社員研修にも対応しています。Schooの新入社員研修パッケージには、新入社員がまず身につけなければならないビジネスマナーや報連相に関する知識から、ビジネスパーソンとして必要なOAスキルやコミュニケーションスキルまでがラインナップされており、新入社員に必要なスキルや知識をこの研修パッケージで網羅できます。
さらに、社員に研修動画を受講してもらった後に、意見の共有会やディスカッションを行うことで、学んだことをより効果的に定着させることができます。
-
新社会人のためのビジネスマナーの基本を学ぶカリキュラムです。第一印象の磨き方(身だしなみ・挨拶・敬語)や、社内マナー(ホウレンソウ・名刺交換・電話応対など)について解説しています。
-
社会人としてのマインドセットを習得するためのカリキュラムです。「思考」「実行」の2つの視点で、すぐに現場で実践できるビジネスに必要な力を学びます。
-
見やすいグラフやスライド資料の作成方法を学ぶカリキュラムです。独学で悩みがちの本テーマを、具体例や実践例を交えながらお伝えします。
-
若手社員向けのロジカルシンキングに必要な思考法について学ぶカリキュラムです。論理性を高めて業務を遂行していく際に必要な思考法について解説していきます。
-
Excelを活用したデータ分析について学べる研修パッケージです。データ分析をする際の考え方から、「並べ替え」「オートフィルタ」「ピボットテーブル」などのExcel分析に必要な機能について学ぶことができます。
-
ビジネス文書やメール作成ついて学ぶカリキュラムです。社会人として求められる文章能力について詳しく解説していきます。
-
若手社員向けのロジカルシンキングに必要な思考法について学ぶカリキュラムです。論理性を高めて業務を遂行していく際に必要な思考法について解説していきます。
-
Wordの基礎技術を学習するためのカリキュラムです。Wordの操作方法や文書作成の基礎などを学ぶことができます。
-
Excelの基礎技術を学習するためのカリキュラムです。新入社員や若手社員が知っておくべき基本スキルについて学ぶことができます。
-
ファシリテーショングラフィック(グラレコ)のスキルを磨きたい、トレーニングをしたいという方向けの実践的な研修パッケージです。
3.管理画面で受講者の学習状況を可視化できる
Schoo for Businessには学習管理機能が備わっているため、研修スケジュールの作成を容易に行うことができます。さらに、社員の学習進捗度を常に可視化することができる上に、レポート機能を使って学んだことを振り返る機会を作ることも可能です。ここでは学習管理機能の使い方を簡単に解説します。

まず、Schoo for Businessの管理画面を開き、「研修を作成するという」ページで作成した研修の研修期間を設定します。ここで期間を設定するだけで自動的に受講者の研修アカウントにも研修期間が設定されるため、簡単にスケジュールを組むことができます。

この、管理者側の管理ツールでは受講者がスケジュール通りに研修を受けているかを確認することができます。もし決められた研修をスケジュール通りに行っていない受講者がいれば注意したり、話を聞くことができるなど、受講者がしっかりスケジュールを守っているかを確認することができます。
07まとめ
本記事では、新入社員研修の中で声出しを行う場合のテーマや注意点などについて解説しています。声出し研修を懸念する声がある中、まだまだ多くの企業で採用されている研修テーマです。本記事でご紹介している内容を新入社員研修の中で声出しを行う際に参考にしていただき、新入社員の成長に役立ててください。
▼【無料】若手の離職を止めるには?〜多様な個性を重視するインターネット的な会社の作り方〜|ウェビナー見逃し配信中

Z世代の自律型組織開発法をテーマにしたウェビナーのアーカイブです。将来の会社の成長を担う若手世代。「すぐに離職してしまう」「モチベーションの管理方法がわからない」など、Z世代を含む若手の扱いに対して課題を抱えている人事責任者の悩みに対し、若手社員の成長を促進する組織作りについて深掘ります。
-
登壇者:高木 一史 様サイボウズ人事本部 兼 チームワーク総研所属
東京大学教育学部卒業後、2016年トヨタ自動車株式会社に新卒入社。人事部にて労務(国内給与)、全社コミュニケーション促進施策の企画・運用を経験後、2019年サイボウズ株式会社に入社。主に人事制度、研修の企画・運用を担当し、そこで得た知見をチームワーク総研で発信している。