鈍感力とは?従業員をストレスから守る鈍感力の鍛え方を解説

鈍感力とは、ストレスを過度に受け止めず、必要なことに集中する力のことです。ビジネスにおけるパフォーマンス維持やメンタルヘルスのために、鈍感力の鍛え方や注意点を解説します。
- 01.鈍感力とは
- 02.ビジネスシーンで鈍感力が注目される理由
- 03.鈍感力が高い人の特徴
- 04.鈍感力の鍛え方
- 05.ビジネスシーンで鈍感力を発揮する際の注意点
- 06.社員の鈍感力を鍛える|Schoo for Business
- 07.まとめ
01鈍感力とは
「鈍感力」は、作家・渡辺淳一の著書『鈍感力』(集英社文庫)によって広く知られるようになった言葉です。ストレスの多い現代社会において、あらゆる刺激や批判に敏感になりすぎると心が疲弊してしまいます。鈍感力とは、そうしたストレス要因に対して「すべてを受け止めるのではなく、上手に受け流す」ための力です。過剰に気にしないことで、自分の心を守りながら前向きに行動する力として、ビジネスの現場でも注目されています。
▶︎参考文献:集英社文庫|鈍感力
02ビジネスシーンで鈍感力が注目される理由
厚生労働省の調査によれば、仕事でストレスを感じている労働者は82.7%に上ります。こうした背景から、企業には従業員のメンタルヘルス対策として、年1回のストレスチェック実施が義務付けられています。過度なプレッシャーや多様な価値観にさらされるビジネスの現場では、ストレスを適切に受け流す「鈍感力」が重要なスキルとして注目されています。
▶︎参考資料:令和5年労働安全衛生調査(実態調査)
▶︎参考制度:ストレスチェック制度について(厚生労働省)
03鈍感力が高い人の特徴
鈍感力が高い人には、共通する思考や行動のパターンがあります。ストレスを溜め込まず、他人の評価に左右されない一方で、失敗を引きずらない柔軟さや、自己肯定感の高さを持ち合わせています。マイペースで楽観的な性格もその一つで、これらの特徴が組み合わさることで、ストレス社会でも安定したパフォーマンスを発揮できるのです。
1:ストレスを溜め込まない
鈍感力が高い人は、ストレスを感じてもそれを必要以上に抱え込むことがありません。嫌な出来事や否定的な言葉に過敏にならず、受け流す力を持っているため、感情を引きずらずに切り替えることができます。ストレスとの適度な距離感を保つことで、心身の健康を守りながら、安定したパフォーマンスを発揮できるのが特徴です。
2:他人の評価を気にしない
鈍感力が高い人は、周囲からの評価や視線に振り回されることが少なく、自分の信念や判断を大切にします。「どう思われるか」よりも「どう行動すべきか」に意識が向いており、必要以上に他人と自分を比較しません。結果として、自己決定の軸を保ちながら、落ち着いた態度で仕事を進めることができます。
3:失敗を引きずらない
ミスや失敗をしても、過度に自分を責めず、すぐに気持ちを切り替えて次の行動に移せるのが鈍感力のある人の特徴です。反省はしても、後悔にとらわれることはなく、前向きな姿勢を維持できます。こうした回復の早さは、ビジネス環境において継続的なチャレンジを可能にし、成長につながる要素となります。
4:自己肯定感が高い
鈍感力のある人は、自分の存在や行動に対して肯定的な見方を持っています。他人からの評価だけで自分の価値を測らず、自分の努力や成果を素直に認めることができます。自己肯定感が高いため、困難な状況でも自分を信じて立ち向かうことができ、安定したメンタルを保ちながら働くことが可能です。
5:マイペース
他人のペースや空気に過度に合わせず、自分のペースを大切にするのも鈍感力がある人の特徴です。焦らず冷静に物事を進めるため、急なトラブルやプレッシャーにも動じにくくなります。マイペースであることは、周囲から見ると頑固に映る場合もありますが、長期的には安定した成果を出せるスタイルです。
6:楽観的
鈍感力が高い人は、物事を前向きに捉える傾向があります。トラブルや課題が発生しても、最悪の事態を過度に想像せず、「なんとかなる」と考えて行動に移せるため、結果的に困難を乗り越える力を発揮します。楽観的な視点は周囲にも安心感を与え、チーム全体の雰囲気を良くする効果も期待できます。
04鈍感力の鍛え方
鈍感力は、以下の方法で鍛えることができます。
- ・1.完璧主義をやめる
- ・2.「なんとかなる」と思うようにする
- ・3.コントロールできないものがあることを知る
- ・4.メタ思考・視点を身につける
- ・5.マインドフルネスを実践する
鈍感力を鍛えるには、思考や捉え方を柔軟にする習慣が重要です。完璧主義をやめてまず行動すること、過度に深刻に捉えず「なんとかなる」と考えること、コントロールできない物事を手放すことが土台になります。さらに、自分を俯瞰して見る視点(メタ認知)や、今この瞬間に集中するマインドフルネスの実践も、感情に流されず安定して働くうえで有効です。これらを意識的に取り入れることで、日々のストレスと上手に付き合う力が養われます。
1:完璧主義をやめる
常に100%を求めていると、心が疲弊しやすくなります。完璧を目指すあまり、他人の評価に過敏になり、仕事の進行にも支障をきたす可能性があります。6割の完成度でもまず行動し、周囲と協力しながら成果を高めていくことが、結果として高パフォーマンスにつながります。
2:「なんとかなる」と思うようにする
トラブルや不安に直面したときは、「なんとかなる」と考えることで、過度なストレスを軽減できます。この姿勢は、思考を一時的にリセットし、解決策に集中するための土台になります。楽観的に構えることで、前向きな行動が生まれやすくなります。
3:コントロールできないものがあることを知る
他人の感情や環境の変化など、自分ではどうにもならないことに執着しない意識が重要です。変えられないことを受け入れ、気持ちを切り替えることで、精神的な負担を減らすことができます。
4:メタ思考・視点を身につける
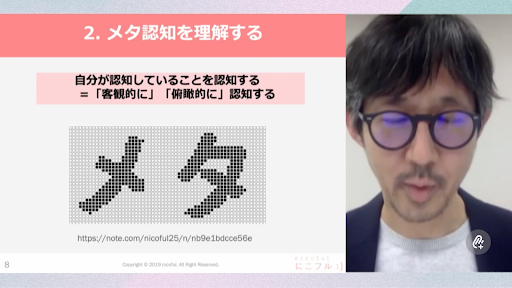
メタ思考とは、自分の思考や感情を一段高い視点から観察することです。講義内では「認知していること自体を認知する」「自分の状況を俯瞰的にとらえる」といった表現で紹介されています。この視点を持つことで、感情に流されず冷静に行動でき、トラブル時のストレス対処にも効果を発揮します。
▶︎授業引用:「メタ認知」を高めるマインドフルネス
5:マインドフルネスを実践する
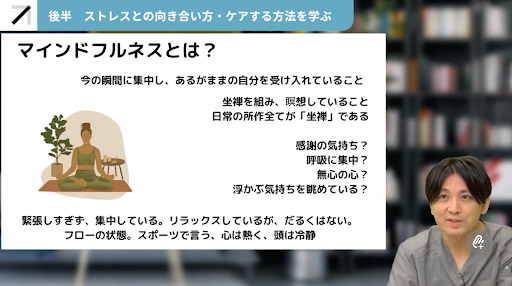
マインドフルネスとは、「今この瞬間」に集中し、あるがままの自分を受け入れる状態を指します。講義では、緊張しながらも集中している“ゾーン状態”が例として紹介されています。深呼吸や瞑想を通じて、この状態を意識的に再現することで、ストレス下でも仕事に集中しやすくなります。
▶︎授業引用:こころのメカニズムと対処法
05ビジネスシーンで鈍感力を発揮する際の注意点
ここまで述べてきた通り、鈍感力はストレスマネジメントに必要なスキルです。しかしビジネスシーンにおいては適切に発揮しなければ、信用を失うことにつながりかねません。以下に注意点を3つ挙げます。
- ・1.発揮する場面としない場面の見極めが必要
- ・2.直属の上司には使わない
- ・3.事前の信頼残高に左右される
1.発揮する場面としない場面の見極めが必要
鈍感力は自身のストレスになりそうな情報を、上手にスルーすることです。しかし、すべてをスルーすることは避けなくてはなりません。自身のことを思っての苦言やアドバイスには素直に耳を傾けるべきです。また部下や後輩が困っている状態に、気がつかないふりをするのも問題です。本当に向き合うべきことはスルーせず、真剣に向き合う姿勢を周囲に見せておかなくては、ただの「いい加減な人」と認識されてしまいます。発揮する場面とそうでない場面を理解し、自身でコントロールするのが鈍感力の正しい使い方です。
2.直属の上司には使わない
鈍感力は原則として、直属の上司には使わないほうが無難です。鈍感力の度が過ぎた場合、ただの「いい加減な人」と認識される恐れがあることは先に述べた通りです。直属の上司にこうしたマイナスの印象を与えてしまうと、その後の仕事に影響がおよびます。大事な仕事を任されなくなり、成長の機会を自ら奪ってしまうことになるでしょう。
3.事前の信頼残高に左右されることも
鈍感力を発揮しても許されるかどうかは、それまでの信頼の積み重ねに左右される側面があります。本当に向き合うべき問題には、正面から向き合い解決に導く姿勢を周囲が認識しているか。困っている部下や同僚がいたらスルーせず、すぐに助け舟をだしているか。こうした普段の信頼の積み重ねがあることで、鈍感力を発揮しても信用を失わないのです。
06社員の鈍感力を鍛える|Schoo for Business

オンライン研修サービス「Schoo for Business」では、ストレスマネジメントやメンタルヘルスに役立つ講座も数多く提供しており、鈍感力を高めるための土台を築くことができます。マインドフルネスやメタ認知といった実践的なテーマをはじめ、感情との付き合い方や思考の切り替え方を学べるコンテンツが豊富に揃っており、現場での安定したパフォーマンス発揮を支援します。
| 受講形式 | オンライン (アーカイブ型) |
| アーカイブ本数 | 9,000本 ※2023年5月時点 |
| 研修管理機能 | あり ※詳細はお問い合わせください |
| 費用 | 1ID/1,650円 ※ID数によりボリュームディスカウントあり |
| 契約形態 | 年間契約のみ ※ご契約は20IDからとなっております |
鈍感力やストレスマネジメントに関するコンテンツ一覧
| 講座 | 時間 |
| カスハラから自分の心を守る | 1時間 |
| 弱メンタルでもうまいことやる | 1時間 |
| 元コンサルが教える ストレスに負けないためにできること | 1時間 |
| 人間関係のモヤモヤをなくす科学的な方法 | 45分 |
| 口ぐせで心の免疫力を上げる | 1時間 |
| 背伸びをしないメンタルトレーニング | 1時間 |
| ストレスの正体 不調のサイン | 1時間 |
| 精神科医に聞くストレスとの向き合い方 | 1時間 |
Schoo for Businessの資料をダウンロードする
大企業から中小企業まで4,000社以上が導入

Schoo for Businessは、大企業から中小企業まで4,000社以上に導入いただいております。利用用途も各社さまざまで、IT人材育成もあれば階層別研修やDX研修としての利用、自律学習としての利用やキャリア開発の目的で導入いただくこともあります。
導入事例も掲載しているので、ご興味のあるものがあれば一読いただけますと幸いです。以下から資料請求いただくことで導入事例集もプレゼントしております。そちらも併せて参考にいただけますと幸いです。
07まとめ
ストレス社会といわれる現代において、鈍感力は自分の心を守るための重要なスキルです。ただ無神経になるのではなく、必要なことに集中し、気にしすぎない思考を持つことで、心の安定と仕事の成果を両立することができます。鈍感力は意識的に鍛えることが可能であり、メタ認知やマインドフルネスなどの思考習慣を取り入れることで実践につなげられます。組織としても、誤解なく正しく活用できるようサポート体制を整えることが求められます。


