チームビルディング研修の内容とは|目的・カリキュラム例を紹介

チームビルディング研修とは、メンバーが主体的に行動し、協力して高い成果を出せるチームを作るための研修です。チームビルディングは企業の成長だけでなく各社員の成長にも重要で、強いチームは会社全体に好影響を及ぼします。本記事では、その効果とおすすめのゲーム・研修内容を紹介します。
01チームビルディング研修とは
チームビルディング研修とは、共通の目的や目標に向けて協働し、高い成果を生み出せるチームを構築するための研修です。対象は新規プロジェクトメンバーや部署内の編成替え直後のチーム、組織間連携を強化したい職場など幅広く、円滑なコミュニケーションや信頼関係の醸成、役割の明確化を通じて生産性向上や離職防止といった効果が期待できます。
チームビルディングの意味
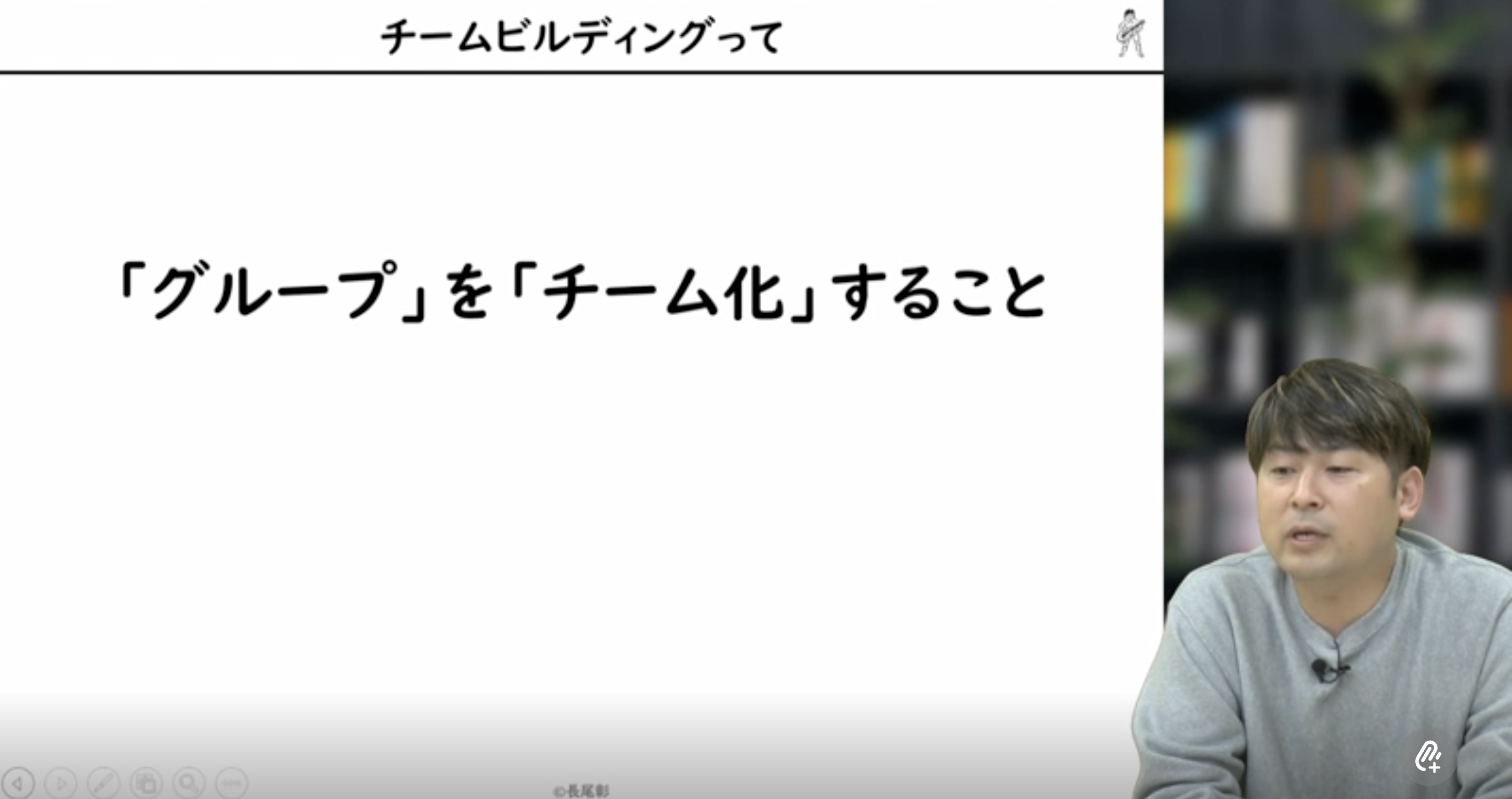
チームビルディングとは、単なる集まりであるグループを、主体性と協働性を備えたチームへ成長させる取り組みを指します。社会学者ブルース・タックマンが提唱した「フォーミング(同調期)」「ストーミング(混沌期)」「ノーミング(調和期)」「トランスフォーミング(変態期)」という4段階の発達モデルが有名で、段階を経てメンバー同士が役割や目標を自ら設定し、相互補完しながら成果を上げられる関係へと変化します。このプロセスを理解し適切に促すことで、メンバーの強みを最大限に活かし、組織全体のパフォーマンス向上につなげることができます。
02チームビルディング研修の目的
チームビルディング研修を実施する目的には主に以下が挙げられます。
- 心理的安全性を高める
- コミュニケーションの質を高める
- チームワークの重要性を体験する
- 責任感を醸成する
この章では上記の目的について詳しく解説します。
心理的安全性を高める
まず、形成期(フォーミング)から混乱期(ストーミング)の状態に移行するためには、心理的安全性を高めて、メンバー全員が自分の意見や感情を表現できるようにする必要があります。そのため、形成期(フォーミング)におけるチームビルディング研修の目的は、心理的安全性を高めることと言えるでしょう。
そして、日本企業における多くの組織やチームが形成期(フォーミング)で停滞しているため、チームビルディング研修の大半は、心理的安全性を高めるために実施されます。
心理的安全性を高めるには、集団や組織で流通する情報量を増やすことが重要です。そのためには、単純にお喋りをするだけでは意味がありません。メンバーそれぞれの特徴や個性、強みや弱みも含めて、相互理解を進めるための情報が組織や集団の中で多く流通して、飛び交うような工夫をする必要があります。
▶︎関連記事:心理的安全性とは|ぬるま湯組織との違いや高める方法について解説
コミュニケーションの質を高める
コミュニケーションの量を増やして、心理的安全性が確保されれば、自然と第2ステージの混乱期(ストーミング)に移行します。このステージにおけるチームビルディング研修の目的は、コミュニケーションの質を高めることです。
混乱期(ストーミング)に入ると、反対意見や批判的なことを言う人が出てきます。その際に、チームの和を乱すからと、これらの意見を封殺してしまうと形成期(フォーミング)に戻ってしまうのです。
そのため、反対意見や批判的な発言の背景や理由を理解するために、ちゃんと周りが傾聴しなければなりません。また、その反対意見に対しても異論があれば述べる必要があります。つまり、声の大きい人の意見で物事を決めるのではなく、メンバー全員が納得いくまで話し合い、意見をとにかく発散させるという取り組みが大事なのです。
このような建設的な対話ができる関係性を作るということが、コミュニケーションの質を高めるということです。このコミュニケーションの質、つまりは建設的な対話ができる関係性を作ることが、統一期(ノーミング)に進むための鍵となります。
チームワークの重要性を体験する
チームワークの重要性を体験することは、メンバーが共同作業の価値を理解し、実践するための重要なステップです。研修でのプログラムを通して、個々の力を合わせることで、単独で行うよりも大きな成果を上げることが可能です。
また、チームでの活動を通じて、お互いの強みや弱みを理解し、補完し合うことができます。加えて、共同作業を通じて、メンバー間の信頼関係が深まり、より強固なチームが形成されるでしょう。
▶︎関連記事:チームワークとは?必要な理由や最大化させるためのポイントを解説
責任感を醸成する
責任感を醸成することは、チーム全体の成果に対する各メンバーの責任意識を高めるために重要です。
第一にチームビルディング研修では、個々の貢献意識を向上させることが可能です。これにより、メンバー一人ひとりが自分の役割と責任を理解し、積極的に貢献する意識が高まります。
また、研修プログラムを責任持って遂行することで、自己効力感が向上し、自信を持って仕事に取り組むことができます。加えて、個々が責任を持つことで、チーム全体としてのパフォーマンスを向上させることが可能です。これらの目的を達成するために、チームビルディング研修では様々なアクティビティやエクササイズが行われ、実践を通じて、責任感を
▶︎関連記事:責任感とは?ビジネスシーンで求められる責任感を解説
03チームビルディング研修のプログラム例
本章では、Schooを用いたチームビルディング研修のカリキュラム例をご紹介します。ここで紹介する内容は、チームの成長段階や課題に合わせて段階的に学べる構成になっており、リーダー層から一般社員まで幅広い対象に対応可能です。新チーム発足時や組織の風土改革を進めたいときなど、具体的な行動変容とチーム力向上の両立を目指す研修として活用できます。
| 第1回 | チームビルディング-リーダーの振る舞いを学ぶ- |
| 時間 | 60分×4コマ |
| 研修内容 |
|
| 第2回 | “I”から“ We”へ踏み出すチームビルディング |
| 時間 | 60分×1コマ |
| 研修内容 |
|
| 第3回 | チームの成果を引き上げる 熱狂の火種 |
| 時間 | 60分×2コマ,60分×1コマ |
| 研修内容 |
|
04チームビルディング研修の内容
チームビルディング研修の内容は主に以下の4種類があります。
- 1.座学による知識習得
- 2.ゲーム研修
- 3.アクティビティ研修
- 4.合宿研修
チームビルディング研修と聞くと、ゲームやアクティビティ研修を想像する人が多いです。しかし、これらだけでは楽しかったり、仲良くなれたりするので、研修満足度は高くなる傾向にありますが、楽しかったで終わってしまい、実務に戻った際には何も得ていないという状態に陥りやすいでしょう。
その状態を回避して、チームビルディング研修の効果を最大化するためには、座学による知識習得で「チームビルディングの必要性」・「タックマンモデルのフレームワーク」などを、個々のメンバーが理解しておくことが重要です。
1.座学による知識習得
座学による知識習得は、いわゆる"研修"です。集合研修やオンライン研修など、座学による知識習得の方法は多岐にわたりますが、業務の忙しさなどを加味して適切な手段をとる必要があります。
メンバー全員の参加時間を確保できるのであれば、オフラインの集合研修でも良いでしょう。
一方で、全員の予定を調整するのが難しい場合は、eラーニングを活用したオンライン研修を用いて、全員が好きな時間と場所で研修を受けられる状態を目指す必要があります。
2.ゲーム研修
ワークショップやゲームを用いて行うチームビルディング研修は、多くの企業で導入されています。次の章でご紹介しますが、何も道具を使わずに体だけを使うゲームや、ピンポン玉を使うゲームなど、研修で使われるゲームには様々な種類があります。ただ楽しくゲームをすることが目的ではなく、ゲームで協力してゴールを目指すというプロセスの中で、チームで力を発揮する能力を身につけます。
3.アクティビティ研修
室内でゲームを活用した研修に加えて、屋外で行うアクティビティ研修もチームビルディング研修における手法の1つです。具体的な内容としてはアスレチックや軽いスポーツなど、ゲームと同じくチームワークを養うことができる内容が多く、楽しみながら行える研修です。室内で行うよりも屋外で行う方がコミュニケーションが取りにくいため、チームメンバーのコミュニケーション力が鍛えられるというメリットもあります。
4.合宿研修
チームビルディング研修には、合宿型の研修も効果的です。何より、チームのメンバーと過ごす時間が長くなるため、メンバーの良い面と悪い面の両面を見たうえでゲームやワークショップ、スポーツ・アスレチックなどに臨むことになり、結果的にチームワークが深まることになります。ただ、合宿の宿泊費や、交通費など、経費がかなりかかってしまうため、導入する際には予算に合った方法を考えるようにしましょう。
05チームビルディング研修におすすめのゲーム
チームビルディング研修には、ゲームを活用することが有効であると言われています。ゲームには数分で行えるものから数時間、数日間かけて行えるものまで存在します。ここでは、数分で手軽に行うことができるゲームをご紹介します。
ジェスチャーゲーム
| 人数 | 3〜8人 |
| 所要時間 | 10分〜 |
| 遊び方 |
|
事前準備がほとんど不要で、お題さえあればどこでも実施可能です。言葉を使わずに表現することで、意思疎通力やノンバーバルコミュニケーション能力を鍛えられます。
バースデイライン
| 人数 | 8〜15人 |
| 所要時間 | 5〜15分 |
| 遊び方 |
|
言語・非言語両方の重要性を体験できるゲームで、短時間で盛り上がります。
ピンポン玉リレー
| 人数 | 6人〜 |
| 所要時間 | 10分 |
| 遊び方 |
|
軽く不安定なピンポン玉を扱うため、集中力と連携が求められ、自然とチームワークが強化されます。
ウソつき当てゲーム
| 人数 | 5〜10人 |
| 所要時間 | 10分 |
| 遊び方 |
|
会話の中で相手の意図を読み取る力や傾聴力を養うことができます。
条件プレゼン
| 人数 | 10〜20人 |
| 所要時間 | 30分 |
| 遊び方 |
|
短時間で行え、プレゼン力・発想力・チームの連携を高められます。
ペーパータワー
| 人数 | 3〜8人 |
| 所要時間 | 5分 |
| 遊び方 |
|
限られた素材で工夫し、協力して成果を出す力を鍛えます。
質問ゲーム
| 人数 | 4人〜 |
| 所要時間 | 1分〜 |
| 遊び方 |
|
短時間で親交を深められ、質問力や傾聴力の向上につながります。
似顔絵当てゲーム
| 人数 | 5人〜 |
| 所要時間 | 15分〜 |
| 遊び方 |
|
紙とペンだけで楽しめ、観察力やチームの一体感を高めることができます。
06チームビルディング研修を行う際のポイント
チームビルディング研修も他の研修と同じく、意識すべきポイントとして以下があります。
- 対話を意識させる
- 質問力・聴く力を身につけられるようにする
- 達成感を得られるようにする
- お互いの長所を見つけられるようにする
- 主体性とリーダーシップが定着できるようにする
この章では各ポイントについて詳しく解説します。
対話を意識させる
チームビルディング研修は、ディスカッション形式で行われる機会が多くなると思います。ディスカッション形式で研修を行う際に注意する必要があるのが、本当にディスカッションをさせてはいけない、ということです。
基本的に、ディスカッションは相手に自分の意見を論理的に伝えることで相手を納得させる行為を指します。勝敗を決めるものではありませんが、納得させようとする過程でヒートアップし、研修の趣旨から逸れてしまうことがあります。そのため、ファシリテーターなどを配置し、対話を意識させることが大切です。
質問力・聴く力を身につけられるようにする
質問力と聴く力は、コミュニケーションにおいて重要なスキルであり、チームビルディングには欠かせません。対話を意識したコミュニケーションを促し、質問と傾聴を繰り返すことで、これらのスキルを高めます。
質問力や聴く力には個人差があるため、ファシリテーターは不足している受講者を見極め、重点的にサポートすることが求められます。
振り返りを行う
振り返りは研修の最後のステップとして重要です。意見や感想を引き出し、課題を明確化することでPDCAサイクルを回せます。チームビルディング研修では、率直な意見を得ることで受講者同士のつながりを強化できます。
研修終了後の自由な会話の場を設けることで、本音を引き出し、信頼関係をさらに深めることが可能です。
達成感を得られるようにする
達成感はモチベーションとエンゲージメントを高め、研修効果を持続させます。明確で達成可能な目標を設定し、小さな成功体験を積み重ねることで、最終的な達成感を強化できます。
達成結果はチーム全体で共有し、祝うことで一体感を高めることができます。
お互いの長所を見つけられるようにする
長所を発見し合うことは信頼関係を強化し、協力体制を築く基盤となります。研修中に多様な役割やタスクを経験させ、強みを発見できる機会を増やします。
また、フィードバックセッションで互いを称賛することで、ポジティブなコミュニケーションが促進されます。
主体性とリーダーシップが定着できるようにする
主体性とリーダーシップは、チームの持続的な成功に不可欠です。研修中に交代でリーダー役を経験させ、問題解決を自ら提案する文化を育てます。
メンター制度を導入し、経験者が新メンバーを支援することで、実践的なリーダーシップスキルを習得できます。
「研修をしてもその場限り」「社員が受け身で学ばない」を解決!
研修と自己啓発で学び続ける組織を作るスクーの資料をダウンロードする
■資料内容抜粋
・大人たちが学び続ける「Schoo for Business」とは?
・研修への活用方法
・自己啓発への活用方法 など

07チームビルディング研修|Schoo for Business

Schooでは約9,000本の授業を保有しており、チームビルディング研修に関する授業も多く揃っています。その上、自己啓発にも効果的な内容の講座を毎日配信しているため、研修と自己啓発の両方に対応することができるシステムになっています。
研修と自己啓発を掛け合わせることにより、誰かに要求されて学ぶのではなく、自発的に学び、成長していく人材を育成することが可能になります。ここでは、Schooの具体的な活用方法と、特徴、さらにはどのようなメリットがあるのかを解説します。
| 受講形式 | オンライン (アーカイブ型) |
| アーカイブ本数 | 9,000本 ※2023年3月時点 |
| 研修管理機能 | あり ※詳細はお問い合わせください |
| 費用 | 1ID/1,650円 ※ID数によりボリュームディスカウントあり |
| 契約形態 | 年間契約のみ ※ご契約は20IDからとなっております |
Schoo for Businessの資料をダウンロードする
チームビルディング研修に関するコンテンツ一覧
Schoo for Businessの資料をダウンロードする
大企業から中小企業まで幅広く導入

Schoo for Businessは、大企業から中小企業まで幅広い企業にご導入いただいております。利用用途も各社さまざまで、階層別研修やDX研修としての利用もあれば、自律学習としての利用もあり、キャリア開発の目的で導入いただくこともあります。
導入事例も掲載しているので、ご興味のあるものがあれば一読ください。以下から資料請求いただくことで導入事例集もプレゼントしております。併せて参考にしていただけますと幸いです。
08チームビルディング研修のよくある質問
ここからは、Schooのチームビルディング研修についてのよくある質問を、Q&A形式でご紹介します。
質問:チームビルディング研修の内容について教えてください。
回答:Schoo for Businessを使ったチームビルディング研修では、チームビルディングに必要なコミュニケーションスキルやマネジメントスキルなどを学ぶ講座がよく利用されています。研修を通じ、チームで成果を出す方法や、メンバーが力を発揮できる環境づくりについて学びます。
質問:授業はどのように選んだらよいですか?
回答:スクーでは職種別・階層別に様々な研修パッケージをご用意しています。研修パッケージはいくつかの授業で構成されており、目的や対象に合わせてテンプレートを選択するだけで、簡単に研修を開始できます。チームビルディング研修パッケージの例としては、「チームビルディング研修パッケージ」や「組織マネジメント研修パッケージ」などがあります。
質問:当社の状況を踏まえたマネジメント研修パッケージは作れますか?
回答:授業を組み合わせてオリジナルの研修パッケージを作成できます。また、スクーでは階層や職種に応じた研修テンプレートをご用意しているため、1から研修を作る手間をかけずに社員に合った研修を始められます。まずはお気軽にご相談ください。<お問い合わせフォーム>
09まとめ
チームビルディング研修は、コミュニケーションの質や心理的安全性を高め、責任感を醸成することを目的に実施されます。研修では対話の機会を増やし、チームメンバーの相互理解を促すことが重要です。そのためには、グループディスカッションやゲームなど、自然と対話が生まれるようなプログラム設計が有効です。

