2/12(Thu)
2023年1月23日 11:34 更新

グローバル化やIT化によって企業間の競争が激化する中、業務の質の改善は欠かせません。ここでは業務改善に直結する見える化について、Schooオリジナル授業『業務改善のはじめ方 プロセスの見える化』を参考に、言葉の意味とメリット・デメリット、方法まで、まとめて解説します。

業務の見える化とは、業務効率の改善を目的として業務の計画・工程などの活動を視覚的に認知できるようにすることです。
使われている言葉から「見える化=業務上の何らかを見えるようにすること」だろうと予測できる方はいるでしょう。一方、見える化とよく似た言葉に「可視化」もあります。
ここからは見える化の意味を正しく理解できるよう、類義語の「可視化」との違いと、見える化の起源を解説します。
「見える化」と「可視化」は、そのゴールが異なります。両者はブラックボックス化している情報を明らかにする点で同じですが、可視化は見えないものを見える状態にすることを目的とし、見える化はその先の業務改善までを目的に含んでいる言葉です。そのため、可視化は様々なデータを、グラフ化したりマッピングしたりする時によく用いられます。
▼可視化の例
▼見える化の例
上記のように両者に違いはあるものの、可視化によって明らかになったデータを業務改善に活用することができるので、可視化は見える化の一部だと言うこともできるでしょう。また、両者を区別せず同じ文脈で使用されることもあります。
見える化の起源はトヨタ自動車株式会社の『トヨタ生産方式』にあります。「異常が発生したら機械をただちに停止して、不良品を造らない」と「各工程が必要なものだけを、流れるように停滞なく生産する」の2つを柱として確立されたトヨタ生産方式の根底には「ムダの徹底排除」の思想が存在しており、ムダを発生させない仕組みをつくることで、経営の圧迫を防いでいるのです。

そして見える化とは、トヨタ生産方式の中でも「問題やムダの所在を視覚でとらえられるように明確にするよう取り組むこと」とされていました。トヨタ生産方式の中で視覚で認識できるようにすべきとされている項目には、生産現場での作業方法や順序、物の管理、作業の進捗管理、安全管理などが挙げられます。
またトヨタでは作業現場で問題が発生した際に管理者があんどんを点灯させる『あんどん方式』と必要な部品や数量を書いた札(かんばん)を生産工程が進むのと同時に回すことで必要な時に必要な数だけ部品を調達できる『カンバン方式』が見える化の具体例となっています。
※参照:トヨタ自動車株式会社公式HP

見える化の定義やその背景を知ったことで、見える化が企業の経営問題を解決するための問題を明らかにすることだと理解できました。ここからは、見える化が私たちの業務に必要な理由を2つ解説します。
「見える化の起源」でも解説したように、見える化とはムダの発生による経営の圧迫を防ぐために情報を視覚的に認知できる状態にすることでした。つまり見える化によって業務のやり方や順序が視覚で理解できるようになれば、必要以上に時間を要している業務や、業務の効率向上を妨げている作業を突き止めやすくなるのです。
DX(デジタルトランスフォーメーション)とは直訳で「デジタル技術による変容」を意味する言葉で、デジタル技術によって生活や企業が展開するビジネスを変容させていくことを指します。そしてDXの効果を最大化させるために欠かせないのが見える化です。
DXの順序はまず、現場の情報を集めてデジタル化することから始まります。つまりDXの順序のうち、見える化は現場の情報を収集する際に欠かせない手段なのです。見える化によって視覚的に認識・整理したデータをコンピュータやAIで分析することで、はじめて現場の業務改善に活かせると言えます。

ここまで見える化の定義を理解することで、見える化の最終的な目的と役割が、情報を視覚的に認知できるようにすることで業務のムダを省く業務改善であると分かりました。次では見える化が業務に与えるメリットを7つ見ていきましょう。
1つ目のメリットは、見える化によって業務に当たる個人が持っている情報や、管理者が把握し切れなかった状態が視覚で認知できるようになっているため、業務の課題も自ずと見つかりやすくなる点です。例えば、コールセンターのオペレーターが1日あたり50本の問い合わせ電話に応対する目標が掲げられている中、実績は1日20本だったとします。
現状と理想との差異に対して、オペレーター個人の応対の流れを見える化すれば「問い合わせへの平均応対時間が長すぎる」ことやトークスクリプトが機能していない課題が分かるかもしれません。
業務が見える化されれば、ムダのない業務フローの立案もできるようになります。見える化による課題発見と効率的なフロー立案の結果、個人のスキルに依存した業務ではなく、誰もが同じ品質で業務ができるようになるため、リスクやミスを仕組みによって防ぎ、軽減させやすくなるでしょう。
またワークフローがあることによって、業務内容は担当者だけではなく、管理者にも認識されるようになります。その結果、ダブルチェックの質や異常を察知するスピードも上がり、より高品質な業務に繋がるのです。
特に多くの人数が関わる業務に対して、各作業にどれだけの時間や費用がかかっているのかは分かりにくいものです。これに対して見える化は業務の状態と発生した問題やムダを視覚で認知できる状態にすることであるため、コスト削減にも繋がります。
Webサイトのデザイン制作で外部のフリーランスクリエイターに制作を依頼した場合を例にしてみましょう。見える化によって、作業の工程や工数が明かにできていれば、当初作業完了まで1人月(1人で作業完了させるまで1か月かかる計算)と見積もっていたところ、完成まで時間がさらにかかりそうだということが早期に分かり、業務のムダを省くよう動けるので、結果的にコスト削減に繋がるのです。

4つ目のメリットは、情報共有が円滑になることです。見える化では日々の業務で埋もれていた情報がデータとして認識されるようになるため、大まかな状況の把握・共有だけではなく、具体的な数値も把握・共有しやすくなります。
例えば、結果として業務の進捗が本来の60%しか進捗していない状況があるとします。この中で業務が見える化されていれば、各作業工程での進捗状況やムダ、エラーが数値として把握できるようになっているため、関係者の報告もより具体性のある内容が伝えられるようになるでしょう。
1~4つ目の見える化のメリットでは、業務のムダや質の改善について解説してきました。これらに加えて、見える化は業務以外の範囲にも幅広く影響しています。それがここから解説する人事や教育、組織開発に関する影響です。まず人事評価の見える化については、従来の属人的な評価からデータによる公平な評価に改善できるようになります。
正当かつ公平な人事評価は正当な報酬に繋がり、優秀な人材が離職するリスクを避けられるようになるため、企業にとって人材や各人が有する知識やスキルが蓄積される好循環になるでしょう。

人材育成の見える化では在籍している社員の職種やスキルなどの情報を視覚で認識できるようにします。これによって、担当している業務に必要なスキルに対して足りないスキルが明らかになり、人材のスキルマップ作成や人材育成、人材の適所配置、さらには企業に足りない人材やスキルまで明らかにすることができるのです。
組織が大きくなると他の部署や関係者が有している情報が広く行きわたっていなかったり、そもそも情報がどこにあるのか分からなくなってしまう場合も少なくありません。しかし、見える化の習慣がある組織では情報が行きわたっているだけではなく、それらが認識できるように整えられています。このような状況から、組織に暗黙の了解が少なくなり、従業員が自発的に情報を共有し合うようになり、共通認識と一体感が生まれるのです。
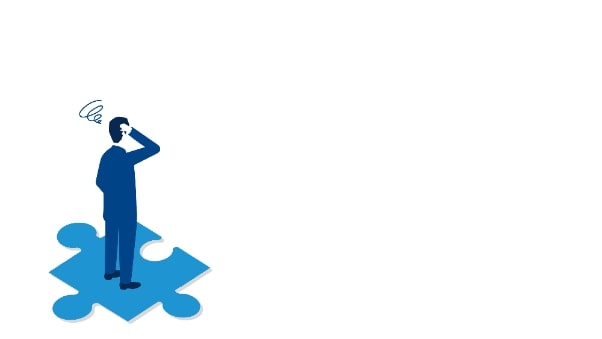
見える化は業務の工程や工数に加え、業務の問題を把握できる大きなメリットがあると分かりました。一方、複雑かつ多様なデータを整理し、視覚的に認知できるようにするには、後述するようなマップやマニュアルの作成をはじめとした、集中力と専門性を要する作業も必要になります。
つまり業務の見える化は一朝一夕には叶わないことが大半なのです。このような見える化の性質によって生まれやすい代表的なデメリットを次で2つ解説していきます。
業務の見える化はムダの削減と生産性向上に効果がある一方、ミスを防ぐためにマニュアルを順守しなくてはならない風潮に伴って、管理者から「監視されている」ような感覚を抱きやすくなります。
監視されているような感覚は、新しいアイディアの創出を妨げてしまう可能性も否定できません。またマニュアル化されていないパターンが発生した場合に臨機応変な対応がしにくくなる傾向があると言えるでしょう。
業務を見える化させることに一定の労力が必要になるため、見える化によって実現したかった目標や状態ではなく見える化自体が目標になってしまう可能性があります。
例えば従業員の作業効率化によって、残業時間を削減したいことが目標であったのにも関わらず、現場の業務を仔細まで見える化しようとするあまり、当初より従業員の残業時間が長くなってしまうケースも考えられるでしょう。
最後に現場で活用できる、業務を見える化させる方法を5つ解説していきます。業務の効率化や生産性の向上の妨げになっている問題に対して解決策になりそうな方法があればぜひ実践してみましょう。

プロセスマップとは主に標準的な業務の工程と手順を図式で可視化したものです。プロセスマップを作成することで業務の計画立案や意思決定の全体像や手順が明らかになり、例外的な処理が省かれ、各業務工程の質とスピードが向上しやすくなります。プロセスマップの作成手順は以下のとおりです。
スキルマップとは担当業務に対して必要なスキルを取得レベルごとに表した図です。一般的なスキルマップは縦軸に業務内容と業務に対する必要スキル、横軸に個人名が記載されており、クロスする部分に必要スキルの習得度合を記載して見える化する図です。
スキルマップの作成によって目指すべき姿や必要な能力が明確になるため、モチベーションの向上や、不足する能力やスキルに対して適切な人材教育を受けやすくなります。
業務の見える化においてマニュアル作成は業務を標準化し、ムダを省くことで生産性を上げる効果があります。また急な担当者の変更にも対応できるため、担当者の経験不足によるミスを防止しやすくなります。
業務マニュアルは事業・組織の変化や担当者の変更などによってバージョンを更新していくことで、より実務に活用しやすいようになります。そのため、業務マニュアルは担当者が編集しやすいように格納場所やバージョン管理のルールを決めておくと安心です。
さらに業務マニュアルは社内の業務改善に留まらず、外部のパートナーとの情報連携や納品物の品質管理にも役立つので、第三者が理解しやすいように図表やグラフ、チャートを活用しながら作成すると良いでしょう。
業務の見える化をする中で、業務や問題に関するデータを第三者にわかりやすく提示したい場合はグラフやチャートを活用するのも1つの方法です。
グラフの一般的な例にはExcelやGoogleスプレッドシートの活用が挙げられます。またチャートの場合は分解(全体像を細かく分解する)、特性表現(複数の要素の比較)、時間軸表現(時系列関係を明らかにする)の中から適切なチャートを選択して、情報を整理しましょう。例えば業務全体のスケジュールを見える化させたい場合はガントチャートを用いて各作業の工数を可視化させる方法があります。
Schooでは業務プロセスの見える化の意味、見える化の具体的な方法まで、まとめて授業『業務改善のはじめ方 プロセスの見える化』で学ぶことができます。
< コース詳細 >
デジタルに強い組織運営へ成長していくためには、業務課題を発見することが重要だと言われています。そして業務課題を発見するために役立つ手段の1つが「業務プロセスの可視化」です。このコースでは業務プロセスとその可視化技法を学び、潜在的な業務課題発見の糸口を掴みましょう。
先生プロフィール

土方 雅之 (ひじかた まさし)
株式会社カレントカラー 代表取締役。1992年、東京大学電気電子工学科 卒業。 同年、日本電気株式会社(NEC)に入社。 大規模プロジェクトのシステムエンジニア、プロジェクトマネージャを経験。2008年から全社基幹システム改革プロジェクトでのBPM(ビジネスプロセスマネジメント)方法論の設計と展開の責任者。 業務改革体系の企画・設計・展開の責任者。
見える化したい情報によっては、ヒートマップや勤務時間や残業時間の記録アプリをはじめとした専用ツールの導入が必要になる場合もあります。
特に在宅勤務が取り入れられるようになった時代背景や、競争が激化する市場でDX化が推進されていることから、業務効率化・生産性向上のための見える化専用ツールは近年増えているので、見える化の目的に合ったツールを探して見ましょう。
ツールがよく利用される分野としては、以下があります。気になるツールがある場合は、直感的に導入するのではなく、見える化の目的が達成できるか確認して、検討しておくと効果が期待しやすいです。

見える化専用ツールが活用されている分野を知ったところで、専用ツール用いて業務の見える化に成功した事例を次で見ていきましょう。
自動車や電子機器の部品を扱うメーカー事業や流通事業、オーダーメード部品製造サービスmeviyなどを展開する株式会社ミスミグループ本社は、業務工程をドキュメント化することで判断基準を統一した後、マーケティングや顧客との関係を見える化するツールsalesforceの活用によって営業とマーケティング業務の「一元化」「自動化」を進めました。具体的には一元化・自動化では、ミスミグループ本社のデータベースからターゲット層を抽出し、顧客情報基盤やサービス利用履歴などを専用ツール上に登録し、業務自動化にも活用されているそうです。
※参照:https://www.salesforce.com/jp/customer-success-stories/misumi/
株式会社USEN-NEXT HOLDINGSでは従業員の視聴時間や学習の様子を把握することで、自律した学習と自らキャリアを開拓できる組織の醸成を目指しています。「学びの見える化」のために株式会社USEN-NEXT HOLDINGSが導入した専用ツールは職種・階層ごとの必要スキルに合った研修が受講できるSchoo for Businessです。管理画面から社員の受講状況や学習時間が分かるようになっています。
業務の見える化とは目標を達成するための日々のたゆまぬ業務改善に欠かせないプロセスです。業務を見える化させることで実現したい目標をしっかり見定めた上で、見える化の方法を試していきましょう。Schooでは業務効率化を含む、ビジネススキルに関する授業が月額980円で受け放題です。ぜひ活用してくださいね。